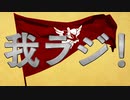ウィリアムズF1とは、F1世界選手権に参戦するイギリスのレースチーム、コンストラクターである。
2017年現在の代表者は、創設者であるフランク・ウィリアムズ。だが、彼は年齢上の理由から段階的に身を引いており、事実上のトップは副代表であり娘のクレア・ウィリアムズである。
2020年8月にチームはアメリカの投資会社ドリルトン・キャピタルへ売却され、同年9月のイタリアGPをもって、フランクとクレアの親子はチームを離脱した。
概要
正式名称は、ウィリアムズ・グランプリ・エンジニアリングで、F1での参戦の他、他のカテゴリー向けのレースシャシーやパーツの開発、提供も行っている。
1980年代、90年代においてはチャンピオンを幾度も獲得し、フェラーリやマクラーレン、ロータスと並び、F1の名門と言われる。 しかし近年では優勝すらも遠ざかっている。
歴史
F1参戦(1969~1976年)
ドライバーやメカニックを経験したフランク・ウィリアムズは、1966年にフランク・ウィリアムズ・レーシングカーズを設立。
1969年に親友であったピアス・カレッジをドライバーに起用してブラバムの中古マシンを購入し、F1に参戦した。
元々才能のあったカレッジだっただけに、デビューイヤーに2度2位を経験した。しかしデ・トマソのセミワークスとなった翌年はマシン熟成に手こずり、その年のオランダGPで、カレッジは事故で亡くなってしまった。
その後は成績不振となり、1972年には初めての自作マシン、ポリトーイFX3を出走させるも結果は悲惨。1973年にはイタリアのメーカー、イゾとマールボロのスポンサーを得て参戦を続けるが、1975年に奇跡的な2位表彰台を獲得した以外はテールエンダーの常連のようになり、さらには資金不足で破産しそうになった。
なお、この中で1974年のマシンに初めてFW03のナンバーを付けた。なぜ03から始まるかというと、これまでのマシンにさかのぼってナンバリングしたためである。
1976年に、カナダの富豪、ウォルター・ウルフのスポンサードを受け、潤沢な資金によってそれまでの債務を解消することが出来たものの、今度はウルフ自身がチームを運営しフランク・ウィリアムズを外す目論見が出たことで、チームを売却して一時グランプリから去った。
新体制~第1次黄金期(1978~1982年)
1977年に、一度チームに関わっていたパトリック・ヘッドを口説き落とし、共同オーナーとして資金を出資し合い、ウィリアムズ・グランプリ・エンジニアリングを設立。
パトリック・ヘッドがデザイナー、後にテクニカル・ディレクターとしてマシン開発を行うようになった。
ヘッドは先進的なものにはすぐに手を出さず、納得のいくまで検証し、理解できてから投入するという現在まで通じるウィリアムズの保守的、堅実的な社風、理論ができあがった。
実際、ロータスが1977年に導入したグラウンド・エフェクト・カー(ウィングカー)相手には、敢えてオーソドックスなFW06で堅実に戦う。1年間検証の後、上手くロータス79のパクリアレンジを加えたものとして1979年にFW07としてデビューさせた。このマシンによってチームは念願の初勝利を上げる。そして、FW07は稀代の傑作マシンとなり、あわててロータスのデッドコピーを作った結果大やけどするか、上手くいっても本家を超えられないライバルチームを尻目に、3年間の使用で2度のコンストラクターズタイトル、アラン・ジョーンズが1980年にオーストラリア人としては2人目(1人目はジャック・ブラバム)のドライバーズタイトルを手にした。
1982年にはティレルの6輪車の発想を転換し、後輪を4輪として全てをフロントタイヤ同様のサイズで補える6輪車を開発した。これは、巨大なリアタイヤを小さくすることでグラウンドエフェクトのエアトンネルを大きくし、より強力なダウンフォースを得ようとしたもの。さらに4輪で地面を蹴ることによる強烈なトラクションを得て、加速面でも利点を得られるはず。だったのだが、後部の重量がかさんでバランスが悪化するのがどうしても解決できず、この年の6輪車の導入を断念した。
しかし怪我の功名と言うべきか4輪にコンバートしたFW08は、引退したジョーンズに変わってエースとなったケケ・ロズベルグのクイックなマシンを好むスタイルに合い、彼がチャンピオンを手にした
ホンダとの提携、第2次黄金期(1983~1987年)
1983年シーズンを前に、ヘッドは依然6輪車の投入を狙っており、FW08Bとして実車も完成していた。だが、シーズン前にウィングカーと共に6輪車そのものが禁止となり、結局4輪車のままフラットボトムに改造したFW08Cを使うことになった。そしてルノーが先鞭を付けたターボエンジンがパワーで圧倒するようになり、自然吸気エンジンを使い続けたウィリアムズは苦しくなっていった。名手ケケを持ってしても、パワーの差が帳消しになるちょい濡れのモナコで勝つのが精一杯だった。
その年の後半に、ウィリアムズはホンダエンジンとワークス供給契約を結び、同年の最終戦に搭載マシンをデビューさせた。最初のフルシーズン、1984年こそ1勝のみと苦戦したものの、翌年の後半には熟成なったホンダエンジン搭載のマシンは幾度の勝利を手にするようになった。なお、この時のFW10はモノコックがチーム初のカーボンコンポジットとなったものの、リアサスペンションに旧式のロッキングアーム式を採用し続けており、空力的にも劣る無骨なマシンだった。しかしホンダのパワーがそれらの弱点を補ってあまりあったのである。なお、シーズン後半にはリアサスペンションもプルロッド式となるなど改良され、終盤のレースは3連勝を飾ることになる。
1986年にはナイジェル・マンセルと2度のチャンピオンを手にしたネルソン・ピケの体制になり、昨年までよりはるかにスリムになったFW11によってコンストラクターズタイトルを獲得した。しかし、ドライバーズタイトルはマンセルとピケの争いの間をかいくぐったマクラーレンのアラン・プロストが取るという、まさにトンビに油揚げをさらわれる羽目になった。
さらには、大きな不幸として私用で出かけたフランク・ウィリアムズが自動車事故で重症を負い、下半身不随の障害が残ってしまう。しかし、これにめげずにフランクは車椅子に乗ってまでグランプリの現場に通うようになる。「車椅子の闘将」の誕生であった。
翌年には改良型FW11Bが作られ、変わらずマンセルとピケが激しいタイトル争いを繰り広げた。だが、マンセルが自滅する形で負傷し、ピケがドライバーズタイトルを手にし、チームも連続してコンストラクターズタイトルを手にした。
しかしホンダはウィリアムズとの関係を解消してマクラーレンにエンジンを供給することを決めてしまう。ピケもロータスに移籍、セカンドドライバーにはリカルド・パトレーゼが加入する。
1988年には車高とロール制御をコンピューターと油圧ダンパーで行うリアクティブサスペンションを搭載したFW12を投入するが、信頼性やパワーで劣るジャッドV8エンジンと不安定なサスペンションによって優勝を逃してしまう。こうしてマンセルも勝てるマシンを求めてフェラーリに移ってしまった。
ルノーとの提携、第3次黄金期(1989~1997年)
その間にウィリアムズは、ターボでチャンピオンは取れず、ターボ禁止による自然吸気エンジン開発を行うために活動休止していたルノーとワークス契約を結び、1989年にはルノーV10エンジンを搭載したFW12Cを導入した。ドライバーはパトレーゼとベネトンから移籍したティエリー・ブーツェンのコンビとなった。
シーズン中にFW13が導入され、この年に2勝を挙げ、コンストラクターズ2位に躍り出た。翌年は、改良型のFW13Bを投入したが、結局勝ち星は変わらず、翌年のマシンの開発に集中したこともあって終盤ではジリ貧になった。日本GPでは格下のラルースにも負けるなどして、コンストラクターズランキングはフェラーリばかりかベネトンにも抜かれ、4位に終わった。
1991年には先進的なマシンデザインを行うエイドリアン・ニューウェイを引き抜き、フェラーリに移籍して引退を考えていたマンセルを口説いて復帰させた。FW14はニューウェイの先端的な空力処理をしつつもヘッドによって手堅くまとめたマシンで、この年にはチャンピオン獲得まであと一歩まで迫った。
1992年には改良を続けてきたリアクティブサスペンションを搭載したFW14Bを投入。空力を最大限に活用できるようになったことで圧倒的な速さを見せつけ、マンセルに待望のドライバーズタイトル、チームにコンストラクターズタイトルをもたらした。が、翌年の契約に関してチームとマンセルが対立しマンセルはシーズン途中で引退表明。翌年にはCARTに転向してしまう。
1993年には1年間の浪人生活を送っていたアラン・プロストと前年にFW14Bの開発に貢献したデイモン・ヒルをテストドライバーから抜擢。より洗練されたFW15C(当初は92年後半に投入予定だったが、あまりにもFW14Bが余裕だったため、テストで熟成を重ねてCスペックになっていた)によってダブルタイトルを手にした。が、マンセルに続き今度はプロストもシーズン途中で引退表明。
1994年にはアイルトン・セナを起用するも、ハイテク機器の禁止によってリアクティブサスペンションが使えず、FW16は不安定で信頼性の低いマシンになってしまった。
セナは2度のポール・ポジションを手にするもトラブルによって完走すら出来ず、第3戦のサンマリノGPでもポールを獲得するがステアリングトラブルにより、高速カーブのタンブレロを曲がり切れずそのままウォールに激突し、事故死してしまう。→イモラの悲劇
その後、デビュー3年目のデイモン・ヒルと新人のデビッド・クルサード、そしてスポット参戦で復帰したナイジェル・マンセルによってコンストラクターズタイトルを手にした。
1995年はミハエル・シューマッハとベネトンに両方のタイトルを獲られてしまうものの、翌年にはジャック・ヴィルヌーブを起用、コンストラクターズタイトルを奪取するとともにデイモン・ヒルにドライバーズチャンピオンをもたらした。
ところが、この年のフランスGPにてエンジンサプライヤーのルノーが1997年を最後に撤退することを発表。さらに、チームはBMWエンジン獲得を目的にドイツ人ドライバーを乗せる事を画策したため、イタリアGP前にヒルの解雇を発表。が、これに関してニューウェイが激怒しチームを離脱してしまう。こうして、ヒルの後釜にはハインツ・ハラルド・フレンツェンが座ることになった。
1997年にはヴィルヌーブとシューマッハとの熾烈なタイトル争いが行われ、最終戦で辛くもヴィルヌーブがチャンピオンを手にした。また、コンストラクターズタイトルも獲得した。しかし、ヒルとニューウェイの抜けた穴はあまりにも大きく、次第にマシン開発は迷走しつつあった。
1998年、チームは前年型のエンジンをそのまま使用して(メカクロームがメンテナンス。1999年にはスーパーテックが供給) いたものの、開発が終わったエンジンの性能は衰え、勝利すら味わえなくなった。
翌年は両ドライバー共に新たな展開を求めてチームを去り、ミハエル・シューマッハの弟として注目を集めつつあったラルフ・シューマッハと、CARTでチャンピオンを何度も取って満を持してF1再挑戦してきたアレックス・ザナルディのコンビとなった。しかしラルフが何度か表彰台に食い込んだ他は振るわず、ザナルディは全くの不発に終わって再びF1を惨めに去ることになった。
BMWとの提携(2000~2005年)
1999年にル・マン向けのプロトタイプカー、V12LMRを開発した縁もあってか、ターボ禁止以降グランプリから遠ざかっていたBMWと2000年からワークス契約を結んだ。初年はさすがに開発に終始し、勝利は無かった。この時に、ジェンソン・バトンがデビューを果たしている。
2001年にはラルフ・シューマッハ、ファン・パブロ・モントーヤを起用、それぞれで4勝を挙げて再びチャンピオン争いに加わるようになった。
しかしフェラーリ、マクラーレンとの戦いでなかなかタイトルには届かず、2004年のブラジルGPを最後に勝利からも遠ざかってしまった。この中で、FW26は「セイウチノーズ」と呼ばれる革新的デザインを投入したが、思ったような効果は得られず結局終盤にありきたりなノーズに戻している。そして、遂に長年マシン設計に携わってきたパトリック・ヘッドは第一線から身を引くことになる。
2005年にはBMWからワークスチームとして買収したいとの打診があったが、フランク・ウィリアムズらは拒否。
さらに成績不振も相まってBMWと確執が生まれ、BMWは予算の高騰で疲弊していたザウバーを買収することを決め、ウィリアムズと結んでいた2009年までの契約は打ち切られた。ドライバーはマーク・ウェーバーとニック・ハイドフェルドに変わっていたが、両者とも表彰台の一角を得るだけに終わった。
プライベーターへ(2006年~2013年)
2006年にはワークス供給できるエンジンを手に出来ず、フォードの支援を失ったコスワースエンジンを導入した。ドライバーにはGP2初代チャンピオンのニコ・ロズベルグを起用した。しかし、シーズン序盤は入賞争いを繰り広げたものの、戦闘力・信頼性の低下もありヨーロッパラウンド以降は入賞もままならなかった。
2007年にはトヨタエンジンを採用するも、ワークスではなくカスタマー契約であった。ロズベルグは3度の表彰台を経験するものの、勝利には遠かった。もう一人のアレクサンダー・ヴルツも未勝利のままF1を引退した。
2008年は後釜に座った中嶋一貴とのコンビとなったが、今度もロズベルグが2度表彰台に登ったのみ。
2009年にはロズベルグはこまめに入賞するも表彰台に上がれず、チームメイトの中嶋一貴に至ってはノーポイントに終わってしまった。2010年までこの体制が続くかと思われたが、トヨタが完全撤退を決めたため供給も打ち切られた。
2010年に再びコスワースを採用したが、チームもコスワースも資金不足で戦闘力が低下。ロズベルグはウィリアムズに見切りをつけてメルセデス(それは前年のチャンピオンチーム、ブラウンGPが名を変えたものだった)に移籍。入れ替わりに前年までブラウンで走っていたベテラン、ルーベンス・バリチェロがシートを得た。その中で、ブラジルGPにおいて新人、ニコ・ヒュルケンベルグが久々のポール・ポジションを獲得した。しかし、全体的にジリ貧の状況は変わらず、スポンサーも数多くが引き揚げてしまう。
2011年にはベネズエラの支援を受けるパストール・マルドナードを起用するも、獲得できたのはたった5ポイントで、現体制、つまり1977年以来のなかで最低得点を記録した。そしてパトリック・ヘッドも完全にグランプリの現場を去ることになった。
2012年、1997年以来となるルノーと契約を結び、ウィリアムズ・ルノーの黄金コンビが復活した。ただし黄金期とは異なりこちらもカスタマー契約である。バリチェロに変わって、アイルトン・セナの甥ブルーノ・セナが加入し、マルドナードとコンビを組んだ。しかし戦闘力は格段に上がり、トップチームにも肉薄するまでになった。その中で、スペインGPではマルドナードがポール・ポジションを獲得、さらには優勝を果たした。チームの勝利自体が8年ぶりであり、カスタマーエンジンでの勝利は1983年以来となった。これらによって、76ポイント、ランキング8位とまずまずの結果を得ることが出来た。
しかし、翌2013年はまたもマシンの戦闘力が落ちてしまう。ブルーノ・セナに代わり、リザーブドライバーからバルテリ・ボッタスが昇格したが、成績はチーム全体で5ポイントと2年前に逆戻りしてしまった。マルドナードはチームを離れ、ロータスへと移籍することを発表した。
メルセデスとの提携(2014年~)
2014年、F1はこれまでのNAエンジン+KARSのシステムに変わって、ターボエンジン+複雑なエネルギー回生システムを含んだPU(パワーユニット)を動力源とした。当然、チームもこれに対応せねばならず、メルセデスからPUの供給を受けることを決定していた。ドライバーはフェラーリからベテランのフェリペ・マッサが移籍した。新たなメインスポンサーとしてマルティニが付き、マルドナードの離脱後も契約が残っていたベネズエラ国営企業との間でも違約金の形で資金が払われた。BMWワークス時代以来の潤沢な資金が集まったが、それでもフェラーリなどのトップチームに比べれば半分程度のものだった。
さて、戦績の方はこれもBMW時代以来の予選でのフロントロー(1,2位)独占を達成するなど確実に上向いた。ボッタスの成長もあって、優勝こそ無かったがランキング3位という久々の好成績となった。
2015年もほぼ同じ体制が続き、表彰台の一角を何度か占めてみせた。ランキングも同じ3位だった。
2016年、やはりマッサとボッタスのコンビは続いたが、どうしてもトップチームに追いつくまでには至らない。逆に、同じメルセデスPUを使うフォース・インディアが力をつけてきて、直接的な相手は彼らとなった。結局コンストラクターズランキング5位と少し勢いが落ちてしまった感があり、マッサがこの年限りで引退を表明した。彼にとって最後のブラジルGPでは、盛大な引退セレモニーが行われ、マッサは数多くの優勝経験はあれども無冠のままのドライバーのひとりとしてグランプリを去った。
…ところが。
メルセデスチームのニコ・ロズベルグがチャンピオン決定後突如引退を表明したのだ。その後釜に急遽ボッタスが移籍することになり、シートが一つ空きとなってしまった。これによってマッサは引退を撤回しセレモニーの感動は茶番となったが、リザーブドライバーから昇格したカナダ人のランス・ストロールとコンビを組むことになった。
2017年は、1977年以来の現在のチーム体制が40週年を迎えることからマシン名をFW40とした。もう1年走ることになったマッサだが、結局は入賞を何度かするにとどまる。一方のストロールは当初は親の七光りによるペイイング・ドライバー(資金持ち込みでシートを得る、つまりドライバーとしてのレベルは二の次)と見られていたが、地元のカナダGPで初入賞すると、続くアゼルバイジャンGPで3位に入り表彰台に登ってみせた。この年はランキング5位と順位はキープしたが、4位のフォース・インディアにはポイント数で大幅に差をつけられてしまった。
2018年、今度こそ引退したマッサに変わり、ロシア人のセルゲイ・シロトキンがチームに加わった。しかし、ニューマシンのFW41は失敗作に終わり、ドライバーは両名ともに低迷を極めた。なんと2戦でしかポイントゲットできず、コンストラクターズランキングは最下位とまさにチーム状態はどん底に落ちた。さらに、このシーズン前にマルティニがスポンサーからシーズン終了後に撤退することが発表されており、もう一つの資金源であるストロールも、父親がフォース・インディアを買収して彼を移籍させることになり、泣きっ面に蜂の状態となってしまった。
2019年、新たなタイトルスポンサー「ロキット」を得て、ドライバーはかつてBMWザウバーやルノーで活躍するもラリーでの負傷で9年もF1を離れていたポーランド人のロバート・クビサと、イギリス人の新人ジョージ・ラッセルのコンビで復活を図る体制となった。しかし、不振から抜け出すどころかライバルと争う事すら困難な程に低迷し、荒れたドイツGPでクビサが辛うじて1ポイントをゲット(しかも自力入賞ではなくアルファロメオ勢のペナルティによる繰上げ)したものの、昨年に続いてコンストラクターズランキングは最下位に終わった。クビサはかつての輝きを取り戻すことはとうとうなく、ラッセルがクビサを大半のレースで上回って見せて、才能の片鱗を感じさせたのが唯一の救いだった。
2020年、ドライバーはクビサに代わって昨年のリザーブドライバーを努めたニコラス・ラティフィが加入。しかし、コロナウィルスの世界的流行の影響でシーズン開始が大幅に遅れる中、メインスポンサーの「ロキット」が離脱。とうとう資金繰りに行き詰まったチームは、せめてチームそのものの消滅を回避するために売却先を探すことになった。8月、アメリカの投資会社ドリルトン・キャピタルへチームは買収された。9月のイタリアGPをもって、フランク・ウィリアムズとクレア・ウィリアムズはチームを離脱。ウィリアムズ一家は43年にわたるチーム運営から完全に手を引いた。チーム名称と本拠地は当面は受け継がれる模様。
シーズンの方はというと、前年に比べればマシンの戦闘力はある程度改善され、予選Q2にも度々進出するようになった。が、肝心の入賞に中々手が届かず、15戦終了時点で10チーム中唯一ノーポイント。最高位は11位が4回(ラッセル1回、ラティフィ3回)となっており、特にトスカーナGPではラッセルが一時9位を走行するも、2度目のリスタートに失敗し11位に終わった。そんな中、第15戦バーレーンGP後にメルセデスAMGのルイス・ハミルトンが新型コロナウイルスに感染し、翌週のサヒールGPを欠場する事になった影響で、メルセデスの育成ドライバーであるラッセルが急遽招集され、サヒールGPではリザーブドライバーのジャック・エイトキンが代役を務めた。
2021年シーズンはメインスポンサーを欠いたままの状態ながら、マシンのFW43Bは明らかにエンジニアリング面が改善。ラッセルがベルギーGPでチームにとって2014年以来のフロントローを獲得。レースは悪天候でたった1周で中断してそのまま成立となったため、これも久々にハーフポイント扱いとは言え2位表彰台を得ることになった。ラティフィもハンガリーGPでのラッセルとのダブル入賞を含めて複数回の入賞を果たし、チーム全体の成績はランキング8位にまで回復した。
2021年シーズン終了をもってラッセルが離脱し、メルセデスに移籍する。
2022年シーズン、ラティフィは残留し、後任としてアレクサンダー・アルボンが加入する。
お家芸
このチームを語る上で欠かせない点として戦略・ピット作業のミスの多さが挙げられる。
特に有名なのが1991年のポルトガルGPと1997年のモナコGP。
1991年ポルトガルGP
予選4位だったナイジェル・マンセルはスタートでマクラーレンの2台を抜き2位へ浮上、その後トップを走行していたチームメイトのリカルド・パトレーゼに順位を譲られトップに躍り出た。
この日、ライバルのマクラーレンはウィリアムズに全く歯が立たずマンセルにとって非常に楽な展開であった。
そしてタイヤ交換のためピットインし、作業を終えてピットアウトしたのだが…直後に右リアタイヤが外れて他チームのピットに転がっていってしまった。原因はタイヤをはめたクルーがタイヤのナットを締め終わる前に作業完了の合図を出してしまった事だった。
ナットを締め損なうミス自体はウィリアムズに限らず他チームでも時折見られるミスであり、これだけなら20年以上も話題にされたりしない。重要なのはここからである。
この後、タイヤが外れてピットレーンに立ち往生していたマンセルのマシンにタイヤを再装着して再スタートさせるのだが、本来であれば自チームのピットまでクルーが押し戻さなければならないところをピットレーン上でそのまま作業を行ない、マンセルは黒旗を振られ失格となってしまった。
・当時の流れ
タイヤをはめたクルーが「作業完了」の合図
↓
ジャッキを降ろす
↓
ナット担当のクルーが「ダメだ」の合図
↓
ロリポップが気付かずにマンセルを発進させ、タイヤがポロリ
↓
ピットレーン上でマンセルのマシンにタイヤ装着
↓
黒旗が振られる(失格)
余談だが、マンセルはフェラーリに所属していた1989年の同GPでもピットレーン上でのレギュレーション違反(バックギア使用)で黒旗を振られている。この時は無視してレースを続行した挙句、トップを走行していたアイルトン・セナに接触しリタイアに追い込んでしまったため、罰金と翌戦の出場停止処分を受けている。
1997年モナコGP
予選ではハインツ・ハラルド・フレンツェンが初のポールポジション、ジャック・ヴィルヌーヴが3位を獲得し、ここまでは順調だった。
決勝スタート直前に雨が降り始め、他チームがスタート前にウェットタイヤへの交換や、セッティング変更で慌しくなる中、ウィリアムズは雨はすぐ止むと信じスリックタイヤでスタートするという暴挙に出る。
しかも予選2位のミハエル・シューマッハが大雨用のセッティングに変更していたにも関わらずである。案の定、暖まっていないスリックタイヤでは走れない程に路面が濡れ始め、スタートでミハエル・シューマッハにあっさりトップを奪われた。当然ながらウィリアムズ勢は全くペースが上がらず、只でさえ狭いモナコで大渋滞の原因となる。
3週目にヴィルヌーヴがウェットタイヤに交換するが、この段階でも一番雨が少ない時に使うインターミディエイト(当時、グッドイヤーのウェットタイヤは3種類あった)に交換。だが、直後に雨脚が強くなり結局スタート時の二の舞となってしまい、最後はサン・デボーテでガードレールにヒットしリタイア。
直後に、フレンツェンもウェットタイヤに交換するが、まだ雨が止むと思っていたのかヴィルヌーヴより一段上のウェットタイヤに交換。結局フレンツェンもペースが上がらず、こちらもヌーベル・シケインでガードレールにヒットしリタイア。
ウィリアムズ首脳陣のグダグダな作戦に両ドライバーが振り回された挙句に周回遅れにされ、路面状況に合わないタイヤが原因でクラッシュするというトップチームとしてあるまじき醜態を晒す羽目に。どうしてこうなった。
歴代ドライバー
- アラン・ジョーンズ
- クレイ・レガツォーニ
- カルロス・ロイテマン
- マリオ・アンドレッティ
- ケケ・ロズベルグ
- デレック・デイリー
- ジャック・ラフィット
- ジョナサン・パーマー
- ナイジェル・マンセル
- ネルソン・ピケ
- リカルド・パトレーゼ
- マーティン・ブランドル
- ジャン=ルイ・シュレッサー
- ティエリー・ブーツェン
- デイモン・ヒル
- アラン・プロスト
- アイルトン・セナ
- デビッド・クルサード
- ジャック・ヴィルヌーヴ
- ハインツ=ハラルド・フレンツェン
- アレッサンドロ・ザナルディ
- ラルフ・シューマッハ
- ジェンソン・バトン
- ファン・パブロ・モントーヤ
- マルク・ジェネ
- マーク・ウェバー
- ニック・ハイドフェルド
- アントニオ・ピッツォニア
- アレクサンダー・ヴルツ
- ニコ・ロズベルグ
- 中嶋一貴
- ニコ・ヒュルケンベルグ
- ルーベンス・バリチェロ
- ブルーノ・セナ
- パストール・マルドナド
- バルテリ・ボッタス
- フェリペ・マッサ
- ポール・ディ・レスタ
- セルゲイ・シロトキン
- ランス・ストロール
- ロバート・クビサ
- ジャック・エイトケン
- ジョージ・ラッセル
- ニコラス・ラティフィ
- アレクサンダー・アルボン
関連動画
関連商品
関連項目
- F1世界選手権
- フォーミュラ2(ワンメイクマシンの設計・供給を行っている)
- ルノー
- BMW
- トヨタ
- メルセデス・ベンツ
- 中嶋一貴(2007~2009年まで在籍)
- KERS(フライホイールを使った独自のものを開発。F1では使用しなかったが、アウディ・R18などに搭載された)
- 3
- 0pt