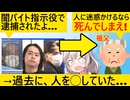概要
そもそも「ファンファーレ」とは、特定のイベント開始などの合図として演奏される音楽であり、競馬の場合、発走前に競走を盛り上げる音楽として流される。
流されるタイミングは国により異なるが、日本の場合、馬がゲート入りする直前のスターターが旗を振るタイミングで流される。
ファンファーレは吹奏楽編成となっていることが多いものの、電子音(シンセサイザー)によるものもある。
日本の競馬ファンファーレ
日本の競馬には中央競馬(JRA)と地方競馬があり、それぞれでファンファーレの扱いも異なっている。
中央競馬の場合、会場と競走の種類別で全21曲が用いられる。(参考:ファンファーレを音楽的に研究 )
)
ちなみに現在日本の競馬では発走前にファンファーレが鳴るようになっているが、少なくとも1959年(昭和34年)頃までは流れていなかったようである。
ラジオNIKKEI(当時の日本短波放送)の関係者が「いつスタートするのかわかりにくい」の一言がきっかけで、独自に中継放送でエドアルト・シュトラウスが作曲したポルカ「テープは切られた」を流したところ、競馬会から好感を得られ競馬場内でも流れるようになり、その後1986年から1988年の間に現在の各競馬場でおなじみのファンファーレが流れるようになった。
| 競馬場 | 平地競走 | 障害競走 | |||
| 一般競走・特別競走・ GI以外の重賞競走 |
GI競走 | 特定レース限定 | |||
| 札幌・函館 | 全3曲 作曲:鷺巣詩郎 | (なし) | (なし) | (なし) | |
| 福島・新潟 | 全3曲 作曲:服部克久 | 作曲:すぎやまこういち ※福島では開催なし ※新潟は代替開催のみ |
(なし) | 全2曲 (「GI以外」「GI」) 作曲:三枝成彰 |
|
| 中山・東京 | 全3曲 作曲:すぎやまこういち | (なし) | |||
| 中京・小倉 | 全3曲 作曲:川口真 | 作曲:宮川泰 ※小倉では開催なし |
名鉄杯限定(中京) | ||
| 京都・阪神 | 全3曲 作曲:宮川泰 | 宝塚記念限定(阪神) 作曲:早川太海(公募) |
|||
なお、あくまでも上記は原則であり、代替開催の場合別会場のファンファーレが差し替えられたりすることもある。例: 2021~2023年の1回中京開催(京都金杯からきさらぎ賞までの週)は京都競馬場の改修の都合で、中京競馬場で開催されたが、通常であれば代替競馬場の中京・小倉のファンファーレが使用されるが、同時期の第3開催場が小倉競馬場で、中京と小倉で同じファンファーレを使用すると混乱の元になることから、この時は中京競馬場では京都・阪神ファンファーレが流れた。(小倉競馬場との開催が被らない1回中京1〜4日目も同様。)(このような事例は過去には1994年の3月、この時も京都競馬場の改修の都合で阪神開催が中京に、本来の中京開催が小倉に振り分けられた時も阪神大賞典などでこのようなことが行われていた。sm40199905 )一方で2020年~2022年ローズステークスは阪神→中京であるが、この時は同時期に小倉競馬場の開催がないので同じファンファーレが流れる心配がない事から流れたのは中京・小倉重賞ファンファーレであった。
)一方で2020年~2022年ローズステークスは阪神→中京であるが、この時は同時期に小倉競馬場の開催がないので同じファンファーレが流れる心配がない事から流れたのは中京・小倉重賞ファンファーレであった。
変わったところでは2011年のマイルチャンピオンシップ南部杯は、東北地方太平洋沖地震の影響により盛岡競馬場が被災したこと(修繕自体はどうにかなったが、高額レースの開催には資金面で問題があった)、及びJRA側でも開催日程に浮きが生じていた(年間開催日数の上限が決まっているが、3月12日と13日が開催中止になっている。阪神競馬場で3月12日に開催予定だった分は3月21日に開催したが、3月13日分が未処理のままだった)ことの利害の一致に伴い東京競馬場で開催されたが、その際は岩手競馬JpnIのファンファーレを用いた)。また、2021年毎日王冠では、すぎやまこういち氏の死去に伴う追悼の意をこめ、GI競走のファンファーレを用いている。JpnI競走についてはGI競走と同じものを用いる(例: 2018年JBC)。
また例年5月に京都競馬場で行われている栗東ステークスは、地元の栗東市のさきらジュニアオーケストラによる演奏の音源が使われているが、2021年2022年の中京競馬場での代替開催においても京都・阪神の特別競走のファンファーレが流れた。
その他では競馬学校生の模擬レースやsm22217346 、ジョッキーベイビーズの決勝レース前のファンファーレもG1ファンファーレが使用されたりする。sm33981035
、ジョッキーベイビーズの決勝レース前のファンファーレもG1ファンファーレが使用されたりする。sm33981035
地方競馬の場合、主催者別にファンファーレを設けているが、扱いには差があり、普通競走(一般競走)用と特別競走用が同一の曲である主催者もある。また主催者が同一でも競馬場が異なると異なるファンファーレを採用していた事例もある(例:かつての岩手競馬=盛岡競馬場と水沢競馬場)。2024年現在、地方競馬の一主催者のファンファーレ曲数が最も多いのは岩手競馬(6曲、ただし2024年は全レースで旧ファンファーレを使用するため12曲)、最も少ないのは笠松競馬(2曲)である。また、JBC競走(2020年以降)、ダービーシリーズ(2023年廃止)およびは固有のファンファーレを用い、各競馬場のファンファーレは用いない。
- 普通競走用と特別競走用が同一の曲:船橋競馬、大井競馬、川崎競馬、金沢競馬、笠松競馬、園田競馬・姫路競馬
- ダートグレード競走(国内統一格付け)とそれ以外の重賞が別の曲:岩手競馬(JpnIII・JpnII・JpnIで別の曲[1])、船橋競馬(2011年より)、大井競馬(国内格付けと国際格付けで別の曲[2])、川崎競馬、名古屋競馬、園田競馬(2024年より)
| 競馬場 | 楽曲1 | 楽曲2 | 楽曲3 | 楽曲4 | 楽曲5 | 楽曲6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広 | 一般 | 特別 | 重賞 | ばんえい記念 | ||
| 門別 | 一般 | フレッシュチャレンジ | 特別 | 重賞 | ||
| 盛岡(ダート) | 一般 | 特別 | 重賞 | JpnIII | JpnII | JpnI |
| 盛岡(芝) | 一般 | 特別 | 重賞 | |||
| 水沢 | 一般 | 特別 | 重賞 | |||
| 浦和 | 一般 | 特別 | 準重賞 | 重賞 | ダートグレード | |
| 船橋 | 一般・特別 | 準重賞・重賞 | ダートグレード | |||
| 大井 | 一般・特別 | 左回り | 準重賞・重賞 | ダートグレード | 国際GI | |
| 川崎 | 一般・特別 | 準重賞 | 重賞 | ダートグレード | ||
| 名古屋 | 一般 | 特別 | 重賞 | ダートグレード | ||
| 笠松 | 一般・特別 | 重賞 | ||||
| 金沢 | 一般・特別 | 選抜 | 重賞 | |||
| 園田・姫路 | 一般・特別 | 重賞 | ナイターメイン | ダートグレード | ||
| 高知 | 一般 | 特別 | 交流 | 準重賞 | 重賞 | |
| 佐賀 | 一般 | 特別・特選 | 重賞 | |||
| 共通 | JBC |
ファンファーレは録音されたものが流されるのを基本としつつも、大きなレースでは生演奏を行う場合もある。中央競馬の場合、原則として古馬マイル戦及び古馬牝馬限定戦を除く全てのGIレースでファンファーレの生演奏が行われており、GIレース以外でもその地方の開催で最も大きいレース(札幌記念、七夕賞など)や、そのレース独自のファンファーレが設定されているレース(名鉄杯など)でファンファーレの生演奏が行われる場合がある。またヤングジョッキーシリーズのファイナルラウンドでは特別競走の生ファンファーレが演奏される。地方競馬でもJpnIレースを中心に生演奏が盛んに行われている。
関連動画
関連項目
脚注
- 4
- 0pt