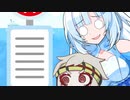株式会社関水金属は、東京都新宿区西落合に本社を置くKATOブランドでおなじみの鉄道模型メーカー。日本型Nゲージのパイオニアである。
概要
1957(昭和32)年に東京都文京区にて創業した。当時は金型屋としての性格が強かったが、1965(昭和40)年に日本初のNゲージ鉄道模型であるC50とオハ31系を売り出して以降はプラスチック製を専門とする鉄道模型メーカーとして活動するようになった。
自社製に対するこだわりが強く、車体から動力車のモーターやら歯車まで全て自社設計となっている。また、設計についても謎の特許技術を駆使して行っているため、時には実車が間違っている模型の方がかっこいいと言われることもある。これにより製品価格も他社より抑えられている。
また、TOMIXに比べて「新しい技術や仕様の導入に積極的」という側面がある。たとえばN700系新幹線で全周幌を再現すべく、かなり特殊な連結 機能つきの幌を導入してみたり、いわゆる「振り子式車両」や「車体傾斜装置つき車両」を再現するためにE351系や885系の台車に傾斜機能をつけたり等。(後者の機構はKATOが特許を取っているため、他メーカーが追従できないという側面もある)
但しこれが必ずしも成功するかというとそうでもなく、 N700の全周幌は「リアルだけど扱いが難しい」ため後継車のN700Aでは採用されなかった。(幌が壊れての修理持ち込みがかなり多かったらしい) 車体傾斜装置にしても、カーブ走行時に車両を傾けて走る姿は確かに迫力があるのだが(傾斜の角度はかなりオーバーなのでリアリティがあるかと言われたら少し首を傾げるしかない)、なにぶん車体を無理矢理傾けるため、脱線の原因になったりもする。特にカント(傾斜)つきレールを走らせると、カントと振り子機構のダブルで傾斜するためかなり凄い角度になるし、S字カーブでは変な方向に車体がブレるので、正直危なっかしい。
総じて、良くも悪くも「進取派のKATO、保守的な設計のTOMIX」という方向性があることは否定できないだろう。
海外展開も積極的で、米国型、欧州型、英国型のいずれも発売している。アメリカには現地事務所としてシカゴに「KATO USA」を有するが、いずれもMADE IN JAPANにこだわっており、日本国内で購入できるものは逆輸入品の扱いとなっている。台湾新幹線の車両も発売している(日本未発売)。
最近では初めての人でも楽しめるような製品構成が多くなっており、数年前には見られなかった関連商品を載せるといった気遣いもなされるようになった。
ラインナップ
車両
主力製品で、一番力を入れてるだけあって先述の通りの高品質を誇る。最近では「マイ・Nゲージを手に入れよう!」やら「線路に載せて出発進行!」といったキャッチフレーズを掲げ、初めての人でも安くて気軽に始められるような形態で売り出す事が多くなってきている。また、人気商品は「ベストセレクション」として再生産の頻度を高めたりだれでも手軽に手に取れるような製品構成で送り出すようにしている。
模型の仕様としてライバルのTOMIXとの大きな違いは、ユーザー取り付けパーツ等の少なさが挙げられる。特に最近のものではReady to Runを謳い、ユーザー取り付けパーツ等一切なしで買ってきてすぐ走らせられる、というものすらある程。但しその結果、たとえばTOMIXではインレタになっていることが圧倒的に多い車番などが固定で印刷されているため、複数編成を同時に走らせると「全部同じ車番」ということになる。このあたりは手軽さ(KATO)かリアリティ(TOMIX)か、の択一とも言える。
また、TOMIXは長編成(だいたい10両を超えたあたり)からは編成にモーター車を2両組み込むことが多いが、KATOは原則としてモーター1両での商品構成になっている。(東北新幹線E2系+山形新幹線E3系のように別セットの併結は流石にモーター2両での運転になる) そのためコストが抑えられて安価で購入できるし、動力車が協調できずトラブルになる心配がない反面、勾配がきつい等の走行条件では不理になることがある。(但しモーター車単体での出力は大抵の場合KATOのほうが高いので、走行性能がTOMIXの半分しかない、ということはない)
他に、概要にも書かれているように「実車より模型のほうがかっこいい」ということもしばしばある。そのため、前述の車番の問題もあり、リアリティを追求したい人にはあまりお勧めできないだろう。
造形としても、「模型として現実的にするための妥協」が見られることがある。極端に細かくなるパーツをオーバースケールで表現することで強度を確保したり、くどくなりすぎるモールドを一部廃したり等。
KATO製品を扱う上で若干注意すべきは、室内灯、ボディマウント型カプラー等が本当に独自規格であることが挙げられる。特に室内灯ユニットは、比較的互換性のあるTOMIX・グリーンマックス・マイクロエースとは大幅に違う仕様になっている。ボディマウント型カプラーにしても、マイクロエースや一部のグリーンマックス製品のようにTOMIXのボディマウント型カプラーを使える、ということは無い。まあ他社製カプラーや室内灯に勝手に互換性持たせてるグリーンマックスやマイクロエースはそれはそれでどうなんだって話かもしれないけど。
103系、20系気動車など、ライトのつかない古くからの製品も製造を継続しているのが特徴で、近年では「KOKUDEN」「LOCAL-SEN」といったダサい親しみやすい愛称をつけ、パッケージを簡素にする一方で価格を特に抑え、年少者の鉄道模型への敷居を低くするのに貢献している。
貨車製品も、1970年代までに発売された製品は一律税抜き500円という、21世紀の今となっては驚異の価格で販売され続けている。コンテナ車のコンテナが一体成型で積み替えられない点、全体的にオーバースケールである点など、今となっては見劣りする点もあるが、気軽に長編成にトライすることができる。
完成品の他にもAssy(アッシィー)パーツとして車体・台車・動力ユニットなどの部品を単体で販売しており、改造派からは好評で迎えられている。とくにクーラーや台車といった汎用品は人気が高く、発売開始直後に完売した例が数えきれないほどある。ちなみに昔は動力ユニットのネジや車体のガラス単体といった細かい部品も分売されていたとか。
代表製品:D51・C62・EF65・EF510・103系・E231系・オハ31系・24系25形・コキ10000系・コキ104系・チビロコ(ポケットラインシリーズ)
線路
ユニトラックとして、単線線路・複線線路・高架線路・特殊線路など某ライバル会社ほどではないが豊富なラインナップを取り揃えている。複線プレート線路「俺の立場は…?」
レイアウトへの固定を前提しない組み立て式線路としては、発売が1980年代に入ってからとやや出遅れたものの、リアルな狭い複線間隔、当初からポイントモーターを内蔵式とする、4番ポイントはネジ交換だけで選択式と非選択式を切り替えられる(DCCへの発展が簡単)などの特徴をもつ。TOMIXがファイントラックシリーズを始めるまでは、クロスレールの種類もユニトラックのほうが多かった。
また、フレキシブル線路をはじめとする固定式線路もまだまだ生産しており、ユニトラックと相互利用ができるため支持を得ている。
ストラクチャー
ストラクチャーといっても、当初はホームや詰所といった鉄道施設を中心としたラインナップであったが、複線プレート線路を送り出してからはジオタウンと称して、住宅、ビル、道路といったものを売り出すようになった。
ジオタウンは道路も含めたトータルシステムとして開発され、建物類もその規格に則って設計されている。そのため買ってきて並べるだけで、常設のレイアウトを持たなくても、簡単にリアルな都市の再現ができる。これは、ユニトラムシリーズにも引き継がれている。
歴史
1957(昭和32)年 有限会社関水金属彫刻舎として創立
1959(昭和34)年 東京都新宿区に本社を移転
1965(昭和40)年 日本初のNゲージ鉄道模型C50・オハ31系発売
1980(昭和55)年 株式会社カトー設立
関連商品
関連コミュニティー
関連項目
外部リンク
- 5
- 0pt