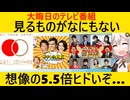- ほめる
(2) - 掲示板を見る
(24) - その他
九九式艦上爆撃機(きゅうきゅうしきかんじょうばくげきき)とは、大日本帝国海軍が運用していた急降下爆撃機である。
通称は「九九式艦爆」、「九九艦爆」。
概要
ドイツの多用途機He70を参考にして愛知航空機が設計・製造した。
全金属単葉機となり前代の九六艦爆に比べると大幅に近代化した機体となる。
外観上の特徴として固定脚が挙げられるか。少なくとも零戦と見間違えることはないはず。
正式採用の時期を考えると固定脚はやや時代遅れであったかもしれないが(1937年に正式採用された九七艦攻は既に引き込み脚であった)、製造・整備のしやすさ、急降下爆撃の際ダイブブレーキとしても作用する、ということから悪い選択ではなかったと思われる。海軍も堅実な設計を求めていたし。
そんな九九艦爆は、太平洋戦争において零戦・九七艦攻と共に帝国海軍機動部隊の主力として活躍する。
特に、戦争前期は高い技量を持ったパイロット達によって多大な戦果を上げており、最も多くの連合軍艦船を撃沈した爆撃機と言われる。
ちなみにパイロットの技量の高さの象徴としてよく挙げられるセイロン沖海戦では、英空母ハーミーズに対して命中率83%、英重巡コーンウォール、ドーセットシャーに対しては命中率88%、と人間離れした記録を残したほどである。(急降下爆撃の命中率は平均20%あればいいと言われていた、との話がある)
だが、そんな高い技量を持ったパイロットであっても撃墜されることは免れない。
九九艦爆は運動性・航続距離こそ高水準を誇っていたが、防御に関しては所謂「紙装甲」のため対空砲火・敵戦闘機の迎撃には脆く、太平洋戦争初期から少なくない損害を出していた。
加えて米海軍は新型機の投入やレーダー・VT信管などを用いた防空体制を充実させていったため、九九艦爆は撃墜される数が次第に増加。
帝国海軍もエンジンの改良などで性能向上に努めたがもはや焼け石に水であり、パイロットからは「九九式棺桶」「窮窮艦爆」などの不名誉なあだ名を付けられた。
後継機として「彗星」が開発されていたものの開発が遅れに遅れ、結局終戦まで九九艦爆は使われ続けた。特攻機として使われた機体も多かったようだ。
九九艦爆は、太平洋戦争前期の帝国海軍の快進撃を支えた名機であることに疑問を差し挟む余地は無いが、後期は悲惨な境遇にあった。
本機は帝国海軍の栄光と敗北を体現した航空機であると言えるのではないだろうか。
関連動画
関連静画
関連商品
関連コミュニティ
関連項目
掲示板
-
22 ななしのよっしん
2020/09/29(火) 12:32:19 ID: VxWPqXWwB9
エンタープライズやヨークタウンの例見る限り全然致命的になったように見えないんだけどな
魚雷当てない限り米空母はびくともしない -
👍1👎0
-
23 ななしのよっしん
2023/04/06(木) 13:00:45 ID: rWtkaIQXwb
インデペンデンス級のプリンストンとか、レイテ沖海戦で日本軍爆撃機一機の爆弾から誘爆引き起こして沈んでるがな
-
👍0👎1
-
24 ななしのよっしん
2023/09/14(木) 23:56:28 ID: VxWPqXWwB9
軽巡改装の軽空母にラッキーパンチ当てただけの例持ち出されても困るんだが
-
👍1👎0
おすすめトレンド
ニコニ広告で宣伝された記事
急上昇ワード改
- 74
- 13
- 1
- 72
- 7,735
最終更新:2025/12/18(木) 03:00
- 43
- 75
- 291
- 180
- 93
最終更新:2025/12/18(木) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。