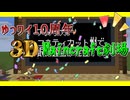- ほめる
(6) - 掲示板を見る
(19) - その他
比較言語学とは、ある語族に属する諸言語を比較し、そこから得られるデータをもとにそれらすべての言語の源である祖語を再建する学問のことである。
概要
一般的に比較言語学といえば印欧語比較言語学 (G. indogermanische Sprachwissenschaft) のことを指す。他にもセム語の比較言語学もあるが、一番研究が進んでいるのはやはり印欧語比較言語学であろう。
ここでは印欧語比較言語学について説明する。
印欧語比較言語学は印欧祖語(Proto-Indo-European: PIE)を再建する学問である。
ヨーロッパの人々は古来より自分たちの周辺の言語が似通っているということは気づいていた。ギリシアのプラトーンやローマのワッローらはそのことを本で言及している。
しかし、中世に入ると、自分たちの周辺の言語が似ているのは当たり前だという風潮が浸透した。その理由はキリスト教の浸透である。中世ではキリスト教の教えは絶対であるという考えを持っていた。そのため、なぜ似通った言語があるのかという疑問は、バベルの塔の神話によって説明されるようになってしまった。
また、このころは全ての言語の起源はヘブライ語であるといった誤った考えが広まっており、中世の学者全ては我らの言語の起源はヘブライ語であると信じて疑わなかった(このヘブライ語起源説を最初に唱えたのはかの『神の国』で有名なアウグスティヌスである)。
しかし、この考えが変わり始めるきっかけとなったのはサンスクリット語の発見である。サンスクリット語は2000年前もの昔の言語であるが、単語や文法、さらには屈折語尾等が遠く離れたラテン語やギリシア語と酷似していた。彼らにとって距離的にも空間的にもかなり離れたアジアの地に、彼らの言語と似通った言語が存在していたことは衝撃であった。
そして、近代に入ってこの学問が起こるきっかけとなったものがある。それはウィリアム・ジョウンズ(1746~1794)によるスピーチである。ジョウンズは、イギリスがインドへの支配を着実に固めている時に判事としてカルカッタにやってきたイギリス人である。彼は判事を職業としていたが、実はれっきとした言語学者であり、アヴェスター語の文法書を出すなど盛んに学術行動をしていた。
彼はインドに着任した後、インドの古代言語であるサンスクリット語に興味を抱き、それを研究していくうちに彼にある疑問が浮かんだ。それは、サンスクリット語とヨーロッパではなされている言語は実は「共通の源」(Common source)から発しているではないかという疑問であった。
彼はそのことをアジア研究会(インドに来てすぐジョウンズが設立した研究会)の3周年記念大会のスピーチで発表した。このスピーチはアジア研究会の機関紙である『アジア研究会』にのったことでヨーロッパの学問に多大なる影響を与えた。
だが、残念なことに彼の祖国であるイギリスでは彼の着想が根付かなかった。彼の着想が注目され、その着想を根付かせ、一気に進展させたのはドイツと北欧の人々であった。
その後、研究は一気に進み、音韻論・形態論などの分野が再建されるに至っている。いまでも研究がなされているものの、社会言語学や生成文法などのメジャーな言語学の陰に隠れ、あまり人気のない学問となってしまっているのが現状である。
比較言語学はドイツ・フランス・北欧で盛んに行われていたため、比較言語学を勉強しようとするならばドイツ語やフランス語などが読めなければ話にならない状態である。英語で書かれたものも多く存在するが、やはり比較言語学後進国であるため内容などが良いとは全く言い切れない事情がある。そのため、比較言語学を勉強しようと思うのならドイツ語やフランス語が読めるようにならなければならないだろう。
著明な印欧語比較言語学者
様々な有名な学者がいるが、数が多いため書ききれない。そのため、かなり著明な学者に限り記載した。
フリードリヒ・シュレーゲル (Friedrich Schlegel 1772-1829)・・・ドイツ人。1808年に『インド人の言語と知恵について』を刊行。序文では上記のジョウンズの講演について触れられている。
フランツ・ボップ(Franz Bopp 1791-1867)・・・ドイツ人。1816年に刊行した『ギリシア語・ラテン語・ペルシア語・ゲルマン語と比較したサンスクリットの動詞活用組織について』が注目され、印欧語比較言語学が独立の学問として成立する基礎となった。
ラスムス・ラスク(Rasmus Rask 1787-1832)・・・デンマーク人。実は「グリムの法則」を発見した最初の人物であるが、彼は論文をドイツ語ではなく、デンマーク語で書いたため、その論文『古ノルド語あるいはアイスランド語の起源の研究』(1814年提出、1818年刊行)はあまり注目されなかった。その結果「グリムの法則」の発見の名誉はグリムに奪われてしまったのである。
ヤーコプ・グリム(Jacob Grimm 1785-1863)・・・ドイツ人。「グリム童話」で有名なグリム兄弟の兄である。彼はれっきとした印欧語比較言語学者であり、著書『ドイツ語文法』の1822年改版においてかの有名な「グリムの法則」を記したことで、この法則に名が冠されることとなった。
アウグスト・シュライヒャー(August Schleicher 1821-1868)・・・ドイツ人。再建形を用いて印欧祖語で寓話を書こうと試みた最初で最後の学者である。彼は「馬と羊たち」という寓話を印欧祖語で書いたが、結局失敗してしまった。しかし、彼は印欧語比較言語学の基礎を作り上げた人物であり、この失敗だけを取り上げて彼を批判するのは的外れもいいところであろう。
フェルディナン・ドゥ・ソシュール(Ferdinad de Saussure 1857-1913)・・・フランス人。かの有名な『一般言語学講義』のソシュールである。彼は印欧語比較言語学者の中でももっとも素晴らしい人物であったが、ドイツで、現在で言うアカハラをうけ、その研究をやめてしまった。彼の考えの中でも最も有名なのが「喉音理論」(ラリンガル理論)であり、この考えは当時は否定されていたが、今では印欧語比較言語学の常識となっている。
エドゥアルト・ジーファース(Eduard Sievers 1850-1932)・・・ドイツ人。
ホルガー・ペーザーセン(Holger pedersen 1867-1953)・・・デンマーク人
ヘルマン・メラー(Hermann Möller 1850-1923)・・・デンマーク人。当時酷評されていたソシュールの「喉音理論」に注目し、これを支持し、ソシュールの穴を修正しながら「喉音理論」を進展させた。
エドガー・ハワード・スタートヴァント(Edger Howard Sturtevant 1875-1952)・・・アメリカ人
イェジィー・クリウォヴィッチ(Jerzy Kuryłowicz 1895-1978)・・・ポーランド人。ヒッタイト語でḫで表される音はソシュールが「喉音理論」で言及していた音であるということを論文で指摘した。
エミル・バンヴェニスト(Èmile Benveniste 1902-1976)・・・フランス人。メイエの弟子
オズワルド・セメレーニ(Oswald John Louis Szemerény 1913- 1996)・・・ハンガリー人。彼の著書は印欧語比較言語学を勉強する際には参考になるであろう。
高津春繁(こうづ はるしげ 1908-73)・・・日本人。彼は日本語で印欧語比較言語学の本を書いた人物である。今は絶版で手に入れられないかもしれないが、印欧語比較言語学を学ぶなら是非とも入手しておきたい書物である。ただし、書かれた時代が古いため旧字体などが頻繁に現れ読みにくいのと、内容が少し古いため間違っているところも多々あるところ、そしてなにより絶版であるため入手が困難であること、値段が高いことが欠点であろう。
アンドレ・マルティネ(André Martinet 1908-1999)・・・フランス人。彼の著作の日本語訳があり、学ぼうとする者は必読であろう。
関連項目
- 印欧語比較言語学
- グリムの法則
- フェルディナン・ド・ソシュール
- インド・ヨーロッパ語族(印欧語族)
- 言語学
掲示板
-
17 ななしのよっしん
2019/11/01(金) 01:28:16 ID: kPgXk18Gj0
知っている限りだとポルトガル語(ヨーロッパ)には2人称複数の活用自体はあるけど、既に指摘されているように2人称単数の敬称として使う場合がほとんどで、そのまま「君たち」という意味で使っているのは北部の田舎の人たちだけ。
隣のスペイン語(ヨーロッパ)の2人称複数はそのまま「君たち」という意味で日常的に使っていたはず。
-
👍0👎0
-
18 ななしのよっしん
2022/01/05(水) 07:03:15 ID: hrffuQZLxq
何十年も前に否定された古い説とかが普通に市井で語られることがあるから言語学者にはもっと積極的に最新の説を広めて欲しいと思う
でも言語学に興味ある人なんか少ないだろうなあ -
👍1👎0
-
19 ななしのよっしん
2022/07/28(木) 07:13:21 ID: dEZHA5Qruk
比較言語学は「うちの民族はあいつらよりも上」って選民思想になりやすい学問だからな
-
👍2👎0
おすすめトレンド
ニコニ広告で宣伝された記事
急上昇ワード改
- 159
- 350
- 217
- 21
- 77
最終更新:2025/12/14(日) 08:00
- 43
- 172
- 57
- 282
- 110
最終更新:2025/12/14(日) 08:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。