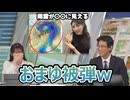笠戸(海防艦)とは、大東亜戦争中に大日本帝國海軍が建造・運用した択捉型海防艦14番艦である。1944年2月17日竣工。艦首を2回も喪失する大被害を受けながらも終戦まで戦い抜いた。1948年9月25日に解体完了。
概要
艦名の由来は山口県下松市の笠戸島から。瀬戸内海国立公園の一部で、島の半分は国有林に指定されている自然豊かな島。笠戸の名を持つのは本艦で2代目である。先代は日露戦争でロシア義勇艦隊から拿捕したカザンを改称した笠戸丸。微妙に名前が異なっているからか笠戸が就役した後も笠戸丸の名で運用され続けている。
択捉型(甲型海防艦)は占守型をベースに簡略化を進めた戦時急造型である。開戦前、帝國陸海軍は東南アジアの欧米植民地の攻略を企図していたが、占領後に本土・南方間を往来する輸送船の護衛兵力が不足している事に気付く。艦隊決戦を重視する方針上、駆逐艦を護衛に割く訳には行かないので北方警備用の占守型海防艦をベースに新型護衛艦艇を設計。それが択捉型であった。1941年8月に実行へと移されたマル急計画において択捉型14隻の建造が決定し、基本設計は10月10日に完成。
戦時急造型とは言っても占守型を若干簡略化した程度で、相違点と言えば舵を量産に適した吊舵へ変更、艦首の直線化、居住設備の簡易化、爆雷搭載数の増加(18個→36個)など実に微々たるもの。機関に関しては22号10型ディーゼル2基2軸から全く変わっていないので同じ速力と航続距離だった。要は複雑な構造である占守型からあまり変わってない訳である。また、南方航路で運用する想定でありながら何故か暖房用の補助缶を搭載していたり、旧式駆逐艦から転用した平射砲は仰角が33度しかないため対空戦闘に向かないなど問題点も多く抱える。
一応工期は占守型の約9万から約7万(56%)にまで削減されたが、戦時急造型として見ると不満が残る結果となってしまう(1隻完成させるのに平均11ヶ月を要する)。加えて開戦前は海防艦の役割が明確ではなかった事もあり、対空兵装は占守型と同じ25mm連装機銃2基のみ、電探も大変貧弱と改善の余地を多く残し、後に順次強化されたとはいえ兵装が戦況に即していなかった。このため、より一層簡略化と対空・対潜能力向上を推し進めた御蔵型、日振型、鵜来型が誕生していく事となる。それでもノウハウの蓄積により択捉型最後の就役艦である笠戸は同級中最短の201日で完成している。ちなみに最長は1番艦択捉の418日。択捉型は計14隻建造され、このうち8隻が戦没、6隻が終戦まで生き残った。占守型とあまり変わっていないからか艦艇類別等級によると占守型扱いとなっている。
笠戸は最後に就役したためこれまでの戦訓が取り入れられ、就役時から電探を装備。後の改装工事で2番12cm単装平射砲を撤去して25mm連装機銃を2基から5基に増備、爆雷投下台を投下軌条に換装、対潜迫撃砲や逆探装置を新たに装備、艦橋窓に防弾板を装着するといった小改良が見受けられる。
要目は排水量870トン、全長77.7m、最大幅9.1m、喫水3m、機関出力4200馬力、最大速力19.7ノット、乗員150名。兵装45口径12cm単装平射砲3基、九四式爆雷投射機1基、爆雷投下軌条2基、爆雷36個、掃海具。
艦歴
1941年8月より開始されたマル急計画において第330号艦の仮称で建造が決定。建造予算は551万2000円であった。戦争も佳境に入った1943年8月10日に浦賀船渠にて起工、8月31日に笠戸と命名され、種別を海防艦、艦型を占守型と定められる。12月9日に進水式を迎え、1944年1月10日に川島信少佐が艤装員長へ就任。彼は第8号掃海艇の元副長であった。翌日より浦賀造船所内に艤装員事務所を設置して事務を開始する。そして2月27日に竣工。艤装員事務所を撤去するとともに川島少佐が艦長に着任、佐世保鎮守府所属の警備海防艦となり、海防艦の訓練を担当する呉鎮守府部隊呉防備戦隊へ部署した。
1944年2月29日に横須賀を出港、3月2日に佐伯へと入港して慣熟訓練を開始。乗組員の基礎力錬成に努める。18日間で一通り訓練を終えた笠戸は3月20日に連合艦隊へ転属となり、最初の護衛任務に従事するため3月30日に呉を出港、4月1日、淡路島の洲本へ寄港する。ここで横須賀に向かう東山丸、阿蘇山丸、能登丸と合流し、3隻を護衛して翌2日に洲本を出発。既に本土近海にも米潜水艦が出没し始めていたが何事も無く4月3日に横須賀へ辿り着いた。
その頃、中部太平洋では連合軍が反攻に転じており、トラック諸島とマリアナ諸島に対する空襲、並びにエニウェトクの失陥を受け、大本営は絶対国防圏をマリアナ諸島=中西部カロリン諸島の線まで後退させる事を決断。最前線の島となったマリアナ諸島に第14軍、第29軍、関東軍から抽出した部隊を送るため「松輸送」と呼ばれる緊急輸送作戦が開始され、笠戸は第14師団と第35師団の第一陣をパラオまで進出させる東松5号船団に加わる。
東松5号船団の護衛と1回目の艦首切断
4月7日午前3時30分、東山丸、阿蘇山丸、能登丸、三池丸で編成された東松5号船団を、第3護衛船団司令部を乗せた駆逐艦皐月(旗艦)、笠戸、満珠、第4号駆潜艇(第4号海防艦とする資料もある)の4隻が護衛して館山を出発。重要任務ゆえ輸送船は全て優秀船舶で占められていた。パラオに向かう途上で米機動部隊接近の報が入り、4月10日午前10時30分に父島の二見港へ退避。笠戸は湾口から敵潜が入ってこないよう僚艦とともに監視任務に就く。4月12日20時5分、満珠が発見した敵潜を追って皐月や第4号とともに父島を出撃するが、敵情を得られず翌13日午前6時30分に満珠と帰投。
4月18日13時50分から14時10分の間に笠戸、第4号、満珠が父島を出港、やや遅れて16時17分に船団が皐月を伴って出港してパラオを目指す。そして4月24日午前11時15分に無事パラオへ到着して任務を完了させた。船団が兵員と物資を急速揚陸させている間はパラオ周辺の対潜哨戒に従事する。
4月26日16時40分、引き揚げる民間人や軍人等を乗せて東松5号船団がパラオを出発、これを笠戸、皐月、満珠の3隻で護衛する。ところが帰路には思わぬ災難が待ち構えていた。4月27日午前2時50分、米潜水艦トリガーが船団を雷撃して阿蘇山丸と三池丸が被雷。笠戸は救援のため三池丸のもとに向かうが、午前3時5分、二度目の雷撃で艦首に魚雷が直撃。中破させられて乗組員8名が死亡、2名が重傷を負う。東山丸にも魚雷が命中していたが幸い不発だった。三池丸は漏れ出た燃料によって火だるまと化して船体放棄(翌日沈没)。阿蘇山丸と笠戸はかろうじて沈没を免れ、浅瀬に囲まれて潜水艦が活動出来ないコッソル水道に退避。下手人のトリガーは第4号駆潜艇の爆雷投下によって撃退された。翌28日に船団はパラオへ反転入港。5月1日から20日にかけて、現地のパラオ工作部で損傷した艦首を切断して仮設艦首を取り付ける応急修理を行う。5月22日に輸送する陸軍部隊を乗せてパラオを出港、翌23日にヤップ島へ到着して部隊を揚陸し、5月24日にパラオへ帰投した。
5月26日午前6時、特設駆潜艇瑞鷹丸とともに特設運送船興新丸を護衛してパラオを出港。5月28日16時30分にダバオへ到着し、現地で新たに笠置山丸を加えて5月30日に出港、6月4日にマニラへ到着した。キャビテ軍港で短時間の応急修理を行った後、興新丸のみで編成されたマタ22A船団を護衛してマニラを出発。6月9日に台湾南東部高雄へ寄港する。6月11日、輸送船10隻で構成されたタモ20A船団を第58号駆潜艇、第90号特務駆潜艇、特設砲艦長白山丸、砲艦興津とともに護衛して高雄を出港、6月14日に興津が護衛より離脱したが、道中何事も無く6月17日に門司へ入港。本格的な修理を受けるため同日中に佐世保へと回航された。しかし何らかの事情で佐世保では修理が行えず、やむなく6月23日に佐世保を出港して翌日釜山へ入港。朝鮮重工の釜山船渠にて入渠修理を受けた。修理中の8月20日、軽巡五十鈴を旗艦に据えた対潜専門部隊の第31戦隊へ編入。
8月24日修理完了。8月28日に鎮海を発って同日中に佐世保へ戻った後、リハビリのため9月3日に呉防備戦隊に編入され、翌4日から9月29日まで佐伯湾で訓練に従事。訓練を終えた笠戸は9月30日に呉へと回航し、10月4日に第1海上護衛隊に転属して早速次の護衛任務に臨む事となる。10月10日に門司を出港、同日17時にモマ05船団が集結中の伊万里に到着して合流する。
東南アジア方面での活動
10月16日18時20分、10隻の輸送船で編成されたマニラ行きのモマ05船団を、駆潜艇5隻(第17号、第18号、第23号、第27号、第28号)とともに護衛して伊万里を出港。各輸送船は、アメリカ軍の来攻が近いフィリピンに送る第54独立混成旅団約1万名を積載していた。道中の10月20日に笠戸、三宅、干珠、満珠の4隻で第21海防隊が新編される。翌21日16時にモマ05船団は高雄へ寄港。ここで笠戸は護衛から離脱し、10月22日正午に馬公へ移動したのち澎湖諸島近海で対潜掃討任務に従事。10月26日午前4時に馬公へ帰投した。翌27日午前8時、馬公へ入港したミ23船団から特設工作艦白沙が切り離され、笠戸と三宅は白沙をシンガポールまで護衛するよう命じられる。10月29日に馬公を出発し、11月12日にシンガポールへの進出を果たす。
11月17日17時10分、練習巡洋艦香椎、海防艦満珠、鵜来、能美、三宅、第17号、第51号、機雷敷設艇新井埼とともにヒ80船団(加入船舶7隻)を護衛して出発。11月20日午前6時にサンジャックから応援に来た第23号海防艦が護衛に加わり、代わりに午後12時40分に第17号がサイゴンへ向かうため護衛を離脱。翌21日午前2時35分には視界不良が原因で船団が二つに分かれてしまうトラブルがあったものの午前11時55分に問題なく合流。11月22日午前11時50分に陸軍徴用船日南丸が機関故障を訴えて船団より落伍、鵜来が護衛に寄り添うが18時15分に復帰する。11月24日13時、日南丸、満珠、第51号がバンフォン湾に向かうため離脱(第51号のみ護衛に復帰)。11月28日午前9時30分に新井埼、良栄丸、有馬山丸が高雄に向かうため離脱した。そして被害皆無のまま12月2日早朝にヒ80船団は六連へ到着、翌日門司へ入港して護衛任務を終了する。
12月25日、笠戸は第21海防隊から除かれて第12航空艦隊千島方面根拠地隊へ転属。
12月26日、シンガポールから門司を目指す途上で基隆に退避していたヒ82船団(ぱれんばん丸1隻のみ)を海防艦久米、択捉、昭南、第9号、第19号とともに護衛して出発。ヒ82船団は出発時こそ5隻いたが、インドシナ沖で米潜フラッシャーの襲撃を受けて3隻が一挙に撃沈され、生き残った橋立丸も高雄で分離していたため現在は1隻のみとなっていた。笠戸は船団全滅を避ける目的で護衛に加えられたと思われる。
1945年1月1日午前9時に上海南東の舟山列島を出発、1月3日に舟山北北東の泗礁山泊地に到着して仮泊し、翌4日午前8時30分に出発。危険な東シナ海を一気に突破、1月8日18時4分に六連へ無事帰投する。その後は佐世保工廠に入渠して整備を受けた。
狭まる包囲下、日本近海での船団護衛
1月12日、アメリカ軍は南シナ海へ機動部隊を侵入させ(グラティテュード作戦)、16日まで香港及びインドシナ方面の船舶を盲爆、ヒ86船団やヒ87船団が壊滅させられてしまう。とりわけ輸送船とタンカーへの被害が大きく、また米機動部隊の南シナ海侵入を許した事は南方航路の閉鎖が間近に迫っている事を意味していた。そこで帝國海軍は生き残っているタンカーをかき集めて「特攻輸送」を企図した南号作戦を1月20日に発動。
2月3日、鎮海警備府電令作第6号により笠戸、沖縄、択捉の3隻は黒山島部隊の指揮下に入り、南号作戦の一環でシンガポールから本土に向かって帰投中のヒ88A船団の直接及び間接援護の命を受ける。これに伴って午前2時に佐世保を出港し、六連と黒山群島を経由して2月5日に駆逐艦樫、杉、第41号海防艦が護衛するヒ88A船団(加入船舶は2TL型戦時標準船せりあ丸のみ)と合流を果たし、2月6日15時に加徳水道へ到着。現地で海防艦沖縄が護衛に加わった。ここまで来れば本土はもう目前である。2月7日午前5時に加徳水道を出発、道中で択捉を護衛に加えながら16時30分にヒ88A船団は六連へと到着。せりあ丸が運んできた1万7000トンの航空機用ガソリンは和歌山県下津港の石油基地に揚陸されて南号作戦の第一陣は見事成功に終わった。
2月10日正午、択捉、沖縄、第39号とともに今度はモタ35船団(加入船舶2隻)を護衛して門司を出港。2月14日14時に泗礁山泊地へ到着した際に笠戸と択捉が護衛より離脱、代わりに門司へ向かっている第108号輸送艦、陸軍機動第101号艇で編成されたタモ42船団を護衛し、2月20日午前0時50分に青島外港で仮泊。2月23日17時に門司へ帰投した。
この護衛任務完了を機に笠戸は本来の任地である千島列島方面へ転戦する事になり、2月25日から3月6日16時まで舞鶴に寄港した後、3月8日15時に大湊へと到着。4月6日、海防艦国後とともに特設運送船長和丸、陸軍輸送船紅海丸からなるキ602船団を護衛して大湊を出港。翌7日午前4時55分に浮上中の敵潜を発見・交戦するが取り逃がしている。道中の4月10日、笠戸は大湊警備府部隊第104戦隊に転属し、宗谷防備部隊に部署。4月13日午前2時に幌筵島片岡湾に到着して護衛任務終了。4月19日13時、紅海丸1隻で編成されたツ901船団を護衛して出発し、4月25日に釧路へ寄港する。本来であればここで護衛完了であったが、第104戦隊司令部より紅海丸を津軽海峡まで護衛するよう命じられ、翌26日20時にツ901船団と釧路を発つ。4月28日に紅海丸を函館へと護送した。航続距離の関係から東北以北には米軍機が出現せず、跳梁跋扈する潜水艦のみが主な脅威だったため他の場所と比べるとやや安全と言えた。
5月7日14時52分、千島列島に向かうキ704船団(加入船舶4隻)を福江、択捉とともに護衛して小樽を出港。5月14日18時15分に目的地の片岡湾へ到着した。5月19日午前1時30分、帰路も択捉や福江とヲ904船団を護衛して片岡湾を出発、5月24日21時45分に小樽へ帰投する。続いて5月28日20時、陸軍部隊を乗せた2E型戦時標準貨物船安房丸、海軍一般徴用船北進丸で構成されたオ船団を護衛して小樽を出発、道中で稚内から出港してきた第47号海防艦が合流し、6月1日に千島列島中部の松輪島へ到着。護衛任務を終えると6月10日から17日にかけて北海道西方で対潜掃討に従事する。
2回目の艦首切断
6月22日午前1時、小樽沖で笠戸が8100m離れた先に潜む米潜水艦クレヴァルをソナーで探知、対するクレヴァルも笠戸を発見して夕雲型あるいは吹雪型駆逐艦と推測する。彼我の距離が縮まる中、先に仕掛けたのはクレヴァルだった。笠戸の正面から最後に残っていた魚雷2本を発射し、このうち1本が艦首に直撃して艦橋より前の艦首部分を喪するとともに大破、乗組員26名が戦死する。魚雷を使い果たしたクレヴァルはトドメを刺さずに逃走したため命からがら助かった。
翌23日に何とか小樽まで帰り着いた笠戸は小樽船渠に入渠、仮設艦首の取り付け工事を行う。6月26日、二代目艦長に川本源蔵少佐が着任。7月15日、米第38任務部隊所属の敵艦上機が小樽を空襲し、港内の笠戸、第47号、第55号海防艦が損傷。対空戦闘で笠戸の乗組員1名が戦死した。7月26日に仮設艦首の取り付け工事が完了。本格的な修理のため大湊への回航を待っている時に8月15日の終戦を迎える。
終戦後
1945年8月26日に自力で小樽を出港し、8月29日に佐世保へ入港。一応航行可能ではあったが復員輸送任務に適さないと判断され、9月10日に第4予備海防艦(廃棄予定の艦)に指定、海軍省の解体に伴って11月30日に除籍となる。1947年2月1日、佐世保地方復員局所管の行動不能艦艇となり、5月3日に二度目の除籍を迎える。
そして1948年5月31日から9月25日にかけて天草で解体された。
関連項目
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
おすすめトレンド
ニコニ広告で宣伝された記事
急上昇ワード改
- 117
- 250
- 56
- 549
- 4
最終更新:2025/12/16(火) 00:00
- 43
- 178
- 64
- 285
- 112
最終更新:2025/12/16(火) 00:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。