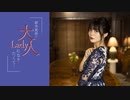ウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン(1908~2000)とは、20世紀に活躍した哲学者、論理学者である。
概要
論理実証主義批判によって形作られた意味論や存在論が、多大な影響を与えた人物である。
アメリカのオハイオ州アクロンに生まれる。バートランド・ラッセルに触発され、数学を専攻してオバーリン大学を卒業。その後ハーバード大学哲学科で博士号を取得。そのまま同校で教鞭をとり、1948年には教授へとなった。
クワインのとった立場はホーリズム(全体論)と呼ばれる。それまでの論理実証主義は、1つの命題はそれ単独で審議を確定できるとしていた。しかし命題そのものは他の命題とそれぞれ関係しあっており、ひとまとまりの体系を作っている。そのため、一つな実験や観察によって全体の中のどれでも改訂できる、全面的改訂可能論(デュエム・クワイン・テーゼ)が唱えられるのである。だから単独の命題だけで真偽を検証することはできない、とするのだ。
またそれまでの論理実証主義では、分析哲学が取り扱う言葉の意味や概念だけで決まる分析的真理、科学が取り扱う実際に確かめなくてはならない総合的真理、の2種類に真理は分けられるとしてきた。しかしクワインは実験の結果につじつまが合わない場合、分析的真理である矛盾律や排中律などの論理法則の方も変更されてしまう、としたのだ。例えば、光が研究の結果、粒子でも波でもあるため排中律を否定し「光には質量がある」が真でも偽でもある、とされたことである。
よってクワインは、すべての真理は総合的真理であり、論理実証主義に出る幕はもはやなく、経験論である科学を認識論である哲学に導入すべき、とする自然主義の立場をとったのである。
そしてクワインの哲学の重要な概念は「経験主義の2つのドグマ」である。これまで、分析的真理と総合的真理は明確に分かれているとするドグマ1、命題と事実は1対1で対応しているとするドグマ2、の二つが頑なに前提にされてきたが、それは単なる独断に過ぎない、とクワインは主張したのだ。つまり、繰り返しになるが、すべての真理は総合的真理であり、理論はたくさんの他の理論から成り立っているため観測結果である事実からつじつま合わせができてしまう、というのだ。
よって重要なのは理論の真偽ではなく、その理論が人間にとって有用か無用か、というネオプラグマティズムが新たに興隆したのであった。
またクワインは、翻訳の不確実性などほかにも重要な概念を導入しているので、時間があるときに調べてみよう。
関連商品
関連項目
- 0
- 0pt