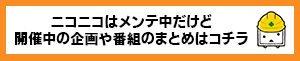概要
日本語において、音節が別の音に変化すること。大別して、イ音便、ウ音便、促音便、撥音便の4つがある。動詞連用形に顕著だが、音便は語中語末において起こり、語頭には起こらない。
音便の問題点はいくつかある。
1.どのように起こったか。
音便の起こった原因については諸説あるが、はっきりとしない。一応、*-CV>*-Vとなった結果とされているが、それでも説明のつかない変化も多く、*-CV>*-C'V>*-C'>-V'と見做した方が良いのではないかと言った考えもある。また、語によっては二つの音便形が現れるものもあり、特にハ行四段活用において、近畿方言と東国方言(例:買うて⇔買って)で異なる反映となっており、これらがなぜ違うのかも不明である。
2.音便の起こっていない単語と起こっている単語では何が違うのか。
音便の古い例では、櫂(かい)(<掻き、掻く)などがある。その他、語中語尾において、音便形の見える語は中央語、方言問わず多くあるが、そうでない語例えば「巻(まき)」がなぜ「*まい」となっていないのかといった問題である。また、音便は四段活用の連用形に起こり、なぜ同音である上二段活用の連用形(例:起きる、起きて)に起こらなかったのか、といった問題もある。
イ音便
音がイの音となるものを指す。
カ行四段活用(カ行五段活用)、ガ行四段活用(ガ行五段活用)の連用形+テ形、タ形で起こるほか、形容詞の連体形でも起こった。
- 書きて→書いて
- 咲きて→咲いて
- 割きて→割いて
- 泣きて→泣いて
- 剥ぎて→剥いで
- 急ぎて→急いで
- 高き(山)→高い(山)
- 美しき(女)→美しい(女)
なお、方言や古文体においては、サ行四段活用(サ行五段活用)でも起きる例がある。
ウ音便
音がウの音となるものを指す。近畿方言のハ行四段活用(ハ行五段活用)では、標準語で促音便となるものがウ音便となるのが普通である。また、同様に標準語の敬語体及び、近畿方言における形容詞の連用形でもウ音便となる例がある。
- 言ひて→言うて(→ゆーて)
- 早く→はやう(→はよう)
促音便
「ッ」となる音のことを促音便という。タ行四段活用、ハ行四段活用、ラ行四段活用の連用形+テ形、タ形に見られる。
- 立ちて→立って
- 買ひて→買って
- 貼りて→貼って
例外として、「行く」はカ行四段活用だが、促音便化する。
- 行きて→行って
撥音便
「ン」の音となるものを撥音便という。ナ行変格活用、マ行四段活用は連用形+テ形、タ形で撥音便となる。
- 噛みて→噛んで
- 死にて→死んで
また、名詞でも見られる。
関連項目
- 0
- 0pt