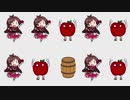バウムクーヘン(Baumkuchen)とは、ドイツ発祥の洋菓子である。
バームクーヘンと表記することも多い。
概要
バウムとはドイツ語で「木」、クーヘンとは(生クリーム等でデコレーションしない)「ケーキ」のことである。
通常は丸いドーナツ型をしており、何層にも重なった生地が特徴的。その層が木の年輪のように見える。
芯に生地をかけながら薄く焼き、それを何層にも重ねていく。
芯は回転するのでまんべんなく熱が通る訳である。
樹木の生命力を神聖視するヨーロッパの土着文化の影響からか、結婚式によく供されるらしい。同様に日本においても縁起物として引き出物・贈答用の高級洋菓子として広まった(昭和世代の外側から一枚ずつそーっと剥がしながら食べた経験はないだろうか)が、現在では薄くスライスされた煎餅サイズのものがスーパーやコンビニで気軽に手に入るなど、日本人の方がドイツ人よりもバウムクーヘンを食べているという話もあるくらいポピュラーな菓子である。
第一次世界大戦後、中国の青島から大阪市西区の収容所に戦争捕虜として抑留された民間のドイツ人菓子職人カール・ユーハイム(ユフハイム、 Karl Joseph Wilhelm Juchheim)によって日本に伝えられたとされる。日本政府は、近代国家としての成熟ぶりを内外に示すため、ドイツ人戦争捕虜たちを国際法に完全にのっとって丁重に扱った。そのため地域住民と収容所ドイツ人捕虜との交流は盛んで、多くのドイツ文化が同時に伝えられる中で、バウムクーヘンも日本に根付いていったのである。
トリビア
- ユーハイムは捕虜解放後はコレラが流行していた青島へ帰るのを断念して日本に留まる。銀座の喫茶店「カフェー・ユーロップ」に勤めた後は横浜に移り喫茶店を開いたが、わずか1年半後に関東大震災により店を失う。やむなく家族を連れて神戸の三宮に移り喫茶店「JUCHHEIM'S」を開くと、他の店がここから菓子を仕入れるほどの人気を博す(日本で初めてマロングラッセを出したのもここ)。
しかし第二次世界大戦中は物資不足のために菓子が作れなくなり、菓子工場はドイツ海軍用のパン工場となるが、空襲で罹災し閉鎖された。大戦が終結する1日前、ユーハイムは静養先の六甲山ホテルで妻エリーゼに看取られて安らかに息を引き取った。享年58歳。8年前の異常行動(ドイツで治療されて回復はしたが、以前の陽気さは失われ、働けなくなった)と医者の中風という所見から察するに、何らかの脳に関する疾患が死因と想われる。
その後ユーハイムの遺志を受け継ぐべくJUCHHEIM'Sの有志とエリーゼが立ち上げたのが、現在も日本を代表する洋菓子メーカーの一つ「ユーハイム」である。エリーゼは1971年に神戸で亡くなり、夫と共に芦屋で眠っている。
ちなみに戦時中に閉鎖された工場は終戦後白系ロシア人の菓子職人ヴァレンティン・F・モロゾフ(ユーハイムと双璧を成す神戸の洋菓子メーカー「モロゾフ」の前身である「神戸モロゾフ製菓」創業者フョードル・D・モロゾフの息子)が借り受け、自身の経営する「コスモポリタン製菓」(2006年廃業)の菓子と在日外国人用配給パンの製造を行った。 - 『新世紀エヴァンゲリオン』で碇シンジが惣流・アスカ・ラングレーと一緒にエヴァ弐号機に搭乗した際、「ドイツ語で考えなさいよ!」と要求したアスカに対し、「バ・・・バームクーヘン?」と返して怒られたのは余りにも有名である。うん、だいたいあってる。
- 『ドラえもん』に、「夢カセット」と言う道具のコンテンツの一つとして「バームクーヘンマン」というキャラが登場したことがある。
関連動画
関連項目
- 4
- 0pt
- ページ番号: 2864102
- リビジョン番号: 3226223
- 編集内容についての説明/コメント: