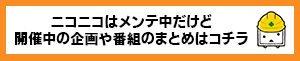彼岸花(ひがんばな)とは、秋に赤い花を咲かせる植物の名前である。
曖昧さ回避
概要
学名はLycoris radiataで、キジカクシ目ヒガンバナ科に分類される多年草。花は赤いことが多いが、稀に白みがかったものもある。
日本では9月中旬の彼岸のころに咲くため、彼岸花と呼ばれるようになったと考えられる。花が咲き終わった後に葉が伸び、翌年に葉は枯れる。
道のわきなどに生えていることが多いが、有毒性がある。ひどい場合は死に至る場合もあるので絶対に口にしないように。
この花は「死」「あの世」と合わせて語られることが多い。この由来については様々な説があるが、植物学者で千葉大学名誉教授の栗田子郎氏のサイト「草と木と花の博物誌(Webアーカイブ) 」内の「ヒガンバナの民俗・文化誌(Webアーカイブ)
」内の「ヒガンバナの民俗・文化誌(Webアーカイブ) 」に掲載されている以下の説がまとまっており詳しいので、引用する。
」に掲載されている以下の説がまとまっており詳しいので、引用する。
1) 奈良時代ないしは平安時代、救荒植物として九州に渡来した。
2) ミラ(ニラ)類のツルボの一種とみなしスミラ(スミレ、シミラ)と呼んだ。有毒性を強調するときはドクを頭に付けた。
3) スミラという名は『日葡辞書』に載るまで文献に残らなかったが、救荒植物として栽培し、四国、中国、近畿地方へと伝播して言った。このルートに沿ってさまざまなスミラ系の里呼び名が生まれた。この間、食糧にならない赤い花は注目されなかった。球根を太らせるために花茎が伸び始めると開花する前に切り落としていたかもしれない。また、大切な非常食ゆえ、意図的にタブーとし、表舞台には立たせなかったのかもしれない。
4) 室町時代、僧侶がヒガンバナの深紅の花を仏典に登場する曼珠沙華とみなし、積極的に寺院や墓地に移植して増やし、この花が庶民の目に留まるようになった。その結果、墓地に咲くヒガンバナが、当時布教のために盛んに描かれていた地獄草紙の地獄の炎を連想させ、僧侶の意図から離れてこの花を不吉なものと考えるようになったのかもしれない。
5) 江戸時代、飢饉は繰り返されたものの、農耕技術の発達や新田の開発により、救荒植物としての価値は次第に忘れられ、限られた地域の古老たちの記憶にとどまるにすぎなくなった。この過程で、不吉なものに対する恐れや好奇心から爆発的に里呼び名が増えていったのであろう。
栗田氏によると彼岸花はもともと中国大陸原産であり、何らかの原因で日本に渡来してきたとされる。
「救荒植物」というのは飢饉のときにのみ食べる植物のこと。水に晒してアクを抜けば、毒も抜ける(絶対に真似して食べないこと)。鎌倉~室町時代のあたりまではこの用途で使われていたと考察されている。
「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)とは、仏教で天にあるとされている花のこと。「神秘」「あの世」のようなイメージはここから来ているのかもしれない。室町時代から僧侶が積極的に寺院や墓地に植えるようになったとされている。
これが墓地というイメージもあって、「地獄草紙の地獄の炎」にもなぞらえるようになったと考察されている(地獄草紙の炎についてはこちら を参照)。
を参照)。
江戸時代には呼び名が増加していく。記録に残っている中でも最も多いとされているのは、「仏教」「死」「葬儀」にかかわるものである。ちなみに呼び名の種類は1000余に及んでおり、いかに多くの解釈がこの花にされているかを窺い知ることができる。
なお日本の彼岸花はほぼ全てが三倍体で、種子を残せないため球根で繁殖している。
フィクションの世界でもよく使われる花であり、ニコニコ静画のタグでも2018年現在で300件弱のイラストが投稿されている。
関連動画
関連静画
関連項目
- 2
- 0pt