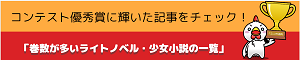放課後等デイサービス(ほうかごとう-)とは、児童福祉法を根拠法とする障害児通所支援事業である。
略称は「放デー」。
概要
障碍のある就学児を対象とする。
放課後や休日などに通所し、自立のための訓練や居場所づくりなどを行う。
対象となる障碍
身体障害、知的障害または精神に障害のある児童(発達障碍含む)が対象である。
障害者手帳などはあれば申請が通りやすくなるが、必須ではない。
法改正前は障碍の種類によって利用できる施設が限られていたが、現在は種類を問わず通所が可能である。
法律上はそうであっても、事業所によって受け入れられる児童や得意とする障碍の種類が異なるため、入所前に十分な調査と管理責任者との話し合いの上で決めれば安心である。
内容
事業所内では、児童は指導員と一緒に課題や遊びを行う。
内容や得意とする分野は事業所ごとに異なるが、以下に一例を示す。
ホームルーム
はじまりの会・帰りの会・○○タイム(○○には事業所の名前が入る)など、事業所によって名前は異なる。
学校の「朝の会」「帰りの会」とやることはほぼ同じだが、これも立派な療育である。
「あいさつをする」「きちんと座る」「先生の話を聞く」「スケジュールや周りの様子を意識する」「おともだちや先生の顔と名前を覚える」「約束を守る」など、ここで学べるソーシャルスキルは多い。
集団課題
利用者全員で同じことを行う課題。
身体能力や問題解決能力などと共に、友達と協力して一つのことをする社会能力を養う。
- お絵かき、工作など
- ゲーム(すごろくやカルタなど)
- 調理(サラダやおにぎり、カップケーキなど)
- 遠足・見学
- SST(ソーシャルスキルトレーニング) 社会参加のためのトレーニング
- 身体活動(リトミック・キッズヨガなど)
個別課題
利用者ごとに設定された課題をこなす。
- 創作活動(お絵かき、塗り絵など)
- 手先の運動(ビー玉入れ、ひも通し、ボタン付けなど)
- 座標・図形能力の訓練(パズルボードやマッチングボードなど)
- 識字能力の訓練(ひらがな・漢字などの練習プリントなど)
- 計数能力・計算能力の訓練(かず・計算の練習プリント、おはじきやそろばん)
- 職業訓練(中学生・高校生にあたる利用者の場合)
- 学校の宿題
お弁当・おやつ
楽しい時間だが、これも立派な療育である。
近年「食育」という言葉が注目されているが、障碍児の場合はさらに基本的なものも対象である。
「食べる前にトイレと手洗いを済ませる」「いただきますとごちそうさまをいう」「座って食べる」「地面に落としたものは食べない」「スプーンやフォークの使い方」「食事中にしてはいけない話題がある」「他人の者を盗らない」「時間内に食べ終わる」「はみがきをきちんとする」など、食事に必要なことを学ぶ。
それ以外の(上記ホームルームで挙げたような)ソーシャルスキルも、食べ物がかかると児童が真剣に守り出すので、達成感をつけるチャンスでもある。
例えば、「ロッカーから必要なものを出し、座って先生の指示を待つ」が苦手な児童も、おやつの時間にはすばやく水筒を出し、先生の呼び出しを待てることがある。
感覚過敏の強い児童の場合、好き嫌いが激しいことがある。無理に食べさせるのではなく、興味を示したタイミングを見計らってうまく挑戦できるようにする。
事業所が食事を用意する場合、アレルギーを持つ児童には特に注意しなければならない。
お弁当やおやつは、事業所で用意する場合と家庭で用意する場合がある。
事業所が用意する場合、お弁当代やおやつ代が別途必要である。
職員は、児童を見守り、一緒に食事を取ってコミュニケーションを楽しむ。
つまり、昼休みの時間に仕事をしているようなものなので労働基準法に抵触するんでは…
自由遊び
楽しい時間だが、これも立派な療育である。
遊ぶおもちゃは原則として事業所の備品を用いる。職員に貸してもらう際に「貸してください」、返すときは「ありがとう」がきちんと言えなければ何らかのペナルティがある(通常、貸してもらえない)。
また、状況によっては遊ばない方がいいおもちゃがある(終了5分前で片付けに時間のかかるおもちゃ、人数が多い場合に場所を取るおもちゃ、食後の自由時間に激しい運動を伴うものなど)こと、そのような場合は我慢して別の方法をとるとも学ぶ。
自由時間は友達との付き合い方を学ぶ機会でもある。一人だけで遊ばずに仲間に入れてもらうことや、逆の立場からは仲間はずれにせず一緒に遊ぶことを学ぶ。ただし程度の問題はある。
何かを貸してもらう際には「貸して」、間違って傷つけてしまったら「ごめんなさい」をいう等、最低限の礼儀はここでも必要である。
職員は、遊びの為に必要なソーシャルスキルを教え込むことも重要だが、それ以上に「息抜き」が大切であることを踏まえ、基本的な規則は守らせつつあまりがんじがらめにしないことも要求される。
また、職員は子どもたちの間に入って遊び、コミュニケーションをとることで愛着や信頼関係を築く。
送迎
保護者が直接送迎してもよいが、多くのケースで職員が送迎を行う。
基本的には、学校(休日の場合は自宅)に車で迎えに行き、自宅へ車で送りに行く。
徒歩や公共交通機関が使われることは極めて稀と考えられる。
危険感知能力が極端に乏しい児童が多い。
職員は、受け渡しの際に、児童の急な飛び出しやシートベルトを正しく装着しているかどうかなど、安全面に充分注意しなければならない。車にはチャイルドロックが必須である。
スケジュール例
以下に、スケジュールの例を示す。
保育園や学童保育に似ているが、療育施設のため、自律訓練のための課題がある。
平日
午前中は、職員が教材づくりや準備等を行う。
児童発達支援事業を兼業している場合は、そちらを行う。
- 14:00-15:00 迎え (登所後はじまりの会まで学校の宿題)
- 15:30-16:00 はじまりの会
- 16:00-16:20 おやつ
- 16:20-17:00 今日の課題
- 17:00-17:20 自由時間
- 17:20-17:30 帰りの会
- 17:30-18:00 送り
土日・祝日・長期休暇
学校の休業日は午前中から夕方頃までの預かりとなる。
児童発達支援を兼業する場合、一緒に過ごすこともある。
学校の振替休業日や、県民の日などの自治体独自の休みも同様のスケジュールとなる。
- 09:00-10:00 迎え (登所後はじまりの会まで学校の宿題)
- 10:00-10:20 はじまりの会
- 10:20-12:00 午前の課題(近くの公園に遊びに行く、など)
- 12:00-13:00 お弁当・歯みがき
- 13:00-14:00 自由時間
- 14:00-15:00 午後の課題
- 15:00-15:20 おやつ
- 15:20-15:50 自由時間
- 15:50-16:00 帰りの会
- 16:00-16:30 送り
利用条件
市区町村に申請し、障害児通所受給者証を交付されると利用することができる。
民間の施設であっても同様に申請が必要なことに注意。
これは、いわゆる「障害手帳」を持つことは必須ではなく、そこまでではないが療育の必要がある児童も対象である。詳しくは自治体に相談されたい。
この際、収入に応じた一定の条件の下都道府県および市区町村から障害児通所給付費が支給され、原則として1割負担で利用可能である。
利用日数は受給者証に定められた範囲内で可能。その際、月の利用限度を超えなければ、複数の事業所を掛け持ちしてもかまわない。
採用資格
児童発達管理責任者(自発管)と、半数以上の保育士または指導員の配置が必須である。
児童指導員および指導員としての任用条件は、大学や専門学校などで児童福祉学・教育学など所定の単位を取得していればよく、このような国家資格があるわけではない。
したがって実際は、教員免許・看護師免許・保健師免許の取得や、福祉施設・教育施設での実務経験を求人条件としている事業所が多い。詳しくは各事業所の求人情報を参照されたい。
児童の送迎があるため、特に地方の事業所では普通自動車免許がほぼ必須である。
関連動画
関連商品
関連項目
- 0
- 0pt