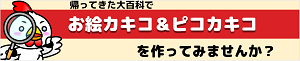概要
衆道(しゅどう)自体は「若衆道」(わかしゅどう)の略。「しゅうどう」ではないので注意。別名「若道」(じゃくどう/にゃくどう)、「若色」(じゃくしょく)という。
平安時代に公家や僧侶の間で流行したものが、中世以降武士の間に広まり、「主従関係」の価値観と融合したとされる。
日本における最初の記録は、日本書紀に遡る。制度や流行としては仏教伝来と同じ時期。つまり、日本古来の伝統ではなく、中国や朝鮮半島に存在した風習だったようである。仏教の戒律においては女性との性交が禁じられていた僧侶が、稚児として寺に入った者を寺社で…おまえら自重しろ。
平安時代には公家にも流行し、ゲイ能芸能の発展に影響を及ぼした。当時の腐女子では盛んにネタにされたんじゃなかろうか。
戦国時代まで来ると、大名・武将が小姓を対象にした話が多数伝えられている。武士道と男色は矛盾することではなかったらしい。江戸時代に書かれた「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」で有名な「葉隠」にも記載がある。
江戸時代においては陰間茶屋での陰間遊び(かげまあそび。数え十三〜四から二十歳ごろの美少年による売色)が町人の間で流行しており、近代まで男色は変態的な行為、少なくとも女色と比較して倫理的に問題がある行為とは見なされず、男色を行なう者は別に隠すこともなかった。
後期においては風紀を乱すものとして扱われるようになり、取締が開始されると衰退、明治維新以降はキリスト教的価値観の流入から急速に異端視されるようになる。
関連項目
- 8
- 0pt