- ほめる
(4) - 掲示板を見る
(25) - その他
「羌瘣(羌カイ)」(きょう・かい ? ~ ?)とは、中国の春秋戦国時代の秦の国に仕えた武将であり、後の始皇帝に仕えて趙の国を滅ぼした人物である。
| この記事の本来の表記は「羌瘣」ですが、「瘣」の字が表記できない環境を考慮して、 「羌カイ」と記述する場合や「羌瘣(羌カイ)」と併記する場合があります。 |
史書では
十八年,大興兵攻趙,王翦將上地,下井陘,端和將河內,羌瘣伐趙,端和圍邯鄲城。十九年,王翦、羌瘣盡定取趙地東陽,得趙王。引兵欲攻燕,屯中山。秦王之邯鄲,諸嘗與王生趙時母家有仇怨,皆阬之。秦王還,從太原、上郡歸。始皇帝母太后崩。趙公子嘉率其宗數百人之代,自立為代王,東與燕合兵,軍上谷。大饑。
と言う事しか記述されていない。
これを翻訳すると、
紀元前229年(始皇18年)に秦は大いに兵を起こして、「趙」の国を攻めた。王翦(オウセン)を将軍とした軍は、上(ジョウ)郡地方の兵を率いて、井陘(セイケイ)を攻撃した。また、楊端和(ヨウタンワ)を将軍とした軍は、河内(カダイ)地方の兵を率いた。
羌瘣は、「代※」の国を討伐した。楊端和は趙の首都である邯鄲(カンタン)城を囲んだ。
※原文は「趙」であるが、『史記』の考証によると、趙の北の土地である「代」にするべきだとする。
紀元前228年(始皇19年)には、羌瘣は、王翦とともに「趙」の国を攻めて、趙の幽繆(ゆうぼく)王(趙遷(チョウセン))を東陽(トウヨウ)の地で捕えて、趙を滅ぼした。続いて「燕」の国を攻撃する為に、軍を率いて、中山(チュウザン)の地に軍を駐屯させた。
となる。その後は、羌瘣には直接関係のない記述が続くのみであり、羌瘣は王翦・楊端和とともに、趙を滅亡させる戦いにおいて、秦の武将となったこと以外は分からない。
秦には羌瘣の他に、「羌」姓の人物も他におらず、その血縁関係を推測することも難しい。
創作では
原泰久の漫画「キングダム」に登場しているが、伝説の刺客一族「蚩尤」の末裔と言う女性剣士になっている。
初登場は、主人公の「信」が魏との戦いに参加した際に、伍長の澤圭や尾平・尾到の兄弟と「伍」を組んだ際に五人一組の一人としてだった。
当初は、独特の民族衣装に身を包み口数も異常に少ない謎の人物だったが、軍神を降臨させる巫舞で軽やかなステップを踏みながら超絶的な剣技を振るうという非常に高い戦闘能力を持っており、その戦闘力の高さと戦術能力を発揮して信を助けた。
その後、暗殺者として信と1対1で戦った事から理解を深め、趙軍との戦いでは信が隊長を務める「飛信隊」の副将となった。
趙の三大天の一人「龐煖(ホウ煖)」と戦った際は、仲間を逃がそうとして巫舞で軍神級の強さの龐煖(ホウ煖)と戦ったが、短時間しか使用できない為に時間切れとなり、疲労困憊で倒れてしまったが、信らとともに脱出に成功し、王騎の最期を看取った。
姉妹同然に育てられた「羌象」を謀殺した幽連に復讐する為、幽連の所在を探して回っている事もある。
当時の羌族について
羌瘣の姓が「羌」であるため、想起されたと思われる、『キングダム(漫画)』における羌瘣の出自として設定された「羌族(きょうぞく)」は、かなり史実とは違うが、古くから実在した部族であり、現在も存在している。
羌族の先祖・戎族
『後漢書』西羌伝によると、羌族の先祖にあたる「戎族(じゅうぞく)」は、太古の時代には、中国にはるか西の土地である「チベット」に住んでいたと伝えられる。
戎族は、牧畜で生計を立て、水や草がある土地を求めて移住する「遊牧民族」であった。父が亡くなれば、息子はその後妻と婚姻し、兄が死ぬと兄嫁をめとるため、未亡人は存在せず、羌族は増加をたどった。
特に、全体の君主は立てず、力が強いものが英雄となり、部族の長となった。人を殺す時は死刑となるが、それ以外の刑罰はない。
戎族の気風として、その兵は山や谷での戦いに長じているが、平地の戦いは苦手とし、持久戦は苦手であるが、勇敢である。戦死をとうとび、病死を嫌う。男女ともに、寒さによく耐えるとある。
戎族は、中国の土地が安定していると服従し、不安定であると反乱を起こした。夏王朝・殷王朝・周王朝の代に、次第に中国に入って来た。春秋時代には中国のあちこちで勢力を有するようになっている。
しかし、(中国の)戦国時代になると、中国の諸国によって滅ぼされ、逃走するか、従属することになる。最後に残り、君主が王を名乗った「義渠(ぎきょ)」も紀元前272年に秦によって滅ぼされる。戎族は中国各地で部族を形成し、それぞれの国家に組み込まれた。
羌族の発生
戎族出身の「無弋爰剣(ムヨクエンケン)」というものが、秦から逃れ、チベット地方にきて、羌族の酋長となった。
この時のチベット地方は、穀物はとれなかったが、獣は多かったので、羌族は狩猟で生計を立てることとなった。無弋爰剣が農業と牧畜を教えたため、羌族からの尊敬をうけることになり、無弋爰剣の子孫が代々、羌族の酋長となった。
無弋爰剣の子孫は子たくさんの人物が多く、彼らは多くの部族に分かれて、羌族は繁栄した。分かれた部族には、(まだ、秦に征服される以前の)蜀の国に入るものも多かった。(この時、分離して、「氐族(ていぞく)」が生まれたとする説もある)。
やがて、無弋爰剣の子孫である「研(ケン)」の代になると、蜀の国を制圧した秦の孝公(こうこう、秦の法律を定めた商鞅(ショウオウ)を用いたことで知られる君主)に服従する(紀元前4世紀ごろ)。研はすぐれた人物で、そのため、研の部族は特に「研種」と呼ばれるようになる。
羌族は、始皇帝の時代までは、秦が各国との戦争に専念していたため、栄えていたが、紀元前221年に天下が秦によって、統一された後、始皇帝は蒙恬(モウテン)に命じて、羌族を討伐させる。羌族は敗れ、また、北の地に逃れた。
さらに後、秦の滅亡後は、羌族は、急速に勢力を拡大した匈奴の冒頓単于(ぼくとつぜんう)に服従し、さらに漢王朝に服従して、隴西(ロウセイ)に地まで移住している。
史実上の羌瘣と羌族の関係は不明であるが、羌族と秦の国はかなり密接な関係にあったことが分かる。
関連動画
関連コミュニティ
関連項目
掲示板
-
23 ななしのよっしん
2023/07/09(日) 08:51:54 ID: UC6F2qxbhJ
>>22
気になったなら自分で『史記正義』とか調べりゃ良いじゃん
ネット上に全文あるんだから
該当箇所が分かってる以上、運が良けれりゃ作業は十数分で終わるレベルだぞ
『史記正義』になかったら、次は『史記索隠』、それにもなければ『史記会注考証』
多分これらのどれかには書いてある
ちなみに俺は別に気にならないから調べない -
👍0👎0
-
24 ななしのよっしん
2023/12/23(土) 11:17:31 ID: MXrUjTMpeh
原文引用して違う解釈をポンと載せてる方がおかしい
しかも引用文の後半無視とか意味わからん -
👍0👎0
-
25 ななしのよっしん
2024/05/19(日) 21:58:31 ID: R8bHJ88M5V
羌族って五胡十六国の五胡にある羌の祖先みたいなイメージだったんだけどもしかして関係ないのか?
-
👍0👎0
おすすめトレンド
ニコニ広告で宣伝された記事
急上昇ワード改
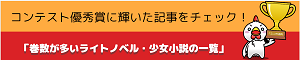
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。