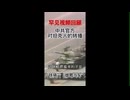定説になった後現在では否定されている物、事柄の一覧とは、一般に広く信じられていた説や物事が今現在否定されている、または強く疑われている事例をまとめていく一覧である。
概要
定説になった後現在では否定されている物、事柄とは、一定の信憑性をもって一般に広く信じられていた物が、科学や知見の進歩によって否定、または疑われている説や物事である。一部ではまだ信じられているが天動説に対する地動説や、今では信じられないが放射性物質が健康に良いなど、一般に信じられていたが科学の進歩によって否定された物をまとめていく。
例えば長らく信じられていた天動説の信憑性は、天が動く様に見える事によっての知見から、一定の信憑性を得て信じられていた。しかし科学の進展から地動説が生まれ、多くの科学的な知見により、現在では地動説が定説となっている。このように、世間で信じられていた物が科学や経験則、観察技術等の進歩により否定されてしまった事柄を挙げて一覧にしていく記事である。
なお、言っていない台詞のような台詞や、UFOなどの存在が疑われるが現在の科学でも否定されていないか、現在でも結論が出ていない事柄は含まない事とする。
定説になった後現在では否定されている物、事柄
| この一覧は不完全です。 調べものなどの参考にはなりますが絶対的に内容が不足しています。 加筆・訂正・情報提供などをしてくださる協力者を求めています。 |
- 天動説
- 宇宙の中心に地球があり、太陽や他の天体が地球の周りを回っているという説。長らく支持されたが、コペルニクスやガリレオ、ケプラーなどによって地動説が確立され否定された。
- 獲得形質遺伝
- 生物が一生の間に獲得した形質が子孫に遺伝するという説。キリンの首が伸びたのは、高いところの葉を食べようと努力した結果、その形質が子孫に遺伝したため、と説明された。しかし、メンデルの遺伝の法則やダーウィンの自然選択説、分子生物学の発展などにより否定された。
- 瘴気説(伝染病の原因)
- 伝染病は、空気中の悪い気(瘴気)によって発生するという説。かつては広く信じられたが、パスツールやコッホらによる微生物(細菌やウイルス)の発見により、伝染病の真の原因が明らかになり否定された。
- 地球平面説
- 多くの文化において、地球は平らであるという考え方が存在した。しかし、古くから地球が球体であるという証拠は存在し、大航海時代を経て広く認知されるようになった。
- 放射性物質含有製品
- 放射性物質が健康に良い、あるいは無害であると誤解され、結果的に健康被害をもたらした事例は歴史上多数存在する。特に20世紀初頭は、放射線の危険性についての理解が不十分だったため、化粧品や歯磨き粉など多くの製品に放射性物質が意図的に利用された。
- 地球空洞説
- 地球の内部は空洞になっており、そこには別の世界や生命が存在するという説。かつては探検家や小説家によって真剣に論じられたり、物語の舞台になったりしたのだが、地震波の伝播研究などにより、地球の内部が核、マントル、地殻といった層状構造をしており、高圧・高温の固体や液体で満たされていることが科学的に明確になっている。
- フロギストン説
- モノが燃えて灰になる過程では、そのモノに含まれるフロギストンという物質が逃げ出しており、燃えるという現象はこのフロギストンの放出過程であるという説。18世紀の科学者の間で広く支持されたが、当初からフロギストンが放出されるはずなのに燃焼した金属は重くなるという矛盾を抱えており、やがてラヴォアジエによって酸素説が提唱されて以降は下火になった。
- 永久機関
- 外部からエネルギーを供給することなく、無限に運動し続け、あるいは仕事を生み出し続ける装置。その概念は古くから存在し、主に2つのタイプに分類された。第一種永久機関は外部からのエネルギー供給なしに、常に仕事を生み出し続ける装置のこと。これはエネルギー保存の法則(熱力学第一法則)に違反する。第二種永久機関は熱源から熱を受け取り、その熱を全て仕事に変換する装置。これはエントロピー増大の法則(熱力学第二法則)に違反し、例えば、周囲の熱を全て集めて動力に変えるような機械のこと。永久機関の構想は、古くから世界各地で見られたが、エネルギー保存の法則の確立などによって、現在では不可能だと見られている。なお、各国の特許庁は永久機関の特許を受け付けていない。
なぜ定説となった説が否定されるのに至ったのか?
定説となる説が一定の説得力を持つのは、以下の複数の要因が複雑に絡み合っているためであると思われる。
- 既存の知識体系との整合性
- その時点で受け入れられている他の科学的法則や事実と矛盾しない、あるいは矛盾が少ない形で説明が与えられると、人々はその説を受け入れやすくなる。全く新しい、既存の常識とかけ離れた説は、よほどの証拠がない限り、なかなか受け入れられにくい。
- 経験的・観察的証拠との合致
- 日常生活の経験や、直接観察できる現象をうまく説明できる説は、強い説得力を持つ傾向があり、例えば、天動説は、人々が日中に太陽が動き、夜に星々が動くのを見るという日常の観察と一致していた。
- 論理的な一貫性
- 説の内部に矛盾がなく、論理的に首尾一貫していることは、その説の説得力を高める。明確な前提から導き出される結論が理にかなっていると感じられると、受け入れられやすくなるものだ。
- 説明能力の高さ(適用範囲の広さ)
- 多くの異なる現象や問題を統一的に説明できる説は、その分説得力が増す。例えば、ニュートンの運動法則は、リンゴが落ちる現象から惑星の運動まで、広範な現象を説明できた。
- 予言能力・予測可能性
- 説に基づいて未来の現象や未発見の事実を正確に予測できる場合、その説の説得力は飛躍的に高まる。実際に予測が当たり、それによって新しい発見がなされると、その説は疑いようのないものとして受け入れられる。
- 権威による支持
- その分野の著名な学者や研究機関が説を支持すると、一般の人々はその説を信頼しやすくなる。歴史的には、宗教的権威が科学的説の受容に大きな影響を与えたこともある(例:キリスト教が天動説を支持した期間)。
- 理解のしやすさ・直感性
- 専門家でなくても、ある程度の内容が直感的に理解しやすい説は、広く受け入れられやすい傾向がある。複雑すぎる、あるいは専門知識がなければ理解できない説は、一般に普及しにくいだろう。
- 既存の社会・文化・宗教的背景との調和
- その時代の社会構造、文化、宗教的信念と大きく衝突しない説は、受け入れられやすい傾向にある。逆に、既存の価値観を揺るがすような説は、強力な抵抗に遭うことがある(例:地動説に対する宗教的抵抗)。
逆に言うと、これらの要素が崩れることで世間一般から定説として覆される事もある可能性があると言える。例えば科学の進歩による観察技術の進歩によって、天動説は覆された。将来の科学的進歩により、現在の定説も覆される可能性があるのだ。バイアスが働くこと無く先入観や偏見を超えて真実や正しい定説にたどり着けるよう心がけたい。
関連項目
- 4
- 0pt