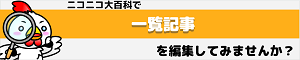太陽光発電とは、太陽から降り注ぐ光で電気を作る発電方式である。
ロマンを追い求める方は → 宇宙太陽光発電
概要
ソーラー発電、太陽電池、光電池などとも呼ばれる。pn接合された半導体などに光子が衝突した際に発生する光起電力効果を利用したものが一般的で、光を効率的に浴びられるように平らな薄板状の構造したものが多い。近年は国からの助成金やエコ住宅への関心の高まりに伴い、一般住宅の屋根に設置されるケースが増えてきている。また、電卓や腕時計など、光を利用した小型の発電は気付かないところで既に普及している。探査機「はやぶさ」が長期間かけて地球へ帰ってこれたのは信頼性の高い太陽光発電パネルの功績も大きい。
種類
そもそも、現在の太陽光発電に用いられる発電素子の種類は多種多様となってきており、ここでの分類に意味があるかどうかすら分からない。これは発電効率の向上のために複数の素材を組み合わせて一枚のパネルにしたり、異なる構造の同一素材を同じパネル上に形成するなど、もはや分類などに意味のない複合型や混成型のパネルが開発されているためである。
シリコン系
ケイ素をベースの材料としたもので、太陽電池とかソーラーパネルと称されるもののほとんどはコレ。
比較的安価に量産できるものの、性能面に関しては少々低い。
温度が上昇すると発電能力が低下するという半導体が抱える本質的な課題は、シリコン結晶構造などを工夫したり、異なる構造のシリコンを複合化することで改善されつつある。
金属系
高性能(高変換効率)でレアメタルやレアアースを贅沢に使った高価な宇宙産業用から、そこそこの性能だがありふれた金属を混ぜ合わせた安価なものまで種類が豊富。高純度のシリコンを必要としないため、シリコン系より低コストで量産が容易なものが多い。金属系とはいえ合金のようなものではなく、金属の薄膜を張り合わせたようなものから、金属化合物を焼き固めたセラミックのようなものまで、その構造は様々。
化合物系
植物が光合成のために色素(クロロフィル)を使っているように、色素に光が当たった際に励起された電子を電極に捕まえることで発電するもの。色素増感太陽電池と呼ばれる。近年モニタに採用される有機ELは電気を流すと光るが、こちらは光を当てると電気が流れる逆の化学反応と考えると仕組みが分かりやすい。発電効率は低いものの使用する色素によっては製造コストは非常に低い。透明な電極を使うことでビルの窓ガラス全体を発電にといった事も期待される。
特徴
太陽光発電は昼夜によって状況が全く異なる太陽光を利用するため、自然エネルギー利用の代表的存在として広く知られており、そのメリットとデメリットは特に議論の中心となりやすい。
利点
- 発電時に機械的に動く部品がなく故障しにくい。
- 発電時に廃棄物、騒音が出ない。
- 電力需要(消費)がピークになる昼間に、電力供給がピークになる。
- 板状の発電部はビルの屋上や壁などの光が当たる場所なら設置可能。
欠点
- 夜間は発電できず、日中も曇りや雨など天候に応じて発電量が低下し安定しない。
- 設置面積あたりの発電効率が従来の発電方式に比べて著しく低い。
- 太陽光に多くあたると発電出力が上がるが、あたり過ぎて発電部が高温になると発電効率が下がる。
- 黄砂、火山灰、雪など日本で見られる一般的な気象現象で発電部が覆われると出力が下がる。
- 山林を切り開いて敷設した場合、土壌の緩みによる地滑りが懸念される。
その他
太陽光発電の基礎となる物理現象は光起電力効果と呼ばれるものだが、これは業界用語であり、一般(物理屋さん)には光電効果としてよく知られている。なんとも難しげな名前だが、その実は極めて単純なもので何らかの物質に光が当たった時、そこから電子が飛び出してくるというものである。かの高名な物理学者アインシュタインがノーベル賞を受賞したのは相対性理論ではなく光電効果に関する研究であったことはあまりにも有名な話である。
関連動画
関連静画
関連項目
- 4
- 0pt






![【モンハンライズ BGM】深い森の幻影/オオナズチ:Rise ver.(高音質) 10分耐久ver. [作業用BGM]](https://nicovideo.cdn.nimg.jp/thumbnails/38769693/38769693.22444883)