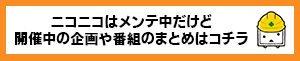汁粉(しるこ)とは、砂糖で煮た小豆を用いた食べ物である。おしるこ、しるこなどと呼ぶ。
概要
水でのばした小豆に砂糖を加え煮立てて甘く味付けし、餅や白玉団子などを入れた料理。
地域によっては餅以外にも白餡やカボチャ、枝豆(ずんだ)や栗などを入れるところもあり、地方料理として定着している場合もある。また一言にお汁粉と言っても、使用される餡の種類によって区別される事が多い。具体的には、
- 田舎汁粉:つぶし餡を用いる。これをルーツの出雲や関西では「ぜんざい」と呼びこれが本来の正しい名称だが、江戸ではその正しい呼び名の「ぜんざい」が広まらず、加えて西と比べて寒冷な地で作った小豆は皮が硬かったため「こんなのは田舎者の食いもんだ、べらんめぇ」と嫌われ、このように蔑まれて呼ばれた。
- 御前汁粉:こし餡を用いる。こし餡が広まったのは前述したとおり皮が硬かったためで、こっちこそが本家本寸法の汁粉だと好まれた。一方、上方近辺の小豆は皮が軟らかかった一方で肌理が粗く、漉すと味が薄くなってしまうため、こし餡があまり好まれず、汁粉自体がそこまで一般的ではない。そして、これも「こし餡のぜんざい」などと呼ぶことがある。むしろ、汁粉とはサンガリアが出している飲み物としてのイメージが強い。
- 善哉:粒餡を用い、餅の上に振りかけたもので、上方ではこれを亀山、小倉、金時などという。ちなみに平仮名で「ぜんざい」とも表記する事がある。
などのように分けられるが、地域性によってバラバラなので使用は注意が必要。ちなみに、中京や北海道、九州、沖縄などでも呼称はバラバラである。
名古屋では汁気のあるものは全部おしるこであり、汁気の少ないものは全部ぜんざいと呼び、箸で食べるものらしい。これが九州では餅を入れるか、白玉を入れるかの違いでおしることぜんざいを呼び分けたりしていることが多い。北海道ではおしることぜんざいの区別はしていない。
そして、沖縄では、ぜんざいとは小豆と餅を載せたかき氷のことである。
元々汁粉は江戸時代にて宴会の後に出される料理として存在し(当初は「すすりだんご」という名称であった)味付けも砂糖ではなく塩を用いるなど現代のものとは違うものであった。汁物の料理という点については同じだが、間食(デザート)以上に酒の肴として出される事が多かったもので、甘い味付けとなって一般にも広く食べられるのは明治時代に入ってからとなる。牛鍋や洋食と並ぶ「近頃のはやりもの」として汁粉屋が出てくるようになった。
甘くて美味しいお汁粉は、子供から大人まで幅広い支持を獲得。子供の好物と言えば大体お汁粉が挙げられるほどの人気っぷりだった。一方、帝國海軍では長期航海から帰港した際に「入港ぜんざい」が振る舞われ、乗組員の数少ない楽しみとなっていた。まさに子供も大人も魅了する魔性の食べ物だったのだ。だが、関東大震災が起きてからは、西洋文化を積極的に取り入れる傾向が強くなり、汁粉屋は激減、カフェ-にとってかわられる事態に(汁粉が大好物だった芥川龍之介が、その頃の嗜好の変貌ぶりとともに怨嗟の声を短編に記している)。
しかし大東亜戦争が始まると、材料の砂糖と小豆が入手困難となってしまう。1943年には製菓メーカーが操業を止め、より入手が難しくなる。それでも特攻隊員や出征する兵士のために僅かな材料を使ってお汁粉が作られた。戦争が終わった後も小豆の価格高騰により、お汁粉は気軽に食べられるものではなかった。現代では、求めれば簡単に味わえるお汁粉だが、戦前から戦後しばらくは宝石のように希少だった。
現在では一般家庭でも鏡開きの時に鏡餅を汁粉に入れて食べるのはご存知の通りで、近年ではカップラーメンと同様にお湯を注いで簡単に作れる汁粉もある。
またコンビニや自販機などではあったか~い缶入り汁粉ドリンクが販売されている。冬の寒い時期に、お世話になった人も少なくないのではないだろうか。ただし小豆の粒入りの場合は最後に小豆の粒が残ってしまい、飲み口に引っかかって中々出てこずにイライラすることもある。その場合、缶の飲み口の少し下側をへこませてやると缶の内側で飛び出たその部分がジャンプ台の役割を果たし、小豆が飲み口から飛び出てきやすくなる。お試しください。
関連動画
関連項目
- 6
- 0pt