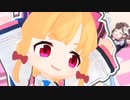蒯通(かいつう、生没年不明)とは、秦代・楚漢戦争時代・前漢時代にいた人物。主に説客(せつきゃく。弁舌や礼法に優れ、各地を巡って領主の外交政策などに影響を与えた人物)として活躍した。
本来の名は、蒯徹(かいてつ)であるが、漢の武帝(名は、劉徹(りゅうてつ)の名と同じであり、その時代の王朝の皇帝の名を書くのは避けること(※)から、「徹」と同じ意味を持つ「通」の名で後世呼ばれた。
※ これは、「避諱」と呼ばれ、皇帝の名や親の名にあたる文字を、同じような意味を持った別の文字あるいは語句に置き換えることなどが行われる。
蒯通は、陳勝(ちんしょう)に仕えた武臣(ぶしん)に対する進言と、劉邦(りゅうほう)に仕えた韓信(かんしん)に仕えた進言でよく知られる。
特に韓信に対する進言については、楚漢戦争を扱った創作作品でも重要な場面として、取り上げられ、蒯通は「歴史学習漫画」や「センター試験」の問題にも取り上げられることがある。
韓信に仕えた後については、『史記』では登場しないが、『漢書』でその後についても記されており、斉の地におもむき、劉邦に仕えた曹参(そうしん)に顧問となったことが分かる。
後漢末に劉表(りゅうひょう)や曹操(そうそう)に仕えた蒯越(かいえつ)・蒯良(かいりょう)は蒯通の子孫であると伝わる。
この項目では、蒯通の進言をうけいれた武臣、司馬遼太郎『項羽と劉邦』において、蒯通の親友と設定された侯公(こうこう)、同じく曹参の顧問となった蓋公(がいこう、こうこう)をあわせて紹介する。
概要
范陽の街を戦乱から救う
蒯通は、中国の范陽(ハンヨウ、現在の北京)の地に住んでいた。
ただ、蒯通は「斉」の地方の人という記述も『史記』には存在し、范陽は燕の地の土地であるため、これは范陽ではなく、斉の范県であるという説もあるが、ここでは、(場所は別として)とりあえず「范陽」としておく。
蒯通は弁士として(燕の)范陽に来ていただけで、范陽の土地の出身ではないかもしれない。
中国を史上はじめて統一した秦王朝では、始皇帝の晩年をはるかにこえる暴政と恐怖政治が、二世皇帝である胡亥(コガイ)によって行われ、追い詰められた陳勝(チンショウ)と呉広(ゴコウ)という人物が、紀元前209年7月に、南の楚の地において、反乱を起こした。
この反乱は大規模なものとなり、すぐに中国各地へと広がった(「陳勝・呉広の乱」)。
陳勝は、北の趙の地にも、配下の武臣(ブシン)を将軍に任じ、軍を派遣した。たちまち、数万の軍は集まり、武臣は武信君(ぶしんくん)を名乗った。秦の政治に不満をいだいていた趙の地では十の城(都市)がすぐに武臣に降伏した。しかし、他の城は降伏せず、守りを固めたため、武臣は蒯通が住んでいる范陽を攻めてきた。
蒯通は、范陽を守る范陽の県令(けんれい。秦の任命した県の長官)である徐公(ジョコウ)に面会を求め、許されると、いきなり、このように切り出した。
蒯通「あなたがもう亡くなられることであると聞いています。お悔み申し上げます。
ですが、あなたが私と会ったことで、生き続けるができます。お祝い申し上げます」
徐公「なにゆえに、君はお悔みを述べるのか」
蒯通「秦の法律は厳しく、あなたが范陽の県令であった十年間、多くの人の父を殺害して、たくさんの孤児を生み出しました。また、刑罰として、多くの人の足を斬り、顔に入れ墨をいれたことは数えきれないほどです。
人々があなたのお腹に刃をいれないのは、秦の法律を恐れているからだけに過ぎません。
今は、天下は乱れ切って、秦の法律は通用しなくなっています。人々はあなたのお腹に刃を刺して、名をあげようとするに違いありません。
これが、私があなたにお悔みを述べた理由です」
蒯通はさらに話を続けた。
蒯通「今、諸侯(各国)が秦にそむいています。この范陽にも、武信君(武臣のこと)の軍が来ているのに、あなたは范陽をなんとか守ろうとしています。范陽の若者たちは争って、武信君に降伏しようとするでしょう。
すぐに私を武信君のところに行き、面会するように命じてください。『災いを転じて福となす』機会は今しかありません」
そこで、蒯通は、徐公に命じられ、武臣の元に使者として派遣されることとなった。
蒯通は武臣に面会すると、こう、切り出した。
蒯通「あなたは、戦いに勝ってから、その土地を攻略して攻めて、その後に城を落とそうとされています。ですが、私が考えるに、これは間違いです。
私の計略に従っていただければ、攻めずに城を落とし、戦わずに土地を攻略します。檄文(げきぶん。木片に書いた連絡文)を各地に伝えていただくだけで、千里の土地を平定することができるのです。申し上げてよろしいでしょうか?」
武臣「どういう計略なのか」
蒯通「現在、范陽の県令である徐公は、(秦王朝のために)兵士を集めて、防戦しようとすべきであるのに、臆病にも死を恐れ、むさぼって、富貴の地位にとどまろうと考えています。天下に先立って、あなたに降伏しようと願ってはいますが、あなたが先に落とした十の城で、秦が派遣した役人を誅殺されたので、恐れているのです。
ですが、范陽の若者たちは、先に徐公を殺して、城を守ってあなたの軍を防ごうとしています。
あなたは、どうして、徐公を「侯(諸侯)」の地位に与えて、封じてしまわないのですか? そうすれば、徐公は城ごとあなたに降伏するでしょうし、若者たちも徐公を殺害しないでしょう。
徐公を「侯」に封じたうえで、美しい車に載せて、燕や趙の土地の郊外を回らせれば、燕や趙の土地も、これを見て、『先に降伏した范陽の県令である徐公があのような立場でいることができるなら』と安心して、城ごと降伏するでしょう。
武臣は、蒯通の計略に従い、徐公を「侯」に封じ、蒯通を通じて、(徐公を「侯」に封じた証である)印を与えることにした。
趙の地では、このことを聞いて、三十数の城が戦わずして、武臣に降伏した。
蒯通はその弁舌で、范陽の県令とその城、土地のみか、趙の地全体を戦乱から救うことができた。
韓信の弁士となる
その後の蒯通の動きは分からないが、やがては、武臣も配下の李良(リリョウ)に殺害され(後述)、秦王朝も滅び、天下は漢の劉邦(リュウホウ)と楚の項羽(コウウ)とで争われることとなった(楚漢戦争)。
楚の項羽は西楚の覇王を名乗り、すでに天下の覇者となっていた。
(明確な時期は史書には記されていないが、おそらくはこの頃に)、蒯通と親しい仲であった斉の地の人物である安企生(アンキセイ)という人物が、項羽と会って、項羽のために献策することを求めたが、項羽はその策を用いることができなかった。
しかし、項羽は安企生と蒯通をなにかの地位に封じようとして、自分に仕えることを求めたが、安企生と蒯通はそれを受けることはなかった(蒯通もまた、項羽のもとにいたか、あるいは、その名声を聞いて、呼ぼうとしたものと思われる)。
やがて、蒯通は(項羽のもとにいたとしたら)、項羽のもとを去った。
項羽と劉邦の争いである楚漢戦争は続いており、その中で、劉邦の大将軍に任じられた韓信(カンシン)が、魏と趙の王を討伐し、その土地を攻略していた。
趙を攻略した韓信ではあるが、項羽との戦いでの兵力不足で悩む劉邦に軍を奪われ、趙の新兵を率いて、斉の土地の討伐を劉邦に命じられていた。
紀元前203年10月頃(紀元前204年の末かもしれない。この時は、10月が年始)、韓信は斉の討伐に向かっていたが、劉邦が別に、参謀の酈食其(レキイキ)を斉に派遣しており、斉の土地は漢に降伏したことを知った。韓信はそこで、軍を進めることをやめようとした。
この時には、蒯通は弁士として、韓信の元にいた。蒯通は韓信に進言した。
蒯通「将軍(韓信のこと)が、命令により、斉を討伐しようとしたのに、漢(の国)では勝手に使者を送って、斉を降伏させました。それならば、どうして、将軍に進軍しないように改めて、命令が出されないのですか? 命令がない以上、進軍しないことがありましょうか?
酈食其は、たった一人で三寸の舌をふるって、斉の七十余の城を降伏させました。将軍は数万の兵を率いて、一年以上かけて、趙の五十余の城を降伏させました。それでは、将軍に就任してから数年たっても、一人の儒者の功績に及ばないことになります。進軍すべきです」
韓信は、蒯通の言葉に同意して、油断している斉の軍を撃破し、斉の国に攻め込んだ。斉王の田広(デンコウ)は漢にだまされたと怒り、降伏の使者である酈食其を煮殺した。
韓信はそのまま斉を討伐し、さらに、斉の援軍として派遣された項羽の武将である竜且(リュウショ、鍾離眜(ショウリバツ)の項目の「鍾離眜に関係する人物たち」参照)も打ち取り、斉を滅ぼした。
紀元前203年2月には、韓信は劉邦によって、「斉王」に封じられた。
必ずしも、鮮やかな計略ではなかったが、蒯通の計略により、漢と韓信は斉を平定し、漢の領土とすることができ、韓信は斉王となることができたが、劉邦の韓信への不信感は広がっていた。
韓信に漢からの自立を説く
この頃、大勢力となった韓信の元に、楚の項羽の使者である武渉(ブショウ、范増(ハンゾウ)の項目、范増に関係する人物たち参照)が来て、韓信に天下を三分する勢力の一つとなり、劉邦から自立するように説いたが、韓信は「自分を大事にしてくれて、大将軍にまで任じてくれた漢王(劉邦)は裏切れない」といって断っていた。
蒯通は、天下の形勢は韓信の動向にかかっていると分かっていたため、計略を献じて、韓信に自立を勧めようと考えていた。
蒯通は人相のことにかこつけて、韓信に進言した。
蒯通「私はかつて人相の術を学んだことがあります」
韓信「先生(蒯通のこと)。人相を見るのはどのようにするのですか」
蒯通「その人の貴賤は体格で分かり、悲しみや喜びの気持ちは顔つきで分かり、成功するか失敗するかはその決断で分かります。これを基準にして観れば、万が一にも間違うことはありません」
蒯通「二人だけでお話したいのですが」
韓信は、側近に去るように命じて、二人きりだけになった。
蒯通「あなたの人相は、諸侯に封じられるに過ぎず、それも危うくて安心することできません。ですが、あなたの背中の相は、貴いことは言い表せないほどです」
韓信「どういったことでしょうか?」
蒯通「現在、楚と漢に分かれて争っており、多くの人々が死んでいます。楚と漢は互いに勝敗があり、ともに苦しみ疲れ切り、兵士は城塞に阻まれて、意欲を失い、兵糧は尽きて、民はうらみを抱いたまま、寄る辺を失っています。
この災いを終わらせることができるのは、とてつもない優れた人物でなければできません。楚と漢の君主の命運は、あなたにかかっています。あなたが漢に味方すれば、漢が勝ち、楚の味方をすれば、楚が勝ちます。
この二つの勢力をともに残して、天下を(韓信が自立して)三分するのが最上です。そうすれば、率先して動く勢力はないでしょう。
あなたのとてつもない優れた才能をもって、多くの兵士を有し、強い斉の地によって、趙と燕の国を従えれば、空白となっている土地を占領し、民の願いによって、楚と漢に停戦を提案すれば、天下は風のように応じてくるでしょう。
大勢力を分断して弱めて、諸侯を立てるのです。諸侯が立つようになれば、天下は(戦乱を終わらせた)斉の恩徳のおかげと思うでしょう。斉の基礎を固め、諸侯に対して徳をもって接して、礼遇すれば、天下の諸侯は、(斉を盟主としてあがめて)、斉に朝貢してくるでしょう。
『天が与えている時に取らなければ、かえって、その罪を受けてしまう。時期が来ているのに、行わなければ、かえって、その災いを受けてしまう』と言います。
あなたに置かれましては、どうか、このことについて熟考されてください」
※ 蒯通の天下三分の計については、後述、「蒯通の天下三分の計は、実現性は存在するのか?」を参照。ここで、分かる通り、蒯通の進言の内容は、「韓信に天下を統一させ、その君主とさせること」ではない。
韓信への説得を続ける
韓信「漢王は私を厚く遇してくださっています。私をご自身の馬車に載せ、ご自身の衣を与えてくださり、ご自身の食事を私にすすめてくださりました。私は、自分の利益のため、義にそむくことはできません」
蒯通「あなたは漢王のために尽くして、万世に残る功業を立てようと願っていますが、それは間違いです。張耳(チョウジ)と陳余(チンヨ)は刎頸(ふんけい)のまじわりを結ぶほどの仲でしたが、その後は、宿敵となり、天下の笑いものとなりました。
猜疑心は多くの欲望から生まれ、人の心は予測しづらいものです。
あなたが、漢王に尽くそうとしても、その信頼は張耳と陳余の仲には及ばず、任されている事業は、はるかに大きなことです。漢王があなたを大事にされ続けると考えられるのは、間違いです。
『野獣すでに尽きて、猟狗(りょうく)煮らる(獲物の野獣がいなくなった後、それを捕まえるために力を尽くした犬が煮られて食べられてしまう)』という言葉もあり、歴史もこれが正しいことを示しています。
さらに、『武勇と軍略が主君をおそれさせるものは、その身は危うく、功績が天下をおおうほどのものは、賞されない』という言葉もあります。これは、大王(韓信)のことを指しています。
あなたは、魏・趙・斉・楚を討伐し、燕を降伏させました。その功績は天下に二人とおらず、その軍略は不世出のものです。
これだけの軍略と功績をあげていたら、楚にいても漢にいても、信用されることはなく、恐れられるだけです。それで、どこに落ち着こうとされるのですか?
あなたの勢いは人臣の立場にありながら、主君をおそれさせるほどの威力があり、天下に高い名声があります。あなたは危険な立場におられるのです」
ここまで来たところで、韓信は蒯通に謝した。
韓信への最後の説得
数日たっても、韓信からの返事はなかった。そこで、蒯通は韓信への説得を続けることにした。
蒯通「『知ること』は、『決断すること』であり、『疑うこと』は、『物事の害になること』です。実行することは大切です。『功業は成りがたく、失敗しやすく、機会は得難くして、失いやすい』のです。時期が来ることは、二度とはありません。よくお考えになってください」
しかし、韓信は、結局、ためらって、漢に背くことにしのびなかった。また、自分の功績が大きいのだから、漢が自分から斉の地を奪うようなことはしない、とも考えた。
そこで、韓信は蒯通の誘いを断った。
蒯通は自分の進言が韓信に聴かれず、(自分の身が危ういと思ったので)、気が狂ったふりをして、まじない師となった。
生涯最大の危機
時は流れ、紀元前196年になった。あの韓信への説得から6、7年が経っていた。
項羽と劉邦の争いは、紀元前202年に劉邦の勝利に終わり、劉邦が天下を制していた。韓信は、結局は斉王の地位を奪われ、なんとか、楚王とはなれたが、それも、謀反の疑いがかかり、紀元前201年に逮捕され、淮陰(ワイイン)侯に降格されていた。
結局は蒯通の進言は正しかった。
蒯通は斉の地に行った。天下は平定されたため、気が狂ったふりや、まじない師の真似はやめ、各地で、遊説を行って、弁士として高い名声を得ていた。韓信に自立を勧めたことは口にしなかったが、范陽を救った名声は、すでに高かったものと思われる。
しかし、突如、斉の国に皇帝に即位した劉邦の詔(みことのり)が下り、蒯通は逮捕されてしまった。
どうやら、淮陰侯であった韓信が謀反の罪で処刑され、死に際に、
「私は蒯通の計略を用いなかったことを後悔している。だから、女子供に図られることになったのも、天命である」
と最後に語ったらしい(韓信を処刑したのは、劉邦の皇后である呂雉(リョチ))。
そのことを呂雉から聞いた劉邦(※)は、「蒯通とはいうのは、斉の弁士だ」と語り、それゆえ、蒯通は逮捕されることになった。
※ 劉邦は韓信の処刑の時には反乱討伐をしており、立ち会っていない。
皇帝である劉邦がその名を知るぐらい、蒯通の「弁士」としての名声は高かったようであるが、それが蒯通の危機を招いてしまった。
蒯通の予期した韓信の命運は完全に当たったにせよ、いずれにせよ蒯通にとっては迷惑な話であったが、蒯通は劉邦のもとに連れられてきた。
わざわざ、話を聞くために自分のもとに連れてくるとは、劉邦は韓信に対して複雑な感情があったことは推測できるが、とにかく、功名な弁士であった蒯通は生涯、最大の危機を迎えた。
劉邦を説き伏せる
劉邦の蒯通への尋問がはじまった。
劉邦「お前が淮陰侯(韓信のこと。謀反人とされたのに呼び捨てでないのは、少しは情があるからだろうか)に謀反することをそそのかしたのか」
蒯通「その通りです。私がそそのかしました。あの小僧(韓信のこと。韓信は若かったのかもしれない)は、私の策略を用いなかったので、自分の意思で処刑されるようにしむけてしまったのです。あの小僧が、私の策略を用いていれば、陛下(劉邦のこと)は彼を処刑することはできなかったでしょう」
劉邦は怒って、どこかの漫画の始皇帝のように、周りに命令した。
劉邦「煮殺せい!」
劉邦「お前が韓信に謀反をそそのかしたのに、なぜ、無実の罪なのだ」
蒯通「秦王朝の法律による統制がなくなり、あの時代は、多くの人物が天下を争っていました。泥棒の犬が聖人に吠えるのは、主人以外に吠えるからにほかなりません。
私は韓信を知っていましたが、陛下を知りませんでした。あの時代に天下を争った人物を全て煮殺すことができましょうか」
劉邦「釈放してやれ」
こうして、蒯通はその罪を許され、また、斉の国に帰ってきた。
それからの蒯通
ここまでの蒯通の事績は、『史記』に記されており、蒯通は創作作品やネットの記事では、その後は不明とされることが多いが、実は、同じく正史の一つにある『漢書』により、蒯通のその後のことの事績も知ることができる。
この頃、斉では劉邦の長子である劉肥(リュウヒ)が斉王に封じられ、かつて、韓信のもとで斉の相国(しょうこく、宰相)をつとめていた曹参(ソウシン)がまた、斉の相国に任じられた。
蒯通も当然、韓信のところで曹参と知り合いであったと考えられる。
曹参は礼儀をもって、すぐれた人物にへりくだり、蒯通はその賓客とされた(※)。
※劉肥が斉王となり、曹参が斉の相国に任じられたのは、韓信が楚王から淮陰侯に降格した後の紀元前201年であるため、『漢書』の時系列はこのようであるが、実際は、蒯通は劉邦から逮捕される以前に、曹参に賓客として迎え入れられていたのかもしれない。
蒯通は、曹参が気づかないことを見つけ、その間違いを指摘し、優秀な人物や優れた才能を持った人材を推薦した。これについては、斉においても、「誰も蒯通に及ばない」と呼ばれるほどの評価を得ていた。
かつて、紀元前206年6月頃、当時、斉王を名乗っていた田栄が、項羽に対抗するために斉の人士に自分に仕えるようにおどして、自分に組みしない人物は殺害していた。
斉の処士(誰にも仕えていない人士)である東郭(トウカク)先生と梁石(リョウセキ)君も田栄におどかされて、強いられて、田栄に仕えていた。田栄が敗れた後、二人は、田栄に屈従したことを恥じ、二人で山に入って隠棲していた。
蒯通はある客から進言を受けた。
客「(蒯通)先生は、東郭先生と梁石君が世俗の人が及ばない人物であることをご存じでしょうか? どうして、彼らを相国(曹参のこと)に推薦されないのですか?」
蒯通は彼らを推薦することを承知して、曹参のところにおもむいた。
蒯通「婦人には、夫が死んでから三日で再婚するものと、前の夫に義理立てして、門から出ないものがおりますが、あなたが妻にするとしたら、どちらがよろしいでしょうか?」
曹参「再婚していない方がよろしいでしょう」
蒯通「それならば、家臣に求めることも同じでしょう。東郭先生と梁石君は斉の地のすぐれた人物ですが、隠居して、節を曲げて意を屈してまで、仕官を求めませんでした。どうか、礼節をもって、この二人をお迎えいただきますように」
曹参「つつしんで、お言葉通りにいたしましょう」
(蒯通と曹参の関係については、「曹参は蒯通の計略に賛同していたのか?」参照)
蒯通は、(中国の)戦国時代の遊説家の計略を論じ、自分の説をまとめて、都合81首として、「雋永(しゅんえい)」と名付けた。
蒯通は、(中国の)戦国時代の燕の名将である楽毅が、燕の恵王にあてて送った手紙を読むと、書を下に置いて、涙を流さない時はなかったと伝えられ、弁士らしからぬ、熱い心情を持っていた人物だったようである。
評価
「蒯通は、様々な弁舌を行って、酈食其を死においやり、斉王の田広を破滅させ、韓信に謀反をそそのかして、傲慢にさせ、三人の俊才を滅ぼしたが、煮殺しの刑罰をまぬがれたのは、まだしも幸いである。
小(蒯通)をもって大(酈食其、田広、韓信)をくつがえし、疎遠な人(蒯通)が、親密な人(劉邦と韓信の仲)をおとしいれたものである。恐れないでよかろうか」
と、無責任な弁舌家であるといった厳しい評価を与えている(※)。
※ 班固は、『史記』を記した司馬遷と違い、儒教や漢王朝第一の考えが強いため、蒯通が韓信に斉を討伐させ、謀反をそそのかしたことにより、韓信と劉邦の仲を裂いたことに対して、強い批判の思いがあるようである。
創作作品における蒯通は、弁士として生きながらも、韓信にかなりの思い入れをし、同情心、理解者としての面が強い人物として描かれやすく、物語の中での重要人物として扱われることが多い。
また、『史記』をベースとした作品が多く、余り『漢書』からは採用されないからか、劉邦から解放された後の『漢書』における蒯通の活躍については、ほとんど言及されない。
『三国志平話』では、蒯通は生まれ変わって諸葛亮に転生したとされるが、なぜか、韓信に転生である曹操に仕えず、彭越の転生である劉備に仕えている。
創作物における蒯通
司馬遼太郎『項羽と劉邦』
「ふるい戦国の世の詭弁や詭計 が、まだ通用するものと信じ、多年、研究している人物」として、縦横術を説くが、劉邦や項羽に相手にされず、韓信の斉討伐の途中で、その幕下に新たに加わった弁士とされる。
政略の感覚が全くない韓信により、その欠点を補うことができる人物として重んじられ、韓信はその言葉に従い、斉を攻め、(この小説では)韓信の数少ない理解者であった酈食其を死なせてしまう。
蒯通は、「韓信の帝国」をつくろうと、韓信のために様々に画策するようになるが、自分の軍才を利用しようとしない寡欲な武人である韓信は思い通りにならず、蒯通の必死の説得にかかわらず、韓信は劉邦を裏切ることはなかった。
蒯通は狂ったふりをして、逃亡するが、韓信の死に際の発言により、劉邦に捕らえられる。
蒯通は、必死に、劉邦に自分の信念を語り、許される(この場面が「大学のセンター試験」に出題されたことがある)。
蒯通は釈放されるが、「死んだほうが、ましだった。天下を動かすために弁論を学んだのに、たかが、おのれの命 をすくうために役立っただけだ」と、つぶやいた、という場面で出番は終了している。
また、史書にはない、侯公(コウコウ、後述)との遊説家同士の友情も描かれている。
蒯通について
蒯通の天下三分の計は、実現性は存在するのか?
蒯通が、韓信に献策したいわゆる「天下三分の計」は「実現性のない献策であったため、韓信はこの献策に乗らなかったことは正解であった」とあったと評されることが多い。
その理由としては、
1 韓信の武将は、曹参、灌嬰(カンエイ)など劉邦に長い間仕えていた人物たちであり、彼らを殺害したり、捕らえたりしても、軍が機能しない。
2 韓信は斉をだまし討ちにして、斉を奪った人物であり、斉の人物たちを登用しようとしても、忠誠心が期待できない。
3 斉一国だけでは、天下三分するには力不足であり、国家運営を行うには経験不足である韓信、蒯通、李左車だけでは、官僚制の形成は期待できず、漢はもちろん、楚にも対抗しにくい。
などが挙げられることがある。
ただ、(創作作品では、蒯通は韓信に天下を奪わせたいと考えていることがあるが)、蒯通の考えは本文で分かる通り、あくまで、「韓信を斉で自立させて、趙や燕とともに、天下三分の勢力を形成させ、天下の国家に戦争をやめさせ、その盟主とさせること」であり、「韓信に天下を統一させること」ではない。
蒯通が「韓信が天下を統一させるように進言した」という思い込みは、「三国志」などの後の時代において、「中国が統一されていること」が当たり前の時代から来るものであり、この時代は、秦王朝の統治期間である十数年を除いては、天下が統一されるのが前提という考えは存在しない(殷王朝や周王朝は、あくまで、都市国家の盟主の扱いである)。
こう考えた場合、「1」の「曹参たちが韓信に賛同せず、彼らを処分しなければならない」という意見も再考の余地がある。曹参たちも、「劉邦からの恩賞がきちんと出るか」は気にしているはずであり、「劉邦に直接的には敵対せず、あくまで平和を望む形であり、自分たちへの恩賞がでるなら」賛同する可能性もある。
特に、曹参は劉邦の武将たちの代表的な存在であり、仲間や部下の代弁者として、劉邦に恩賞を要請すべき立場にあり、劉邦からの恩賞よりも、確実にもらえる韓信からの恩賞を期待する可能性もある。実際に、曹参は、韓信に自立をそそのかした蒯通を賓客として重用しており、劉邦に必ずしも忠実でなかった気配がうかがえる。
その場合は「2」の「斉の人物を無理に登用しなければならない」という問題も解消する。
「3」についても、あくまで「平和を望み、諸国のバランスのもとに斉の韓信が盟主になる形」なら、蒯通の発言どおり、燕王の臧荼(ゾウト)や趙王の張耳(チョウジ)も、粛清される恐れがある劉邦の臣下となるよりも、それを選ぶ可能性がある。
実際に、後に、臧荼は劉邦に反乱を起こして処刑され、張耳はその子の臣下が劉邦暗殺を謀り、国を奪われているため、現実的に考えられる話である。
このように、実際に、韓信が蒯通の言葉通り、「自立できるか」、「臧荼と張耳が韓信に同意し、漢と楚に戦争をやめさせ、天下の盟主となることができるか」はともかくとして、ネットなどで見られる蒯通の「天下三分の計」を否定する意見は、「前提からして誤っている」可能性があることは注意すべきである。
曹参は蒯通の計略に賛同していたのか?
本文の通り、斉の相国や丞相であった曹参は(必ずしも断定はできないが、『漢書』の時系列によると)、「蒯通が、韓信へ劉邦からの自立をそそのかしたことが発覚し、劉邦に処刑されそうになった」後も、蒯通を賓客として重用し、その意見により、多くの人材を登用して、政治を行っていた。
これを見ると、蒯通は、蓋公(ガイコウ、後述)と並ぶ曹参の重要な政治顧問だったように思われる。
曹参は韓信が斉王だった頃も、斉の相国として、韓信の軍事や政治の補佐にあたっていた人物であり、当然、蒯通とは面識があると考えられ、その頃からすでに、かなり親しかった可能性もありえる。
さらに、韓信が酈食其を犠牲にしてでも、蒯通の進言に従い、斉を攻撃した時も、曹参もまた、その軍に加わっており、韓信の副将格であるにも関わらず、韓信を諫めたり、止めたりするような進言は残っておらず、積極的に加担していた可能性もありえる。この時、すでに、蒯通は曹参と面識があり、その進言に同意していた可能性もまた、否定できない。
このように、曹参は蒯通の進言に同調する動きが多々見られるため、曹参は蒯通の「韓信を斉で自立させて、趙や燕とともに、天下三分の勢力を形成させ、天下の国家に戦争をやめさせ、その盟主とすること」に対して、承諾していた、あるいは承諾する可能性は高かったことも考えられる。
上述した通り、曹参は劉邦の武将たちの代表的存在であり、劉邦からの恩賞について、彼らを代表して要求する立場であった。そのため、大盤振る舞いしすぎて恩賞を期待できない劉邦よりは、韓信の方が恩賞を与えられ、「劉邦に直接的には敵対せず、あくまで平和を望む形であるなら」賛同していた可能性も高いと考えられる。
曹参たちは(黥布(ゲイフ)や張耳のように)、「劉邦からの恩賞として、王となることを望んでいたのではないか」と考える研究者もいる。
あくまで、推測であるが、「曹参は劉邦に忠実な家臣であり、韓信の監督的な立場として、劉邦からの命令で、韓信を監視していた」という一般的な理解(そのように主張する研究者もいる)が「必ずしも正しいとは限らない」ということは注意すべきである。
斉の諸子学派について
本文の通り、蒯通たち多くの弁士や学者が、斉の地に集まったのは偶然ではなく、(中国の)戦国時代から諸子百家(しょしひゃっか。様々な思想家の学問の派閥や思想家を指す言葉)が斉に集まっており、斉の地において、そのような学者が大事にされる風土が存在したからである。
これは、戦国時代の斉の威王(在位:紀元前358年~紀元前320年)と宣王(在位:紀元前319年~紀元前301年)が、各国を回って遊説を行い、自分たちの思想を売り込み、互いに論争を繰り広げていた諸子百家のうち、高名な学者を招いて、斉の都である臨淄(リンシ)に集め、上大夫の待遇で優遇した政策によるものである。
集められた諸子百家の学者は、臨淄の稷門(ショクモン)の下に屋敷を与えられ、「稷下の学士(しょくかのがくし)」として総称された。多い時は、千人が集まった。
彼らは激しい論争を行い、互いに思想的影響を与えつつ、その学問を高めあった。このため、臨淄は中国の学問・思想の中心地となり、諸子百家の黄金時代を形成した。
その後、一時期、稷下の学問は戦乱のため、衰退したことがあったが、斉の襄王(在位:紀元前283年~紀元前265年)時代にすぐ復興し、紀元前221年の斉が滅びる戦国時代の最後まで諸子百家は臨淄に集まる状況を続いた。
その後、秦による思想統制や焚書(ふんしょ)などもあったが、生き残った諸子百家によって学問は受け継がれ、蒯通のような遊説家がその学問を生かそうと、秦末の戦乱や楚漢戦争で各地を遊説し、平和な世になると、また、斉に集まってその学問を治世に生かしたものと考えられる。
漢王朝は思想統制をしなかったため、諸子百家は生き残ったが、乱世ではないため、黄老思想の学者と儒学の学者以外は、優遇されることはなく、次第に衰退し、さらに漢王朝において儒学が主流を占めるようになると、完全に滅ぶか、学者が儒学に転向して、その学問は、儒学の一部として吸い取られていったものと思われる。
斉の風土と斉人の気質について
斉の土地に住む人柄などについては、『漢書』地理志や『史記』貨殖列伝に詳しい。
まず、『史記』貨殖列伝によると、
斉は山と海に囲まれ、肥えた土地は千里(約500キロメートル)も広がり、桑や麻を植えるのに適し、人口は多く、麻や絹、塩や魚を生産する。その中心である臨淄は大きな都市である。
住民の気風はおおまかや闊達であり、知恵は充分で議論を好む。土地が大事であるため、簡単なことでは動かない。集団での戦いには臆病であるが、単独の決闘では勇敢であるため、強盗するものが多い。大国の風情があり、民は、士・農・工・商店の商人・行商がそろっている。
としている。
斉の人々は、学問を好み、功名をほこるものが多く、おおまかで闊達であり、知恵もあるが、その反面、おごり高ぶり、徒党を組み、言葉と行動が一致せず、嘘が多く、それを取り締まろうとすれば逃げ去り、放置しておけば、気ままになる。
としている。
斉の人々は、このように「学問を好み、功名をほこるものが多く、おおまかや闊達で、知恵があり、議論を好み」かつ、「おごり高ぶり、徒党を組み、言葉と行動が一致せず、嘘が多い」人物が多い傾向にあるようであり、これは、蒯通ら弁士たちのことを指すものと考えると、うなずけるものが多い。
蒯通に関係する人物たち
ここで、蒯通の進言をうけいれた武臣、司馬遼太郎『項羽と劉邦』において、蒯通の親友と設定された侯公、同じく曹参の顧問となった蓋公(ガイコウ、コウコウ)をあわせて紹介する。
武臣(ぶしん)
陳勝(チンショウ)の古くからの知り合い(※)であり、陳(チン)県に住んでいた。
※ 陳勝は陽城(ヨウジョウ)に住んでおり、かなり離れているため、すでに知り合っていることということは、陳勝や武臣は、元々からただの農民ではなかったのかもしれない。
紀元前209年7月、陳勝は秦王朝への反乱を起こす(「陳勝・呉広の乱」)。
陳勝たちは武臣の住んでいた陳を制圧すると、国号を張楚(チョウソ)とし、王を名乗る。この時には武臣は、陳勝から重んじられる腹心の一人になっていたものと思われる。
陳勝は、賢人として迎え入れられていた陳余(チンヨ)から、「兵をもらい、趙の地を攻略したい」という提案を受けた。
そこで、武臣は、陳勝に将軍に任じられる。武臣は、護軍(ごぐん、副将)の邵騒(ショウソウ)と左右校尉(こうい、武将)の張耳(チョウジ)・陳余と、三千の軍勢とともに、北上させて趙の地を攻略する。
武臣らは、北上して黄河(コウガ)を渡ると、趙のあった河北(カホク)の地に着くと地元の豪傑たちに説いて回った。
「秦の政治は乱れ、刑罰は残虐で、天下を損なうことは数十年に及ぶ。天下の人々は、秦によって長い間苦しめられてきた。陳王(陳勝のこと)は勇気を奮って、天下のために事を起こした。この時において、(陳勝に従って秦を討伐し)、土地持ちの封侯(となる)となろうとしないものは豪傑ではない。諸君らも一緒に無道の君を攻め、父兄の恨みに報いて、封侯されるために、立ち上がろうでないか!」。
河北の豪傑(地方の有力者)たちが賛同すると、武臣は行軍中に兵を集めて、数万人の兵を得た。武臣は「武信君(ぶしんくん)」と号した。武臣は、趙の地にある10の城を降伏させる。その時、秦から送られてきた役人は全て処刑した。
河北の残りの城は全て防衛を行い、降伏に同意するところはなかった。そこで、武臣は兵を率いて、東北にある燕の范陽を攻撃する。
この後は本文の通り、武臣は蒯通の進言に従い、河北の30余の城も降伏させる。
同年8月、武臣はさらに進軍して、趙の都があった邯鄲(カンタン)に地に至った。
この時、武臣は、「王に即位し、自立をすすめ、陳勝の元にもどることに反対する」張耳と陳余の進言に従い、「趙王」を称し、張耳を右丞相(じょうしょう、宰相)に、邵騒を左丞相に、陳余を大将軍に任じる。
正確な時期は不明だが、三国志の司馬懿(シバイ)の先祖にあたり、後に殷王となる司馬卬(シバゴウ)も武臣の配下となり、その武将となっている。
陳勝はやむをえず、妥協して武臣が趙王を称するのを認めたが、武臣らの家族を宮中に拘束し、武臣に、秦への函谷関(カンコクンカン)攻撃を命じる。しかし、武臣は、張耳と陳余の進言に同意し、兵を(秦のある)西に向かわせず、北の燕の地と、南の黄河に近い土地を攻略しようとした。
武臣は、配下の韓広(カンコウ)に燕を、李良(リリョウ)に趙の恒山(コウザン)を、張黶(チョウエン)に上党(ジョウトウ)を攻略させた。
同年9月、韓広は、燕の地で、武臣から自立して、燕王を名乗る。
臣は張耳・陳余とともに、北上して燕の軍と交戦するが、武臣はひそかに出ていってしまい(詳細は不明)、燕の軍に捕らえられてしまった。
武臣を拘束した燕の武将は、趙軍を率いる張耳と陳余に、「趙の土地の半分を分けて燕にくれれば、趙王(武臣)は帰そう」と要求する。趙から十数人の使者から送られたが、燕に使者は殺され、土地を与えることが要求された。
この時、趙の兵舎にいた雑役の兵士の一人が、使者として、燕に行き、「張耳と陳余の本当の望みは武臣が死に、自分たちが王となることである。そうなったら燕は滅びるであろう」と説得する。
そこで、燕は、武臣は返すことに決め、武臣はその雑役の兵が御者を務める車に載って、趙に帰還した。
紀元前208年11月、先に派遣していた李良が恒山を平定したため、帰還して報告してきた。武臣はまた、李良に太原を攻略するように命じた。
李良は秦軍が井陘関(セイケイカン)を塞いでいたため、前進できなくなり、秦から内通の勧誘が行われたが、これを無視して、邯鄲に引き返して増援の兵を請おうとした。
李良が、邯鄲に着く道中で、武臣の姉が乗る車の行列を見て、武臣の車の行列と思って拝謁したが、武臣の姉は酔っていて李良であると気づかず、車から降りずに、騎兵に李良に挨拶させた。軽んじられたと感じた李良は、激高する兵士たちとともに、まず武臣の姉を殺害して邯鄲を襲撃する。
邯鄲にいる武臣たちは、この動きに気づかなかった。武臣は邵騒とともに、李良に殺されてしまい、張耳と陳余は逃走した。
この後、張耳・陳余らは趙の旧王族の趙歇(チョウアツ、陳余の項目「陳余に味方した人物たち」参照)を趙王として即位させ、信都(シント)を根拠地として、趙を再興させている。
あくまで、陳勝の古くからの友人であり、一個人として優れていたかはともかく、乱世において、一国の王となれるような人物ではなかったと思われるが、蒯通・張耳・陳余など多くの人物の活躍の機会をつくった人物であり、孔子の子孫である孔鮒(コウフ)との問答が『孔叢子』(こうそうし)という儒家の書物に残るなど、意外に歴史に多くの足跡を残している。
侯公(こうこう)
姓が侯(コウ)であるが、名が伝わらなかったので、「侯公」と呼ばれるようである。
紀元前203年8月頃、劉邦が険阻によって、項羽と対峙していた。この時、劉邦は項羽の武将である曹咎(ソウキュウ、※)を打ち破り、劉邦の武将であった韓信もまた、項羽の武将である竜且(リュウショ、※)を打ち取り、劉邦の軍は圧倒的優位に立ち、また、兵糧も劉邦の軍は腹いっぱい食べられたが、項羽の軍は、劉邦に味方した彭越(ホウエツ)によって、兵糧を絶たれて、飢えていた。
しかし、項羽によって、劉邦の父である劉太公(リュウタイコウ)や妻の呂雉(リョチ)が人質にされており、また、韓信と彭越の援軍が来ないこともあって、劉邦は思い切って、項羽を攻撃できないでいた。
この頃、侯公は、劉邦の弁士の一人として、劉邦の配下となっていた(臣下の一人なのか、あくまで客の立場なのかは不明)。
劉邦は、まず、配下の陸賈(リクカ)を項羽への講和の使者として送り、劉太公たちを、劉邦のもとに帰すように要請させたが、項羽によって断られた。
そこで、今度は、侯公が、項羽の使者として選ばれ、劉邦に、派遣と説得を命じられる。侯公が項羽を説得すると、項羽は「漢と楚が天下を二分し、(滎陽のあたりに流れる河である)鴻溝(コウコウ、※)より西は、漢の領土とし、東は楚の領土とすること」を約束し、講和に同意する(紀元前203年9月)。
※ かつて、紀元前225年に、始皇帝の将軍であった王賁(オウホン)が、黄河の水を引いて、魏の都である大梁(ダイリョウ)に注いだ時に河になったものが、「鴻溝」と呼ばれていた。
これにより、項羽は劉邦の「父母妻子」を帰した。これには、当然、劉太公と呂雉が含まれ、劉太公の妻(劉邦の実母ではない可能性が高い)と、劉邦の長子である劉肥(リュウヒ)が人質にされていたものと考えられる。
漢軍と楚軍の兵士たちはみな、(戦争が終わったと考え)、「万歳」をさけんだ。
講和の使者に成功し、人質となっていた劉邦の「父母妻子」を帰させることに成功した侯公はこの成功により、劉邦から「平国君」に封じられた。
劉邦は、「侯公こそまさに天下の弁士だ。あいつがいれば、その弁舌で国を傾けることができる」と侯公を評し、それゆえに「平国君」と号させた。
しかし、侯公は、それから身をかくして劉邦に謁見しようとしなかった。
侯公に関する記述はこれだけであり、最後の傍線文は、『史記』では「匿弗肯復見」という文であるが、意味がよく分からない文章であるため、
- 「名を挙げた侯公は、満足して、劉邦のもとから去っていった」説
- 「その後、劉邦が一方的に項羽との講和を破るため、劉邦が侯公を項羽からの詰問の使者などに会わせなかった」説
- 「劉邦の侯公に対する『その弁舌で国を傾けることができる』人物という評価に、後難を恐れて、突然、逐電した」説
がある。
なお、侯公が取り付けた、項羽の劉邦との講和と領土の約束は、劉邦によって一方的に破られ、そのために、項羽は滅亡している。劉邦は、元々から人質を取り返したら、項羽との講和を破るつもりだったと思われ、そのために、侯公を「その弁舌で国を傾けることができる」人物と評したと思われる。
なお、上記の司馬遼太郎『項羽と劉邦』では、侯公は、蒯通と弁士仲間であり、親友とされ、ともに弁舌で天下を動かすことを生き甲斐にして、弁舌のために生きる人物とされ、侯公そのものは『史記』でも、ほとんど登場しない人物であるにも関わらず、主要人物の一人として多くの出番が与えられている。
史書では、特に、侯公と蒯通が知り合いであったことを示す記述は存在せず、これは、司馬遼太郎『項羽と劉邦』における完全な創作である。
蓋公(がいこう、こうこう)
姓が蓋(ガイ(コウ、と呼ぶべきかもしれない))であるが、名が伝わらなかったので、「蓋公」と呼ばれる。
(中国の)戦国時代の燕の名将である楽毅(ガクキ)の一族に、楽瑕公(ガイカコウ)と楽臣公(ガクシンコウ)という人物がいた。楽毅が趙に亡命した後、この二人も楽毅に従い、趙に行ったが、趙が秦に滅ぼされそうになった時、二人は斉へと亡命した。
楽瑕公は、毛翕公(モウキュウコウ)という人物から学んだ黄老思想(こうろうしそう、曹参の項目、「曹参について」の「黄老思想」参照)を楽臣公に伝えた。
蓋公はその楽臣公から黄老思想を学び、斉の高密(コウミツ)や膠西(ロウセイ)という都市でその学問を教えていた。蓋公の黄老思想は、統治に役立つという評判が経っていた。
紀元前201年頃、劉邦の長子・劉肥が斉王となり、曹参が斉の相国に任じられる。まだ、十代と思われる劉肥に代わり、曹参が政治を行うことになり、曹参は斉の各地にいた長老や学者を全て集め、民を安んじる方法をたずねた。
しかし、百人以上いた各人が好き勝手に話し出して、曹参はどうすべきか、決められなくなった。
この時、膠西にいた蓋公は、その評判を聞いた曹参に厚い待遇でまぬかれた。
蓋公は、曹参にあって、黄老思想による治世の方法を曹参に伝えると、曹参は、政治を行う正堂の座を避けて、蓋公に座らせる(蓋公に自ら政治を行うようにした)。
曹参が斉の相国や丞相の地位にいて政治を行った9年の間に、斉はよく治まり、曹参は大いに、「賢相(すぐれた宰相)」と称されようになった。
紀元前193年、曹参は漢の相国となり、漢王朝を治めたが、やはり、すぐれた統治を見せた。
その後、漢の武帝時代の初期まで、蓋公の伝えた黄老思想は、50年以上も前漢王朝の統治方針であり続け、後から採用された儒教と違って、大きな失政を犯したことはなかった。
関連書籍
浅野裕一『諸子百家 』講談社学術文庫
』講談社学術文庫
蒯通に関する専著は存在しないが、蒯通らの大先輩にあたる『諸子百家』への、理解が深めるための書籍を紹介する。
序章で「諸子百家について」説明が書かれ、時代背景と主な思想の概要、彼らの活動とその動機と終焉について記されている(この項目のうち、「斉の諸子学派について」は、この書籍を参考にしている)。
扱っている思想も、老荘思想・儒学・墨子・韓非子は通常通りであるが、それ以外は、楊朱(ヨウシュ)、恵施(ケイシ)、公孫龍(コウソンリュウ)、鄒衍(スウエン)、孫子とラインアップが珍しい。
ただし、儒学の孔子と孟子だけは、特殊な考えで扱われているため、儒学について知りたい方には、まずは、別の書籍をおすすめする。
これで、蒯通ら弁士が活躍した時代背景が理解できる。
関連項目
- 2
- 0pt