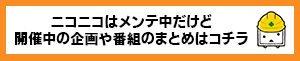普通選挙とは、すべての成人が選挙権を行使できる選挙体制である。対義語は制限選挙
概要
小学校の公民で必ず習うように、我が国は1946年に日本国憲法が施行されて以来、18歳以上の全成人が国政選挙に携われるようになっている。
また、一般的な文脈では年齢と性別に重点が置かれることが多いが、財産資格などの制限撤廃も含まれている。
憲法において、我が国の選挙の基本原則は、誰でも同じ価値を持つ平等選挙、誰が誰に投票したかわからないようにする秘密選挙、選挙人の自由な意思による投票を定めた自由選挙、そして、一定の年齢に達した全国民に選挙権を付与する普通選挙の4つの大原則で成り立っている。
1945年の衆議院議員選挙法(現在の公職選挙法)改正時は、20歳以上の全国民とされていたが、近年の世界各国における成人年齢引き下げの潮流に応じて、2015年に18歳へと引き下げられた。高校生にも選挙権が与えられるということで、記憶にあたらしい人も多いだろう。
普通選挙は、誰にでも投票の機会を与えることによって、民主政治への正当性を与えることを目的としているわけだが、なにを以て『普通』とするかはこの世に議会制民主主義が誕生してから、そして現在に至るまで大きな議論がなされており、結論をみていない。
男女普通選挙が我が国において成立してからも、2013年に成年被後見人(旧・禁治産者)に対する選挙権・被選挙権を与えないとする旨(公職選挙法11条)の規定が違憲であるとの判断が示されたり、2005年にも在外国民への選挙制限を同様に違憲であると示されており、その定義は時代を下るごとに変化し続けている。
しかし、今我々が享受している普通選挙という権利を手に入れるまでには、永い苦難の歴史があった。
歴史
国家における政治に携わる権利は、古代ギリシャにおける直接民主制が廃れて以来、18世紀の中頃にいたるまで、王侯貴族など上流階級に限定されていた。
とはいえ、それに承服している人間ばかりではなかった。例えば17世紀のイングランドで発生した清教徒革命の中にはリルバーン率いる水平派と呼ばれる一派があり、これは読んで字の如く、土地の均分や、選挙権の人民の数に応じた公平な分配、すなわち普通選挙を求めていた。とはいえ、まだまだ貴族による政治が中心であった時代にこの主張は受け入れられ難く、当初は革命を主導したクロムウェルの支持基盤となっていたが、国王チャールズ1世の処刑を契機に対立が表面化し、激しい弾圧を受けることになる。
それから時代を下るごとに、社会契約説や、人権思想が普及して、少しずつ選挙権の拡大を求める声が大きくなっていった。そして、1789年のバスティーユ牢獄襲撃に端を発するフランス革命によって、王政は倒され、遂に普通選挙による民主政が……!! とおもいきやそう簡単にはいかなかった。
そもそもフランス革命に関わった知識人や活動家の全員が、完全な民主政を望んでいたわけではない。彼らの中で(比較的)一致していたのはあくまで絶対王政の打倒であり、その先の政治体制や運用においては百家争鳴ともいうべき様々な意見の対立があった。バスティーユ襲撃直前につくられた国民議会を構成する約1200名の議員の中には極右から極左まで大きくわけて6つの派閥に分かれている。
右派の中心となったのは王党派であり、彼らが求めたのはあくまで絶対王政の軌道修正程度で、国王に法令の拒否権を持たせたり、庶民院の他に貴族院を設置するなど旧体制(アンシャン・レジーム)の少なからぬ維持を主張していた。当然彼らの主張の主軸は軟化したとはいえ絶対王政なので普通選挙など思いもよらぬ事である。二院制は一見民主的にもみえるが、彼らは貴族院の中で、特権階級の牙城を形成して、その権力を維持することに固執していた為、実態はその逆であった。
その反対の左派の中心となったのは、世界史の教科書でも有名なジャコパンバン派である。ジャコバン派は、二院制ではなく、出身階級の別に関わらず国民代表として、国家の意思決定に関わる一院制を主張し、国民による選挙を行うとしていた。しかし、ジャコバン派の中でも内部対立があり、普通選挙による人民議会を求める最左派(民主派)と、制限選挙による資産家による議会を求める中間派に分かれていた。フランス革命の担い手となったのは、新興の裕福な商人などを主体とするブルジョワジーであり、彼らからすれば自分が政治に関われればそれで問題ないからである。
結局、憲法制定は中間派が主導権を握り、1791年制定の憲法では一定以上の納税者のみを選挙人として認める、制限選挙に落ち着いた。(とはいえ、絶対王政を否定して、立憲君主制に移行できたことは特筆すべきことである)
しかし、見れば分かる通りこれでは民主派が納得するはずがない。この憲法によって1791年10月に立法議会が成立したが、後に恐怖政治で名を轟かせることになるロベスピエールの提言で、憲法制定国民議会の解散寸前に、国民議会の議員は立法議会の議員になれない事を決議したせいもあって、素人の集まりと化した議会はいたずらな対立を繰り返して、国外から迫りくるオーストリアやプロイセンなどからの干渉戦争や、ルイ16世の拒否権濫発による停滞、アシニア紙幣のインフレーションなどといった国内外の諸問題を解決できなかった。そのため、市民の怒りが爆発した1792年8月10日のテュイルリー宮殿襲撃(8月10日事件)によって王政が事実上停止され、立法議会は機能不全となった。
8月10日事件の翌日、立法議会は新たなる議会(国民公会)における選挙の規定を公布した。その中では遂に財産による資格制限が撤廃され、21歳以上の男子による普通選挙が行われることが明記されていた。(但し、この時点における普通とはいわゆる一人前の大人を指し、主人の家に住み込む奉公人や召使いは除外され、また女性も参政権が与えられなかった)
こうしてめでたく、世界で初めて普通選挙が行われることとなったが、実際のところ、それで盛り上がっていたのは、テュイルリー宮殿を襲ったパリの民衆たちくらいで、地方の下層労働者は日給惜しさに選挙に行かず、中間層の労働者たちも、せいぜいコミューン(我が国でいう地方選挙)への関心どまりで、国政選挙にはさして興味を持っていなかった。そのため、有権者700万人のうち、投票したのはわずか70万人ほどにとどまり、議会の構成は派閥は入れ替われど、出身階層はそう変わらぬものにとどまった(第一共和政の成立)。
教育が行き届かず、毎日食うや食わずの人が大半の当時のフランスにおいて、普通選挙が真価を発揮するにはまだまだ時間が必要であった。翌年にはジャコバン憲法と呼ばれる、この普通選挙を盛り込んだ1793年憲法が成立したが、選挙の実施は延期され、結局この憲法下で選挙がなされることはなく、ルイ16世の処刑やロベスピエールの恐怖政治を経て成立した、1795年憲法では元の制限選挙へと戻ることに成る。
その後、ナポレオンが政治の実権を掌握し、皇帝となって第一帝政が布かれ、ナポレオン戦争を経てウィーン体制が成立して、時代は一時、普通選挙の思想から離れた復古王政が支配するようになったが、1848年の2月革命によって第二共和政が成立し、その際には大統領と国会議員の選挙で実に56年ぶりに男子普通選挙が復活した。世界史でも説明されるように、1848年に起きた様々な自由主義運動は1815年に成立した、王政のあがきといえるウィーン体制が崩壊し、少しずつではあるがヨーロッパ諸国に自由主義体制への移行を促していった。
そのため、1848年にはスイスが、1849年にはデンマーク、1871年にはドイツで次々と普通選挙が導入されていくことになる。(我が国においては1925年に25歳以上の男子に認められたのがはじまりである)
さて、ここまでの普通選挙はあくまで、男性についてのみ触れてきたが、女性は折からの男尊女卑思想から、選挙権は与えられなかった。しかし、19世紀中盤から、社会主義思想の台頭や、労働組合運動の高まりによって、女性への選挙権導入が叫ばれるようになり、いち早く1893年に世界で初めてニュージーランドにおいて女性参政権が認められた。これは大英帝国で最初の女性市長となったエリザベス・イェーツ女史をはじめとした女性参政権運動の賜物である。20世紀初頭にはオーストラリア、フィンランドなどが続いたが、いわゆる列強諸国での女性参政権は低調であった。
しかし、この潮流を大きく変えたのが第一次世界大戦である。第一次世界大戦はいわゆる国家総力戦であり、あらん限りの国力をすべて戦争に傾注することが要求された。また、第一次世界大戦の死者はそれまでの戦争に比べてまさに桁違いであったことから、男性の大半は兵役に駆り出された為、女性であっても軍需工場や看護などの後方支援などで戦争への協力を余儀なくされることとなる。
そのため、女性運動家たちはその対価として、選挙権を要求し、大戦の終戦直後から、1918年に英国(男女との差がなくなるのは1928年)やドイツで、やや遅れてアメリカ(州レベルでは1911年から)で1920年に女性参政権が認められるようになった。次に主要国で認められるようになるのは第二次世界大戦後で、1945年にフランス、イタリア、そして我が国においてそれに続いていくこととなった。普通選挙自体は先進的であったフランスが、女性参政権では後発組なのは中々興味深い事象であるといえよう。
関連項目
- 2
- 0pt