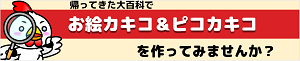社会保険とは、保険の仕組みを利用した社会・国家のシステムである。
日本国においては防貧制度の多くが社会保険で構築されている。
概要
社会保険や保証制度として設計された国家制度としての保険のことであり、日本では多くの社会保障制度や緊急時用のセーフティーネットが公営保険にて実装されている。なお、公営保険の場合には保険収入に合わせて税金投入されることで収支をとる場合が多い。これは私営保険には見受けられない特徴で、補助を行うことにより本来保険として見た場合には不採算である事業に対しての保険を成立させている。
つまり保険の基礎構造(保険を参照)を厳密には守っていないのである。
そうなる大きな理由としては社会保険を組む場合、国家が期待するのは保険の持つ貯蓄性であり、保険料の蓄積は保障の元金であると同時に国家運営に流用するための元本としても見込んでいるためである。社会保険の発祥地であるドイツに限らず戦前に年金を成立させた日本でも目的が軍事費の捻出であり、戦後は公共事業を行うための財政投融資に付け替えられ動作し続けてきた。
その一方で、先進国であれば困窮した国家財政の変わりに国民に負担をもたせることの出来る社会保険は、社会福祉の向上のために有効な手段であり、主に欧州を中心にして普及したのである。
以上のことから、社会保険にはおおよそ以下の特徴がある。
- 保険の仕組みを流用した国の制度である。
- 防貧制度として活用される(制度の基礎構造上、救貧制度に使えない)。
- 運用として資金を他に流用できる。
- 社会保険の多くが保険料だけではなく、税金も投入する形で維持している。
- 一定以上の国民の豊かさがある国でしか採用できない(保険料支払いが出来るだけの豊かさが必要)。
- 上記のことから発展途上国や貧困国ではあまり見られない制度となっている。
- 日本のように保険料を企業と個人で折半払いの場合、事務手続きの大半を民間企業に押し付ける任せることが出来る。
- 上記のことから社会保険の比重の多い日本においては、他国と比べて行政機構の事務量が少なくなっており、結果として公務員総数を軽減できている。日本の公務員の総数が他の国と比較して少ないのは社会保険も関係している。
- 破綻した場合の世界への影響は推察が難しい。理由は運用の形で世界経済に深くかみこんでしまっている例が多いからである。
- 年金系ファンドが多数存在する。
- 2015年時点において資産規模で世界最大の投資ファンドは日本の社会保険の資産を運用するGPIFである。
- 社会保険の加入が強制であるいわゆる「強制保険」の場合が多い。その場合、国民消費という視点で見た場合、税金で負担が強いられるのと大きくは変わらない。
- 日本国においては保険料が上がり続けており、それとは無関係に消費税増税も実施されているため総額としての個人、企業の負担が増加し続けている。
- 上記のことから消費税増税に合わせて、社会保険料、とりわけ企業負担分軽減を強く主張する企業が後を絶たないが、原則として消費税と社会保険には直接の相関関係はない。
- 日本の社会保険は特別会計がそれぞれ対応する形で存在する。これは個別会計を行う為である。
以上のように構造が複雑になりやすく癖のある制度ではあるが、その一方で重宝できる側面があるのが社会保険である。とくに身内での「たすけあい」「おたがいさま」を比較的好む村社会日本人には受け入れやすかった側面もあり、日本では多くの社会システムが社会保険の形で実装されている。
歴史
比較的近年に構築された制度であり、始まりは1880年代のドイツであり宰相ビスマルクの政策であった。当時、イギリスに比較して社会保障が貧弱だったドイツが工業化を進めるにあたって社会保障を国家の税収に頼らず構築するために編み出したものである。
皆保険への道
現在の社会保障の根幹である社会保険の整備は、戦後、1950年代なかばから本格的に開始される。
戦災から復興する過程で、サラリーマンや工場労働者を対象とした職域による被用者保険(医療・年金・労災・失業保険を包括している)は、徐々にその機能を回復しつつあったが、農民や自営業者を対象とした、戦中の地域保険(主に医療を対象)は、 もともと基盤が脆弱で、戦災からの復興で自治体が財政的に疲弊していたため、事実上機能しなくなっていた。このような状況であったため、一から新たな社会保険制度を創設するのではなく、機能している職域保険はそのままで、そこから漏れている人を対象に、追加的な社会保険制度の創設がのぞまれた。そこで、1958年に誕生したのが、「国民健康保険(以下、国保)」である。
職域による被用者保険の未加入者は、市町村を単位とした国保が受け皿となった。
なお、1961年までに全ての市町村で国保が組織され、医療保険の皆保険が制度的に達成された。同一の保険制度で、職域保険と地域保険が混在するのは、世界的に極めて珍しい例であり、現在もなお日本の医療保険はこの枠組で運営されている。
また、年金保険制度は1959年に「国民年金保険法」が制定され、これもまた被用者保険の未加入者を対象とするものであった。年金保険は、国保とは異なり、管轄は国家単位でおこなわれた。現行の基礎年金制度と厚生年金制度による2階建ての構造は、1985年に施行されたものであり、当時の枠組みとは異なる。
制度の変遷に関する詳しい説明は割愛する。
国保の保険料は、国民健康保険税として扱われ、開設当時から納付が義務とされたため、全市町村で国保が整備された時点で、原則的には医療保険の皆保険が達成されたと言える。が、国民年金保険料の納付は、給付が「納入期間に応じる」ものであったので、1986年に20歳以上の保険料納付が義務付けられるまでは、原則的には皆保険ではなかった。かくして、1960年代には、社会保険の骨子である公的な医療保険制度と年金保険制度が整備され、日本の福祉国家体制は加速していくこととなる。
福祉元年と福祉国家の危機
1960年代は、池田内閣の「所得倍増計画」や東京オリンピックによる好景気に象徴されるように、日本が先進国への道を突き進んだ時代であった。国民所得の増大は、税収や保険料の増加を意味し、社会保障政策においても、医療保険給付率や年金給付額の引き上げとその給付内容が拡充された。
さらに、政治の世界では、社会運動の流れもあってか、革新政党の躍進が目立った。1967年には東京都で社会党・共産党推薦の美濃部亮吉が知事選で当選し、全国に先駆けて高齢者の医療費(窓口負担)の無料化をおこなった。これに負けじと、自民党田中角栄内閣も、1973年を「福祉元年」と定め、全国で高齢者の医療費(窓口負担)無料化と、老齢年金の賃金物価スライド制を導入した。
しかし、その矢先、第一次オイルショックが勃発する。日本国内では物価が高騰し、加工貿易に頼っていた国内産業では生産が滞り、1973年は戦後初のマイナス成長となった。日本の高度経済成長は終りを告げ、低成長時代へと突入する。その中で、今まで好調だった税収や保険料収入が滞ることは必然であった。しかし、社会保障制度は、高成長期の水準で勘案されていたため、その後、膨れ上がる社会保障関連財政は、国家予算を大きく圧迫することとなる。
1970年からの10年間で、社会保障関連支出は6.9倍(GDP比2.0倍)の伸びをみせている。これにともない、続く80~90年代では、保険料率や急率の見直し、病床規制などといった、財政抑制のための諸改定が相次ぐこととなった。
このような社会保障財政膨張は、日本に限ったことではなかった。
西側諸国で高福祉国家の代表格であるイギリスは、手厚い保障の対価である重税から国民の労働意欲の低下を招き、オイルショックによる失業率の上昇が、社会保障財政を悪化させていった。また、西ドイツでも「社会保障費(特に医療費)の急激な拡大」と「貧困人口の増加」が指摘された。
本来、社会保険による社会保障制度は国民のリスクを軽減するための政策であるが、それが拡充しているにも関わらず、困窮する国民が増加するという、矛盾に満ちた状態に陥ったのである。くしくも、ローマクラブが市場主義による『成長の限界』を説いた数年後に、市場の失敗を補うはずの社会保障政策を旗印とした、福祉国家体制はその危機を迎えたのである。
日本の社会保険一覧
- 年金保険
- 医療保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)
(2002年の改正自動車損害賠償保障法で再保険部分が撤廃され、現在は純粋な民間保険となっている。) - 森林保険
- 貿易再保険
- 地震再保険
- 漁船再保険
- 農業共済再保険
- 預金保険機構
- 農水産業協同組合貯金保険機構
関連動画
関連商品
関連項目
- 4
- 0pt