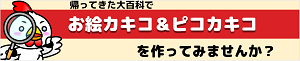連邦とは、強い権限を持つ、複数の国家あるいは自治体(以下は便宜上、構成体と称す)などが連合して対外的に一国家として成立した国体である。この連邦制に基づいて成立した国家を連邦国家(または、連邦国)と呼ぶ。
概要
連邦国家の最大の特徴としては、対外的(外国から見て)には一つの国家として扱われるが、内情はそれぞれの国家に所属する構成体から、主権の一部を譲渡される形になっていることである。
すなわち連邦制を採用する国家においては構成体をまとめる、首都におかれる中央政府(連邦政府)が存在する。しかし中央政府の役割は、日本のように権限と財源が大きい中央政府とは違い、あくまで外交・軍事といった対外的に一つの国家として扱われる以上やるべき職務に限られる。地域主権の究極な形である。
そのため行政はもとより、立法や司法も構成体が有することが多い。アメリカなどでは連邦に加盟する構成体が共通して持つアメリカ合衆国憲法と、州がそれぞれ独自に持つ州憲法の二つがあり、後者は構成体である州内において通用する。
もちろん建前や国号にのみ、連邦制あるいは連邦と称して、ほとんどの権利ないし機関が中央政府の職権下にある国家もあり千差万別である。
なお、連邦制だからと言って共和制であるとは限らない。
そもそも連邦という言葉自体は共和制・君主制と言った君主の有無を問題とせず、構成体と中央政府との関係を指すのである。実際に連邦制を導入しているベルギー王国、アラブ首長国連邦、マレーシアといった例もある。
中央政府と連邦制
このように連邦制は大きな権限を持った構成主体が連合をして、対外的な一国家を形成しているため、地域主権や地域の独自性が大きく、中央政府の強大な権限はある程度減少する。連邦制にはこれに起因する影響がある。
一つは連邦内の構成体同士の経済格差。中央集権国家の場合、中央政府が強力な権限を持っているために徴税権を行使し、予算を編成し、それを執行することができる。それを利用し生産性の低い地域に対し公共事業を行って社会資本を整備したり、産業政策を行うことで不均衡を是正することができる。経済力の強い地域から弱い地域への富の再配分を行える。
連邦の権限が弱いとこれらが限定的にしか行えず、格差が広がったまま是正されないこともある。その状態で統一された通貨を用い資本が自由に移動し生産が行われると、何かと生産性の高い構成体が、生産性の低い構成体をフルボッコにしかねない。
しかし、構成体間の競争原理を失わせるということでもあり、また居住地に使われるはずの税収が無関係な過疎地域に注ぎ込まれるということは都市部の人々からすると不満となりうる。
例としてアメリカは州や市によって税制が大きく異なる。
極寒のアラスカ州などは特に低い税負担だが競争力の高いニューヨーク州は重税で知られる。
一方、中央集権型で地方交付税を分配している日本の地方自治体は都市部も過疎地もほぼ横並びの税制を敷いている。
また地域の経済格差は、そのままその地域に住む人々の福祉や教育にも影響する。端的に言えば豊かな地域は高度な教育を行い所得を向上させることができるが、貧しい地域はそれが中々できず、結果として所得が低いままになってしまう。
これらへの対策として中央政府の権限を強化するという方法があるが、あまり強くすると構成体からの反発も出てくる。かといって「貧乏なのはその構成体の自己責任」とするのなら、「じゃあ自己責任だから、通貨発行権と徴税権を全部よこせ」ともなりかねない。
また司法権の行使、具体的には犯罪捜査などにおいても弊害が生じうる。構成体が高い自治権を有して各個に司法権を持っている場合、連邦の司法権はきわめて限定的になってしまう。構成体域内の犯罪だけならまだ良いのだが、現実には複数の構成体にまたがる広域犯罪が発生するのは珍しくない。よって構成体の司法権が強ければ強いほど、捜査や検挙が不十分になったり、全くできなくなる恐れがある。
対策としては連邦レベルで捜査を調整する機関や、構成体に優先して重大犯罪や広域犯罪を捜査する連邦警察を設置することである。ただし連邦警察の権限が強すぎると、やはり構成体の司法権が弱くなってしまい、自治権が弱められるということになりかねない。
構成体が強すぎるとバラバラの国が融通の効かない状態で存在しているだけだが、中央の権限が強くなれば構成体が主権を持つ意義が怪しくなる。構成体の自治権を尊重すればするほど、連邦国家はこのジレンマに陥ってしまうのだ。
ジレンマによる中央と構成体の溝が深くなると、さらに深刻な事態を招きかねない。中央政府が権限を行使しても異を唱える構成体が従わない、構成体が独立を宣言して公国を自称する、構成体がオーストラリアにコロニーを落とす、仮面をつけたロリコンでマザコンの将校が赤くて3倍速い兵器で立ち向かってくる、若さゆえの過ちを認めたくない、坊やだから死んでしまう、ジェットストリームアタック、「見える、私にも見える」←気のせい、など。構成体の自治性・独立性が強い故に本国からの孤立、独立を目指すことも想定できるということだ。
上の例の大半はフィクションなのでまだ笑えるが、事実連邦国家では構成体と中央政府、及び構成体同士で悲惨な内戦が発生することが歴史上しばしばあり、結果として国家自体に重大なダメージが残ることも稀ではない。例えば
- アメリカ合衆国:南北戦争
南部諸州が奴隷制への中央政府の圧力を理由にアメリカ連合国として分離独立を宣言。最終的に合衆国は連合国を屈服させ、分離した諸州を再び連邦傘下に加えることに成功するが、南北戦争での両軍の戦死者50万人は未だに合衆国史上最悪の数字である。 - メキシコ合衆国:テキサス独立戦争
アメリカ人入植者が多かったテハス州が中央政府の中央集権体制への移行に反発してテキサス共和国として分離独立を宣言。そこからテキサス共和国はメキシコ政府軍を撃退し、そのままメキシコ政府の承認を得ることなくアメリカ合衆国へ加入、その結果最終的に発生したアメリカ合衆国との戦争でメキシコ合衆国は国土の3分の1を喪失することとなった。皮肉なことに、このアメリカがメキシコから奪い取った広大な領土の扱いが上の南北戦争の遠因となることになった。 - ロシア連邦:チェチェン紛争
ロシア連邦内の自治共和国であるチェチェン共和国がロシア連邦の前身であるソビエト連邦のスターリン時代に行われた圧政への不満を背景にロシアからの分離独立を宣言。ロシア連邦に対し圧倒的に小勢力だったチェチェンであったが、チェチェン側の激しいゲリラ戦によりロシア軍は少なからぬダメージを受け、戦争は泥沼化した。最終的にチェチェンはロシア連邦にとどまったが、未だに独立派の息の根は止まっておらず、イスラム過激派を引き込んでロシアにおけるテロリズムの温床となっている。 - ユーゴスラビア社会主義共和国連邦:ユーゴスラビア紛争
連邦内での事実上の筆頭勢力であったセルビアに中央政府が大きく接近したことに、その他の連邦の構成諸国が一斉に反発し、連邦から離脱。連邦を構成する諸構成体同士の民族対立を背景とした凄惨な内戦の果てに、最終的に14万人の死者を出してユーゴスラビア連邦は完全に解体された。
のような例があげられる。このように連邦制及び地方分権もノーリスクというわけにはいかないのである。
道州制について
日本においては、中央主権制を採用しているが今現在、道州制の導入が検討されている。
これは都道府県を編成・統合させ、大規模な構成体の領域とその構成体の機関に「道」あるいは「州」という名称をつけ、その道州に多くの権利を与えるといったものである。
いわゆる日本独自の連邦制の一種だと考えられる。
連邦制国家の国号について
前述のベルギー王国で述べたとおり、国号に「連邦 (Federation) 」という言葉がなくても連邦制を導入し、構成体が強大な権限を持つ国家はごまんとある。だが、合衆国 (United states) などの国号について何が違うのか疑問に思うものがある。それについて以下に述べたい
連邦 (Federation) 、連邦共和国 (Federal republic) 等の「連邦」を国号に含む国家については便宜上詳細は割愛するが、首長国連邦については記述する。
合衆国(アメリカ、メキシコ)
現在、連邦制をとる国家のうち「合衆国 (United states)」の国号で呼ばれる国家が二つある。すなわちアメリカ合衆国とメキシコ合衆国だ。アメリカ合衆国の英語での正式な国号は「United States of America」、日本においてはState(ステート)を「州」(幕末では「衆」となる)と訳しているがこのStateは「国(Country)」と称することもできる。この例に則り、直訳すると「国(邦)の連合体」がふさわしいように見えるが、単純に英語の「Federation」に該当するのは「連邦」とし、「United States」を「合衆国」としているのである。
それ故、構成体である州に大幅な権限を与えているアメリカ、メキシコの合衆国制と呼ばれるのも連邦制と大きな差異はない。
もともと1844年に清国とアメリカ間に結ばれた望廈条約(アメリカと清国間に結ばれた不平等条約)において、アメリカのことを「美利堅合衆國」と記述してあったので、日本も幕末にアメリカに対して「合衆国」の国号を使用したのがきっかけである。それ以来、「United States」の訳として「合衆国」を当てはめるようになった。
メキシコはスペイン語圏であり、正式なスペイン語の国号を「Etados Unidos Mexicanos(エタードス ウニードス メヒカーノス 通称、メヒコ)」と称し、公式な英語の国号を「United Mexian States」としており、これを合衆国と訳している。
ただ最近は連邦制と合衆国制、この二つの差異が大差なく便宜上まとめる役割や語呂のよさなどから、アメリカ全土の公的組織機関の用語について、連邦政府、連邦議会、連邦警察などと「合衆国」よりも「連邦」をつけて呼ぶ場合もある。
首長国連邦(UAE)
英語においては「United Alab Emirates」であり、この「Emirate」とは首長(アラビア語ではアミール)という呼称を持つ、君主が統治する国家のことを指す。直訳すると「連合アラブ首長国」といったところである(複数のsは訳出しがたい)。
イスラム系中東国家の場合は、昔ながらの絶対君主制(世襲)が存在している。アラブ首長国連邦の場合も七つの首長国(アブダビ、ドバイ、シャールジャ、アジュマーン、ウンム・アル=カイワイン、フジャイラ、ラアス・アル=ハイマ)から構成されており、それぞれの首長国トップには絶対君主である首長(アミール)がおかれている。そしてこの7つの首長国が1971年のイギリス統治から独立を果たし、連邦を組んだ。
そして現在においても連邦大統領には一番領土面積・人口が大きいアブダビ首長国の君主家より、副大統領兼首相には二番目に大きいドバイ首長国の君主家が世襲で就任する。
誓約者同盟(スイス)
ドイツ語のEidgenossenschaftの直訳。ごくまれにスイスにおいて使われる日本語名の国号。
スイスにおいては、スイス連邦と日本においては呼ばれる機会が多い。スイスはもともと国家全体の公用語として四言語(ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語)が存在する。そのうち最も話者の多いスイスドイツ語による正式国号では「Schweizerische Eidgenossenschaft(シュヴァイツェリッシェ アイトゲノッセンシャフト)」である。Eid(アイト)は誓約、Genossenschaft(ゲノッセンシャフト)は仲間・同胞・同盟を意味する。この二つが組み合わさって造語となった。なので日本語に直訳すると「盟約によるスイス同盟」すなわち、「スイス誓約者同盟」とも呼ばれる。上記同様、連邦とは大差はない。
英語においては「Swiss Confederation」であり、Confederationとは国家連合を意味する。
関連項目
- 10
- 0pt