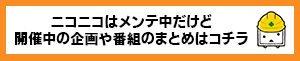路線バスとは、バスの運行・営業形態の一つである。
概要
乗合バスともいい、あらかじめ定めたルート(路線)を決められた日時に運行し、運賃を支払うことで誰でも乗車できるバスである。根拠となる法律は道路運送法。都市間を高速道路経由で結ぶ高速バス、はとバスに代表される定期観光バスも路線バスの仲間である。ここでは主に一般道をルートとする一般路線バスを中心に記述する。
人々にとって最も身近な交通手段ではあるが、利用者数は1964(昭和39)年をピークに減少を続けており、地方では一般路線バスの縮小が止まらず、バスの走らない集落も珍しくない。更に2020(令和2)年に生じたコロナ禍による外出自粛が拍車をかけており、都市部ですら運行回数の削減、運行系統の短縮・整理が目立つようになっている。
路線と運行系統
割と混同されているが、実は路線と運行系統は異なる概念である。
- 路線
- 乗合バスを運行するために使用する道路の区間を指す。起終点、主な経由地(ともに町名・地番)、距離などを所管官庁に届出を行い、認可を得る必要がある(この認可を俗に路線免許と呼ぶ)。また停留所(バス停)の設置場所や設置間隔も認可を得る必要がある。
- 運行系統
- 認可を得た路線において、実際に時刻を定め営業運行する区間・運行計画を指す。たとえばA駅~B町間の路線において、A駅発B町着の便を何時出発、何時到着という時刻や運行時間、何便運行するのかといったことを決めて届け出る。こちらは認可は不要である。
- A駅~B町間の路線の途中、C病院という停留所までは利用客が多いため、A駅発C病院着という区間便を運行する際も届け出のみで済む。A駅~C病院~D団地という新路線を計画した場合、C病院~D団地間の路線認可を得たなら、A駅~C病院間の路線認可は不要であり、その上でA駅~D団地間の運行系統も届け出のみで運行可能である。
運行系統のタイプ

|
この項目は独自研究を元に書かれています。 |
基本的な分類
- 往復系統:基本型
- 一般的な鉄道路線のように起終点の間を結ぶ系統。一部片道のみの系統もある。
- 往復系統:ぶんぶんゴマ型
- 往復系統のうち、中間の経路が往復で異なる系統。
- 循環系統:サークル型
- 山手線のように循環する系統。ただしバスの場合は一回転した時点で運行を打ち切ることがほとんど。
- 循環系統:ラケット型
- しゃもじ型とも。アルファベットの「P」のように終点付近の一部の区間が循環する系統。
- 循環系統:鉄アレイ型
- 系統の両端に循環区間がある系統。実例は少ない。
- 寄り道系統
- 特定の停留所に寄り道する系統。往復系統・循環系統どちらにも存在し、寄り道の先が循環区間になる系統も稀に存在する。
循環系統の追分類
※循環区間の回転方向にもバリエーションがある。
- 両回り:終日
- 内回り・外回り双方を終日運行する系統。
- 両回り:時間帯別
- 時間帯によって内回り・外回りが入れ替わる系統。12~14時の間で入れ替わることが多い。
- 片回り
- 回転方向がが終日固定されている系統。
優等種別
一般路線バスは平常すべてのバス停に停車するが、中には停車しない停留所のある「優等種別」が設定されている系統もある。名称は「快速」「急行」「特急」などが付けられるが、事業者によって種別名の示す意味が異なる。
- 全区間主要停留所のみ
- 中・長距離系統で所要時間の短縮のために設定される。特急もしくは急行が多い。
- 起点/終点付近で主要停留所停車
- A-(主要停留所)-B-(全停留所)-C-(主要停留所)-D
- 中距離系統で利用客の分散を図る意味で設定される。急行もしくは快速が多い。
- 途中から停車
- A-(全停留所)-B-(無停車)-C
- 都市の中・短距離の通勤系統で利用客の分散と所要時間短縮のため設定される。急行が多い。
- 起終点以外無停車
- 学校など各種施設の送迎便に設定される。急行が多い。
※北海道など高速道路が未整備の地域では、高速を使わない都市間バスに「特急」を設定する事例もみられる。
免許維持路線
バスファンの記事も参照。
極端に運行回数の少ない路線を指す言い回し。廃止した方がよいのでは…と思われるにもかかわらず廃止しない理由として、バスの路線免許(認可)を返上し廃止すると当該道路における貸切バスの営業に差し支えるとか、再度の認可を得るのが大変だとか、様々な事情で路線免許を維持する必要がある、と判断されているから…らしい。
車両
大きさ・動力等
バスの記事を参照。
一般路線バスでは大型路線バス・中型バスを主に使用している。外国車の導入は連節バスなど限定的で、国産車が圧倒的シェアを占める。昭和の時代までは各社とも新車を購入・運用していたが、平成以降は都市圏を地盤とする比較的裕福な事業者のみ新車を購入しており、それ以外の事業者は放出される12~15年落ちの中古車を購入している。都市圏ではCNGバス・ハイブリッドバス等も見られるが、全体的にはディーゼルエンジン車が主流。
床の高さ・座席
ノンステップバスの記事も参照。
交通バリアフリー法施行により、地方の路線バスも多くは床の低いノンステップバスになっている。昭和の時代、大都市圏では「三方シート」という、電車で言うところのロングシート車が多かったが、その後は前向1人掛シート(車両後方は2人掛)が取って代わった。地方では立ち席スペースをあまり考慮せず、2人掛を全体に設置する事例も見られた。前扉直後の1人掛シートは「オタ席」という俗称があるが、新型コロナ禍で閉鎖される事例が目立つ。
装備品
- 行先表示器(方向幕)
- 方向幕の記事を参照。ただし方向幕そのものは絶滅危惧種である。
- 運賃表示器(運賃表)
- かつては「三角表」とも呼ばれる運賃表を掲示していたが、ワンマン運行が広がるにつれて、車内放送に連動する運賃表示幕が使用されるようになった。その後はデジタル表示器にとってかわり、長く使われた。2010年代からはマルチビジョン表示器となり、サイクルで表示内容を変えられるため、CMなどを表示するようにもなっている。
- 運賃箱
- 昭和の時代は、廃車から使いまわす代表的装備品であった。近年は決済手段に対応してより多機能になり、且つ新機能に対応する運賃箱への更新が頻繁に生じ、使いまわすことは少なくなっている。
- 降車ボタン
- 「降車チャイム」、「ブザー」と呼ぶこともある。現在はブザーというにはかわいらしい音のものも多い。形状も様々であったが、近年はある程度統一されたデザインになっている。子供が押したがるものである一方、地域によってはチキンレースでもしているように誰も押したがらないものでもあるようだ。
ドア配置
一般路線バスには片側に1~2箇所のドアを備えており、前輪の前にあるドアを「前扉」、前輪と後輪の間にあるドアを「中扉」と呼ぶ。ただし、慣習的に中扉のことを「後扉」と呼ぶことも多い。ドアを2箇所備える車両は「前中扉車」と呼ばれ、それぞれ乗車用・降車用を使い分けるが、車いす利用者は中扉を乗降兼用で使用する。また、前扉の1箇所のみ備える「トップドア車」は高速バスで圧倒的に多数派であり、定期観光バス・貸切バスにも使用されている。
かつては後輪の後ろに「後扉」を設置する事が可能で、前扉・後扉の2箇所を備える「前後扉車」や、前扉・中扉・後扉の3箇所を備える「3扉車」も存在したが、後扉は交通バリアフリー法への対応が難しいことから近年では姿を消している。さらに歴史を遡ると、バスに車掌が乗務していた時代は中扉の1箇所のみを備えるバスも存在していたが、ワンマン化により淘汰されている。
| トップドアの例 | 前中扉車の例 | 前後扉車の例 | 3扉車の例 |
|---|---|---|---|

|

|

|

|
乗降方法・運賃支払い方法
運賃の支払い方法は、乗車時に運賃箱にお金を投入する「先払い」と、降車時に運賃箱にお金を投入する「後払い」の2種類がある。運賃箱は運転席の横に設置されているため、乗車時と降車時のいずれかで前扉を使用し、そのタイミングで運賃を支払うことになる。
乗降方法と運賃支払い方法の組み合わせは多岐にわたる。以下に簡単にまとめたが、この表に当てはまらないタイプもある。
| 扉数 | 乗車方法 | 降車方法 | 支払方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2扉 | 前乗り | 後(中)降り | 先払い | 均一運賃の路線に多い |
| 申告先払い | 距離別運賃の場合、乗車時に行先を申告して運賃を支払う | |||
| 後(中)乗り | 前降り | 後払い | 距離別運賃の路線はほぼこちら。均一運賃の場合もある | |
| 前乗り | 前降り | 先払い・後払い | 後扉(中扉)は締め切り扱い。地方に多い | |
| 1扉 | 高速バスに多い |
路線バスの運賃制度
運賃制度のバリエーション
- 均一制
- 均一運賃。距離に関係なく一回の乗降ごとに一定の運賃を支払う。従って距離が長くなるほど割安になる。人口の多い大都市圏で採用されているため、結果的にバスは均一運賃と勘違いする人が多くなる。
- 地帯制
- 事業エリアをいくつかの「地帯(ゾーン)」で分割し、ゾーン内は均一、複数のゾーンを跨ぐ場合は割増しになる制度。かつて一部の都市で採用されていた。
- 特殊区間制
- 距離別運賃の一種。乗車距離をある程度反映して設定される「運賃区界停留所」を過ぎるごとに一定の料率で運賃が上がる(ex.1区:190円、2区:220円、3区:240円)。こちらも一部の都市で採用されることがある
- 対キロ区間制
- 距離別運賃の一種。「運賃区界停留所」を過ぎるごとに運賃が少しずつ上がるが、区界停留所間の距離が特殊区間制より短く、路線/系統や停留所間隔によって料率が異なる。最も広く使われている制度。
- 対キロ制
- 距離制運賃の最もシンプルな制度で、高速路線が採用する。
運賃決済手段
- 現金
- 車内で支払う基本的な手段。後述の各種カードやアプリの普及により、割合は減少している。ちなみに均一運賃エリアの利用客はつり銭が出る環境に慣れているが、均一制ではない多くの事業者は「両替式」でつり銭は出ない。
- 交通カード
- 当初はプレミアムのつくプリペイドカードが普及したが、その後非接触式ICカードにとってかわられた。ICカードはチャージにより繰り返し使用できるほか、他の交通機関やお店の決済にも使用可。
- 交通アプリ
- ICカードの機能を搭載した携帯アプリ。クレカや銀行との紐づけによりオートチャージが利用でき、ストレス軽減にもなる。
- 乗車券
- 地方ではターミナル・営業所等で乗車券を販売する事業者があるが、均一制の多い公営バスでも乗車券を発売しているところがある。またイベント等の送迎便ではスムースな乗降のため、あらかじめ乗車券の購入を求める場合もある(事業者社員が出張で販売する)。
また「一日乗車券」や他の交通機関・施設などと組み合わせた割引乗車券などを販売している事業者も多い。 - 定期券
- 近年はICカード化される事例が多い。バスの利用を促すため、土日祝日には通勤定期券が記載された本人以外の家族も若干の料金支払で利用できる制度を設けている事業者もある。
- バス車内でもチャージは可能だが、現金両替と同じく二千円以上の高額紙幣は対応できないことがほとんど。しかしながらバスに多額の両替用紙幣を持たせることは、防犯上も事業者の財政上も困難であり、手元に千円札があるかどうかを乗車前に確認すべし。
- バス車内の支払い方法と決済手段の地域差が、乗り慣れた地域以外でバスを利用するのをためらう要因になっているが、昔から解決の難しい問題である。
現況
運転手
不特定多数の乗客を乗せる場合、当然のことながら二種免許が必要である。路線バス車両は法令上大型車の扱いとなるので、運転手が持っている免許は大型二種免許である。
大型二種免許に対するハードルの高さ、勤務時間の不規則さ、過酷な労働環境、ネガティブキャンペーンなどが原因で多くのバス会社が運転手不足に悩まされている。運転手不足を解消するため、普通免許取得3年以上の人であれば会社で大型二種免許取得費用を負担する制度が多くの会社で実施されている。また鉄道系の会社では高卒でバス運転手候補を採用し、大型二種が取得できるようになるまでは鉄道業に携わせるところもある。
運転手は出勤と退勤時に点呼を行うことが義務付けられている。点呼は運行管理者(補助者)の前でアルコールチェック、健康状態の確認、その日の運行で注意するべき点の伝達、ダイヤ表の受け渡しなどを行う。
同じバス会社・グループ会社のバス同士が離合する場合、運転手同士が手を挙げて挨拶する場合がある。これはお互いに異常が起きていないことを確認する意味合いなどが込められているが、中には事故防止を理由に挨拶をしない会社もある他、長距離高速バスなどでは異なる会社同士でも挨拶することがある。
運転手の勤務形態
一般的な路線バスの運転手は日勤が基本で、休日はシフト制である。
勤務時間は様々で朝の始発からラッシュの終了まで乗務した後、昼間は休憩し夕方の帰宅ラッシュから終バスまで乗務する中休勤務、朝出勤して夜退勤する通し勤務、始発から昼まで乗務する早番、逆に昼から終バスまで乗務する遅番などがある。
高速バスの場合も日勤が基本だが、距離の長い路線だと宿泊を伴う事もある他、JRバス関東・西日本JRバスの新東名新城インターやWILLER EXPRESSの新清水インターなど路線の途中で交代して運転手だけ出発地に戻るという形態もある。
近年はかなり少なくなったが、現地出退勤というものもある。多くの場合、運転手は自分が所属する営業所で出勤・退勤の点呼を行うが、中長距離路線だと終バス到着後に営業所へ帰ること、始発に間に合うように営業所を出庫する事が現実的でない場合もある。
そういった場合、路線の終点近くに現地出退勤用車庫が確保され、そこで滞泊する行路を担当する運転手は車庫の近隣に住んでいる人から選ばれ、出勤・退勤を営業所ではなく現地の車庫で行う。
現地出退勤を行わない場合、宿泊勤務を設定して対応していることもある。
運営状況
都市部・地方含めて路線バスの利用者は減少傾向にあり、かなり苦しい経営状況に立たされている。公営バスを中心に営業係数(100円の収入を得るのにいくら費用がかかるか示した値)が公開されているのでそれを見てもらうと赤字路線の多さをうかがい知ることが出来る。
一般路線では利用者の減少傾向のところが多いが、長距離高速バスでは利用者数が安定しておりそちらの収益で赤字路線を支える構造のバス会社も多い。また自前の自動車整備工場を持っているところでは自動車整備業や各種保険の代理店業務などで設備・人員の有効活用と収益確保を兼ねていることもある。
余談
- 現役のバス運転手いわく、路線バスを運転するときはわざと雑な運転を取り入れているらしい。これは丁寧な運転ばかりしていると乗客が油断して手すりや吊革を掴まなくなるためだとか
- 現在販売されている路線バスは中ドアを開ける時にシフトポジションをニュートラルにしないと中ドアが操作できないようになっている。これは「新ワンマンバス構造要件」という国土交通省が出しているワンマンバスを製造する際に必要な条件をまとめた物の中に「中ドア開時は動力伝達をカットすること」と書かれているため。
- 近年主流のノンステップバスはラッシュ時にドアが閉まらなくなることがある。これは戸挟み事故防止のためにドア付近にセンサーが設けられており、ラッシュ時にはこのセンサーを乗客や荷物が遮ってしまうため
関連項目
- 1
- 0pt