- ほめる
(7) - 掲示板を見る
(48) - その他
概要
1368年に朱元璋が建国し、1644年に李自成に滅ぼされるまで中国を統一して治めていた王朝である。250年続いた王朝ではあるが、北から南から、内から外からと色々と攻められて苦労の多い王朝であった。
最後の漢民族の皇帝の王朝でもある。日本史だと足利義満の勘合貿易や秀吉の大陸侵攻なんかで出てくる。
勃興
元朝末期、政治が乱れ財政が苦しくなった元政府は重い税金を国民に課していたため、これに堪え兼ねた民衆は1351年に各地で反乱を起こした。この反乱の中心となったのは秘密結社の白蓮教徒である。白蓮教徒は目印に赤い頭巾をつけていたので、この反乱は紅巾の乱と呼ばれるようになった。この乱には、後に明朝を建てる朱元璋も参加している。
朱元璋は貧農の生まれであり、若い頃は乞食坊主をするなどの過酷な生活を送っていたが、紅巾の乱に参加してからは一大勢力である郭子興に認められ、1355年には郭の後を継いで一軍を指揮するまでになった。朱元璋は江南の中心地である集慶路(南京)を攻め落とし、応天府と名を改めここを本拠地とした。応天府は地主や知識人が多く集まっており、その中で農民軍の指導者であった劉基の勧めを受けて朱元璋は紅巾の乱から離脱して天下統一を目指し始める。
当時の中国には元朝の他にも張士誠や陳友諒などの朱元璋のライバル勢力が数多く存在していたが、朱元璋は1363年に鄱陽湖の戦いで陳友諒を湖上戦にて破り、67年には蘇州の戦いで張士誠を倒し、その後、元の首都の大都に軍を進めた。68年には応天府(南京)にてとうとう皇位につき、朱元璋は洪武帝を名乗った。即位した洪武帝は一世一元の制を唱え、それまで何かあるたびにコロコロ変えていた元号を、一人の皇帝が一つの元号を用いるとした。
さらに洪武帝は、当時海を荒し回っていた、日明高麗その他、様々な人々によって構成されていた武装商人、通称倭冦と呼ばれる海賊に対抗するため高麗、日本、琉球に使者を送り、対倭冦同盟を呼びかけた。当時の日本は南北朝時代であり、しっちゃかめっちゃかな政治情勢であった。明の大使は九州に勢力を誇る南朝の拠点、征西将軍府の懐良親王の下を訪れるが、南北朝の混乱もあって朝貢関係は結べなかった。
一方で洪武帝は疑心暗鬼の病にかかり始めていた。地方の役人数千人を処刑追放した空印の案と呼ばれる事件を起こし、さらに丞相の胡惟庸を処刑し、関連のある人15000人を殺害した。この中には明建国に手柄のあるものも多くあった。
行政に関しては、現場と皇帝の取り次ぎを行う中書省を廃止して、六部と呼ばれる6つの行政機関(役人を統括する吏部、徴税・財政を担当する戸部、科挙や外交を担当する礼部、軍政を司る兵部、懲罰や裁判を担当する刑部、宮殿の造営や河川の修復を行う工部)を皇帝が直接統治できるように改革を行った。更に土地台帳の魚鱗図冊、課税のための戸籍・租税台帳の賦役黄冊を作り、税や労役の負担を公平にした。また10戸を1グループにして、一番裕福な家に課税と労役を管理させる里甲制をしいて農民の生活を安定させた。
しかし洪武帝の疑心暗鬼は治ることはなく、粛正の嵐は吹き止まなかった。洪武帝は跡継ぎを孫の允炆(後の建文帝)に決めたが、自分の息子である25人の皇子をすべて地方に送り、洪武帝の死後も都に入る事を禁じた。更に建国以来の忠臣であった藍玉を謀反の罪で逮捕し、関連人物をすべて処刑するという暴挙に出る。洪武帝によって処刑された人物は数万人に上るとされている。
永楽帝
洪武帝の死後、帝位を継いだ建文帝は自分の叔父達(洪武帝の子供)に皇帝位を奪われる事を恐れ、有力皇子達を次々と逮捕していった。これに対抗した北京の燕王、洪武帝第四子、朱棣(後の永楽帝)はクーデタを起こし、応天府を陥落させた。これを靖難の役という。
1402年燕王朱棣は応天府で永楽帝となったが、永楽帝はクーデターによって生まれた皇帝であったため、建文帝に仕えていた儒者の方孝孺から燕賊簒位(えんぞくさんい、皇帝の位を奪い取った燕の賊の意)と非難されるなど、知識人からの評判が非常に悪かった。そこで永楽帝は儒教の教典の大編纂事業を起こした。多くの学者を集めて『四書大全』『五経大全』『性理大全』などを刊行し、これを科挙の試験科目とした。これは永楽帝に批判的な学者を取り除く政策でもあった。
永楽帝は応天府から自分の本拠地である北京に遷都し、民間の海上交通や漁業活動、貿易を制限する海禁を出して貿易は国が認めるものに限って利益を独占しようとした。この頃、室町幕府の足利義満は永楽帝に使節を送り、日本国王として認められ、勘合貿易を開始する。それに伴い室町幕府は倭冦取り締まりを強めたため明だけでなく朝鮮、琉球、日本をも苦しめていた倭冦の数も徐々に減っていった。明は日本だけでなく、朝鮮や東南アジアの国々にも使節を送り、東アジアには明を中心とした国際秩序が生まれていった。
しかし、このような中で唯一明に従わなかったのが北方のモンゴル系勢力であった。当時、明朝によって中原を追われた北元は東方のドチン・モンゴル(漢文史料では韃靼)と西方のドルベン・オイラト(瓦刺)に分裂して抗争しており、これにつけ込む形で永楽帝は五度にわたるモンゴリア親征を試みた。1410年にはオノン河畔にてモンゴル軍を破ったが、その後は敵の主力をうまく捉えられず、見るべき成果を残せなかった。また1406年にはベトナムで黎季犛が陳朝を滅ぼし明から独立してしまったために80万の軍を差し向けて明の支配下に置いたが、ベトナムの抵抗は根強く統治は安定しなかった。
一方で、永楽帝は1405年にイスラーム宦官の鄭和に62隻の「宝船」と呼ばれる船と27800人の兵で構成された大船団を南に向かわせた。鄭和はチャンパー(現ベトナム)、マジャパヒト王国(ジャワ島)を経て、スマトラ島のパレンバン、更にはインドのカリカットまで達した。明の船団は兵隊も乗せており、パレンバンでは海賊の施進卿と協力して同じく海賊の陳祖議を海戦にて打ち破った。更に鄭和は4回目以降の航海ではアラビア海を超えてホルズム、メッカやアフリカ東岸にまで到達した。鄭和がアフリカから持ち帰ったキリンは永楽帝を大層喜ばせ、明の栄華の象徴ともなった。
北虜南倭
永楽帝の死後、北方ではオイラトが強大になり東方のモンゴルや女真に勢力を延ばしていた。オイラトはティムール帝国をはじめとするペルシャやアラビアと明の貿易の仲介を行っていたが、明との折り合いが合わず交渉は破綻してしまった。そのためオイラトのリーダーであるエセンは1449年に明の大同に攻め入った。これに対して有力宦官の王振は親征を、于謙は守備を主張したが、時の皇帝正統帝は出陣を決意する。しかし、土木堡にて大敗し、王振は戦死、正統帝はエセンに捕えられてしまった。これを土木の変という。
皇帝が捕まったことを知った于謙は新皇帝の景泰帝をたて、北京にてオイラトとの戦いに挑み、防衛に成功する。その後、人質としての価値を失った正統帝が送り返されてくるも、既に皇帝でなくなっていたため上皇として紫禁城に監禁された。しかし、1457年に皇太子のいなかった景泰帝が病死すると、クーデターが起こり、再び正統帝は天順帝として皇位についた。このように同じ人物が二度皇位につくことを重祚という。天順帝は于謙をはじめとした景泰帝に組した人々をすべて死刑に処す。その後エセンは亡くなったが、モンゴリアの遊牧民の侵入は止まらず、天順帝から皇帝を継いだ成化帝は万里の長城の補修拡大事業に乗り出したため、国家の財政はかなり苦しい状況に陥った。
16世紀になると民間貿易を制限する海禁政策を破って、密貿易がさかんになった。特に塩商人であった王直は密貿易で多額の利益をあげた。日本の種子島に鉄砲を伝えたポルトガル船も王直所有のものであったとされる。しかし明の役人である朱紈が密貿易を厳しく取り締まったために王直は日本の長崎に拠点を移して密貿易を続けた。王直は大船団を作り、やがて海賊の様相を呈し始めた。彼らは日本刀を持ちチョンマゲをして日本人に扮していた。これが後期倭冦である。後期倭冦のほとんどは明人だというのが通説であるが、実際の所は人種や国籍というのが曖昧な時代でもあったため、一概に「倭冦は〜人」と言い切る事もできない。
倭冦の勢力はとてつもなく、時の皇帝の年号をとって嘉靖の大倭冦と呼ばれた。更に北方では右翼モンゴルの有力者アルタン=ハーンが明に侵入を開始する。北からはモンゴル、南からは倭冦という北虜南倭という逼迫の状況に対して、政治に関心がなかった時の皇帝、嘉靖帝は対策をすべて宰相に投げっぱなしにしてしまった。官僚達は軍事費を調達するために銀の徴収をしたが、これは銀の価値をあげ、銀の貿易をしていた倭冦の財力を高めるという皮肉な結果になっていまった。
しかしその後、1553年に倭冦を鎮圧するために胡宗憲が髪浙総督に着任し、王直を罠にはめ捕縛した後に処刑。更に浙江省では戚継光を倭冦討伐に派遣し、勝利をつかみ取っていった。1566年、皇帝、隆慶帝は倭冦を静まらせ海禁政策をやめて、71年にはトゥメト部のアルタンと講和したため、北虜南倭はほぼ収まった。
滅亡
1572年万暦帝が14代の皇帝についたが、わずか10歳であったために大臣の張居正が政治を行っていた。張居正の改革によって財政と国境も安定したが、張居正の死後、改革反対派が勢力を盛り返し、張居正の財産の没収や家族の追放が行われた。万暦帝も政治に関心は薄く、モンゴルのボハイで反乱が起きたり、秀吉が大陸に進出してきても、いまいち対応は鈍かった。更に土豪であった楊応龍が秀吉の出兵に乗じて反乱を起こした。これら三つの戦乱を、万暦の三征と呼ぶ。
数々の戦争の負担は重税となって民衆にのしかかり、さらに宮廷では宦官と東林党と呼ばれる学者が政治を巡って激しく争い、国家はきわめて不安定な状況にあった。
万暦帝の後に即位した泰昌帝は名君として期待されていた人物であったが数ヶ月の在位で急死。その後を継いだ息子の天啓帝は暗君で宦官、魏忠賢の台頭を許してしまう。彼によって大勢の人々が殺され、遼東でヌルハチが台頭するのを無視して賄賂と苛斂誅求が横行、政治は腐敗の一途を辿って行った。
この世の栄華を極めた魏忠賢であったが天啓帝が崩御し、弟の崇禎帝が即位すると没落、自殺に追い込まれるが時、既に遅かった。攻め寄せる後金(清)軍を前に、傾きかけた国勢を立て直そうと崇禎帝は奮闘するが猜疑心の強さによって、名将を処刑をしてしまったり、戦費を賄うために増税をしたり無駄を無くそうとすれば反乱分子を増やしてしまうなど、やることなすこと裏目に出てしまい、反乱軍の李自成によって1644年北京を占領され、17代にして最後の皇帝・崇禎帝は自殺。明王朝は滅んだ。
南明による抵抗
その後、生き残った一部の有力者と彼らに擁立された生き残りの皇族を中心に、明の影響力がまだ残っていた華中・華南の残党勢力を糾合、「南明」と呼ばれる一種の亡命政権を築き上げ、新たな王朝を打ち立てようと目論む李自成ら反乱軍や尚も侵攻を続ける清軍に対し、「反清復明」をスローガンに掲げて頑強に抵抗を続けた。反乱軍が清に滅ぼされるとその残党をも取り込み、1646年の永暦帝の代には名相・鄭成功の活躍と尽力もあり、一時的に清軍を圧倒して押し返してしまうほどの勢いを見せた。
しかし、天下を目前にして時流に乗る清の勢いそのものを止めることは出来ず、次第に形勢を逆転されると南方へと追い詰められ、1662年には最後の皇帝が死去して南明は滅亡した。その後も意志を継いだ鄭成功を祖とする鄭氏政権が台湾に渡ってまで尚も抵抗を続け、日本を含む周辺諸国に形振り構わず援軍を要請(江戸幕府に対する「日本乞師」など)するなどしたが、こちらも1683年には追い詰められて降伏。ここに約300年続いた明の命脈は、再興の夢と共に完全に絶たれることとなった。
明代の政治
洪武帝は統一後の粛清人事において、君主独裁を徹底的に高めていた。そのうちの一つが宰相で、丞相の胡惟庸を処刑した後は宰相職はおかず、皇帝自らが上奏文をチェックして決済をするという手法を取っていた。宰相が行っていた事務処理も皇帝自らが行うことによって他者の専横を防ぐというものであったが、上奏文は膨大な量に上り、とてもではないが一人で出来るものではなかった。
このため、複数の秘書官が上奏文をチェックして、決済文の原案を作っておくのだが、いつしか原案がそのまま決済として通るようになり、従って原案を作る権限を持つ秘書官が事実上の宰相として扱われるようになっていった。つまり、胡惟庸以外の宰相と呼ばれる人物は正式の宰相ではなかったということに留意する必要がある。皇帝の出来不出来がダイレクトに出てしまうのが明代の政治の特徴で、名君の治世が短く、暗君の治世が長かったのが明の不幸と言われているが、運だけの問題ではなかったかもしれない。皇帝の責務は激務であり、時には神経を磨り減らす決断をしなければならず、そのストレスがのし掛ったと考えられるが、暗君の場合には真面目に政務を執らないのでプレッシャーそのものがかからないと思われるからである。
明代の宰相は強い権限を持っていたが、制度で定められた訳でもなく、軍権を持っていたわけでもなく、皇帝の命令を偽ることを周囲から黙認されることによって権力を持つという、冷静に考えてみれば洪武帝が聞いたら関係者たちを一族族滅するほどにとんでもない方法で権力を得ていた。それゆえに立場が曖昧で、この世の春を謳歌していた寵臣が、皇帝の不興を買って処刑されることも当たり前だったので、他朝とは違い、権臣が皇帝を廃擁立することは考えられないことだった。劉勤に至っては皇帝死亡後に失脚することを恐れて謀反を企てたほどである。
関連動画
関連項目
掲示板
-
46 ななしのよっしん
2024/01/19(金) 20:25:14 ID: SbqKIvM/Jc
明王朝の皇帝や名臣や名将や佞臣や姦臣って、妙に面白いエピソードがある人物が多いんだよね。
王陽明も儒者という以上に当時屈指の兵法家で、若い頃は江湖の遊侠になってもおかしくない生き方をしてたし。
北虜南倭と渡り合った戚継光も、戦術指揮官と戦技インストラクターを兼ね備えるだけでなく、超ド級の恐妻家の癖に浮気してたってしょうもないエピソード持ちだし。
あと、名君の宣徳帝も闘蟋にハマって早馬使って強いコウロギを持って来させたし、成化帝なんかおねショタが史実と来てるし。
なんか、それ以前の王朝と比較して、具体的で笑ってしまえる種類の人間臭さが感じられるのが明代の歴史の面白いところかな。 -
👍2👎0
-
47 ななしのよっしん
2024/05/06(月) 16:27:20 ID: S1OWpi+kzX
暗君率高い気がするけど割と長持ちしたよな。
-
👍0👎0
-
48 ななしのよっしん
2024/05/30(木) 20:55:42 ID: SbqKIvM/Jc
明代の暗君も多種多様だからなあ。
一番わかりやすい種類が正徳帝や万暦帝として、嘉靖帝みたいに「自分の権威と影響力の拡大という意味での政局には熱心」「でも具体的な政策には興味ないし失敗したら閣僚に責任を押し付ける」ってタイプもいる。
さらには隆慶帝みたいに「仕事は全部名臣にお任せしてくれるから、なまじっか仕事熱心な皇帝よりよほどマシな暗君」なんてのもいるからね。 -
👍0👎0
おすすめトレンド
ニコニ広告で宣伝された記事
急上昇ワード改
- 389
- 117
- 364
- 51
- 2
最終更新:2024/07/27(土) 12:00
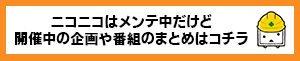
最終更新:2024/07/27(土) 11:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。