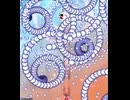- ほめる
(3) - 掲示板を見る
(31) - その他
シベリア鉄道とは、シベリアの広大な原野をひたすら走る鉄道路線である。
概要
シベリア送りにされた亡者の上に成り立っている死の路線である(実際にこの鉄道の建設には犯罪を犯した囚人が多く関わっており、その多くが死亡している)。
世界でも最長クラスの路線であり、長距離列車も世界最長クラスである。ロシア極東沿岸州のウラジオストクからモスクワまでがシベリア鉄道と言われてるが正確ではない。
軌間は1520mmの広軌が採用されている。これも標準軌にした場合、ナポレオンのような侵略者が現れた時に脅威だとする国防上の問題と言われている。
途中中華人民共和国との国境付近を通ることもあり、国防上の問題からバイカル湖の北を通って途中で合流する第2シベリア鉄道(バム鉄道、バイカル・アムール鉄道とも言う)もある。
国際列車も多く、北京やモンゴル、更に北朝鮮まで直通する列車まである。その他、東欧方面への国際列車も多く走っている。それらの列車の中には何日もかけて運行する列車も多く、シベリアの原野をひたすら走る。
モスクワからウラジオストクまで走るロシア号などをはじめ、世界上位の長距離列車の地位の多くをこのシベリア鉄道が占めている。
運行時間世界最長はモスクワとウラジオストクを結ぶ普通列車とされており、9泊10日の超長旅である(同区間を特急のロシア号が7泊8日である。)。
日本とも関係が深く、航空機が発達する前は欧州への最短ルートであった。
長大路線であり、極寒のシベリアを走るとあって、施設の老朽化が大きな問題となっているがロシア経済にとって特に重要な路線とあって、2002年には全線電化、更に複線化工事もあらゆる場所で進んでいるようだ。
現在の経営状況
旅客輸送事業は赤字であるものの、貨物輸送がそれ以上に黒字であるため、シベリア鉄道全体としては黒字になっている。日本ではこういったことは珍しいが、諸外国ではこういった経営形態が常で、シベリア鉄道も例外ではない。
歴史
建設
1888年(明治21年)にパリのシンジケートがロシアの国債5億フランを引き受けた。これを原資として1891年(明治24年)3月に、シベリア鉄道敷設の勅命が下り、皇太子ニコライ(後のニコライ2世)は、東のターミナル予定地のウラジオストクでこれを公表した。1902年末に竣工したが、単線で、バイカル湖上はフェリーで渡していた。[1](ニコライは途中で立ち寄った日本で大津事件に遭っている)
全通後(帝政ロシア~ソ連時代)
バイカル湖を南側に迂回する現在の路線ができたのは日露戦争中である。日露戦争でもこのシベリア鉄道は大活躍し、日本軍を大いに苦しめ……たわけでもないようだ(クロパトキンが退却を重ねたため)。
日露戦争後は日露関係は一転して好転した(とある外交要件で日露の利害が一致したためとされる)が、これもロシア革命でソビエト連邦となる。
しかし、シベリア鉄道はソビエト時代も重要な路線であり、先述のように航空機が発達する前はヨーロッパまで最短ルートであり、また戦前戦後においてもソ連時代は物流大動脈であると同時に、ソビエトに対する反逆者などをシベリア送りにするための死神路線としても大活躍していた(第二シベリア鉄道の建設などに従事していた)。
ソ連時代はやはり国防上の理由から外国人の利用は大きく制限されていたようだが、それでも戦前の航空機発達前はヨーロッパへのルートとしては最短であったため、例えば航路では40日かかっていたパリまでの旅も、下関から釜山へ渡り、朝鮮総督府鉄道から南満州鉄道を経てシベリア鉄道経由で行けば15日で到達できた。ただ、通過ビザの取得は外交官や軍人、高級官僚、政治家などでもない限り難しかったようで、実際にはアメリカの西海岸でシアトルに出てアメリカ大陸を鉄道で横断し、ニューヨークから大西洋航路を使うのがメインだったようである。この場合は20日程度とされた。
航空機の発達によって、シベリア鉄道の旅客路線としての重要度は低下、観光路線としてシフトしているが、貨物積載量そのものは増加しており、ソ連時代は国策によって貨物料金が低価格に抑えられていた事情もあり、日本からヨーロッパへ送る貨物輸送ルートとしては大車輪の活躍を見せていた。
この時代のシベリア鉄道の荷主は実は日本の企業が多かったのである。まだ中国も現在より格段に貧しかったためである。
また海路もこの時期はまだ非常にコストが高いとあってシベリア鉄道も一定の競争力があったのである。
しかし、頭から常に血を流していることで有名なゴルバチョフがソ連最高指導者となる頃になると、設備更新の停滞やソ連の混乱からシベリア鉄道の輸送力は大きく低下、1991年にソ連が崩壊してしまった。
ソ連が崩壊し、シベリア鉄道はロシア連邦の一部となった。電化工事や複線化工事も着々と進んでいるが、ソ連崩壊に伴い相次ぐ値上げが発生(それまでは共産主義国として利用料は低く抑えられていた)、価格的優位性は完全に海路に譲ることとなった。
現在シベリア鉄道で貨物輸送を利用する場合、または旅客が飛行機恐怖症などの理由で鉄道を経由してヨーロッパへ渡る場合、日本海側の各港(旅客の場合、現在は境港から出ているのが唯一である(新潟からウラジオストク行きの航路は廃止された))からウラジオストク行きの船舶に乗り、ウラジオストクからシベリア鉄道(旅客の場合はモスクワ行きのロシア号を利用することになる)を経由し、モスクワからヨーロッパの各国に入ることになる。旅客の場合ロシア号で7泊8日、境からウラジオストクまでのフェリーも2泊3日(冬季は3泊4日)であるから、そこから西洋の各地までの移動時間も考えると2週間は見ないといけないことになる。
今後の予定と海路との競合
シベリア鉄道貨物輸送における最大の敵は何と言っても巨大船舶を使った海路である。スエズ運河を経由しヨーロッパへ巨大な船舶を使えば、所要時間こそかかるもののコストは低く、輸送量は多くなる。
また、シベリア鉄道の問題点として、途中駅などで現地の鉄道職員が「護衛料」などと称し法外な料金の支払を要求することもある。これは、日本の暴力団が行う「みかじめ料」と酷似している。
また、シベリア鉄道の車内も治安が悪く、また国際列車が走っているが、直通先に英語圏がないためか英語がまるで通じず、ロシア語の会話集や鉄道ガイドブックは必須であるようだ。
| シベリア鉄道 | スエズ運河(海路) | |
| 値段 | 割高 | 割安 |
| 輸送量 | 少 | 多 |
| 治安 | 悪 | 良 |
| 所要時間(サンクトペテルブルクまで) | 25日 | 40日 |
このように、所要時間こそ早いものの、ロシアの度重なる不義(特に北方領土問題)などからあまり信用がなく、大勢としては海路が好まれているのが現状である。
実際にシベリア鉄道からヨーロッパに輸送される20000個のコンテナ輸送のうち8000個強は日本のものであるが、船舶は36万個であるからシェアは45対1である。これは一般的には「競争になっていない」という状態である。
しかし、広大な土地により資源に恵まれているシベリアを活かさない手はなく、プーチン政権としてはなんとか自国の経済成長の原動力にしたいようである。実際にロシアの貿易その他あらゆる輸送においてシベリア鉄道は3割を占めている他、国内の旅客輸送の重要な一部でもある。
特に、ロシアでは日本車ブームが起こっており、部品輸送などの需要も期待されている。また、中国からの輸送も盛んである。ソ連時代はシベリア鉄道の国際貨物輸送はほぼ日本が支配的だったが、現在ではシベリア鉄道の信用低下や値上げなどから海路にシフトされ、荷主は中韓が多いようである。
しかし、依然として実質的な経済力では世界第2位(中国の統計は当の中国自身が信用出来ないと認めているため)である日本の需要を取り込むことはプーチン政権にとって大きな課題となっている。
特に中ソ対立以降はロシアにとって中国は仮想敵国であるという点も大きい。
北海道延伸計画、宗谷トンネル
また、日本と関わりの深い将来計画として、シベリア鉄道の北海道延伸案を外すことは出来ない。
現在シベリア鉄道の将来計画として、樺太と大陸を結ぶ間宮海峡トンネルの計画が進められている。元々スターリン時代にシベリア送りにした罪人と軍人を使い計画が進められていたが、当のスターリン自身が死んでしまったため、計画が頓挫、その後北樺太にある油田などの円滑な輸送(冬は海が凍ってしまうため)の目的から間宮海峡にトンネルまたは橋をかける計画が進行中である。
これをサハリントンネル、サハリン大橋、間宮海峡トンネル、間宮海峡大橋などの名前で呼ぶ。2016年に着工する予定とされている。
しかし、ロシア側としてはこの計画だけではまるで採算が合わないため、なんとかして日本を引き込みたい意図があるようである。
つまり樺太の南端から稚内までのトンネル計画である。これによりシベリア鉄道を日本の貨物でうめつくし、海路の需要を少しでもシベリア鉄道に振り向けさせ国内経済を活性化させたい意図である。
ロシアにとっては中国は信用ができない仮想敵国であり、実際には日本も北方領土の問題があるからやはり同様なのだが、日中及び露中は日露以上に敵対関係であるため、ロシア側から見れば北方領土に譲歩してでも日本と組んで共に中国に圧力をかけるメリットが強まれば問題を解決させようとすることが考えられる(あくまで損得の問題である)。
しかし、そうはいっても無条件で北方領土を返還してしまうのは国内世論に対して示しがつきにくい(よほど中国との関係が悪化して誰がどう見ても日本と組むのが得策だというのが明らかなら話は別だが可能性は低い)。
よって、この宗谷トンネル計画を持ち出し日本の負担額を強めた上で北方領土と交換という意図である。これに関しては異説・反論もあるが、日本は島国意識の強い国である事情もあり、やはり北方領土問題を放置した上で一方的にこの計画を持ちだしても100%拒否されてしまうことは容易に想像できる。
そのため、このような計画を無条件で持ち出すほどウラジミール・プーチンも馬鹿ではないということであり(明らかに無茶な条件で提案した所で時間の無駄にしかならず、単なる国家予算の浪費である)、やはり北方領土問題との外交カードの一つと考えるのが妥当と考えられる。
地質学的には樺太と北海道の差は小さく、また水深の差からも技術的には青函トンネルよりも楽であるとされる。
しかし、仮に北方領土返還などなされ(ロシアは信用がないため、現在の自民党政権との交渉では領土返還→トンネル建設の順番になるだろう)諸問題が完全に日本の納得の行く形で解決し、トンネルを作りヨーロッパまで繋がったとしても以下のような問題から、非現実的だと日本の鉄ヲタは指摘している。
- 軌間の問題。シベリア鉄道は1520mmの広軌、欧州や中国などは1435mmの標準軌でこの両者の間では台車交換が行われているが、日本の在来線鉄道は1067mmの狭軌であり、また長距離貨物列車の台車交換の前例もなく、北海道、特に道央道北の豪雪気候(基本的にロシアよりも北海道のほうが雪の量は多い、気温が極端に低い場合、降雪量はかえって少なくなる)から三線軌条も非現実的である。仮に改軌するとしても、そのために工事での長期の運休や改軌後の車両の開発によるJR北海道やJR貨物に対する負担は非常に大きい。
- 先程の軌間の問題から日本の貨物列車のコンテナはシベリアのそれと比べ極端に小さく、輸送効率に大きなボトルネックがある。そのためどうしても効率が悪くなってしまう。
- 宗谷本線に起因する問題。宗谷本線は超閑散路線であり、名寄駅以北は近代化しておらず現在でも最高速度95キロで最新のディーゼル機関車であるDF200は乗り入れができない。即ち、もし貨物輸送をしたい場合、新たな機関車が開発されないとすればDD51やDE10と言った旧式機関車に頼らざるをえない。しかし、このトンネルができている頃には間違いなくDD51やDE10は寿命で退役しており、やはり新しい機関車の開発費がJR貨物に襲い掛かってくる。
- そもそもの問題として、JR貨物は宗谷本線に貨物列車を運転していない。ただし正確にはこれは誤りで旭川駅から北旭川駅(貨物駅)までの間で運行がなされている。正確には第二種鉄道事業者として名寄駅まで登録されているものの、合理化によってトラック輸送に切り替えられている事情から、やはり現在の宗谷本線は貨物輸送を全くといっていいほど想定していない。そのため、ダイヤ上のボトルネックとなる。
- 特に名寄以北は線形が悪く、特急列車も含め1日上下1桁づつの本数しか走ってないとあって交換駅から次の交換駅までの距離(閉塞)も数十キロ単位と長い。かつてはもう少し短かったが合理化による本数削減とともに交換可能駅も減少している。
- 稚内駅とその周辺に起因する問題。稚内駅はかつて1面2線だったが、めったに2線を占めない状況が続き、ついに棒線駅化された。スイッチバックなどの問題もはらんでおり、また貨物ターミナルの土地の問題もある。距離的に宗谷岬側にトンネルが出ることになるため、やはり諸問題が含まれる。
このような問題があるためか、日本政府やJRはこの計画に対して完全無視を決め込んでおり、ロシア側(特にサハリン州)はこの計画に対してかなり積極的で既に国交省や政府と交渉しているとしているのだが、日本側は政府・JR共に賛成反対以前の問題として、意見表明さえしていないのが現状である(ちなみに、初版編集者もJR北海道、JR貨物に問い合わせのメールを送ったが回答は帰ってきてない。つまりは、そういうことである。)。
また、ロシア側から見た問題もある。特に日本からシベリア鉄道貨物輸送において中間利益を得ていた沿岸州は経済的な打撃を受けるため、この計画に反対するのでは?とも言われているが正確なところはわからない。
日本メディアとのかかわり
ソ連時代、この鉄道は重要な軍事施設とみなされ、外国人が自己手配で切符を取得し自由に乗降することも、気軽に写真撮影することも許されなかった。そのため日本人にとっても「近くて遠い鉄道」であったが、1982年にNHKがドキュメンタリー作品『シベリア鉄道』を制作。これはロシア号に乗車し、沿線の風物、人々の暮らしや車内の様子を紹介する、今でいえば『世界の車窓から』のような映像作品であった。このような映像作品の制作は世界的にも稀なことで、作中にも取材許可を得るための苦労が記録されている。例えばトンネルの撮影はただ1箇所しか許されなかったし、許可を受けていてもなお列車の撮影中に市民から通報されるようなことさえあった。この作品は1990年にビデオ化され市販されている。
これに多くの日本人が触発され、シベリア鉄道への興味と憧れを強く抱いた。かの宮脇俊三氏も取材旅行に出かけ 『シベリア鉄道9400キロ』 を執筆。ただしこの際、当局に「シベリア鉄道、ひいてはソ連のすばらしさを伝えたい」という手紙まで書いたものの、全線完乗を果たすことは認められなかった。
ソ連崩壊後はこのような苦労から開放され、ニコニコ動画にも個人撮影による動画がアップロードされている。NHKも2008年に再びシベリア鉄道を題材にしたドキュメンタリー『シベリア鉄道 広大な大地を駆け抜ける 激動のロシア』を制作している。
車両
シベリア鉄道の車両は様々な塗装であり、北朝鮮や中国と言った東洋から遥か東欧の客車を見ることもできるなど多岐にわたる。
しかし、近代化は不十分な部分もあり、第二シベリア鉄道はまだまだ単線非電化の区間も多く、またトイレが垂れ流し式であるようだ。
また暖房装置はエアコンなどではなくストーブが用いられている。これはエアコンなどの故障時に立ち往生などした場合文字通りシベリアの死神の犠牲となり、シベリア送りの亡者と成りはててしまうからである。
関連動画
車窓動画
ヨーロッパ方面行き動画
日本方面行き動画
駅名動画
関連生放送
ウラジオストクからモスクワまでの9288キロの日中の車窓をノーカット
初日
最終日
関連項目
脚注
掲示板
-
29 ななしのよっしん
2023/10/08(日) 15:48:07 ID: tfr1xwsSQ9
いくら貨物取り扱い量が多いとはいえ、北朝鮮から輸入した砲弾をロシア領横断コースで運ばせるのは気は確かかと問いたい。一回運んで終わりじゃないんだぞ
-
👍0👎0
-
30 ななしのよっしん
2024/01/25(木) 02:22:24 ID: /rH7n8QOsP
シベリア鉄道シミュレーター『Trans-Siberian Railway Simulator』開発中、プロローグ版が1月24日に無料配信へ。ウォッカを飲みマフィアの仕事をこなすサバイバル要素強めの鉄道運転
https://news.den faminico gamer.jp /news/24 0123x 
-
👍1👎0
-
31 ななしのよっしん
2025/04/25(金) 11:59:29 ID: rkC8BHRQyY
-
👍0👎0
おすすめトレンド
ニコニ広告で宣伝された記事
急上昇ワード改
- 124
- 65
- 189
- 7,220
- 762
最終更新:2025/12/05(金) 19:00
- 104
- 157
- 260
- 263
- 72
最終更新:2025/12/05(金) 19:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。