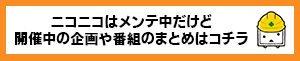BRTとは、バス高速輸送システムの事で、英訳の「バス・ラピッド・トランジット(Bus Rapid Transit)」の頭文字を取ってBRTと略す。
概要
簡単にいうと専用軌道にバスを走らせる公共交通のことである。
その本質は専用軌道にバスを走らせることによって鉄道に近い定時性をバス交通に持たせ、同時に車両単価の低いバスを使用することで損益分岐点を大きく引き下げ経営の黒字化を容易にする点にある。
この条件を満たさない場合には、狭義におけるBRTではないといえる。
なお、広義においては一般道を走るバス交通であっても一部専用線を持つ場合にBRTと呼称される。
歴史
一般的にはブラジルのクリティーバ市で頓挫した鉄道計画の用地を転換し専用バスレーンに仕立てたものが最初のBRTだといわれる。
日本においては廃止された鹿島鉄道の廃線跡を利用した物が有名である。
メリット・デメリット
BRTは上記の歴史からもうかがえるように鉄道廃線後の跡地や未成線などを転用する事が多く、初めから都市計画として作成されることは少ない。
そのため以下のメリット、デメリットが発生する。
つまるところバスと鉄道の中間の公共交通であり、そもそもそういう特性を持つ運行形態であることを念頭に話をする必要がある。
メリット
デメリット
- 鉄道と比較して運行速度が遅い。
- 鉄道と比較した場合に一車両あたりの輸送人員数が少ない。
- 専用道でない場所にて渋滞に巻き込まれるリスクがある。
- 一般的な日本国内における鉄道駅のようなランドマーク的な意味合いを持たない駅が複数発生する。
メリット・デメリットの両方にてDMVとかぶる内容が多い。
これは運行形態が類似しているためである。
しかしながら、DMVと違いBRTの場合には鉄路が存在しないため、鉄道列車との衝突を避けるための閉塞処理を必要としないなどの点に大きな違いがある。
近年、赤字鉄道路線の転換論が出ている路線が複数あるが、転換しても上記のメリットが生かせるかどうかは定かではない。その為、経営上の理由からのみのBRT転換には慎重であるべきである。
その一方で鉄道路線と比較した際に損益分岐点が大きく下がるということは少子高齢化のすすむ現在の日本において地方の公共交通をただのバス路線より利便性の高い状態にて長期間維持できるということの裏返しでもあり、天災などにより完全破損してしまった鉄道の転換(復旧費用のめどが立たない・今後の居住人口増が望めない地域など)などで、今後とも誕生する可能性の高い交通政策のオプションであるといえる。
東日本大震災
被災した三陸縦貫線のうち大船渡線、気仙沼線のそれぞれ一部分について仮復旧の手法としてBRTが採択されている。
これは被災した駅が将来的に移動する可能性が高いため鉄道として即時復活するわけには行かないことと、同時に公共交通を必要とする住民がいることの両面から暫定復旧としてBRTが選択された。実際の運行はJR東日本が元鉄道事業者である宮城交通に委託することで実施している。
BRTとDMV
経営上から見た特性はBRT、DMVともに類似している。
しかしながら乗り物のカテゴリとしてみた場合には、道路路面のみを走るBRTと鉄道路線の走行も前提にされるDMVではまったく違う乗り物であるといえる。
その為、DMVとBRTはどちらか片方が採用されれば、もう片方は採用されることがほぼないという競合関係にある。
なお、技術体系で見るならば路盤に対して専用軌道という特質を付与したBRTと、特殊車両によって既存インフラを使用するDMVの両方を選択することは理論上は可能ではある。
しかしながら費用面ではどちらか片方のみの選択の方が優位となるため、よほど特異な例でない限りは両方が選択されることはないと思って差し支えない。
日本国内に存在するBRT路線(2021年8月現在)
※都道府県別
今後開通予定のBRT
関連動画
関連コミュニティ
関連項目
- 1
- 0pt