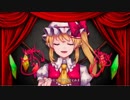エラリー・クイーン(Ellery Queen)とは、アメリカの推理小説家。
フレデリック・ダネイ(1905-1982)とマンフレッド・リー(1905-1971)、従兄弟同士の2人による合作ペンネームである(ダネイとリーの名前もペンネーム)。
早川書房から出る本での表記は「エラリイ・クイーン」。また別名義にバーナビー・ロスがある。
《国名シリーズ》や『Xの悲劇』『Yの悲劇』といった作品で「フェアな論理に基づいた作者と読者の推理ゲーム」という本格ミステリの理想像とされる形式を確立した、本格ミステリの神様である。
作中に登場する同名の名探偵についても本記事で解説する。以下、作家名は「クイーン」、作中の探偵の名前は「エラリー」で区別する。
概要
1928年、マンハッタンで働きながら親しく交際していたダネイとリーは、7500ドルの賞金に釣られて、当時大人気だったS・S・ヴァン・ダインの影響を受けた探偵小説を書き雑誌の懸賞小説に応募。
いろいろ出版社の方でゴタゴタがあって受賞はしなかったものの出版はしてもらえることになり、1929年、名探偵エラリー・クイーンの登場する『ローマ帽子の謎』でデビューした。
以後『フランス白粉の謎』『オランダ靴の謎』とタイトルに国名を冠したシリーズとして刊行され、ベストセラーになる。
1932年に専業作家となり、執筆にあてられる時間が増えたことでバーナビー・ロスという別名義を作り、シェイクスピア俳優ドルリー・レーンが探偵役を務める《レーン四部作》の1作目と2作目になる『Xの悲劇』『Yの悲劇』を発表。
この年はクイーン名義でも『ギリシャ棺の謎』『エジプト十字架の謎』を発表、ミステリー史に残る歴史的傑作を4作続けて出したこの年はファンの間で「奇跡の年」と呼ばれている。
当初バーナビー・ロスがクイーンの別名義であることは公表されておらず、またクイーンが合作ユニットであることも公表されていなかったので、ダネイとリーがそれぞれクイーンとロスとして覆面対談するという手の込んだ二人二役も行われた(クイーン=ロスであることは1940年に公表された)。
解決編の前に読者へ推理に必要な手がかりが全て揃ったことを宣言する「読者への挑戦」という形式を確立し、フェアな論理パズルとしての本格ミステリを完成させたクイーンだったが、ダネイとリーは徐々に純粋な論理パズルとしてのミステリに行き詰まりを感じ始め、国名シリーズは9作目の『スペイン岬の謎』(1935年)でストップ。
その次に出た『中途の家』(1936年)あたりからは登場人物の人間ドラマも重視するようになっていく。『災厄の町』(1942年)から始まる架空の地方都市ライツヴィルを舞台にした作品群や『九尾の猫』(1949年)は、そういった論理的な謎解きと人間ドラマとの両立を目指した中期から後期のクイーンの代表作とされる。
合作の創作法は本人たちは明確にしなかったが、基本的にダネイが全体の設計図となる梗概を作り、リーがそれに小説として肉付けするという手法であったことが明らかになっている。
2人は1958年の『最後の一撃』で名探偵エラリーの登場する作品は終わりにするつもりだったが、結局その後もリーの死去まで書き続けることになった(リーが執筆を担当していない作品や、名義貸しについては後述)。
小説以外では、1939年から1948年まで、名探偵エラリーが活躍する犯人当てラジオドラマ『エラリー・クイーンの冒険』の脚本を担当し、これによって全米での知名度が飛躍的に上がった。ラジオドラマの脚本は短編に書き改められたものも多く、ラジオドラマの脚本集も複数出ている。
1941年からはダネイが推理小説専門誌「エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン(EQMM)」を創刊して新人作家の発掘に力を注ぎ、アンソロジーの編纂で埋もれた名作の発掘にも貢献した。これらの働きから、「エラリー・クイーンはアメリカのミステリそのもの」とも評されたという。
1971年、リーが死去し、小説家としてのエラリー・クイーンの活動は終了した。
1982年にダネイも死去し、現在アメリカではほぼ忘れられた作家になっているが、その作品群は海を隔て、日本のミステリー界にあまりにも大きすぎる影響を与えた。
現在のところ、世界で一番エラリー・クイーンが愛されている国は間違いなく日本である。
ちなみにダネイはデビュー当時から親日家で、作品にはときどき(初期では「タマカ・ヒエロ」とか「マツォユマ・タフキ」なる珍妙な)日本人名や日本人のキャラが登場する。
晩年には来日して、日本人作家のアンソロジーを編纂したりした(『日本傑作推理12選』全3巻、1981年~82年、カッパ・ノベルス刊)。
シリーズに関して
クイーンの作品に《国名シリーズ》《レーン四部作》《ライツヴィルもの》といったシリーズがあることはちょっとミステリに興味のある方ならクイーンを読んだことが無くてもご存じであろう。
以下、それぞれどういう区分なのかを軽く説明する。
まず、大雑把な区切りとしてクイーンの作品は
「名探偵エラリー・クイーンもの」
「ドルリー・レーンもの(レーン四部作)」
「ノンシリーズの単発作品」
の3種類に分かれる。
クイーンの(正典とされる)長編は全部で38作あるが、このうち『Xの悲劇』『Yの悲劇』『Zの悲劇』『レーン最後の事件』の4作がバーナビー・ロス名義で書かれた《レーン四部作》。
『ガラスの村』と『孤独の島』の2作がノンシリーズの単発作品である。
つまり、残る38作中32作がエラリーの登場する作品である(エラリー自身は出てこないが父のリチャード・クイーンが主役の『クイーン警視自身の事件』も便宜上ここに含む)。
でもって、《国名シリーズ》と《ライツヴィルもの》はエラリーものの内部シリーズということになる。
クイーン作品は基本的に各作品ごとに話は独立しているので、どこから読んでもさほど問題はない。ただし、《レーン四部作》はできれば刊行順に読むのを推奨する。
国名シリーズ
デビュー作の『ローマ帽子の謎』から始まる初期作品シリーズ。具体的には以下の9作を指す。
タイトル表記は、最も広く読まれただろう創元推理文庫旧版のもの/現行の角川文庫版のもの。()内は発表年。え?ローマは国名じゃない?こまけぇこたぁいいんだよ!
- ローマ帽子の謎/ローマ帽子の秘密(1929年)
- フランス白粉の謎/フランス白粉の秘密(1930年)
- オランダ靴の謎/オランダ靴の秘密(1931年)
- ギリシア棺の謎/ギリシャ棺の秘密(1932年)
- エジプト十字架の謎/エジプト十字架の秘密(1932年)
- アメリカ銃の謎/アメリカ銃の秘密(1933年)
- シャム双子の謎/シャム双子の秘密(1933年)
- チャイナ橙の謎/チャイナ蜜柑の秘密(1934年)
- スペイン岬の謎/スペイン岬の秘密(1935年)
いずれも名探偵エラリーが活躍し、「読者への挑戦状」が(『シャム双子』を除いて)作中に入っている。また、エラリーの物語の紹介者として、J・J・マックなる架空の人物による「まえがき」が毎回ついている。『ローマ帽子』のまえがきで、エラリーが結婚してリチャード警視や妻子とともにイタリアに隠居してることになってるのは黒歴史。
クイーン作品の中でも最も知名度・評価の高いシリーズであり、「クイーンって何から読めばいいの?」というときは、とりあえず『Xの悲劇』か国名シリーズから読んでおけばいい。
ちなみに作中の時系列で一番最初になるのは4作目の『ギリシャ棺』だが、『ギリシャ棺』から読むべきかと言われるとやや疑問。
なお、日本では『ニッポン樫鳥の謎』(創元推理文庫での訳題、ハヤカワ文庫では『日本庭園の秘密』)というタイトルで出ている作品があり、かつては原題が「THE JAPANESE FAN MYSTERY」であるとされ、国名シリーズの10作目として扱われていた。
しかしこれは江戸川乱歩が広めた都市伝説で、実際の原題は「THE DOOR BETWEEN」であり(かつては「戦時中に対日感情の悪化のため改題された」とか「雑誌掲載時から単行本化の際に改題された」とかもっともらしく言われていたが、現在はどちらもデマとされる)、現在では『ニッポン樫鳥』(もしくは『日本庭園』)は国名シリーズには含まれないとするのが定説である。
この事実関係の確認を踏まえ、2012年から角川文庫で出た国名シリーズには『ニッポン樫鳥』は含まれていな……かったのだが、2024年になって『境界の扉 日本カシドリの秘密』という原題と定着した邦題の折衷案みたいなタイトルで新訳された。
その角川文庫版では『スペイン岬』の次に出た長編である『中途の家』を国名シリーズに準じる作品として「国名シリーズプラスワン」という形で扱っており、『境界の扉』もあくまで「プラス」枠ということらしい。
ちなみに『中途の家』のまえがきには、前述のJ・J・マックの口を借りて「なんでタイトルが『中途の家』なの?『スウェーデン燐寸の秘密』でいいじゃん!(大意)」というセルフツッコミが入っている。
日本では有栖川有栖や太田忠司がこの国名シリーズに倣って、国名や都市名が入るシリーズを展開している。
また、綾辻行人の「館」シリーズや、笠井潔の「矢吹駆」シリーズが全10作予定とされているのは、当時はまだ『ニッポン樫鳥』を入れて全10作と言われていた国名シリーズに倣ったもの。
この件について綾辻行人は「国名シリーズは全9作なのですな。「クイーンの国名シリーズに倣って全10作」と云ってきた「館」シリーズも、ならばもう9作で良いのかも、などと(笑) 」とか冗談めかして語っている。
」とか冗談めかして語っている。
国名シリーズ最大の発明は「読者への挑戦」という形式を確立したこととはクイーン研究者として知られる飯城勇三の弁。
クイーン以前にも「読者への挑戦」があるミステリは存在したが、飯城によればクイーンの「挑戦」は、「作中の手がかりから読者が犯人を導き出せるか」と問うているのではなく、「作中の手がかりからエラリーがどう推理したのか」を読者に問うているのが画期的なのだとか。
また新保博久は、国名シリーズの新規性はそれまでの本格ミステリが「容疑者をある程度まで限定した中での犯人探し」を成立させるために「お屋敷での遺産相続」という形式を必要としたのに対して、クイーンや「劇場」や「デパート」や「病院」を舞台にしたことで都会を舞台に成立させたこと、と評している。
ちなみにクローズド・サークルという形式の長編の最初期の作例が国名シリーズ第6作の『シャム双子の秘密』である(アガサ・クリスティ『そして誰もいなくなった』より6年早い)。
ライツヴィルもの
中期から後期にかけて発表された、架空の地方都市ライツヴィルを舞台とする作品群。長編は以下の6作が該当する。いずれもハヤカワ文庫刊。
こちらも全て名探偵エラリーが活躍する。ただし『帝王死す』はメインの舞台はライツヴィルではない(エラリーが物語の後半で聞き込みのためにライツヴィルに向かう)。
また、直接ライツヴィルは登場しないが、ノンシリーズ長編『ガラスの村』の舞台はライツヴィルのすぐ近くという設定。
短編にもちらほらライツヴィルが登場する作品があり、
「ライツヴィルの盗賊」「GI物語」(『クイーン検察局』収録)
「ライツヴィルの遺産」「ドン・ファンの死」(『クイーンのフルハウス』収録)
「結婚式の前夜」「菊花殺人事件」(『クイーン犯罪実験室』収録)
「結婚記念日」(『間違いの悲劇』収録)
の計7編が存在する。
各作品のストーリーは独立しており、共通するのは舞台と一部の人物名ぐらいで、作品内容には国名シリーズのような統一感や、レーン四部作のような強い連続性はない。前の作品の登場人物名や事件が言及されて時間の流れを感じさせる部分はあるものの、ストーリーに大きく関係はしない。
国名シリーズの頃よりも登場人物の人間ドラマを重視しているのは確かだが、それは中期以降のクイーン作品全体の特徴である。
なお、ライツヴィルものではない長編『九尾の猫』(1949年)は、物語の上では『十日間の不思議』の続編にあたるので、可能な限り『十日間の不思議』を読んでから読んだ方が良い。
現在は『災厄の町』『フォックス家の殺人』『十日間の不思議』『九尾の猫』『ダブル・ダブル』の5作が越前敏弥訳でハヤカワ文庫から出ているため、そちらで順番通りに読むことが可能。
レーン四部作
国名シリーズと並行して発表された、シェイクスピア俳優ドルリー・レーンが登場する四部作。
このシリーズには名探偵エラリーは登場しない。
ロンドンの目抜き通り「ドルリー・レーン」を芸名とした、古風な服装を好む老人。シェイクスピア俳優として名を馳せるも、聴覚を失った事で引退。ニューヨーク郊外の「ハムレット荘」にて元演劇関係者の老人達とともに隠遁している。読唇術を身に着けているため、電話を除けば生活に支障はない。
冷静な観察眼と的確な助言をもって、難事件の捜査に協力。俳優時代のノウハウを生かし、メーキャップを施して別人に扮する事も可能。
『Yの悲劇』が突出して有名なので、「『Y』だけ読んだ」という人も結構いるだろうが、四部作全体を通してドルリー・レーンという名探偵の物語になっているので、できれば四部作を通して読んでもらいたい。まあ、『Z』と『レーン最後の事件』は本格ミステリとしては『X』『Y』より出来が落ちるのは、クイーンファンも否定できないところではあるが……。
日本のミステリで『○の悲劇』というタイトルがついていれば、ほぼ間違いなくこの四部作をパロったものである。夏樹静子『Wの悲劇』、森博嗣『χの悲劇』、米澤穂信『Iの悲劇』などなど。
タイトルをパロっただけで中身は無関係なものから、倉知淳『片桐大三郎とXYZの悲劇』のように、内容までこの四部作のパロディになっている作品までいろいろある。
ちなみにこの四部作、日本で一番最初に訳されたのは最終作の『レーン最後の事件』だったとか(訳題は『紙魚殺人事件』。戦前の話である)。
なんというか、そんなムタイな。
その他の作品
上記以外の作品では、ハリウッドを舞台にした『悪魔の報酬』『ハートの4』のハリウッド2部作(『ドラゴンの歯』も入れてもいいかも)、エラリーの父・リチャード警視が主人公のスピンオフ『クイーン警視自身の事件』とその続編『真鍮の家』などが一応シリーズ扱いできるが、特別分類する意味もあんまりない。『ガラスの村』と『孤独の島』以外はエラリーもの、とだけ覚えておけばいい。
前述の通り、基本的に話はそれぞれ独立しているのでどこから読んでも大丈夫である。
まあ、いきなり中期や後期のマイナーな長編から読むのはあんまりオススメしないが……。
代作に関して
さらにちょっと本格ミステリの古典に興味のある人なら、「クイーンの作品にはいくつか別の作家による代作がある」という話は聞いたことがあるだろう。
エラリーが登場し、後期作品の中では評価が高い『盤面の敵』が代作というのはある種のトリビアのように語られたりする。
フランシス・M・ネヴィンズによる詳細な評伝が出るまで情報がはっきりしない部分が多かったため、今でもクイーンの代作問題については、あやふやな理解の人が多いと思われる。
というわけで簡単にまとめると、クイーンの代作にはおおまかに分けて2つのパターンがあり、
とに分かれる(もうちょっとややこしいのもあるが後述)。
1に相当するのが60年代に発表された長編のうち3作で、この時期はリーがスランプに陥り、ダネイの梗概をもとに、2人のSF作家が執筆を担当した。
『盤面の敵』ではシオドア・スタージョン、『第八の日』『三角形の第四辺』ではアヴラム・デイヴィッドスンが執筆を担当している。また『真鍮の家』もデイヴィットスンの代作と言われていたが、最新の研究ではこれはデイヴィットスンの原稿をリーが没にして自分で書き直したらしい。
この3作(『真鍮の家』も含めれば4作)については、ダネイが梗概を作ったことがはっきりしているため、現在ではリーが執筆を担当した他の作品と同様「正典」として扱われているようだ。
漫画で例えれば作画担当が違うけど原作者は一緒だからどれも原作者による公式作品と見なして問題ないよね、ということである。
一方、2に相当する名義貸しのペーパーバックが本国アメリカでは結構な数が出ており(クイーン名義だけでなく、バーナビー・ロス名義も)、情報が少なかった時代にそのうちの1作『二百万ドルの死者』がクイーンの作品として他の正典とごっちゃになって早川書房から翻訳出版されていた。
現在は、これらの名義貸しのうち比較的評価の高い何作かが原書房から「エラリー・クイーン外典コレクション」として翻訳されているが、こっちはあくまで「外典」であり、正規のクイーン作品とは見なされない。
また、「エラリー・クイーン・ジュニア」名義で出た児童向けの『ジュナの冒険』シリーズ(日本ではハヤカワ文庫Jrから全9巻のうち8巻まで邦訳された。現在は角川つばさ文庫から『見習い探偵ジュナの冒険』のタイトルで1巻と3巻が新訳されている)も同様に完全な別作家による代作。
また、1にも2にも当てはまらないややこしい例としては、ダネイ&リーの執筆によるエラリー登場パートと、他の作家による映画ノベライズとが混ざっている『恐怖の研究』がある。
「ややこしいんじゃボケ、こっちはちゃんとしたクイーン作品だけ読みたいからどれ読めばいいのかだけ教えろ」という方に簡単にまとめると、
- 執筆担当がリーじゃない作品もダネイが話を作ってれば正典扱いだからこまけぇこたぁいいんだよ!
- でも『二百万ドルの死者』(ハヤカワ文庫HM)は完全な名義貸しだから注意
- 『恐怖の研究』(ハヤカワ文庫HM)を読むかどうかは各自の判断に任せる
ということである。具体的には、後述する作品リストに載ってる作品を読めば良い。
なお、短編にもリーのスランプ時期に発表されたものは別の作家が執筆を担当したものが含まれると思われるが、これはクイーン研究家にもどれがそうなのか判断不能らしいので、やはり細かいことは気にしないのが吉である。
日本での評価・影響力
戦前からクイーン作品は日本でも翻訳されていたが、戦前の長編ミステリの翻訳は原書から内容を大幅に省略した抄訳が中心だった。
そのため、緻密なロジックが売りであるクイーン作品の面白さは抄訳ではうまく伝わらず、戦前は「長編より短編が上手い作家」みたいに扱われていたらしい。
戦後、きちんと長編が全訳されるようになると評価が急上昇。
特に『Yの悲劇』は江戸川乱歩が絶賛し、横溝正史が強い影響を受けて『獄門島』を書くなどした影響から、オールタイムベスト不動の1位として君臨し続けた。
アガサ・クリスティ、ジョン・ディクスン・カーとともに本格ミステリ黄金時代の御三家とも称される。
とりわけ初期作品は純粋な論理パズルとしての本格ミステリの完成形としてマニアの崇拝を集め、絶大な影響力を誇った。
「ミステリー=名探偵による論理的な(読者にも犯人が指摘可能な)犯人当て」というイメージの形成にクイーン作品の影響が多大なのは間違いない。
日本では本格ミステリというジャンルそのものの象徴であり、本格ミステリ大賞のトロフィーにはトランプのクイーンがデザインされている。また、作中に作者と同名の名探偵やワトソン役が登場する作品はだいたいクイーンの影響(あるいはクイーンに影響を受けた有栖川有栖あたりからの影響)である。
有栖川有栖や法月綸太郎など新本格ムーヴメントの中心作家が強烈な影響を受けていたこともあり、21世紀の現在に至るまで日本では本格ミステリの神様としてその作品群が読み継がれている。
単に読み継がれるだけでなく、クイーン作品は特に新本格以降、幾度となく評論・研究の対象として様々に分析され、いわゆる「後期クイーン的問題」(詳しくは「名探偵」の記事を参照)をはじめ、新本格以降の日本の本格ミステリに強い影響を与え続けている。
新本格以前は、クイーンは初期から晩年までダイイング・メッセージを多用したことがよく特徴として挙げられ、都筑道夫のようにその点について批判する評論家も多かった。
新本格以降はそのロジックの精密さと、そこから生じた「後期クイーン的問題」の方が重要視されるようになったため、「クイーンと言えばダイイング・メッセージ」とはほとんど言われなくなっている。
ちなみに日本国内では『Yの悲劇』が最も人気が高いが、本国アメリカを含め海外では『Y』の評価はそれほど高くない。
最も人気が高いのは『災厄の町』で、レーン四部作では『Xの悲劇』が最も評価が高いようだ。国名シリーズは日本でも海外でも『ギリシャ棺』と『エジプト十字架』が2強の模様。
で、どれを読めばいいの?
2024年現在では、越前敏弥訳の国名シリーズ(+『中途の家』『境界の扉』)とレーン四部作が角川文庫から出ており、たぶんこれが一番読みやすい。
越前訳クイーンは他にハヤカワ文庫から『災厄の町』『フォックス家の殺人』『十日間の不思議』『九尾の猫』『ダブル・ダブル』『靴に棲む老婆』が出ており、有名どころのクイーン長編は越前訳でほぼ網羅することができる。
創元推理文庫からは2011年から中村有希による代表作群の新訳がスローペースで刊行中で、2024年8月現在、『アメリカ銃の謎』までの国名シリーズと、『Xの悲劇』『Yの悲劇』、短編集の『エラリー・クイーンの冒険』『エラリー・クイーンの新冒険』が新訳済。短編集の2冊は越前訳が出ておらず、この創元推理文庫でのみ読める。
レーン四部作の残りは今となっては古めかしい1950年代の鮎川信夫訳がいまだに現役である。
というわけで、今からエラリー・クイーンを読むなら、越前敏弥訳の角川文庫の15冊+ハヤカワ文庫の6冊、計21長編と、創元推理文庫の中村有希訳の短編集『冒険』『新冒険』の合計23冊の中から読み始めるのがオススメ。
主に青田勝訳でハヤカワ文庫から出ていた残りの中期~後期作品は品切れなので、古書店をあたろう。
名義貸し作品を除けば、クイーンの小説は全て邦訳され本になっているので、古書を探す苦労さえ厭わなければ、未訳作品の存在に歯がみする心配はない。
ガイドブックとしては、星海社新書から飯城勇三『エラリー・クイーン完全ガイド』が出ているが、ガチのクイーンマニアの書いた本のためか、初心者向けガイドにしてはかなりネタバレ気味の記述が多く、クイーン未読の人に勧めるにはいささか躊躇する本なので注意。
クイーン作品は「論理的な推理はすごいけど話は地味で面白くない」と言われがちで、実際ハラハラドキドキのサスペンス性やおどろおどろしい怪奇趣味、驚天動地の大トリックなどを期待して読むと残念な気持ちになる可能性が高い。
だが、思わぬ手がかりから意外な論理を導きだし、多彩な容疑者たちからたったひとりの犯人を絞り込んでいくロジックの面白さを楽しめる人であれば、現代の凝りに凝った本格ミステリを読み慣れた読者でも間違いなく満足できるのがクイーン作品である。
地道な捜査による手がかり集めを退屈に感じる人は、比較的話が派手な『エジプト十字架の秘密』や『シャム双子の秘密』あたりから読むのもいいかもしれない。
あと『Yの悲劇』は有名作だけに思わぬところでネタバレされがちなので、なるべくネタバレを踏まないうちに読んでおきたい。
名探偵エラリー・クイーン
「コナン・ドイルの名前を知らない人でもシャーロック・ホームズの名前は知っている」ので「名探偵を作者と同名にすれば自動的に作者名も覚えてもらえる」という理論で生み出された作者と同名の探偵。
作者と同名の登場人物が出てくるミステリは、クイーンも強い影響を受けたS・S・ヴァン・ダインのファイロ・ヴァンスものが先行するが、そっちはワトソン役であり、作者と同名の名探偵はエラリーが最初である。
広辞苑では誰が書いたのか「初期の作品シリーズの主人公」とか書かれているが、前述の通り、実際はクイーンの正典38長編のうち31作、第1作から最終作までほとんどの作品に登場する。
次の改訂では直してくださいよ岩波書店さん。
本業は推理小説家。父親のリチャード・クイーン警視や、従卒のジューナ(途中でフェードアウト)とともに暮らしている。
決め台詞は「Q.E.D.(証明終わり)」。
シリーズで多数の作品に登場する名探偵は歳をとらないことが多いが、エラリーは全く歳をとらないわけではなく、『最後の一撃』の終盤では老年にさしかかったりしている。とはいえ年齢設定は曖昧。
初期は気取った引用癖やもったいぶった推理からいけすかない若者というイメージが強いが、中期作品以降では事件関係者とロマンスを繰り広げたり、犯人に自分の推理力を利用されて深く苦悩したりと人間味が増していく。その一方で推理力は衰えていく。
いくつかの長編とラジオドラマなどではニッキー・ポーターという秘書がいるが、クイーンはニッキーには全く愛着がなかったようで、登場するたび容姿やエラリーとの関係などの設定がコロコロ変わる。たとえば初登場作ではそのままエラリーの嫁になりそうな展開だったが、その後は特にそんなことはなかったかのようである。
ジューナは『ニッポン樫鳥の謎』を最後に登場しなくなるが、彼を主役にした(名義貸しの)児童向けシリーズ《ジュナの冒険》が発表された。ただ《ジュナの冒険》にはエラリーは出てこないので、名前が同じだけの別キャラなのかもしれない。
ミステリーの歴史においても代表的な名探偵のひとりだが、エラリーがシャーロック・ホームズやエルキュール・ポワロほどの一般的知名度がないのは、映像化のヒット作に恵まれなかったためか。
映画化は何度かされているが、クイーンの理屈っぽい作風は映像化と相性が悪いようで、どれもあまり評判がよくない。
作品リスト
名義貸し、アンソロジーなどはめんどくさいので除く。そっちのリストはWikipediaでも見てください 。
。
長編(正典とされるもの)
- THE ROMAN HAT MYSTERY (1929) 『ローマ帽子の謎』
- THE FRENCH POWDER MYSTERY (1930) 『フランス白粉の謎』
- THE DUTCH SHOE MYSTERY (1931) 『オランダ靴の謎』
- THE TRAGEDY OF X (1932) 『Xの悲劇』 ※バーナビー・ロス名義
- THE GREEK COFFIN MYSTERY (1932) 『ギリシア棺の謎』
- THE TRAGEDY OF Y (1932) 『Yの悲劇』 ※バーナビー・ロス名義
- THE EGYPTIAN CROSS MYSTERY (1932) 『エジプト十字架の謎』
- THE TRAGEDY OF Z (1933) 『Zの悲劇』 ※バーナビー・ロス名義
- THE AMERICAN GUN MYSTERY (1933) 『アメリカ銃の謎』
- DRURY LANE'S LAST CASE (1933) 『レーン最後の事件』 ※バーナビー・ロス名義
- THE SIAMESE TWIN MYSTERY (1933) 『シャム双子の謎』
- THE CHINESE ORNGE MYSTERY (1934) 『チャイナ橙の謎』
- THE SPANISH CAPE MYSTERY (1935) 『スペイン岬の謎』
- HALFWAY HOUSE (1936) 『中途の家』
- THE DOOR BETWEEN (1937) 『ニッポン樫鳥の謎』(『日本庭園の秘密』『境界の扉』)
- THE DEVIL TO PAY (1938) 『悪魔の報酬』
- THE FOUR OF HEARTS (1938) 『ハートの4』
- THE DRAGON'S TEETH (1939) 『ドラゴンの歯』
- CALAMITY TOWN (1942) 『災厄の町』
- THERE WAS AN OLD WOMAN (1943) 『靴に棲む老婆』(『生者と死者と』)
- THE MURDERER IS A FOX (1945) 『フォックス家の殺人』
- TEN DAY'S WONDER (1948) 『十日間の不思議』
- CAT OF MANY TAILS (1949) 『九尾の猫』
- DOUBLE, DOUBLE (1950) 『ダブル・ダブル』
- THE ORIGIN OF EVIL (1951) 『悪の起源』
- THE KING IS DEAD (1952) 『帝王死す』
- THE SCARLET LETTERS (1953) 『緋文字』
- THE GLASS VILLAGE (1954) 『ガラスの村』
- INSPECTOT QUEEN'S OWN CASE (1956) 『クイーン警視自身の事件』
- THE FINISHING STROKE (1958) 『最後の一撃』
- THE PLAYER ON THE OTHER SIDE (1963) 『盤面の敵』 ※執筆はシオドア・スタージョン
- AND ON THE EIGHTH DAY (1964) 『第八の日』 ※執筆はアヴラム・デイヴィッドスン
- THE FOURTH SIDE OF THE TRIANGLE (1965) 『三角形の第四辺』 ※執筆はアヴラム・デイヴィッドスン
- FACE TO FACE (1967) 『顔』
- THE HOUSE OF BRASS (1968) 『真鍮の家』
- COP OUT (1969) 『孤独の島』
- THE LAST WOMAN IN HIS LIFE (1970) 『最後の女』
- A FINE AND PRIVATE PLACE (1971) 『心地よく秘密めいた場所』
短編集(邦訳のあるもの)
- THE ADVENTURES OF ELLERY QUEEN (1934) 『エラリー・クイーンの冒険』
- THE NEW ADVENTURES OF ELLERY QUEEN (1940) 『エラリー・クイーンの新冒険』
- CALENDAR OF CRIME (1952) 『犯罪カレンダー』
- QBI: QUEEN'S BUREAU OF INVESTIGATION (1955) 『クイーン検察局』
- QUEEN'S FULL (1965) 『クイーンのフルハウス』
- QED: QUEEN'S EXPERIMENTS IN DETECTION (1968) 『クイーン犯罪実験室』
- THE TRAGEDY OF ERRORS (1999) 『間違いの悲劇』
上記以外の小説
ラジオドラマの脚本集
最初の2冊は"The Adventure of the Murdered Moths and other Radio Mysteries"(1945)の分冊。
3冊目は"The Adventure of the Crime Corporation and other Radio Mysteries"(1945)から。
4冊目は原書が存在せず、台本から直接の翻訳である。
全て論創社刊、文庫化はされていない。
その他
関連動画
関連項目
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- 相沢沙呼
- 青崎有吾
- 青山文平
- 赤川次郎
- アガサ・クリスティ
- 芥川龍之介
- 浅暮三文
- 芦沢央
- 芦辺拓
- 飛鳥部勝則
- 綾辻行人
- 鮎川哲也
- 有川浩
- 有栖川有栖
- 泡坂妻夫
- アーサー・C・クラーク
- 池井戸潤
- 伊坂幸太郎
- 石川博品
- 石田衣良
- 石持浅海
- 伊藤計劃
- 稲見一良
- 乾くるみ
- 井上真偽
- 井上夢人
- 井伏鱒二
- 今邑彩
- 今村翔吾
- 今村昌弘
- 岩井志麻子
- 歌野晶午
- 内田幹樹
- 浦賀和宏
- 江戸川乱歩
- 円城塔
- 大沢在昌
- 大山誠一郎
- 岡嶋二人
- 小川一水
- 荻原規子
- 奥田英朗
- 小栗虫太郎
- 乙一
- 小野不由美
- 折原一
- 恩田陸
- 海堂尊
- 梶尾真治
- 上遠野浩平
- 加納朋子
- 紙城境介
- カルロ・ゼン
- 川原礫
- 神坂一
- 神林長平
- 貴志祐介
- 北方謙三
- 北村薫
- 北森鴻
- 北山猛邦
- 桐野夏生
- 久住四季
- 倉知淳
- 黒川博行
- 黒田研二
- グレッグ・イーガン
- 古泉迦十
- 甲田学人
- 古処誠二
- 小林泰三
- 小松左京
- 紺野天龍
- 今野敏
- 呉勝浩
- 齋藤智裕
- 佐々木譲
- 笹本祐一
- 細音啓
- 佐藤究
- 三田誠
- 潮谷験
- 時雨沢恵一
- 品川ヒロシ
- 篠田節子
- 島田荘司
- 島本理生
- 斜線堂有紀
- 朱川湊人
- 殊能将之
- 白井智之
- 真藤順丈
- 真保裕一
- ジョージ・オーウェル
- 水野良
- 須賀しのぶ
- 瀬名秀明
- 高木彬光
- 高村薫
- 竹本健治
- 田中慎弥
- 田中啓文
- 田中芳樹
- 田辺青蛙
- 月村了衛
- 月夜涙
- 辻堂ゆめ
- 辻村深月
- 土屋隆夫
- 都筑道夫
- 恒川光太郎
- 天藤真
- 遠田潤子
- 鳥飼否宇
- 中村文則
- 中山七里
- 仁木悦子
- 西尾維新
- 西澤保彦
- 西村京太郎
- 西村賢太
- 西村寿行
- 似鳥鶏
- 貫井徳郎
- 沼田まほかる
- 野崎まど
- 法月綸太郎
- 長谷敏司
- 羽田圭介
- 初野晴
- 早坂吝
- 林真理子
- はやみねかおる
- 火浦功
- 氷川透
- 東川篤哉
- 東野圭吾
- 樋口一葉
- 広瀬正
- ピエール・ルメートル
- 深水黎一郎
- 藤井太洋
- 船戸与一
- 方丈貴恵
- 星新一
- 誉田哲也
- 舞城王太郎
- 牧野修
- 万城目学
- 町井登志夫
- 松本清張
- 円居挽
- 麻耶雄嵩
- 真梨幸子
- みかみてれん
- 三崎亜記
- 道尾秀介
- 三津田信三
- 皆川博子
- 湊かなえ
- 宮内悠介
- 宮城谷昌光
- 宮部みゆき
- 森岡浩之
- 森博嗣
- 森見登美彦
- 矢樹純
- 山田風太郎
- 山田正紀
- 山本巧次
- 夕木春央
- 横溝正史
- 横山秀夫
- 米澤穂信
- 詠坂雄二
- 連城三紀彦
- 魯迅
- 若竹七海
▶もっと見る
掲示板
-
7 ななしのよっしん
2021/03/07(日) 00:53:20 ID: U5szjfJlia
>>2
Zと最後はどうしても下に行くのね… -
👍0👎0
-
8 ななしのよっしん
2021/09/26(日) 08:37:53 ID: 260CtUym/x
エラリーも歩けば殺人事件にあたる
ライツヴィルはあまり推理物という感じはない -
👍0👎0
-
9 ななしのよっしん
2025/10/13(月) 13:11:28 ID: TWbIYLoAul
>>7
『Z』は他3作とパターンも違うので、
「クイーンはレーン最後の事件を『Zの悲劇』にするつもりだったんだけど、何かの理由でもう1作必要になってノンシリーズ用のプロットをレーン物に直し『Zの悲劇』の名前をそっちに付けてしまった。そして名前を取られた『Zの悲劇』を『ドルリー・レーン最後の事件』と改名した。」
っていう説をよく言われるな。 -
👍0👎0
おすすめトレンド
ニコニ広告で宣伝された記事
急上昇ワード改
- 26
- 1,003
- 109
- 1.2万
- 26
最終更新:2025/12/16(火) 18:00
- 43
- 179
- 68
- 286
- 88
最終更新:2025/12/16(火) 18:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。