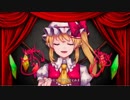中国語の発音ではXingyiquan(シンイーチュェン)と呼ばれる。
序文
御一読される前の注意であるが、本記事は中国武術の難解な専門用語は極力使わず、使用するときはなるべく判り易くすべく、その詳細な解説を試みるてはいるが、本記事は主に、以前から武術のことを好まれ興味を持っている方々や既に形意拳などの中国武術を学んでいる方々に向けて記述された、専門的な記事となっており、その詳細を解説したものである。
門外漢には、やや敷居の高い記事となっているかもしれないが、その点はどうか御一読の前に予め御了承願いたい。
武術を学ばれておられない方々におかれましても、本記事を御一読していただけたなら、形意拳が俗にいわれるような動物や昆虫の真似事をして戦う拳法ではないということを、判っていただけるかと思う。
本記事の開設にあたり、誰もが無料で閲覧可能であるニコニコ大百科という場で、形意拳という中国武術の代表的な門派を例に、有用な知識と技術、現実の武術の有様を知っていただき、手軽にシェア出来たなら、これから武術を学ぶ後進たちや愛好者たちにとって、大きな意義があると確信して記事の作成にあたった。
編集者は実名を明した上で文責を負い、可能な限り誠実に編集にあたったつもりであるが、疑問、ご意見、ご要望等は本記事の掲示板にて出来うる範囲のなかでお答えし、可能な限り閲覧者の希望の反映を行う所存である。
尚、本記事はニコニコ大百科の仕様なのだが、スマートフォンやタブレットからではなく、パソコンのブラウザで閲覧されると、冒頭に各項目ごとのリンク分けがされており、読みたい項目の記事を手軽に参照出来るようになっている。
残念ながらAndroidのブラウザのPCモードではこの機能は使用出来ない。不便であるが本記事を再び閲覧する際は、表示された記事を一気にスクロールしても何十秒と掛からないので、不要な部分は飛ばされることを御薦めする。
一応ニコニコ大百科上で、スマートフォン表示から、PC表示に切り替えることも可能だが、スマホでは文字が細かすぎて閲覧は難儀なことになってしまう。
本記事は内容をどこよりも充実させるべく、価値ある関連動画、写真、書籍、外部の優れたサイトを引用しながら解説している。
文章量だけでも小説一冊分の規模であるが、ある閲覧者のプロ漫画家の方からは、まるで旅をしたかのように楽しんで読んでいただけたという声があり、暇な時にでも少しづつ一冊の本のようにご覧下されば良い記事かと思う。
■初版開設者︰全国スパーリング交流会 札幌支部会長。日本国術総会/太氣至誠拳法武禅会 所属、関西闇武術サークル顧問 西坂 佳晃 。
概要
形意拳は東洋哲学の根本思想、陰陽五行説に合致した体系をもった中国武術である。
槍の操法を徒手の技として創始されたとされている。
天・地・人の三才(天人合一思想)を体現する、三体式(三體式 : 別名を「三才式・子午式・四象式・六合式・母式・三節式・開勢・鷹捉勢」等など)という、人の身体にあてはめると、天の陽の気を受ける頭部を上盤として天、陰の気を吸い上げる下肢を下盤として地、その陰陽ふたつの気が一気となると考えられる、胸腹部を人とする架式(姿勢)を基本の立ち方とし、陰陽五行説における、木・火・土・金・水を体現した、金行劈拳、水行鑽拳、木行崩拳、火行炮拳、土行横拳の5つの単式拳を母拳(基本技)とする。
さらに高級技法として、12種類の鳥獣の勢(イメージと性質を現した動作)を模した象形拳(物の形態に倣った拳法)である、十二形拳という技法群から構成された武術である。
数多くある中の一説であるが、形意拳における「形意」とは、意功を具体的な姿形で以て顕すことである。意功とは武術を鍛錬することで得られる心の強さのことであり、ときに形意拳が心意拳とも呼ばれるのはそのためである。また形は合理的な力と技を導き、意はそれをコントロールする心の総帥である。
三体式
三体式において、天とは、心の本体である意であり、地とは、確りと立つことである、人とは、これらによって発揮される技のことである。
形意拳の基本姿勢である、三体式を文章でのみで誤解なく総てを書き表すことは難しく、ここではなるべく要点だけを述べることとする。
本記事では形意拳の姿を映像や写真を併用して紹介しているが、正確な架式については、必ず師から指導を受け実伝で身に付けて欲しい。なぜならば独習者の主観的感覚というのは極めて疑わしいものであるからである。
なにせ繰り返し実伝を受け何年と修行を積んで身に付いた筈の者でさえ、師から姿勢を直されてしまうものであるからである。中国武術には黙念師容といって、師の姿を思い浮かべ稽古に活かす教えがあるが、しかしそこに師からの直接の口伝が伴っていなければ、勝手な思い込みにより、とても大きな躓きの元となりかねない。
一見似たような動作や姿勢をとって真似ているつもりであっても、内実は大きく異なっているのかもしれない。
三体式は、正しく立つことが出来たならば身体の前方、後方、側面、上下に向かって張るような力が働き、引かれることに対しても耐える力がある堅固な姿勢である。
真横からの圧に対しても、弓歩(空手道の前屈立ちに近い立ち方をする中国武術における基本姿勢)と比べ力があるが、構造上ある程度のものとなる。斜め方向からの圧に対しても堅固とまではいえないが、紹法(実戦で有効な技)においては正側の原則により、自身は向きを修整し、敵と適正に相対して応ずるので問題とはしない。
敵を打ち、敵から打たれた際、さながら避雷針かのように、作用反作用でこちらに返ってくる衝撃を緩和し、その反発力をも敵の力に乗じて打ち返すことを可能とする、万全と考えられる架式(立ち方)である。
三体式を敵との攻防空間を作り出す応敵勢(構え)として用いるかは、伝人によって見解が異なる。構えであるという説と構えではないという説がよく対立するが、編集者の会派では構えではないという見解をとる。
勿論、手を前に差し向けることで間合いを測る、これにより敵に距離をとらせ自らの有利な攻防空間を作り出す、姿勢の変化、つまり誘敵勢によって敵の攻撃を誘うという着法(戦闘法)は、真伝(一門に伝承された実用的な格闘技術や型の解釈、練功法、知識等)を得た者にとっては常識である。
形意拳の構えは、無極勢(予備式)、即ち無構えである。ここから全てが始まる。
多く普及されている中国河北地方から伝えられた形意拳の開門式(起勢、開勢ともいう。門派を表す型の最初の動作)は、無極勢(宇宙の始まりであり天地も無く混沌とした状態)→太極勢(太極は無極から生じ陰陽の母である)→含一気勢(陰陽は本質的に異なるものではなく一気の二相の姿である)→両儀勢(太極の中に陰陽両儀がある)→三才勢(天地人の三才が生じる)という流れで行われる(開門式は各伝系により様々で、無極勢から直接、三才勢をとったり、太極勢から即に三才勢、あるいは太極勢を省略し、含一気勢→両義勢→三才勢という派などもある)。
三才から万物が生じる五行がわかれるのである。
開門式の動作からも、実はいくつかの用法が導き出され、けしてオープニングセレモニーの類ではない。また、この一連の動作自体が練功法ともなっている。
丹念に行われるのであれば、形意拳の源流である戴氏六合心意拳の丹田功と、同様の感覚と効果が得られるのである。
丹田功は優れた気功であると共に実際の運動(動功)であり、形意拳の力の運用法の根本原理を身体で顕すものであるが、気功(養生のための体操と気の操作で得られる功力)としては、会陰穴から背中側、頭頂部、胸部、臍下丹田へと気をまわして溜め、それを発するという小周天功という、気功の代表的なものと同様となっている。
具体的な立ち方であるが、下記の「站樁(たんとう:意味は杭のように立つことを)」の項目で解説している無極式から、足を斜め前方に半歩踏み出す。あるいは無極式から軸となる足を45度の角度で開き、そこから片足を半歩前方に踏み出す。
または平歩(空手道でいう自然立ち)から、左、右へと向きを変え転身して作ってもよい。主流のものは後ろの踵と前足の爪先が、一直線上に揃うように立つが、武術ではしばしば一本のレールに乗るような立ち方と、二本のレールに乗るかのような立ち方があり、三体式においても伝人によって両方がみられるが、べつに後者が間違えだというわけではない。
バランスの奪い合いとなる敵との交戦時において、力の一点集中を重視するか、安定性を重視するかで悩みどころがあり差異が生じたものと思われる。
歩幅は通常の架式であれば半歩から肩幅程度であり、低い架式となれば、一歩からそれ以上をとる。脛から足先までの長さ、あるいはそれに拳一つ分をとる程度という体格に合わせた歩幅の測り方もある。
三体式で立つ際に一番重要なことは、前脚に体重を掛けすぎない範囲で、後ろ脚を軸脚として立つことである。理想は、後ろ脚に7割から9割程度の体重をかけて実とし、前脚には3割りからそれ以下の力をかけ、虚とすることである。
下半身は、抱胯といい、ビキニラインの辺りの股関節の前部を緩ませて折って中腰となり、腰骨の上にスッと自然に上半身を乗せているかのような、力まない姿勢で立つこと。
それには下記の「站樁」の項目で述べる、渾元椿のときと同じく、提肛という肛門を体内に引き上げるようにして、さながら高い椅子に腰掛けるように立つ教えも重要である。
こうして形作られる三体式の腰背部の姿勢を、龍腰、虎背という。
上体については肩垂というが、余計な力を抜いて肩を下に落とし、顎を引いて首を真っ直ぐとし、身体は重力によって、下へと自然に沈んでいくが、頭頂部の百会穴のあたりから、上から紐で吊り下げられているような力を感じ、また重力に逆らって立つことにより生じる、身体を上へと押し上げていく、頭で物を支えるかのような相反する力を感じること。
夾というが両膝両足の間には必ず挟み込む力があること。膝は正面を向き股関節を内旋させて立つこと。このとき足指で地面をしっかり掴むようにする。これによって下肢から螺旋の強い力が生じる。
したがって頭頂部から地面までを軸に垂直に、仮に一本の重心線を引くと、その鉛直下に落ちて示される重心点の位置は自然と後ろ足のやや手前となる。
これは胯を折り、上体を前傾させることに比例して前方向に移動し、自己の重心位置も高くなっていく。
上体の前傾を強め、重心点をこれより前方に置くと、前への踏み込みが容易になるが、大腿四頭筋への相反性神経支配の影響が出やすく、踏み出した際にも大腿四頭筋に膝をロックする力がより掛かるため、歩法の霊活さ(軽快に自在に動けること)はやや低下する。基本的に重心の高さと安定性はトレードオフである。
そのため上体を極端に前傾させ過ぎない範囲で丁度良い立ち方を求める。
脚を挟み込むように立てと説く、夾字訣と、三体式で形作られる頭頂部、背中から腰背部の作りは重心沈下の要である。
初心者によくみられる間違いだが、上記の要訣に反して、立ち方は立身中正だと思い込み、そして本人は真っ直ぐ立っているつもりであるのだが、実は上体が後ろに仰け反た立ち方をとってしまって、虎が獲物に襲いかかるかのような力ある体勢を説く、虎背と虎抱頭の要求を満たせぬまま立ってしまい、重心の纏まりが弱い架式となっている例がよくある。
これでは敵に前方から推されて僅かな圧力を受けた程度のことで、容易に身体ごとすべて推し崩されてしまう。
そして構造的な強さが欠けバランスを保つには適正な姿勢ではないため、そのような体勢をもって動こうとしても、不安定で、重心の沈下も不足しているので、どこか軽く浮いたかのような拙い動作となってしまう。
これでは一応動けていたとしても、実戦での使用には全く耐えられないことになってしまうので、厳に気を付けて避けて欲しい。
手腕の作りに関しては、前足側と同じ方の手を、人差し指を軸に他の4指でボールを掴むかのように、わずかに指を曲げた手形の掌を作り、その掌心を前方正面に向ける撲面掌(形意掌)、あるいは八卦掌でいうところの竜爪掌(撲面掌の要領で小指側の掌根部を前方に向ける。親指と薬指、小指には敵を掴む意図が暗示され、人差し指と中指には敵の眼に指を刺しこむ意図が暗示されている)とし、肘を適度に落とし、腕は前方に伸ばしすぎず、曲げすぎず、緩やかな円を保つように伸ばし、胸の高さから首の高さに掌心を置き、眉間と手の虎口との間に、弾力のある糸が張ってあるかのように思い、同時に掌心にも仮想の前方からの圧力を感じる。視線は前方または虎口穴を見る。後ろ脚側の手も掌心を下方に向けた開手(陰掌)とし、下方からの仮想の圧力を抑えるかのように臍下ないし脇腹の横のあたりに置く。
大別すると掌心の向きにより、挺腕式と坐腕式にわけられる。
挺腕では橈骨手根関節を屈曲させず、掌心は下向きとなる。坐腕では掌心を前方に向ける形となる。この違いを比較検証することで、自己の体感する仮想の圧力も自ずと変化することが判るであろう。
形意拳に限らず武術の架式の大原則であるが、膝と肘、胯を揃え、手先、足先、顔の向きを揃わせることである。
これは後述する外三合の一例で、中国武術では鼻先、手先(武器の尖端)、足先の三点を一直線上に揃えることを、三尖照あるいは三尖相照と形容する。技のインパクトの際、この様な姿勢がとれているのであれば、合理的に力を集中発揮させ効果的に威力とする事が可能なのである。
上半身は、さながら槍を持って構えるかのように、上体をやや斜めにして、三尖照の要求を守り前方正面を向く。これが形意拳における正身である(斜中有正︰斜めに構えるようで正面に向かって仮想の敵と相対する)。
上体を斜めとする角度は概ね45度であるが、派によって正身が正面構えに近いものから、空手の半身の構えに近いものまでかなりの幅がある。これはおそらく各派の伝人ごとに得意とする戦闘法や用勁、体質等に様々な違いがあったことによると思われる。
簡単にいうと、三体式という姿勢は、順歩劈拳の落勢(日本武道でいう残心。打ち終わりの定式の姿勢)を現している。
以上が基本となる単重の三体式と称される立ち方である。これに対し脚に体重を五分五分にかける立ち方を、双重の三体式という。
双重は単重にも増して非常に堅固な架式となる。特に前方からの圧力に対しては、主に後ろ足に体重がかかる典型的な後屈姿勢である、単重の三体式よりも遥かに強い。
単重の三体式はゼロモーメントポイントがより、後ろ足の踵の方に位置するため、双重よりも歩行の際のトルクを効率的に得られるため動き易く、短勁(後述にある「三層道理」の項目で詳しく解説している)を打ち易いが、敵の猛烈な突進に対しては双重の架式よりも耐え難い。
双重は「将を敵とする(強い敵を相手に戦える)」それ相応の架式だといわれている(重心については、下記にある「站樁」の項目、発勁については「発勁」及び「三層道理」に詳しく解説しているので、そちらも参照のことを)。
先ず三体式では双重であってはならず、単重であることが要求されるが、三体式の道理が体得出来たらならば、単重であるか双重であるかという形式は、そのどちらでもよいとされている。
『形意拳術には道芸、武芸の分があり、三体式には単重、双重の別がある。武芸を練りしは双重である。このとき重心は両腿の間にある。全身で力を用い清濁をわけず、先天と後天のちがいを弁じない。』宋世栄『拳意述真』述宋世英先生言 三則より
《下の写真は左から、形意門の代表的な達人の一人である、孫禄堂の壮年時代に撮影した正身単重の三体式(挺腕)と、晩年の正身双重の三体式(坐碗)》
なお中国の郭雲深派形意拳の伝人である尚済師は、本来、開門式で打ち出す劈打は劈拳ではなく、鷹捉(劈掌)であると述べている。
鷹捉手とは、鷹がその鋭い爪で襲いかかり獲物を把握するかのように攻撃する、十二形拳鷹形のうちの一技である。
用法の一例としては、敵の腕や身体を掴み、あるいは敵に掴ませたのを拿法(逆技)で手首に関節技をかけ、敵の体勢を引き落としつつ、鑚拳(鑚掌)で突き上げ、続いて劈掌で劈打(上から叩き打つこと)し、敵を叩きつけて倒すという例があげられる。
これとは別に、鑽拳の後に掌打にて前方へ真っ直ぐに突く、推掌であるという説もあるが、このように用法には諸説があるものである。
参考までに紹介するが、開門式においての意念と気の操作としては、下丹田(無極勢)→中丹田(太極勢)→下丹田(含一気勢)→上丹田(両儀勢)とめぐらせながら、呼吸と共に体内の古い濁気を吐き、かわりに新鮮な気をとり入れる。
その気を引き上げ引き千切るかのように三才勢となり、虎口穴に視線を注ぐことで気の移動が成され、まるで焔のような覇気を纏った佇まいとなる。
このように気は意識によって導かれるものである。
東洋において事象の根源であるとされる『気』と称されるエネルギーについては、たとえ、その存在が、どのようなものであるかを理解出来ずとも、物理的に有ろうが無かろうが、運用側には全く支障のないのものである。
先人たちの教えに完全に一体化された概念であり、武術を学ぶことの上で便利な指標である。その利用は上達において重要であるといってよいだろう。
形意拳には古典的な姿勢な要求に、形意拳四像という教えがあり、これらは「鶏腿」「龍腰」「熊膀」「虎抱頭」(これに「猴相」「虎背」「鷹捉」「雷声」が追加された教えもある)と表現されている(戴氏六合心意拳では「虎背」ではなく、かわりに「亀背」とある)。
六合(身体の)という教えでも、「鶏腿」「龍身」「熊膀」「虎抱頭」「鷹爪」「雷声」の六つが挙げられている。他にも姿勢については八字訣など、夥しい数の教えもあるが、要訣(武術のコツを説いた教え。口頭で伝えられる口訣、歌で表した歌訣などある)は多数あり、詳しくは本記事の関連項目で紹介している『拳意述真』などの、いにしえの達人たちが記した著作にある古拳譜や市販の形意拳の技術書などを参考に調べて欲しい。とはいえ拳譜も後の伝人たちによって加筆修正されていたりと、様々記述内容が異るものがあり、その要訣の解釈さえもその理解度によって伝人ごとに異なることも稀では無いことには留意して欲しい。
ただし武術の技法を教科書的にドリル形式かのように教えるという発想は、近代の発想であるので、より新しい技術書ほど詳しい解説がなされているかもしれないが、外部に秘伝を隠すために、あえて詳細な要点をピン抜きをして隠して公開したり、表にはフェイクを交えて教授するという行為は、武術では本当によくあることであるので、自分の師との確りとした信頼関係を結んで得られた実伝の方を重く信頼し、外部からの知識は、その全てを鵜呑みにしてはならない。
書籍や動画で得たような解説で、この技の用法は必ずこのような使い方であるなどと決めてかからず、そのような解釈や見解もあるのだと、あくまで一例として参考とする程度が無難であろう。
武術の一つの動作から導き出される用法は柔軟で、様々である。武術は敵に対策をされないようになんでも隠したがるものである。
無論、本記事についても編集者は師から教授された技術と、実際に稽古することで身につけた知識、経験をもとに出来うる限りの表現で、わかりやすく包括的に書き表しているつもりだが、本記事が中国武術や形意拳のことを知りたいと望む万人に対して、全く不足なく理解される絶対的に正しい解説であるとは思ってはいない。
こういうと元も子もないが、他人が動画や文章で解説したものなどよりも、自身が実伝をもって教えを受けたことの方が遥かに優り、身につけられるものである。
本記事はあくまでも上達の為の豆知識。ここがよくわからないと思った時の参考書のように、ああ、なるほどなと確認する時に活用して欲しい。
姿勢の教えについては、形意拳のものよりも具体的でわかり易い、太極拳の要訣を利用して理解するのも有用である。
だが立身中正や円襠など解釈次第ではどうとでも受け取れ兼ねない抽象的な教えもあるが、実伝を伴うならば形意拳の要訣とも矛盾することはない。
太極拳の代表的な要訣については、太極拳の記事にてそれぞれ解説を行っている。
補足として中国武術には、三幹九節という身体を区分する基本的な教えがある。
一幹:腰を根幹とし外が腰、内が腹。中幹を脊髄とし外が脊髄、内は心。頭を末節とし外が頭で内は脳。
二幹:肩が根節、肘が中節、手が末節。
三幹:胯が根節、膝が中節、足が末節となる。
これら各部位を周身一体とさせ、気血を滞りなく運行させることによって、適正な勁力が発揮されると考えられている。
三幹九節は中国武術において重要な基本的知識であり、覚えておくと稽古の際にとても便利であろう。この三幹九節(身体全体)を協調させることで、強い力が発揮されると説くのが外三合の概念である。
また形意拳では東洋医学由来の四梢説という概念も古来は重視した。
筋(肝)の梢は指と爪、血(肝腎脾)の梢は髪の毛、肉(脾胃)の梢は舌、骨(腎)の梢は歯である。これら四梢を驚起させ身体の内部を協調させることで、強い勁が生まれると説いている。
この教えには精神を高揚させることで、火事場の馬鹿力的な強い力を得るのだという判り易い理解もある。
三体式と同様な意図の姿勢は他門派でも採用されており、詠春拳なら側身馬(戒備勢)、八極拳なら半馬式(四六式)、太極拳なら後座式などがあり、空手の後屈立ち、太気拳の半禅、意拳の丁八歩なども、三体式と同じ意味を持つ立ち方といってよい。
初心者の場合、厳密に三体式の諸々の要求を守って立とうとすると、普段、他のスポーツなどで鍛えていても、繰り返し立って慣れるまではハムストリングの辺りがとても苦しく、30秒、1分と保たない、架式自体をとることが不可能だという事態もよくあるのだが、まずは高架(高い姿勢)でも構わないので、師からの教えを受けながら、適正な架式で立てるように努力すべきである。
たとえ高架であっても、三体式の要訣で求められる要求に適っているのならば、重心が沈下し安定した堅固な架式を作り出すことが出来る。
よくいわれる樹木や杭のように立てという教えが、しっくり来ないなら、さながら道路工事で置かれるカラーコーンのように立つことである。自分はバランスが最適な状態で地面に置かれた物体であると思ってよい。ただし人体はカラーコーンとは違いバネがあり、自ら動くことが出来る物体であることも考慮する必要はある。
注意するが三体式站樁の際、ただ長時間立ったようにみせかけるだけなら、時折、足裏を動かして接地圧を逃したり、体重を少し前脚の方に移すなどして楽をすれば良いだけだが、これでは重心を保つための強さを得る鍛錬としては、殆ど意味が無いものである。あまりにも苦しくなったら素直に軸足をかえ、片脚を交互に休めつつ無理なく稽古が続けられるように立つのである。
これは形意拳の分派の意拳(大成拳)の話しとなるが、社会主義思想が強かった解放直後の頃の中国では、日々の決められた分の仕事が終わると暇となったが、当時は娯楽も少なく、とくに他にやることもなかったので、錬拳の時間は自然と長くなったというが、皆、適度にだらだらと稽古をしていたという。
站樁の際に壁の方を向いて熱心にやりながらも、時折、稽古仲間たちと雑談を楽しみながら稽古していたそうである。
それと長時間の練習を行うことで知られる本場タイのムエタイの選手たちにおいても、厳しく鍛えるときもあれば、リラックスして流すときもあり、敢えてだらだらと練習することで気力を保ち、集中するべきときは集中出来るようにし、同時にスタミナも養成するようである。
武術は根を詰めすぎても稽古は続かず、上達はあまり捗らないものである。生活に支障を来さない範囲で練習を継続して欲しい。
編集者の個人的な見解であるが、得てして達人は一見、練習嫌いかのように見える者も多いのだが、これは思うに自転車に乗ったことのない者に、僅かな練習で乗れる者も居れば、苦労してやっと乗れる者が居るかのようである。
コツをつかみ自転車に乗れるようになったのであれば、もう自在に漕いで目的地に行くことが出来るようになったのであるから、乗るための練習などもう不要となることと通じるかと思う。
武術では、要求される身体能力は自転車に乗ることよりもやや難しく、そのコツを得ることが人によっては困難である。
武術を稽古していてもコツである拳理を得られなければ、いつしか漫然とした型に嵌った考え方に囚われ、しだいに見栄えを良く型を行うために型の練習を重ねることが、武術の上達への限られた道であるかのように錯誤してしまいがちである。
そうした目的と手段が混同した有り様で居ることで、結果、武術本来の存在意義である護身の部分が朧げとなって顧みられなくなり、その実用性を高めていくという稽古本来の意味も廃れてしまい、やがて錯誤したまま稽古を続ける者も、型の上達が頭打ちになると、武術の稽古を続けることに自己表現やエクササイズ以上の意義を見い出せなくなって飽きてしまったら、別の面白そうなものに興味が移り、もう武術自体を辞めてしまうといった残念な例がよく見られがちである。
話を戻すが武術は動くものであるから站樁功など1分程度で良いと述べるような、極端な主張をする者に実力は無く、理解も浅い例が目立つ。そして、そのような主張は形意門の伝統的な教えではない。
例えば、形意拳の代表的な達人であった郭雲深の最後の弟子である王向斉は、3年もの長きの間、ただただ、站樁ばかりを稽古させられたという。
声高に楽をして上達出来ると主張する、未熟者の動きには安定感がなく、上体が後ろにのけぞり重心が浮いて見え、動作に協調性がないのがみてとれる例がとても多い。大成への躓きのもとであり絶対に惑わされないように。
古人いわく、静の中に動があり、動の中に静があるという。動静は完全にわかれているようでも、内に絶えない流転を含み、その流転によって動静は一体となり、武術の根本的な原理となっている。剛柔、虚実も同じである。
五行を、陰陽一体、動静一体、攻防一体、起発一体、虚実一体の五種と説く教えもある。
陰と陽は、西洋のプラスとマイナスのように完全に対立する概念とは異なるものである。
武林(中国武術の界隈)では古の教えを腐しながら、まるで自分が新たに発見したことかのように武術の原理を語り、独自の用語を造ったりしては、先人の教えを無理やり否定しようとする愚か者が時おり見られるのだが、彼らの先人の教えに対する理解は甚だ浅はかなものである。
誤解しているどころか、実は先人が説く教えと結局同じことを述べ、それが全く新しいものであるかのように主張して気づかない者たちすらいるほどである。
彼らのような者たちは師との信頼関係が作れなかった半端者が殆どであると断言出来る。
後進のためあえてキツイ言い方をするが、謙虚さとは程遠い愚劣な人間性ゆえ、習ってすぐ道場を破門されたような問題のある人物や、道場での人間関係が上手く行かず、老師(中国武術でいう先生のこと)から余されて、もう君は自分で道場を出した方が良いよ(^^)と放逐されたが、武歴だけはそれなりにあるような半端者が、売名の為にメディアに露出して書籍やビデオを出してしまい、最悪、高名な師匠筋の名を掲げて道場を開設し、果ては営利目的で武術の知識に欠ける者たち相手に、義務教育レベルの物理学などの知識をもって、しかもその理屈からも完全に間違った原理を語り、詐欺同然の出鱈目な内容の動画を作成して販売したり、ネットから広告収入を稼いでは、平気で他派や他武道の悪口を好んで貶めて、武術・格闘技全体へのヘイトを撒き散らして恥じないのである。
彼らが言葉を変えて手を変えて武術を利用し、あまつさえ古伝の教えを詐欺とまで言って罵るが相手にするものではない。
優秀な指導者は、先師たちやその教える武術に愛があり、弟子にはその魅力を余すこと無く語り、弟子の練度の向上に合わせて、明快かつわかりやすく、武術のコツを根気強く何度も繰り返し教え続け、確実な成果に導いていくものある。
反面、できない生徒をバカにしたり嗤うのは、明師とはかけ離れた半端者がよくすることである。最初からなんでも簡単に出来るようになる者など極限られた才能に恵まれた者だけのことである。
金行 劈拳
劈拳(へきけん:ピー・チュエン←カタカナは中国語の発音に似せた表記)は、斧や鉞をもって斬り下ろすような打法(劈打)をいうが、伝えられる派によって動作には多少の差異がみられる。
握った拳で打ち下ろす(劈捶)派もあれば、開いた手をもって振り下ろし、掌全体や掌根の最も硬い部分である小天星(豆状骨のあたり)で、手刀に近いかたちで打ちつける派もある。これで敵の顔面や胸部を打つ。
劈拳の勁道は正経十二経の始まりである、手太陰肺経を伝い放たれるようになっている。
肺経の雲門穴は中府穴から延び、中府穴の根は体内に潜り肺へと至り、 肺からは手陽明大腸経→中脘穴(臍上四寸にあり、十二正経の流注経路の循環の始まりと終わり、五行の気の交差点である経穴。中国武術では「気の弾薬庫」と呼ばれ、また形意拳の源流にあたる戴氏六合心意拳においても、古拳譜『形意拳基本行功秘法』において中丹田であると解説されている)→足厥陰肝経へと、五行穴の流注経路は循環している。
肺で練られた肺気は五行穴の気の流注経路を伝って全経絡を循環し、太陰経に属する脾(脾胃)の食物から得られる穀気と共に、各五行に区分される各臓腑を動かしていく力(後天の気)となる。
即ち肺気を充実させることは、身体を強健とすることの最初の要であり、これが形意拳が最初に劈拳から練習をはじめることの理論的な根拠となっている。
劈拳を構成する動作には鑽拳が含まれるが、これを起鑽(金鑽)という。母拳のなかのさらなる母拳であることから、先天の横(先天の黄:先天の鑚拳)とも称される。
陰陽五行説では土は金を生むからである。五行説のなかでも特に有力な説だといわれる土王説では、土こそが万物の王であり、土から万物が生じると説いている。
さらに土王説の一種である陰陽主運説でも、土は陰陽を共に兼ね備え、水金は陰に属し木火は陽に属するとされる。また黄とは方位においては中央のことである。
この先天の横を発射台として後天の横が打ち出され劈拳へと変化する。これが劈拳の起落(動作の最初と最後)である。
陰陽五行説によれば、金は水を生み、水は木を生み、木は火を生み、火は土を生み、土は金を生むというように木火土金水の5つの属性は、相生の関係にあり、また同時に金は木に打ち勝ち、水は火に打ち勝ち、木は土に打ち勝ち、火は金に打ち勝ち、土は水に打ち勝つというように相克の関係であると説くが、これは形意拳においても同じである。
例えば互いに五行拳を打ち合って稽古する対練套路(空手道でいう約束組手)を五行砲というが、この別名を「五行相生相剋対拳」といい、相手の崩拳に対して劈拳を返し、劈拳に対しては砲拳を返すというように、相手の攻撃に対して打ち勝つ技を次々と連環させて打ち合う練習法がある。
この五行砲の套路の運行線と攻防の軌跡で、五芒星と六芒星を描いて、形意五行陣法図の五行相生相剋を表す派すらある。この対打で用いられる切掌(掌心を下に向けた手刀で水平方向に斬り払うように打つこと)で、崩拳を斬り払いながら封手(敵の攻撃を封じ無効にしてしまうこと)し、退歩しながら防御する動作は、劈拳の変化とされ、横劈掌ともいい金克木の理合である。
拳術の攻防の中では五行は必ずしも相生相剋の関係を保つわけではないが、これは相侮といって五行の力関係が逆転し、本来、剋す筈のものに剋されてしまうという現象や、相乗といって相剋関係が行き過ぎてしまう現象が影響を及ぼすからだとされる。だが、五行説では五行の力関係を相互制約する、勝復という作用が必ず働くと説くので、拳術も相生と相剋の原則からは離れることはないという。
劈拳で肺の気、鑽拳で腎の気、崩拳で肝の気、砲拳で心の気、横拳で脾気の運気を行ない、東洋医学でいう五臓の気を養うとされる。五行拳の打法の中にも、経脈、経筋と経穴、下半身と上半身、正面と背中側というような対比で陰陽が顕され、五行の相生相剋が体現されている。
たとえば動作の中で、手脚や身体の経穴・経絡を擦り合わせ開勁(勁を引き出すこと)することを摩経(摩脛 :その一例の摩脛歩とは、膝を上げ足で、脛の内側を擦り合わせるように歩くことを指す)といい、型の中に左右非対称の動作がある場合は、それは利き腕利き足を考慮したものなどではなく、身体における陰陽から導き出された、自然な方向性や身体操作が反映されている。経絡・経穴を基準に動作することで最適な姿勢が導き出されるのである。
これらはけして迷信や宗教、オカルト雑誌に書かれている戯言のようなものではない。長い歴史と伝統に育まれた老荘思想等の東洋哲学や東洋医学を論拠とした理合である。
下の写真は『陳氏太極拳図説』から無極より太極が生ずる様を説明したイラストと、五行の相関関係を表した五行相生相克図である。
東洋の考え方は、古義(古の教えを守ろうとする派)は重視し、新派(古の教えよりも体育的な考えを重視する派)は軽んじ、まるで無いかのように語るものだが、形意拳を理解する上において非常に便利なものであるので、知っておくと先人が説いた教えとの断絶が防がれ、道に迷わないことであろう。
東洋思想とはいうが、現代人の思う思想や政治信条とは異なり、さながら西洋の科学のように理路整然と論理展開がなされ、これが東洋においての総ての物事の考え方の基本にあった。
水行 鑚拳
鑽拳(攢拳 さんけん:ズワァン・チュエン)は、正確な表現ではないが、よくボクシングでいうところのアッパーカット的な打法だといわれ、下方から陽拳(拳心上)を突き上げる打法の抄拳の一種である。
空手道でいう「裏拳顔面打ち」の要素も兼ね備えている。雷の如き速さで鑽出され、水のように柔らかで、敵の防御を下方より掻い潜らせて挿手する打法であるが、用法においては束身(身体を束ねると表現する力が整った姿勢)し、身体ごとこの鑽拳の強い姿勢であたり、敵の防御や技をカウンター的に叩き潰して抑え(截勁)、あるいは鑚拳を敵に敢えて受けさせ、次の技に移行する用法示例(用法の一例。型の分解)も多くみられる。突き出す方と反対側の拳を截拳といい、こちらの手も敵の攻撃を防御したり、掴みながら打つことなどに用いられる。
つまり鑚拳は形意拳の招法の第一の起点となる、攻防一体の技である。
形意拳で握拳を作る際(開いた手から拳を作ることを換掌式という)は、前腕を捻じり、手はまるで卵を掴んで割らないかのように螺旋状に小指側から柔らかく握り、強くは握りこまないことが基本である。
こうして捻じりあげて作られる手形を螺絲拳 (らしけん)という。拳の形状は、人差し指の第二関節が突出し、小指側より人差し指、親指側が高くなっていないとならない。これは武術で俗にいう、いわゆる空心拳の一種である。
(らしけん)という。拳の形状は、人差し指の第二関節が突出し、小指側より人差し指、親指側が高くなっていないとならない。これは武術で俗にいう、いわゆる空心拳の一種である。
インパクトの瞬間、強く握り込み、通臂(背中から手先に力が通ること)させた威力を貫通させるという説もあれば、自然と手形が潰れて拳となることで、人体の内部に対してさながら、ホローポイント弾のような重く、波状的な威力を与える説とがあるが、どちらも正解である。
ちなみに握拳を作る際、人差し指の第二関節を突出させて強く握り込む手形は鳳眼拳といい、空手道でいう中指の第二関節を突出させる、中高一本拳のような手形を、鶏の心臓の形状に見立てて鶏心拳という。
これらの手形は、人中穴、期門穴、乳根穴など経穴への点穴法(経絡・経穴に対する点打法)や肋間に打ち込んで胸骨の骨折を狙うのに用いるため、必然的にインパクト時に強く握り込むこととなる。
人体の硬い部分を狙う場合は硬く(劈拳なら小天星で打つ)、柔らかい部分を狙う場合は、柔らかいように打てば(推掌や劈拳なら掌全体を用いる)よいのである。
形意拳などの内家拳は、人体をさながら液体で満たされた皮袋のようなものであると考え、人体の内郭(内部)を受傷させるために、その打法には不思議と流体力学的な作用を働かせる工夫がなされている。
木行 崩拳
崩拳(蹦拳/ 弸拳 ほうけん:ポン・チュエン)は縦拳による直突きである。
さながら日本拳法の打突にも似ている。まるで箭弓で矢をいるような打法である。肝の気である肝火を用いる。崩拳によって肝臓を緩ませ、伸縮させることで肝の陽の気である肝火を炎上させるとされる。
古伝の練習方法では、肝臓の位置が人体の右よりであることから、左足が虚で右足が実となる、右拗歩(右逆突き:左脚を前での右拳打)と、左順歩(左順突き:左脚を前での左拳打)で打つ形でのみ行われ、左拗歩、右順歩で行われることはなかった。
拗歩崩拳を放つ際、通常の三体式よりも歩幅を詰めて足を引きつけて打つ打法があるが、このときの歩幅の狭められた高い姿勢の架式を、小三体式(高架の三体式をこう呼称する会派もある)ともいう。
崩拳の招法の一例としては、敵の打突に合わせて半歩踏み込みながら起鑽の要領で挿すように握拳を突き出し、敵の腕を袖絲勁(しゅうしけい:形意拳における、纏絲勁の一種。主に肘から上の前腕を捻じることで作られ、下肢からの力を導くものである)によって下方に巻き落とし、封手(摩擦力と柔らかさを生かした粘勁で捉える)し、その動作を崩拳の蓄勁(ちくけい:発勁の前段階。蓄が無ければ発することは出来ない)とし、そこから崩拳を打つ半歩崩拳(単臂崩拳)という、突きの途中の動作を受けとして用い、防御と攻撃を両立させた崩拳の代表的な技法や、安身砲対打の中で暗示されている敵の右の突きを、こちらは右手で内から外へと巻き込んで抑え(纏法という)、さらに左腕で敵の肘関節を下から打ちつけるように挟みとりながら敵の肘をサブミッション(拿法の一種で鉄歯法(分筋搓骨法)という)で捕らえつつ、敵の体勢を引き崩し、左脚で膝蹴りを行い最後にトドメとして拗歩右崩拳を打ち込む、穿天鉄歯崩拳などがある。
火行 炮拳
炮拳(礮拳/砲拳 ほうけん:パオ・チュエン)は縦拳による打拳と、これも正確な例えではないが、突き出す方とは反対側の手で、空手道でいうところの上段揚げ受けのように、前腕を回内させて内から外に片方の手を払い上げるような動作を伴う打法である。
拗歩炮拳を特に大砲にたとえて炮式ともいう。心の気である心火を用る。心火は肝火と同じく陽気に属し上へ上へと炎上する性質を持ち、打法の性質からか、敵の上段、顎を打ち貫くことに適している。
突き出す方と反対側の拳も防御だけではなく、抑えつけて打撃を放ったり、肩関節を捉える関節技にも活用出来る。砲拳は鑚拳と崩拳の変化技であり、身体を開き、そして閉じる力で猛烈な勢いをもって打ち出される。
これを開合といっている。さながら古代に攻城兵器として使われた弩砲でもって、弾丸の巨石を放つかのように打つ。
ちなみに奇門八字功の頂字拳には、白鶴亮翅のあと換歩し、素早く軸足をスイッチして変え炮拳を放つが、この技の名を反身砲という。
白鶴亮翅は、両翼に広がり展開した軍団が敵を囲み、一気に撃滅させる兵法の様に喩えた技であるが、このあと繰り出される炮拳は、さながらドドメを刺すため敵を強襲する砲撃部隊の如きものであろう。
具体的な用法の一例だが、例えば敵が右上段廻し蹴りを放ったとすると、我は右斜めに右足を編歩(斜め外側前方へのサイドステップのこと)して踏み込み、蹴りのインパクトゾーンを避けつつ、自分の右掌で蹴りの脛を拍打(手のひらで叩くこと)し、その補助に左腕で起鑚のように(空手の内受けの要領に近い)敵の顔面に向けて挿して、蹴りを我の両の手で以って受ける(こう両手で受けると、もしサイドステップせずにまともに蹴られたとしても打たれ負けず防御が出来る)。続いて敵の双足間に向け、我の左足を踏み込み、三角歩(歩法については下記の項目を参照のこと)を行いつつ、挿し込んだ左起鑚を翻して空手の上揚げ受けのような形とし、敵の蹴り足を払い落とし、右掌を握り拳と変え、縦拳を敵の顔面に向けて放ち震脚して突き貫くなどがある。
土行 横拳
横拳(おうけん:ファン・チェン)は鑽拳を、内から外へ半円をえがいて弾くように、一気に打ち払う打法である。この表現も適切とはいえないが、詳細は実伝をもって確かめてもらいたい。
空手道でいうところの内受けのように、相手の打拳を内から外へ弾いて受けるように用いたり、相手の側面に打ち付けたり、あるいは手のひら側を下に向けた陰拳の状態で、真っ直ぐ錐で刺すかのように突き、インパクトの瞬間にこれを鋭く回外させ捻りこみながら陽拳とし、空手道の下突きのように打ち貫く。
技の示例としては、三才歩、反三才歩で斜めから入り、一方の腕で相手の腕を抑え、肝臓、脾臓、顔面などを打ち貫く。
なぜか形意拳家のなかに横拳を軽視する者がよく見られるが、打法の単純さから単なる受け技のように思われるのかもしれない。だが「十二横捶」という、横拳の変化を学ぶ型を持つ派さえあり、古来も重要であったことが伺える。横拳は五行において土行であり、形意拳の技の起点となるものの一つと位置づけられている。
これら五行拳を握拳で行うものを五拳母といい、開手の螺絲掌で行うものを五掌母という。
五掌母は主に後述する暗勁の練習の際に行われることが多い。この際は柔らかな動作で慢練で練っていく。使用する際は八卦掌の穿掌のような使い方や掌打として用いる。
五行拳の練拳は劈拳から相生説の順番に、鑚拳→崩拳→炮拳→横拳と練られることが多いが、劈拳→崩拳→鑚拳→炮拳→横拳というやり方もベーシックである。後者は金行劈拳で肺気を補うことで弱まる、木行の肝火を崩拳で盛んとし、次に水行鑚拳で腎陽の気をという具合に気を補っていく。いずれも東洋思想的根拠に基づいたものである。
余談であるが、よく世間に流布された門外の人間が語る形意拳の達人の逸話に、見様見真似の自己流や不器用で愚鈍さゆえに、崩拳だけを繰り返して、功夫(ゴンフー/カンフー:武術的実力のこと。中国武術の総称の意味もある)をつけて師に認められ達人になったというストーリーが語られるが、これはあくまでも面白おかしく作話された単なる民間の俗説に過ぎない。
最初に学ぶ劈拳すら難しくて覚えられないような者は、三体式で立つこと自体出来ない筈である。
漫画の某『拳児』で語られているような荒唐無稽の創り話をそのまま真に受けないように。そのような俗説の類いは拳法の奥義は突き技であると思い込んだような、語った者の願望や得手不得手、好みが反映されたものに過ぎない。このような俗説は形意門の伝統的な教えからは乖離し中正を失っており、偏向し過ぎた異端である。形意拳はなにより中庸の道を重んずる。
<『でき得ないことを信じるということは、本当にでき得る恐るべき力に対してわかってないということもいえる。これはマジックまがいの表演を見て信じる人は、本物の威力を見て、マジックと思うのに似ている。
例えば、ある中国拳法の名人が人を打った。ところが打たれた人はフッ飛ばされて木の枝にひっかかって死んだとか、人の脳天を一撃したところ打たれた人は目玉がとんで出て死んだとか、鷹爪拳で筋肉をひきちぎった、というストーリーがあるが、グリズリーやコダックベア(アメリカ大熊)でもあるまいし、人間の力でできることとできないことがあるのである。
秘術というものは、そうした動物の持つ大蛮力の限界にせまるものではなく、全く違った意味において人間の持つ能力の限界を超えていくものであり、これが秘術なのである。
正しく功夫を学ぶ人は、あくまでその現実を重んじ、架空の話や能力を聞いてまどわされることのない真剣な学習精神から、常識では不可能と思われていたことも次第に習得して、できるようになるのであって、これは夢を見ないで現実を尊ぶ心から生まれてくるものなのである。』龍清剛 著『中国拳法 秘伝必殺 鉄砂掌』より
十二形拳
十二形拳 概要
形意拳には五行拳の応用であり高級技法とされる、十二形拳という動物の意念と形態を模した各種の象形拳がある。
それらは、龍形拳、虎形拳、鶏形拳、猴形拳、馬形拳、燕形拳、 蛇形拳、鷂形拳、𩿡形拳(「鳥台」形拳)、鷹形拳、熊形拳、鼈形拳の12種に分類される。
十二形拳は例えば、馬形ならば両拳で打つ双馬蹄手、片手で打つ馬蹄十字崩拳など、複数の様々に異なった動作を含むが、それぞれの象形拳に分類されている。単式で練るだけでなく、例えば馬形拳の套路というように、それぞれの十二形にカテゴライズされた様々な技を繋げて打つ連環套路をもっている派もある。
他にも鶏形の総合套路である四把捶(鶏形四把捶)、十二形拳の総合套路には全形を連環させた雑式捶(形意十二形合一拳)。対練套路には対打である安身砲(形意十二形大用対拳)がある。
五行拳の各種単式套路、五行連環拳や八式拳のような套路のなかにも十二形拳の動作は含まれている(狸猫倒上樹回身式(龍形回身式)、虎形回身式など)。
また古伝では順歩劈拳を鷹形式といい、鷹形拳であるとし、拗歩右崩拳を黒虎出洞と虎形拳とみなし、順歩左崩拳を蟄龍出現と龍形拳とみなすというように、五行拳そのものでさえ十二形拳に分類させることが出来る。
これは形意拳の原型であった心意拳が、手の形、歩法、あらゆる動作に十大形(形意拳の十二形拳にあたる象形拳)にあげられる動物をあてはめ原則としたことの名残りだと思われる。
十二形拳の套路は、後世に八式拳や雑式捶などの套路から個別に技を抜き出されて創られたという説もあるが、先師たちの教えから、古来から重要とされていたのは間違いはないであろう。
ひとつ特に注意がしたいが、虎形拳の虎撲手(双掌での劈打のこと。いわゆる敵の気血のめぐりに害を与える打法である打血法の一種にあたる)で、相手の胸を強打することは、後遺症や心臓震盪の危険があるため用法対打でも絶対に行ってはならない。
劈拳・劈掌についても対錬では肩口を打つこと。胸部を打つ場合は、せいぜい太極拳の双按のように推す程度か寸止めに必ず留めて欲しい。軽く打ったつもりでもコントロールが効かず思わず威力が出てしまうことがある。
そして点穴法(経絡・経穴を狙って受傷させる打法。用いる手形、攻撃方法、角度などのコツがある。摩擦を用いる場合もある)で有効であるように、相手の重心を浮かし、上体を仰け反らせた状態にさせて打つと、この場合は死穴となる乳根穴により一層効かせられることになり危険度はさらに高まってしまう。
また推手などの対錬中に無知な者が、相手の胸部を無遠慮に打っての事故がありがちであるので厳重に注意して欲しい。
武術を稽古するなかで、胸部への打撃による数秒の心停止や不整脈などを経験した者も多く居るだろうが、けして甘くみてはならない。
医学的にも致命的な不整脈は、胸部への打撃のタイミング次第では容易に起こり得るといわれ、慎重を期すべきである。1分程度、脈拍がとぶことは問題とはされないが、それが2分、3分ともなるとしだいに意識はなくなり、 やがて呼吸も完全に停止する。こうなると医師が心臓マッサージや人工呼吸で救命にあたっても、生還率は7割にも満たないのである。
十二形拳 概要その2 技法内容
龍形拳
伝説上の動物、龍を模した象形拳である。龍の性質は火に属し、これを練ることで肝火と心火を盛んとし、形意拳で火焼身式と例えられる強い心身を作り上げるといわれる。
龍形拳として練られる技法は二つあり、先ずは蹴りが伴わないもので、軸足を蓋步し順歩で起鑚を放ち、後ろ足もつま先を外に向けた形で踏み込み、同時に拗歩鷹捉(劈掌)を放ち、そこから身を沈め低い架式の坐盤式となり、定式は脚をクロスさせて、鷹捉を低く打ち込んだ形となる。この姿勢を龍形式という。この要領でジャンプしてその場で交互に打つものもある。
二つ目は崩拳や連環拳の套路にある狸猫倒上樹(龍形回身式)とほぼ同じ要領のものである。三体式から踏み込み、あるいは換歩して軸足を変えながら、順歩で起鑚を放ち、続けて順歩踩脚で敵の腹部や膝を蹴り貫く、そのまま敵を掴んで引き崩し、敵の後頭部や背中の死穴である霊台穴を鷹捉で叩き打ちつつ、地面に敵の身体を打ち付けて倒す。この形を山猫が樹上から落ちて死んだ姿に喩え、狸猫倒上樹と称している。
注:文章では技法内容は解説しきれないので十二形拳の詳細な姿は、関連動画を参照のこと。
虎形拳
トラが獲物を撲り倒して喰らう様を模した象形拳である。技法には両掌を打ちつける虎撲。上方に両掌を打ち上げる虎托。鑚掌で打つ虎攔。両掌の手指を下方に向け、掌根部を向き合わせて下腹部などを打つ虎抱。拳心を上に向けて敵の拳を挟みとりながら突く虎截。拗歩右崩拳で突く虎撑など多数の技がある。奇門八字功の斬字拳にある握拳を用いず全て開手で虎撲を行う虎撲把や、同じく斬字拳にある洪家拳の胡蝶掌のように、両手掌根部を向き合わせ、手指を外側に分開させて打つ、頭拳も虎形拳の一種と思われる。
虎形の代表的な技法である虎僕手(虎僕子)は、先ず三体式から左掌の上に右掌を重ねクロスさせ、左方外側斜め45度に編歩(歩法については下記の項目で解説している)して進むと同時に、両手を翻して、両の拳心を上とする陽拳として握り込み、下腹部の前に合わせるように両陽拳を引きつけ、右足も左足の踵側に引きつけ、つま先を立てるように地に足を付ける、堤空歩(縮歩)となる。
この形を堤歩握拳収腰式といい、別名を虎形勢と称する。ちなみに劈拳の套路で使われる虎形回身式は、握拳収腰式を経て向きを変えるためその名で呼ばれている。
次はこの虎形勢から右に編歩しつつ両陽拳を起鑚の要領で突き上げ、その拳を翻して開掌とし、跟歩して震脚しつつ両掌打を打ち下ろす。
左右にジグザグに進みながら虎撲を数回繰り返したら、風擺荷葉回身式という堤空歩から後ろ足を軸に、くるりと風に巻き上げられる木の葉のように後方に向きを変える転身動作を行い、そのまま虎撲を続けるか、静かに封掌して収式(型の終わりに行う動作)を行い套路を終える。
猴形拳
サルの仔の霊活な姿を模した象形拳である。文章で動作の解説は困難で断念する。各自、動画等で確認のこと。
馬刑拳
ウマが馬柵を勢いよく飛び越えるときの蹄の強さを模した象形拳である。
空手の正拳突きのようなかたちのインパクトで突く、片手突きの馬蹄十字崩拳と、両拳で突く両手突きである双馬蹄手が代表的な技である。
用法は、片手、或いは両腕で相手の攻撃を抑えてさえぎり、片拳ないし両拳で敵を打つ。敵の腕に上から自分の前腕をぶつけ、敵の腕を封じつつ、腕をぶつけた反動を用いて、敵に間髪入れず突きを放つなどの応用も効く。套路では踩腿と組み合わされる技法もある。
拳の軌道は手首を効かせて上から下へと、スナッピーに突くやりかたもあれば、ボクシングのストレートように直線的に、あるいはフックのように曲打もする。意拳・太気拳においてもよく使われるポピュラーな打法でもある。相手の両こめかみを同時に挟み打つものを牛角捶と編集者のところでは呼んでいた。鑽拳と同じくこちらから仕掛けるとき重宝する技である。
鼈形拳
ワニが水中で力強く泳ぐかのように、あるいはアメンボが、水面を滑らかにスイスイと移動するかのように、ジグザグに軽快に進みながら技を繰り出す。別名を鼈雲手(雲抜)という。
名が示すとおり、見た目や用法は太極拳の雲手の要領に似ている。敵の攻撃を両掌で円を描くように次々と廻し受けて捌きつつ、体勢の崩れた敵に切掌でもって打ち込む。この時、人指と親指を伸ばし、他の3指を指の第二間接で折り曲げた、八字掌とすると、捌く際に敵の袖口に曲げた指を引っ掛け易く、また勁力が纏まり易い。腎気を盛んとする。鮀形拳と表記する派もある。
鶏形拳
鶏の腿の力強さとその闘争心を模した象形拳である。総合套路は鶏形四把捶という。
敵の攻撃を拍打して逸らし、崩拳で期門穴から胸元を拳で擦りつけながら顎を突き上げ、体勢がのけぞって重心が浮いた敵に、再び崩拳を打ち込んで倒す金鶏食米。独立式となりながら目や首に穿掌を放つ金鶏独立。肘打ちや靠撃として使える金鶏上架、金鶏報暁などがある。
燕形拳
燕が水面に向かって急降下し、急上昇する勢いに倣ったのが、燕形の燕子抄水である。動作としては潜り込むように低くなりそこから前方に跳躍して裏拳で打つ。
𩿡形拳(「鳥台」形拳)
チョウゲンボウが獲物を捉える様を模した象形拳である。技法は白鶴亮翅とその応用技となる。漢字は鳥へんを魚へんに変えて「魚台」としている派もある。
鷹形拳
タカが鋭い爪を以って獲物を捉える様を模した象形拳である。鷹捉手という。
要領と定式は河北派形意拳の第一路、五行拳の劈拳とほぼ変わらない。派によっては動作に白鶴亮翅が伴い、劈拳とは手形や姿勢に変化がある場合がある。劈拳と比べると、より掴んで攻撃する意味合いがあるという。河北地方の形意拳では熊形と合一されて練習される例も見られる。
鷂形拳
ハイタカが林の中を巧みに飛行する様を模した象形拳である。技法には鷂子入林などがある。ちなみに鷂子入林の過渡式は、山西派形意拳では三体式と並んで看板的な姿勢である堤水式と同様な姿をとる。
蛇形拳
ヘビが素早く草原を進み、瞬時に鎌首をもたげ地から跳び上がって攻撃してくる様を模した象形拳である。
熊形拳
弾肘頭など横に向いて肘を打ち付ける肘打ちや、アッパーカットのように片拳を突き上げる技、龍形拳の要領とほぼ変わらない動作で深く前傾して敵を抑えつける技などがある。
十二形拳は代表的な技は各派で概ね共通ではあるが、例えば山西派には十二形拳だけで40種以上もの技法があるといわれ、各派で伝えられた技法内容にはかなりの差異があり様々な技法が伝わっている。
套路
套路については百種類以上もの膨大な数の套路を持つことで知られる蔡李佛家拳ほどではないが、各派で多数の型が伝えられている。
最古の套路は四把捶である、いや八字功だ、老三拳と呼ばれる、劈掌、劈拳(劈捶)、崩拳 (別説 1:劈、鑚、崩 / 別説 2 : 劈、崩、砲)だなどといわれているが、現代では、もはや真偽のところは不明である。
各派で比較的差異が少ない技法は、五行拳と十二形拳の代表的な技だけである。なので同名の套路であっても技法内容は歴代の伝人系統ごとに異なっている。
下に紹介したものはあくまでも参考であり、この他にも形意門の発展と共に、いくつもの套路が創られていったので、他所のは自分のところとは動きが異なっている、あの套路が伝わっていないから他派には全伝がないなどと、けして浅はかにも思わぬように。
形意拳(心意拳)の套路は原初はたったの三つしか無かったとも伝えられている。
また形意拳には套路にはない過去の伝人が得意とした招法も口伝的に伝わっており、全ての技法が套路の中にコンプリートされているわけではない。
ちなみに套路は身体を練り、武術に使える体力と身体能力の向上も強く意図している。武術を実用とするつもりであるならば、いずれ套路の分解用法は知る必要はあるが、初心のうちはあれこれ疑問に思わず、一通り習熟を見るまでひたすら熱心に稽古することである。
形意拳の秘伝套路と呼ばれる八字功については、原初から存在していたのか、郭雲深が創ったものだったかは諸説あり不明で、よくいわれていた説では郭から伝えられた李存義が制定したものだといわれていたが、近年になって山西派にも八字功と呼ばれる套路があることが判明し、その俗説は間違いであったことが判明している。
先に奇門八字功(硬八字功)があり、後に正門八字功(軟八字功)が創られ、正奇硬軟の2種に別けられたものと思われる。八字功は、火焼身式(排打功の一種)という、まるで我が身が燃え盛る炎であるかのように、全身に気が滾った状態を得るための練功型であると同時に、他の型と比較して、より形意拳の原型である、心意拳の形態を多く残しているかのような印象の技法群でもある。
大劈(大きく手刀で振り落とす)である斬劈手など、他の套路では殆どみられない技が多数ある。具体的な技法構成については、中国や台湾の武術関連のインターネットサイトを調べて参照して欲しい。
■単練套路
五行拳、進退連環拳(五行連環拳、形意連環拳)、十二形拳(鶏形四把捶を含む)、八式拳(八勢、意形八式拳、形意八式拳)、雑式捶、出洞入洞、八字功、出入洞など。
■対練套路(約束組手)
三花砲対打、五行砲対打(相生相剋対拳)、安身砲対打、双手砲対打など。
腿法(蹴り)
蹴り技については練功法として旋風脚など、様々な技が練習されるが、クラッシックな套路の中に高く蹴り上げるようなものや、圏脚(廻し蹴り)のような蹴り技は見られないが、山西派の一部で多彩な蹴り技を得意とする武術の鴛鴦脚との交流により、「形意鴛鴦脚」という套路をもつ派も存在し、また現代では割と高く蹴り上げる場合もみられ例外はある。
形意拳のメインとしている蹴り、半円を描くように膝を上げ、踵で相手の腹部や膝関節を正面から強く踏みつける、踩腿(さいたい)と呼称する、鷹爪翻子拳の低踩腿、八極拳の斧刃脚と同様な蹴り技である。
古の形意拳では「踼(踼脚:蹴り上げ)を忌み(嫌い)、踩(踏みつけ)は宜しい」といった。
この蹴りは非常に何気ない動作でありながら反面威力が大きく避けられ難い。低リスク、ハイリターンである。
だがこのような膝を正面から踏み砕く関節蹴りは、殆どの格闘競技においても簡単に選手生命を奪ってしてしまう、忌むべき悪質な技だと認識されており、ルール上は禁止されているのが通常である。
許可されている極一部のプロのMMAの試合においても、やりすぎれば白い目でみられ、禁止とすべきだという非難が、たびたび起こって収まらないほどである。
脛を鍛え上げる必要もないので使いやすく、威力もカーフキック(足元、脹脛を狙った下段廻し蹴り。芦原空手では転ばす時によく使われる)どころではない。
であるので軽めの組手でも、絶対に用いてはならない。練習では太腿を軽く踏むストッピングくらいで止める方が良い。
膝の正面に対しては軽く蹴ったつもりでも、相手に深刻な傷害を与える結果になりやすい。前の膝を内側に入れることで関節蹴りに対して、強い架式を作るのだという主張もあるが、動きの中で蹴られては到底無事では済まないこととなる。
安身砲などの対練の例では、相手が蹴ってきたら前足を引いて軸足を入れ替え、もし蹴られたとしても、インパクトの際の衝撃を逃がせるような対処をしている。
前足が虚で後ろ足が実であれば、このように対処して虚実転換して逃がれることが出来る。つまり逆にいうと前屈で立つ、踏み込むときを狙ってさりげなく繰り出すと、敵は対処が困難となるということだ。
八卦掌の用語となるが、歩を進める動作自体にも暗腿といって、蹴りが暗示されている。
接近しながらさり気なく敵の脛などを下段を蹴って、ガリガリと踏んでやるのだが、靴を履いた足でこれをやられると被害は洒落にならないものがある。ちなみに蹴るぞ!と勢いよく攻撃の気配を強く出しなから蹴ると、敵に察知されて回避されてしまう。
形意拳に高い蹴り技がみられないのは、利があってそうすると訊くが、寒い地方で発展した武術なので、一般的に人々は皮の厚いブーツを履いており、それで下段を蹴れば、たちまち勝負がついたからだという説すらある。
独立勢(堤空式など)といって、片足立ちとなって膝を抱え上げる姿勢は膝蹴りを暗示している。
套路の中で下勢(仆腿式)から、独立勢に移行するような動作には、身を沈め敵を地に引き倒し、あるいは掬い上げ、これを後方に逃れようとする敵に向かって跳躍し、膝蹴りを叩きつける用法が一例としてあげられる。
内家三拳の代表的な達人であった孫禄堂は、まるでサルの如く身が軽く、このような技を得意とし「活猴(かつこう:活きザル)」と渾名されていた。
七拳
形意拳は全身が拳であると考える。七拳といって拳足だけでなく手、肘、足、膝、胯、肩、頭といった身体のすべて、末節(手足の末端)、中節(肘膝)、根節(肩背臀部)を技撃に用いる。つまり全身を武器とする。
一例としては靠撃(こくげき・震靠法・膀法)といって、肩や背中を敵に叩きつける打法もある。
武術の打撃力は、攻撃に用いる部位が手→肘→肩と、体幹部に近くなるにつれて、その威力は飛躍的に増大していく。
拳と比べて当てる面積が広くなるので、威力は低下し効かせることが出来ないなどという、愚かな主張は、真の靠撃を一度でも喰らってみると、たちまち霧散する妄想であったことが即わかることであろう。ちなみに編集者は師から組手中に靠撃を受けて肋骨を3本も折られている。
世間でよく誤解されるが、靠撃は助走を用いて勢いをつけて行うタックルの類の技ではない。敵の攻撃を防御してから、いきなりそのカタチで放つような、漫画や格闘ゲームで見られる使い方などはしない。踏み込んで近距離での攻防となった際に、敵の突きや、あるいは防御しようと構える敵の手腕に対して、こちらは換歩震脚しながら自らの前腕で上から強く叩き打って落とすなり、纏法で敵の手腕を巻きとりながら排除し、それによって敵の体勢が崩れ無防備となったところに、すかさず一撃を与える技法である。
それと古流武術の愛好者が、競技格闘技の愛好者にやたらといいたがってしまう、目や金的への急所攻撃であるが、実際には彼らが述べるほど簡単なことではない。
金的への打法であるが、戦闘中に敵の股間を蹴りにいったところで、確実にダメージを与えることは実に難しい。
相手は木偶ではないのだから無論動き、防御もされてしまうが、万全な体勢をとった敵、伝統的な空手の組手構えや、中国武術の三体式のような架式をとった敵の股間を、離れた間合いから踼脚で蹴り上げたところで、敵の脚と腰の作りによって自然と阻まれ、的確に睾丸に命中させることは容易くはない。
それよりも金的を狙うのであるならば、敵と極めて近接した際に、蛇形拳や鶏形拳の腕を振り上げる動作をもって、敵の股間に腕を挿し込み、搬打(ばんだ:前腕を打ちつけること)や空手道でいう背刀や握拳の拳眼側を用いて、睾丸を下方から打ち上げ(崩捶:心意拳系では、挑領(挑掌)と呼称する)叩き潰す、あるいは振り上げた手で把握して握り潰す(撩陰掌)の方が確実性が高い。
たとえば鶏形拳の一技である、鶏挑領(金鶏報暁)は、肩で叩きつける靠撃と崩捶を連環させる強力な技である。
次に眼窩への攻撃であるが、目は離れた間合いからの顔面への突きの際、狙わずとも自然と当ててしまうことも多いが、あえて狙う場合は空手の一本拳にあたる鳳眼拳や鶏心拳で突く、鶏形拳の金鶏独立で打つ要領で裸眼手(指の力を抜いて五指を適度に開いて打つ穿掌(貫手)。ジークンドーの貫手、ビルジーでも用いられる手形)や、切掌(手刀で水平に切り払う打法)で軽く打ち点撃を行う。
眼窩は打たれると、容易に網膜剥離や眼底骨折を起こしやすいが、眼球自体は硬く潰して失明させてしまうことは難しい。
だが招法を以て敵の頭部を据物のように固定して押さえつけ、眼窩に鑚掌の螺絲掌(掌を上に向け開手した手形の穿掌。螺絲掌は螺旋をともなった開手の総称である。穿掌として目を攻撃したり暗勁による内臓や脳を受傷させる打気・打血法に使われる)で強く挿し込み、それでスプーンで抉り出すかのように眼球を抉り出して害する技法もある。
掌を下に向けた貫手の状態では眼窩を抉ろうとして強く挿しても、眼窩の圧力や眼球の硬さに負けて指の間接が曲がってしまい容易ではないが、逆向きの貫手であれば、壁などを押して実験してもらえたら分かるだろうが、構造的にこの手形は強く、眼窩の奥深くまで指をめり込ませることが可能であり、この手形を用いての攻撃は八卦掌でもよくみられるものでもある。また倒した敵の後頭部を踏みつければ、眼球はたちまち飛び出すともいう。
多少残酷な描写となってしまったが、武術とは最悪、敵を殺害する技術となるゆえ、仕方ないものと思って欲しい。
しかし、これらの技法も攻防技術あってのことであり、盲目的に急所攻撃の有効性を高らかに謳うことは、武術でよくある安易な誇大宣伝の一種である。
実戦では相手もまた急所攻撃をやってくるのでお互い様なのである。
ちなみに私の古くからの友人で、かつて大阪の不良であった者は、ニコニコと微笑みながら敵意を隠して近づき、こんにちはと言いながらさり気なく目に指を突き込み、やはり人を刺す時も笑顔で無言で挨拶をするようであった。組織から命を狙われると海外に逃げて行方をくらまして難を逃れている。プロはこんな感じである。
兵器(武器術)
武器術についてだが、形意拳は槍術を元に創られたとされるため、槍を最重要視している。大槍から穂先を外した大杆子と呼ばれる、長さが3メートル以上ある白蝋棍(ハクロウコン)の一種は、練功器具としてよく用いられる。
槍の他にも、春秋大刀 、棍
、棍 、剣
、剣 、刀
、刀 、三節棍
、三節棍 、九節鞭
、九節鞭 、暗器
、暗器 (隠し武器)などの各種兵器の操法が伝えられている。
(隠し武器)などの各種兵器の操法が伝えられている。
五行刀など、武器においての五行拳のような套路を制定した派もあるが、しかし孫禄堂の書いた形意門の重要な資料である『拳意述真』によると、古の形意門では武器術の練習は殆ど行われておらず、門派独自の器械套路(武器の型)もなかったようだ。
武器の型は形意門の発展とともに各派の先人たちが編み出し独自に整備していったものである。
だが形意門の先人には、李存義など刀術の達人と誉れ高い者たちもいるが、それは中国武術では「兵器は手の延長」といい、拳法が武器術の基礎訓練となるからである。
であるので拳法家が武器術に優れているのは、いたって当然のことである。たとえば少林拳で有名な嵩山少林寺さえも、拳術よりも先に棍術の方が先に知られ誉め讃えられていた。
それと中国武術ではよく武器の尖端からでも発勁が出来るというが、それは武術が教える姿勢と諸動作が、適切な力を手先にだけではなく、手に持った武器の先にも、下肢から作られた構造的に強い力を伝えることが出来るようになっているからである。
形意拳の伝説的な達人の一人である尚雲祥には、構えた相手の槍に、自らの槍の穂先をぶつけただけで、相手は強い衝撃を受け、たまらず槍を落としてしまったという逸話がある。
たまに現代において、槍や剣の稽古など無意味だと、素人考えな物言いをする者がみられるが、武器術を稽古することによって、纏絲勁など拳理への理解がより深まる練功法となり、拳法の方にも良いフィールド・バックがあるから稽古するのである。
余談であるが日本の古流剣術において、剣は秘伝とはしないが、槍術を一子相伝の秘伝とする流派があるが、かつての戦場でのメインウェポンであった槍は、単純であるようで技法には剣以上に奥深いものがあり、容易に刀剣を凌ぐ殺傷力が得られる兵器である。
現代に剣術流派は数多く残っているが、槍術はその多くが失われているのは、そのような理由からなのかもしれない。
中国武術において実用に際して言及を避けることが出来ない暗器(隠し武器)についてだが、投擲する物が非常に有効性が高い。
たとえばダーティーなものだが、ガラスの破片や剃刀の刃、刃物を細かく砕いた破片等に、トリカブトの毒を塗って卵の殻に詰め、蝋で固めた「飛蝗石」は、投げつけて命中すれば敵の身体に内容物で傷つけることで殺傷させることが可能だが、一度使用すれば砕けてしまうものなので、敵に拾われて投げ返される恐れはない。
竹筒などの円筒状の筒に、砂鉄、塩、砂利、唐辛子粉を仕込んで筒先を紙で封をした、「迷魂砂」は、敵の顔面に向けて振り放つことで、その場で即、敵の視力を奪うことが可能である。砂鉄が敵の角膜に突き刺ささって錆びることで長期的に視力を損なわせることも可能である(現代では砂鉄が角膜に入ると、眼科で鉄錆が広がった部分を削り取るため、失明させるまでには至らない)。
また筒は投石器としても使え、小石を高い威力で投げ放つことが出来る。
パチンコ玉を指で弾いて眼を狙う「如意珠」は、戦闘中手の中に珠を隠しておけば敵には気づかれ難い。
ちなみに鷹爪翻子拳には、套路の中に地面の土石を掬って敵の眼に投げつける意味の技法があるのだが、投石も非常に有効である。
戦国期の日本においても、甲斐武田軍には投石が得意な武将が幾人もいたほどである。この時代の童は、生き残る術として親から投石で人を殺す方法を学んだという。
現代の日本においては、路上で見あたらなくなった石の代わりに缶コーヒーが携帯しやすい。これが護身具だとは誰も気づかないことであろう。
武林よもやま話
この項目は多分に余談的な記事となるが、中国武術の界隈の憂うべき現状と豆知識を解説する。
不要に思う者には、一読したら読み飛ばすことを勧めるが、しかし読んで不快に思うのであるならば、できれば自身の行いをまず反省され、武術の未来のため態度を改めていただきたい。
武術では歴代の伝人たちが、各々工夫していくうちに外形が変わり、それが原因でうちが本家拳だ、元祖拳である、裏本家拳、いや真伝拳だ!という風な、証明がしようが無い不毛な主張が発生し、他派を断固認めないというケースがあまりにも多い。
しかし同じ名の型でも技法内容が異なっていたりするのは、極めてよくあることなのである。
「味道の違い」というのだが、老師が昔ながらの各人の個性を活かす教授法をされると、たとえ同じ門下であろうとも、拳風が異なるということも珍しくはない。人間の身体の作りや気性は各々違ってあたり前であるからである。
たとえば身体の作りの違いについて下盤を例に解剖学的に違いを述べてみよう。
大腿骨頸部の長さ、骨盤の臼蓋(受け皿の部分)の向きと深さ、大腿骨頸部の角度、腿骨のねじれ角度、仙骨と腸骨を繋ぐ仙腸関節の可動範囲(仙腸関節を繋ぐ靭帯は、人の身体の中で最も頑丈な靭帯であり、柔整鍼灸学校の解剖学の授業ではその可動範囲は0度と教えられるが実際は動いている)などは人それぞれ異なっており、股関節周りの運動は解剖学的形状の違いで物理的に大きな影響を受けている。
武術の動きの中で強い力を導き出すことに拘りがあるならば、解剖学的にわからないとしたとしても、明師は経験上これらは考慮するものである。
人体には200以上の関節があり、これらも先に腰の骨盤を例にあげたように人それぞれである。
すなわち絶対に正しい姿勢であるとか動作などはあり得ないわけで、武術では先ず、概ね正しいとされるものが基本として指導されるが、これを各々に合った実戦で使える形に最適化させるのが、指導者と各人の工夫、あるいは本人の才能である。
大成のためには、各人が自分の体質と優れた部分、弱点を把握し、それを活かし補うために招法や発勁、練功法を研究、修行していく必要がある。つまり自分の武術は自分が作っていくものである。
伝統武術は、たとえ同じ師に学んだ筈の同門、同派だとしても、違いを比較検証していくと、外形や技法内容どころか、果ては伝わっている拳譜の内容、漢字まで異なっているほどである。
であるので、もしも自他の先生が自分のとこは真伝、あそこは偽伝、失伝している、真伝が伝わっていないなどと声高に主張しているなら、そうですか(^^)、そうですね(^^)と右から左へ聞き流しておくのが、くだらない事で悩ませられず健全である。
武術家は自分の流派や伝系を尊ぶあまり、その流派に伝えられた「正しい動作」に固執して、ものを述べることがありがちだが、正しいといわれる動きも、人間の普遍的な動きの中の極一部を、各世代の伝人たちが、その体質や戦術、思想に合わせて取捨選択したものに過ぎない。
上手い下手、正しい間違いも基準が変われば、どうとでも変わるものである。
勿論、重心の安定すら顧みない動きは、実用にはならず法則どころの話ではないが。
また源流を求めたところで、その形態が過去から変化しているものでないとは、誰も保証することは出来ない。
「あそこはインチキだよ」と言ったところで、人の家族関係や拝師、伝承などはエスパーでもなければ、その本人と証を立てた者にしか分からないことである。
そしてどんなに師伝がはっきりしていると誇ったところで、そんなものも他の伝系からしたら、些細な違いを挙げ連ねられて簡単に、あそこは亜流(^^)、真伝を得ていない(^^)で済まされてしまうのである。
それでも他派を貶め、愚弄した物言いを好む者は、自分の贔屓にしているものが価値を下げられると恐れ、憎んでいるか、そこに利害関係があるか、僻んで嫉妬している、あるいはコンプレックスの裏返しで、人を蔑むことで優越感を得て溜飲が下り愉快だという、心の動きが健康的な者とは、異なる者である場合でしかない。
武術を離れた一般世間から、たちまち白い目で見られてしまうような言動の者がイキリ出しては、悪目立ちするのも武林(中国武術の界隈)ではよく見られる光景である。
このような者たちとは、あまり同じステージに降りて相手をしないことである。相手に武力が欠る場合、それは道義的に正しくても、世間からはただの弱い者虐めだと受け取られかねない。
ちなみに上から目線で他のところの武術をやたらと批評したり、うちのは他所のと違って真正武術である。自分のとこの流派には、一見殺しの秘密の技がある。それに比べて、あの先生は誰それに負けたのだ。あの先生は某先生に怯えて挨拶もせずに帰っちゃった。情けないよね。あの先生は金で段位を買ったのだ!というような、くだらない与太話を好んでペラペラと喜んで喋るのだが、肝心の本人には全く実力が欠けているという有様を皮肉り「口功夫」という。
そして自分は掌門人だ、嫡伝だ、真正であると誇り、大言を述べるが、実際は表演(演武)専門で、型ばかり多少見栄えが良いばかりで、いざとなると負けることを恐れ、全く戦うことが出来ない見かけ倒れの者のことを「死功夫(カタ屋)」などともいう。
また、短期間のうちに、様々な会派やセミナーを渡り歩いては、全くひとつの武術に腰を据えて学ぶ気が全く見られない者のことを、「カンフールンペン(武術ルンペン 武術ジプシー)」などと界隈では呼んでいる。
古来「良師は三年かけて探せ」というが、邪な理想を求めて彷徨う彼らが探し求めるものは、自己を肯定してくれて、楽をして簡単に実力が付くという便利な技術や、身を飾るブランド、神秘的でオカルティックな謎の拳法を探し求めているかのようで、実用の技術としてや趣味として長年武術に打ち込んでいる者からすると、不純で邪なものを感じさせるものがある。
程度の低い者の中には自分から、他人や他派を酷く愚弄しておいて怒りを買い、報復の気配を察すると武徳を語って言い訳をしてみたり、実は自分は病気で身体が弱い、私は貴方に脅されている被害者なのだと開き直り、情けない姿をみせて恥じない者たちすら見かける。
こういった悪質な気性の者は、驚くことに様々な者たちとトラブルを起した結果、責任を追求され収拾が付かなくなっては、SNSのアカウントを消して逃走したり、書き込みを全て消して息を潜めたり、自分の会のホームページや、有志たちから金銭を集めて、サーバーを借りて作った筈の掲示板すらも消して身を隠すのだが、ほとぼりが冷めると、愚かにもまた同じ様にイキリ出しては、同じような愚行を延々と繰り返し、さらなる悪評と怒りを買うのである。
だが、こんなことにも限度があるので、この様なやからは、稽古場所やセミナーの会場を伏せるなどしないとならない破目となっている。
そういう者たちの一人が、義憤に駆られた武術家に、身をもって制裁を受けた例が電子掲示板やSNS上で幾度か話題となったこともある。
残念ながら、本当は虚勢を張っただけの半端者で意気地なしの気弱な臆病者と、法螺吹き、詐欺師の類が、自己の実力とは全くべつのところでピーチクパーチクと囀り騒がしいことが武林ではよくみられがちなのである。
これらはべつに本人たちは殺されたいとやっているのではなく、その時アルコールで悪酔いしていたり、脳の関係で易刺激性や易怒性が高いゆえ感情が抑えられず、後先考えない衝動的な物言いをして、トラブルを起こすのが大半なのであろうから、それを本気になって怒ったり、責め過ぎるのも、もしかしたら良くないことなのかもしれない。
とはいえ狭い武林では、武術家は友人を一人またぐと皆知人ばかりで、本来は、武林皆兄弟、家族ともいえる親しい付き合いも可能なのである。
理想としては人格を養い、教養を身につけ、他人に対して尊重し優しく、言動に慎みを忘れない丁寧な態度で接することが出来れば、四海皆兄弟(世の中の人は、みんな兄弟のようなもの)なのであり、これが真の武徳とされるものの基礎となるものなのである。これは表面的にいいフリこいて、陰で人を見下すとかで無いことも言っておく。人として仁義によった矜恃をもって生きていきたいものである。
無論これは自他に甘く敵に寛容になれと言っているわけではない。
他者が築いた人間関係、価値観を尊重せずに、わずかな見識の中で自らが思い込んだ「正しさ」を強弁し、全否定から侮辱、見下して嗤うという振る舞いは、そもそもの考え方自体が醜く、間違っているとしかいえない。
上記のような愚行をやたらと人様に見せてしまうと、社会の常識の目からも嫌悪され、引かれてしまうのである。また性格が悪い者のところには、自然とコンプレックスを抱えた僻み屋たちが集い、醜く腐臭を放つものである。
自分に甘い者たちが集い、遥かに実力の高い者を下げて述べ、自分たちを高く上げて語り増長する姿は、傍からみたら滑稽極まりない。
ただし武術では自流が貶められた際、自らがリスクを負い、相手側に直接足を運んで反論し、戦えるほどの覚悟がある場合や直接本人に会ったとしても、堂々と言える反論、提言、苦言であれば、これは卑怯さや陰湿さからはほど遠く、武術家として筋の通った立派な態度であり、相互理解と和解のためには必ずしも悪くはないことである。
武術に対して誇りのある先生は、他からの中傷や疑問に対しては、どうぞうちにいらしてください(^^)という堂々とした態度をとるものである。
真正武術を標榜しているくせに、推手をお願いしたり、話を聞きに行く程度のことで怯えて逆上し、すぐに決闘は法律に反する!だとか、道場破りは警察に即通報します!だとか、弁護士を介してなら会います、あなたからのメッセージは今後読みませんから、電話にも出ません。などの、なさけないインチキ武術家のいうテンプレのような滑稽な言葉は、けして吐かないものである。
かつて、龍清剛(故人。京都在住の武林隠者。陳氏太極拳の中興の祖ともいえる、陳発科の高弟、王鶴林と義兄弟であった。生前、台湾の「中華國術會武壇國術推廣中心」の創始者、劉雲樵とも親しかった)が、狼派(武用格闘技派)と喩えたような武闘派では、自派の名誉を傷つけられたなら、他の道場に乗り込んで比武を行うことなどべつに珍しいことではなかった。
しかし現代では、国内の中国武術は戦うことが出来ない羊派(健身派・芸術派)が大数をしめ、まるで生花か体操の教室同然となり、日本の在来武道や各種格闘技と比べ軟弱で、とても武技を練っているとは思えない現状となっており、それを憂いた指導者自らが半ば自嘲して、中拳などと中国武術と界隈を、その情けなさを表した侮蔑的なイントネーションをはらむ言葉で呼ぶことすらある。
日本の中国武術の界隈は、残念ながらその普及初期から、スピリチュアル志向に傾き過ぎた言動を好んだ権威とされた紹介者たちや、そのシンパで利害関係から偏向した情報を紹介した雑誌、マンガなどの悪影から権威化と迷信が頑迷に蔓延り、本来格闘技には向かない極端に弱々しい者たちが集まり、さながらなにかのカルトのような様相がみられ大きな病根となっていた。
そこに古くから日本に移住していた、華僑の武林隠者たち、台湾、香港などが由来の実用志向が色濃く残された凄みのある武術と、同様な有様が本質である中国本土由来の民間武術、あるいは完全にスポーツ化された表演武術などが混沌的に入り混じり、しかし互いに反発しあって、大きな結束はみられないのが国内の中国武術の現状である。
しかも玉石混交なのである。優秀な武術家の選別は、メディアは全くあてになっていない。売名を好む者は、小さな成功に過ぎなかったり、なんの実績も無かろうと出たがるが、長い武歴を持ち、実績が確かで修行者の間で真に達人と呼ばれる武術家たちの多くはあまり表に出て騒がれることを好まない傾向にもある。
中国武術には拝師(拜師)という、日本武道における、内弟子制度のようなものがあるが、かつて古人は武術の真伝は人を選んで伝え、伝えるに値する者がいないのであれば失伝させよという、厳しい姿勢で継承させてきたが、現代では昔日ではあり得ないような大金を積み、拝師することが平然と語られ噂されていたり、商売として外国人を含めた多くの者に拝師を行わせる、中国人老師もおり、またこれは誠実なのか不誠実なのか、さっぱりわからないのだが、拝師は出来るが、外国人に教えられることはこれ以上ないと、わざわざ断りを入れてくる老師までいるという。
海外で有名老師や様々な門派の先生に会うと、「あんたでも弟子でもよいから、自分の武術を受け継いでくれ」と頼まれるという噂をお聞きする某先生に訊くと、嘗てはこのような拝師制度を悪用するかのような、高額の謝礼金が要求されるようなことは、中国武術の伝統には無かったといわれた。
謝礼金は、拝師式の際の必要品を賄ったり、祝の席の宴会で、飲食の足しになる数万円程度であったり、せいぜい月謝に毛が生えた程度が本来であったといわれている。
それどころか謝礼金を受けとらず、弟子の生活の面倒さえみて拝師門徒をとる先生も居たほどである。
現代の拝師ビジネスの悪例だが、高額な拝師料のおかげで、同門にまるで金で段位を買ったかのように思われて反感を買い、門内での序列をめぐった嫉妬、陰湿な嫌がらせが起こることを避けるため、拝師を勧められても断る学生さえも居るのである。
また商売に賢しい先生は、指導者資格の更新費などの名目で、拝師門徒から金銭を徴収し続けるケースも見られる。
拝師門徒というものも、それが即ち免許皆伝というわけではなく、学生(一般生徒)、外門(他の道場に所属している者)から正式に、その老師の元に入門し、これから研鑽を積んでいく者をあらわす言葉である。
古くはこの拝師門徒にも、徒弟、門生、示範徒生、把式匠などといった序列があった。
示範が教練(指導員、師範代)と言った程度の意味で、把式匠は、その老師の門下の把式場(道場)で全伝を得て最も優れた実力を持つ者をいう。この別名を得意門徒(得意弟子)ともいう。また拝師門徒を入門弟子と、入室弟子(特に優秀な弟子)に区別するところもある。
拝師を受けると一応、伝人を名乗ることは出来るのだが、大陸や台湾に1年や2年にも満たない、短期間の渡航を繰り返しては、老師に学んだとか、拝師をしたなどという者に、腕前も疑問だが、果たしてこの先生、自分の師との信頼関係、人間関係を構築出来たのか?と疑うような、人格の者が見られるのは上記のような理由からである。
10年15年と長期間異国で錬拳する者は、5年程度の留学では、お客さんだと評しているようだ。外国人、異民族という壁を乗り越え、信用を得るには、通常長い年月と実力の確かさが必要となる。
そんな僅かな期間の留学にも関わらず、日本に帰ればすぐに先生と呼ばれ、20年、30年と修行を重ねた自分よりも遥かに日本で長く指導されている、先輩たちが目に入らぬかのように、本場で習わなければ、この武術は理解出来ず身につかないと、声高に述べる悪例もみられる。
そして中国、香港や台湾、陳氏太極拳の陳瑜や陳正雷、南京の王波などの老師たちのように、伝統的な気風を尊ぶ老師たちには、拝師に際し、自派の系譜に外国人の名前が、そのまま記されることを嫌い、あるいは、もうその弟子は、我が民族の伝統を受け継ぐに足る者となったという証として、中国人風の名前を授ける慣習があるが(同じ中国人に対しても姓名を与える老師も多くいる)、これを拝師名(武芸名・芸名)という。
いわゆる中国名、カンフーネームというものは大体これであるが、中には真実はわからないが、拝師名とは関係のない芸名を自分で名乗る者も見られるともいわれている。
拝師に際し弟子は、開祖以来の伝系、門人としての誓句が記され、老師及び立会人、自分の署名等が記帳された拝師帳に署名する。
これをそのまま弟子に与えるところもあれば、二部作り片方を拝師門徒に与えるところもあるが、拝師帳を記録として師に預けるものとするだけのところもある。
そのようなところでは、やがて弟子の誠意と実力が師から認められると、師よりあらためて拝師帳とは別に、自分の門徒であるということを正式に証する回帳(証言書)が与えられるのだが、師の信用を得られず、必ずしも与えられない者さえもいるという。
拝師帳は、拝師式の際の祝賀で展示されるが、その後は一切余人に見せるものではないため、勝手に拝師門徒だと名乗ることも、恥知らずであれば可能であろう。
中には弟子でもないのに、有名老師がセミナーの際に記念品として参加者に渡した色紙を、老師の死後に公開して、それを利用して教室の宣伝に使ったという悪辣な例もみられる。
それと門派によっては拝師に際し、字輩というその門派の流祖から何代目にあたるのかを示す、漢字をひとつ与えられるが、古来武術家はこれを上記の拝師名や、道号に組み込むこともあった。
だがこの字輩の上下関係をめぐって、実力とは別のくだらない争いが起こることがあり、現代では面倒なので拝師名や字輩は表では大っぴらに明かさない者もいる。
伝系が上の方になると、たとえ年上で先輩にあたる者に対しても、師兄として対応することになるのだが、もはや開祖から数百年を過ぎ、ヤクザの親子関係でもあるまいし、現代には合わない慣習ではなかろうか。
ちなみに形意門の字輩はあるところと、無いところがあるようだ。山西派や尚雲祥派にはあるが、一説によると少なくとも李洛能の時代からあったものではなく、二代目以降の誰かが、独自に始めたものといわれている。張占魁派のように、八卦掌のものをそのまま当てはめて使用している派もある。
本来、字輩は一門の内外に弟子の序列を知らしめるために、学生を含めて周知されるべきものであって、秘密とされるものではない。であるので、これを知っていれば不正に使用することも可能である。なにせ門派の伝人の墓碑に数十代後の字輩が記されていたりするので、成りすますのは簡単であろう。
拝師をしていても、後に師との人間関係が悪化し、破門や放逐、それに近い絶縁関係になっているという例もよく聞くのだが面子の問題となり、門派の恥となるので、外には周知されていないケースもあり、この場合、そういった者の師兄弟たちは、勿論承知しているが、ただ白い目でみて放置しているのである。
そういった場合、老師の書籍や公式ホームページ上で公開されている伝人系譜から、静かに名が消され、暫くすると別の者に同じ拝師名が与えられていたり、破門された者のところで、門派の秘伝であると称して、母団体に無い型が続々公開されるなどの、おかしな兆候が現れることがあるので察せられはする。
このような者たちと比べたら、まだ自分の師匠の名を教えられないと、暗に師に破門されたことを打ち明ける者の方が遥かに潔いであろう。
更に酷い場合、老師の生前仲違えしていたことが周知であったのにその死後ちゃっかり、自分は一番弟子だったとか、入室門徒だとか言い出す、恥知らずも居るのである。事情を知る者は呆れ果てしまうが、死人に口なしである。
俗に拝師門徒と師は、家族と同然と語られるが現実は厳しいものである。
拝師に際し弟子は、けして師を脅かさないことを重く誓うが、師も弟子も人間であるのだから、利己的な行動に走ったり、互いに好き嫌いは出るのである。このような例を知ると、誰々に拝師しましたという看板文句もそのまま鵜呑みには出来ないのがお分かりであろう。
この他にも中国武術でよくあるしょうもない対立としては「表演拳」VS「伝統拳」、「外家拳」VS「内家拳」、「元は満族が学んだエリートの武術」VS「田舎の民間武術」、「台湾や香港、東南アジアに流布した中国武術」VS「中国本土の中国武術」、「前身が中央国術館系という体育学校」VS「新中国で設立された新興の体育学校」、「北派」VS「南派」、近親門派間での流祖、先生の偉さ比べなど各種正統をめぐったイキリ争いが多数観測されがちである。
はっきり言うが他流を下げても、自派や自己のステータスが微塵も上がるわけでもなく、傍から見られると、かえって大きく下がる一方なのである。今の時代、こんなことは共感性を得られず、最悪な行為と思われよう。
本当に自己の武術に対して誇りがあり、この国で受け入れてもらいたいのなら、他武道や格闘技があたりまえにやっているように真剣に、そして明るく稽古に取り組む姿を世の中に見せていただきたい。
恩人や友人が貶されているなどの義憤からの怒りは真っ当であろうが、恨みがないのに他への思い込み、僻みでする誹謗中傷などとても良くない。
他派にあれこれ重箱の隅を突いたように述べる者の言葉は、傲慢さや無知の反映であり、同時に劣等感の裏返しである。
武林では多くの人間関係が、事情を聞いてもわけがわからない、くだらない傲慢さ、性格の悪さから起こった軽挙妄動ゆえの不毛なイキリ合いの果に崩壊しているのである。
なかには自身の道場経営のビジネスに利用しようと、敵の敵は味方と双方の対立を煽っては抗争を仕掛け、漁夫の利を得ようと動く邪な者も見られるほどである。
こういった者は策が失敗すると、多くの者を利用し傷つけた加害者本人であるのに、被害者を装い、かつての弟子や恩人などをスケープ・ゴートにして語り、弁舌巧みに声をあげて恥じることがなく、自身は実際の脅威に立ち向かうことを恥も外聞もなく避け、奇妙な精神的勝利法に頼っては、仲間内に勝ち誇るものである。
そのような者は他人を煽ってけしかけるような振る舞いをよくみせる。
武術は女子中学生のやるような、女の子同士の陰口や教祖を奉る新興宗教ではない。
どうか、そういうのは表沙汰にならない範囲でほどほどで止めていただきたいものである。あまりに女々しく性格悪く、ブザマでみっともないところをみせ過ぎると、中国武術などまともな感性の者は誰もやりたくなくなってしまいかねない。
口が悪くなり大変申し訳ないが、これでは伝統武術はいかにも戦えるような感じがしない、パッとしない見た目陰キャな人々だけが集まり、武術って、このままの自分で良いんだなあ…(^^)とかと、向上心を自から打ち捨てるかのような大きな誤解をされ、ついには格闘技として到底実用にはならない、手品のような旦那芸やヲタ芸のようなものを披露するばかりのわけのわからない代物に変質しきってしまうであろう。
これを防ぐには中国武術を愛好する1人、1人が武術ってカッコいい!強いぞ!と思われような魅力ある姿をみせ、社会に対しても健全な姿をみせることが大事であろう。
まだ喧嘩沙汰ならわかるが、決して武術やカンフーを名乗っておいて卑劣な強制わいせつや痴漢で捕まってくれないでいただきたい。
武術に文化的側面はあるが、武術とは本来闘争において必要とされ生み出された技術であり、それを研鑽する真剣な場が道場であるということも忘れてはならない。
近年、イスラエルのクラヴマガやロシアのシステマのような軍事格闘技、インドネシアのシラットが実用的かつ武術的で、日本で人気を博しているが、ところが日本の中国武術は、その全盛時代であった1980年代のような人気を取り戻すことはなく、年々その愛好者は減少していく一方である。
激動する国際的状況から、1970年代、1980年代の日本人が、中国と中国文化に抱いていた好感と憧れは、すっかり薄れてしまい、今後も日本人の対中感情は悪化する一方だと思われる。
そのせいで、いつか浅はかな者たちから中国武術を愛好する者が、理不尽な迫害にさらされることがあるかもしれない。
中国武術の愛好者たちが、その武術と発祥地での政治的問題などを切り離し、その発祥地で倫理に反する義憤に駆られるような行いがあれば、気兼ねなく駄目だと声を上げることは、中国武術が現代の中国という国家が持つマイナスのイメージと紐付けされて、善からぬレッテルを貼られてしまうことへの大きな抵抗になると考えられる。
これが立場上、どうしても出来ない者は、日本の中国武術の今後のため、政治的な発言についてはどうか一切沈黙していただきたい。
そして中国武術は、既に日本に根づいており、もう本場だとか、国家や伝説的な伝人による有りもしいない権威やブランドだとかに依らないものに移行し、在来武道のように実力勝負で自立するべきだと、編集者は個人的に強く思っている。
とはいえ過去、編集者に「中国武術なんてものは、財団法人日本武道館に登録も出来ない如何わしいもので、私はそんなものに関わるつもりはない(笑)」という旨を放言した名門の古流の高段位者が居たが、在来武道にもこのように権威に依って他を下げ、心の平安を得る者はごまんと居るのだが他山の石とすることである。
スポーツとしての中国武術も、世界大会を開催できるほどの力のある団体は世界的に見ても数少なく、また残念ながらイデオロギーを理由に分断もみられる。
例えば世界的な団体としては、米国政府の主導で中国共産党による政治的な影響を排除するかたちで設立され、台湾政府が運営を行う「台湾省国術総会」などが加盟して関係が深い、華僑系武術の最大組織といわれる「世界国術総会(The World Kuo Shu Federation )」、中華人民共和国で設立され運営されている「中国武術協会」や、日本最大の中国武術の協会である「日本武術太極拳連盟」などが提携している「国際武術連盟(IWUF
)」、中華人民共和国で設立され運営されている「中国武術協会」や、日本最大の中国武術の協会である「日本武術太極拳連盟」などが提携している「国際武術連盟(IWUF )」という二大組織がある。
)」という二大組織がある。
これらと提携していない小規模の団体が開催した大会に、むこうから招待されて出場してみると、ちゃんとした資格制で審判として育成されていない者が、不審な身内贔屓の審判を行い、酷い場合は大会のあとで、入賞が取り消されるなどされて、嫌な思いをしたという選手たちの話も昔から聞き飽きるほどである。
表演、散打にしても小さな派閥の中だけで行こなわれる、独自のマイナールールで行っていては、世界のレベルに到底ついていけなくなってしまうだろう。
台湾においては、太極拳の推手が国家によって競技化され、学校教育のなかにも取り入れられている。スポーツの一つとしても、国術(中国武術の中華民国における総称)の評価は高く、その道に進む若者は多い。
中国においても、空手やテコンドー、MMAの人気が高まってはいるが、体育学校や民間の武術学校でウーシュー(中国においての武術の総称であり、武術という名のスポーツをも指す)は盛んで、その競技人口は他国を凌ぐものである。
元々、中国武術には日本武道のような段位制度はなかったのだが、現代では国際的な大組織から、日本の武術太極拳連盟、全日本太極拳連盟、様々な協会、教室まで独自に段位を認定することが多く行われている。
これらは、一定の基準や審査を経て、授与されるものであるが、組織の権威を背景とした格付け、スポーツ化をあらわしている面は否めなず、このせいで昔日の中国武術の姿であった武縁とも思える、人から人への素朴な伝承とは、良くも悪くも変質が見られている。
発勁概論
中国武術でいう「勁」「勁力」とはやたらと、力むことで発せられる不合理的で稚拙な力ではなく、武術において有用な、もっとスマートな力をそう、ふんわりと言い表したものである。
あまりにも便利な言葉であるので拡大解釈され、あたかも神秘的なものであるかのように喧伝されるが、近代に入ると西洋からの新しい考え方を取り入れ、そのような曖昧模糊な表現を嫌い、ただ発力と言い表す意拳の王向斉のような武術家も現れた。
また広東省、福建省のような中国南部で発展した南派少林拳の中にも、合理的な力を確信的に「力」だと言い表し、勁力というような、ふんわりとした表現をしない門派もみられる。これら白鶴拳などに代表される門派では脚から起こる力を地根力、震えるように発する力を震身力などと言い表している。
昔の北派中国拳法、内家拳を学ぶ者たちは、南派少林拳を愚弄して述べることが非常に多かったのだが、その言動は概ねプライドの問題であったり、彼らの実戦的な強さに対してのコンプレックスや、北派や内家の中国武術を学んだ日本人の一部が、自分の武術は空手道と比べて、より高級なものだとして、空手を見下したゆえに、外見が近い姿の南派武術を同じようなものと評し、臭したい意図が過分に反映されたものであった。
南派中国拳法も内功をとても重視しており、高度で実戦性の高い武術である。その流れは形意拳から派生した、意拳や我が国の空手道に大きな影響を与えている。
形意拳が第一に基礎とする発勁は、整勁という、身体の各個重心が整った構造的に強い姿勢から生み出される力である。
それに前進する力(推進勁)、踏歩する際の震脚による補強や脊椎、下丹田を中心とする縦回転と表現され、翻浪勁などと呼び称される波状に伝えられる力、衣服の袖を巻き込むかのような、螺旋的な蓄勁・発勁である袖絲勁などの回転を伴う力が働き、そしてそこに意念が加わる。
心と意が合い、意と気が合い、気と力が合うを内三合という。
「意」とは、意思をも含まれるが東洋医学では心の本体をいい、日本語でいう「本能」に近い概念である。日本武道では、しばしばこれを「気」、「気の働き」と説明している。
肩と胯が合い、肘と膝が合い、手と足が合うを外三合という。
胯(クワ)とは、股関節のビキニラインのあたりのことをさす。収胯(胯を折るともいう)することで、腰椎の前彎を弱め、脊柱起立筋を隆起させることを、「命門を開く」という。
肩と胯を合わせることで、重心に対して適正に立つことが可能となる。その際、上半身の多少の前傾は問わない。
むしろ命門を開いた状態での歩行を実現する際は、直立して進むよりも、適度に上体を前傾させることで、しっかりと軸足に力が乗り、力の途切れがない強いかたちを保ったまま歩行することが可能となる。
六合とは、心の働きによって心神を全身に貫注させ、気力を働かせることで内外、つまり心と身体の合一を得ることが、武術では極めて重要であると説いている教えである。
形意拳は「六合をもって法となし、五行十二形をもって拳となす」といわれる。法とは守らねばならぬ規律である。六合を無視しては武術としてはじめから成り立たないのである。
長々と述べたが門外漢向けに簡単にいうと、敵を撃ち倒すという強い意思と勢いとが合わさることで武術の技は、人を撃ち倒すという本来の目的に達するのである。
先人は武術の技には身体と心が伴っていなければ、実戦では使い物にならないと強く戒めているのである。
たとえば日本の古武術においても、いざ実戦となると生命の危機に恐怖して、実力が発揮出来ない者のことを道場剣法だとか、畳の上の水練者などいって嘲るが、実戦に耐えられる強い精神力、覚悟のあり方を得るということは、武術において最重要の課題である。
そして先人は六合の基礎は丹田にあると説いている。
人体には丹田と呼ばれる穴所が3箇所あり、それらは頭頂部、あるいは眉間にあるという、神を蔵するとされる上丹田、胸腹部にあるという気を蓄するとされる中丹田、臍下の三寸にあるという精を蔵するとされる下丹田の三つである。
これらを体感出来ず、あくまで観念的なものであるとしたとしても、東洋では古来からあると説かれているものであるため、無いと完全に否定することは、先人からの伝統の一切を廃することと同義であろう。
古来から形意拳は数ある中国武術のなかでも実戦の究極と謳われるとおり、その打撃力は鋼鉄球にも喩えられ、随一の威力だと評されている。
非常にシンプルにして合理的な体系をもっており、ゆえに『太極十年不出門、形意一年打死人(太極拳は10年は練習しないと使えないが、形意拳は習って1年で人を打ち殺してしまう)』という諺さえもある速成さを誇っている。
『形意拳術の道は極めて易しいが、極めて難しいともいえる。易しいというのはこの拳術の形式がいたって易しく、いたって簡素で繁雑ではないからである』孫禄堂 『拳意述真』より。
形意拳の打突は他派と比べるとモーションが小さく、素人目には一見手打ちで繰り出されているかのようにも思われるが、実際は、まるで精密機械が動作するかのように、全身を周身一体させて発した勁力は纏まっており、通臂され十分な威力がある。
むしろ体幹からの勁力の伝達が露骨に、はたから分かりやすく見てとれるような大げさな打法は、勁力を纏めることが難しく、真伝を得た先人たちが誇った、形意拳本来のもつ一撃の威力など到底発揮出来ることはあり得ない。熟達するうちに形意拳の打法はコンパクトなものとなるはこのような理由からである。
虎形回身式など、回身式(転身して向きを変える動作)で方向転換する際は、単なる振り返り動作では終わらせず、扣歩、擺歩により下肢から反作用的に起こる、螺旋の力を途切れさせず、手にまで伝えられるようにも工夫して欲しい。
これは発勁、招法にも活用出来る効果的な力の使い方でもあり、圏帯法(投げ技)にも用いることが出来る。
古来形意拳では「手で打つこと三分、脚で打つこと七分」というが、形意拳の打撃は、手は脚のように用い、脚は手のように用いる。打拳は腕で打つのではない。
やや誤解をまねく表現となるかもしれないが、敵を打つのは脚で、まるで手を伸ばして物をとるかのように脚で移動し、敵に当たる身体である。手はそれを補完し、まるで脚で地面に立つかのように敵と自分とを支えるのだ。
それが重い威力ある打拳となる。突きは脚が至れば手が至るのだ。上下相随である。突きは拳を打ち飛ばすなどという思い込みを捨て稚拙な力を抜き、姿勢が作り出す構造的な力を信じて気張らず打つべし。
中国武術でよくいわれる内勁とは、内功と称される身体の内部に形作られるとされる、功力(地力)をベースに、身体の中から発揮される効率的な力を、そうふんわりと形容したものである。
ある者は、それを気の働きによるものだと表現し、ある者は丹田の力、ある者は呼吸力であると述べるが、そのどれもが正しいといえる。
また武術に熟達する者からは、総じてそれは筋肉の力では無いと語られるが、胸椎から腰椎、腸骨、大腿筋膜張筋へと繋がり、股関節の伸展を司るインナーマッスルである、大腰筋、腸腰筋、呼吸を司る横隔膜などの運動と、それらによって刺激される、内臓を包む腹腔、腹膜、腹直筋などに腹部や脚、背中に感じる感覚を、丹田の働きとし、筋肉の力では無いと形容しているものと理解しても構わない。
勿論、東洋思想的な理合でも、それによって導き出される力が真に有効であるならば、内勁の解説としては正しい。
また精神の働きが無ければ、いかなる勁力も発揮出来ないのであるから、意念などの心の働きを重視することも正しいといえる。たとえ気功的な説明をされることはあっても、それは武侠小説で描写されるような荒唐無稽なものではない。
他者の動きのなかに内勁があるのか無いのかは経験者はある程度みてとれるが、それを批評し、強くそうだと主張する者の根拠は、過分に雰囲気的なものに過ぎない。
自派とは異なる動きをする者の内勁をみとり、ましてや実力を正確に判断することなど不可能である。
武術の熟達者の動きは、一見素人めいたシンプルなものとなるケースもままみられ、それを未熟な実力でいる者が浅はかな見識で評論など出来るものではない。
内勁も気の働きのように、自らが体現することで以て語る、体感上のことであるともいえる。
内勁、功力などは、その優劣を明らかとするなら、比武(果し合い)を以てしかありえない傾向の話題であるので、もしも他派の内勁を話題とするならば、争いの原因となりかねないので内和で止め、外でいうものではない。
論外だが、重心の沈下を用いた発勁を、ただの落下運動であると誤解している者すらいるが、この程度の者たちと武術の技術論を、まともに語り合っても話が通じることはない。
中国武術では、「高手(達人)の応敵勢に低架(低い構え)なし」といって、たとえ腰の高い姿勢で動いていたとしても、その重心はしっかりと落ちていて、常に安定しているものである。
静止した状態において自己が体感する力は、主に重力によって感じる重さであり、この重さは、敵と接触したときに活かせるものであるが、位置エネルギーを用いて、打撃力の源であるかのように語るのは、全く無理がある。
たとえば人間の総質量をMとすると、腕の質量は0.15M。その位置エネルギーが全て腕が持つ運動エネルギーに変換されたとするならば、9.8×Mh=0.5×0.15M×V×V。変形すると、V=√130h。仮に1メートル分の位置エネルギーが、全部腕の運動エネルギーに変換されたとしても、拳速は時速41キロ。
理論的には、ここまでやってやっとプロボクサーのパンチほどの威力となる。
だが実際にやろうとすると、例えば身長180センチの者の重心位置は、大体、足下から1メートルなので、落差1メートルを作りだすには、身長2メートルの者が突っ立った状態から、床にうつ伏せに倒れて、やっと重心が1メートル落ちた状態となるという有様で、位置エネルギーを直接的に打撃力に変換するという説が、いかに現実的ではないということがこれでお分かりであろう。
また落下を大いに語る者は、浮いて不安定になってしまうことのデメリット、初動の遅さや敵に乗ぜられる、空きとなる部分を語ることがなく、技撃を前提とした身体操作とは思えない。
ただ非接触時での連続的な推進力を意図し、歩法に活用している可能性はあるので、武術的技法として軽浮からの落下の多用も、完全には否定出来ないが、形意拳の伝統的な身法とは異なるものである。
無闇にコンセプトの異なるものを混ぜると、武術として使い物にならないものとなる恐れがあるだろう。
くれぐれも注意しておくが、発勁はあくまでも手段であり、武術であればその目的は、身を守ること、有り体に言うと、敵を倒すことにある。強い威力の発揮はこの目的のための一要素にしか過ぎない。
嘗て、ことさらに発勁をセンセーショナルにとりあげて、武術の秘伝や奥義であるかのように言われたものだが、程度にもよるが発勁は、どちらかというと武術の基礎であり、学ぶための前提にあるものである。
発勁論については、以下にある「三層道理」でも補足しているので参照のこと。
三層道理
形意拳では三層道理(三層功夫・三種錬法)といい、明、暗、化の三段階に分けて繰り返し拳を練ることを説く。
明勁
第一層目の明勁(換骨功夫)では、拳足を素早く動作させ、特に進歩には快さを求める。「骨堅きこと鋼鉄の如し」というように剛的に形を厳密に鍛る。適正な力と姿勢を整えることで鋭く剛い力の発揮を稽古する。
動作と呼吸を一致させ、発声(雷声)、震脚などの発音が伴ってもよい。これが錬丹の三易における練精化気である。
ここで震脚について補足するが、震脚は打撃の質を変えることが出来る技法でもあるが、自己の重心沈下を確認する際の、分かりやすい目安ともなっている。重心が浮いた状態では、その音は軽いが、各個重心が纏まって重心が沈下した状態では、意図的に強く踏まなくとも、その音は自然と大きく鋭く響く。
震脚は意図的に大きな音を鳴らそうとして、強く踏歩するものではない。重ねて言うが、重心が落ちているがゆえに、自然と大きな音が鳴るものである。
このような重心が落ちて安定している体勢が作れているのであれば、素速く軸足を踏み変えることも、前進後退することも自由自在である。
これはあらゆる門派のものでもいえることだが、表演などで魅せるために、無理やり大げさに強く踏んで打ち鳴らすようなものは、ちゃんとした震脚とは殆どなっておらず、単に居着いているものとなっている。それと架式と動作が適正であれば、震脚で踵を痛めることも、その衝撃で、身体を痛めるようなことはない。自己の理解の浅さと未熟を震脚のせいにしないように。
なにやら世間では、震脚を誤解している者も多くみられるのでさらに追記する。
震脚によって確かに、威力の質は変わるが、震脚は主に打撃力の向上のために行われるというよりは、敵に踏み込んで打突した際、自分が敵にあたり負けしないように、インパクトの瞬間に、地に杭を打つように、その場に重心を固定化させることによって、その反作用を打ち返すことで、敵の位を奪い、突き飛ばす(刺し貫く)というのが第一の意味である。
このとき打拳は、慣性力や身体の伸展の力も加わり、敵の身体に突き刺さるようにのめり込み、相当の威力が生じるのだが、これは半分オマケともいえる追加効果である。
納得出来ないのであれば、槍術か銃剣道の試合でもやっていただけると、即座に理解出来ることであろう。たとえば、相手と突進し合い、同時に打突となったような場合、より力強く震脚のように踏み込み、その場にしっかりと、重心を固定化させた方は、木銃の先端(タンポ)を胸当て(裏布団)に命中させたとしてもブレることなく突き貫き、打突をキメることが出来るが、これが疎かであると、相手の突進力に負けてしまい、木銃は肩の防具や胸当てから簡単に逸らされて、一本となることはけしてない。
もしこのような事態が、甲冑をまとった槍で突き合うような戦闘で起こったとすれば、致命的なことになるであろう。無論徒手の攻防においても同じである。形意拳や八極拳など震脚を多様する拳術は、槍術が元となって生まれた門派である。先ず震脚は、槍の操法(刀術、大刀でも震脚が用いられる)が反映された技法であることを考慮して欲しい。
次に踏歩する際、後方斜め下方向に蹴り込むことで、下肢で生じた反作用を前方への威力や突進力に変えるという説を見かけたが、殆ど徒労であろう。編集者が学習した形意拳、八極拳、陳氏太極拳、太気拳、その他の武術でも、震脚は行われるが、それらは全て真下に踏歩するものであって、前進、後退しない場合でも震脚が行われるのだが、問題なく打撃力は前方にも発揮され、対象に威力を与えることが出来ている。
下肢からの勁力を伝えるものは、何も露骨な前方への体重移動だけではないのである。それは、螺旋運動を用いて下肢からの力を導き出す、陳氏太極拳の纏絲勁であったり、台湾の武檀八極拳で語られる、身体を開くことで発せられる、十字勁のようなものであったり、太極拳全般でいう、全方向に張る力である掤勁、あるいは太気拳でいう上下の力、前後の力、意拳でいう六面力である。
これを「丹田と手が繋がる」、「重心を敵に送りこむ」と表現した達人もいたが、発勁とは、自己の重心をまとめ安定させることで、適正なバランスが保たれた強い姿勢を作ることが、最も重要な基礎となるのであるから、言葉足らず気味ではあるが、発勁を体現できる者にとっては感覚的に頷くものがある。
下手に地を蹴り出すように威力を出そうとしても、それは武術の動きとして遅く非力で、重心と摩擦力を十分に活かすことが出来ておらず、結果、力が途切れることになる。
それ以前に、人間の骨格筋は、螺旋状に力が働くようなスパイラル構造となっており、下肢からの力を自然と、効率的に上肢へと伝えられるように元から作られているのだ。
陸上競技においても、日本で長く保守的なコーチが教えていたような、地面を強く蹴って走れと指導された選手は、世界的なレベルと比べてタイムが伸びなかったが、脚を回転を速くしろと説く、欧米の指導法に則ると、途端に記録が向上したという例がある。
武術は状況により、地面を蹴る場合も蹴らない場合もあるが、前方に身体を移動させることが、強力な発勁の条件ではない。下で紹介している、清風館の森本師範の分勁の動画のように、足を止めた定歩の状態でも、大きな力を発揮させ、物体を打ち貫くことが可能である。
それとよく混同されているが、軽浮の状態から、強制的に一気に身を沈めさせ発勁に利用する沈身(中国武術では多用はされないが、日本古武術だと柳生心眼流に同様の力の出し方が頻繁に見られる)と、重心を沈下させ安定させた体勢を保ち、これを発勁に利用する沈墜は、同じようでいて両者は全く別なものである。
形意拳や八極拳の熟練した使い手が、前進して技を発する際にも大きく身を沈み込まず、腰の高さや頭の高さが変わらないのは、後者の沈墜を用いているからからである。
これがわからず高手の動きを見て腰が高く、沈墜勁がないと誤解する者がいるが、彼らはまだ浅い理解に留まった者である。
とはいえ、たとえば意拳・太気拳は、沈身が発力の重要な基礎となっており、身体を大きく沈み込ませ伸展運動させる、神亀出水試力の要領は、推手や組手などでよく用いられ、身体の沈み込みが悪いというわけではないのは注意しておく。だが浮ききってしまって力無く、落下するだけの有様では、多くの修行者が憧れる強大な発勁からはかえって大きく遠ざかるのである。沈墜と沈身では発勁の方法が全く異なることは理解すべきであろう。
ちなみに武術業界で俗に、「疑似発勁」と呼ばれる、ブルース・リーのワンインチパンチを表面的に模したような、宴会芸的な打ち方を披露する者もよくみられるが、このような打ち方には、真の寸勁のような威力はなく、重心の浮いた状態を作るため実用とはならない。
疑似発勁のよくあるやり方は、先ず手を開いて指を伸ばし、拳を加速させるための距離をかせいでおき、次に身体を沈めると同時に肩を伸ばし、拳で打つ対象を擦り下ろすようにプッシュする。その際、後ろ足から前足に体重を移動させるなどである。中には後ろ足で蹴って、前方にスライド移動して打つことで、それを寸勁だと強弁する者も観られるが、そんなものは疑似発勁以下の代物である。
他にも武術でよくある宴会芸だか、相手に二人羽織をさせたり、防具を付けされた状態の相手を打って衝撃力を伝えさせることで浸透勁であると称する者もいるが、これは、たとえばニュートンのゆりかごが見せるように、固定されていない物体には変形等で衝撃を吸収する機能がないと、たとえどんなに分厚かろうと衝撃を向こう側の物体にも伝えるもので、そんなものはつまり、まやかしのようなものである。
それで打たれた相手がケロッとしているようならば、威力もない詐欺みたいな見世物ものに過ぎない。
あと震脚を語るのであるならば、生身の身体を打って、震脚がある場合と無い場合を比較すれば、その効果は語るまでもなく明らかに体感出来る。
震脚を用いると威力は炸裂するように効き、震脚を用いないと威力は重く残るように効く、どちらも武術的に打たれると、ダメージがあるもので危険で、普段から単撃、排打功などで打たれ慣れていないと、試し難いであろうが、納得が出来ないのであれば、他の箇所を打つより比較的安全であるので、練習相手の肩口でも互いに打って試してみたらよいであろう。
サンドバッグだけ打っていても、はっきり言って何もわからないのである。
ただ物体を推すだけならば、自己の質量と突進力さえあれば、それらしくみせることは出来るが、修行者の誤解を増長させ、躓きの元となっている場合が多い。武術の打撃は単なる体当たりとは異なり、格闘技術として使える工夫がある。
言っておくが、編集者は震脚がまるで使えないものだとか、勁力を生み出すために役立たないと述べてはいないので、誤解しないで欲しい。
ただ、やたら震脚、震脚と言い出して、その効果を喧伝することは、やたらと丹田、丹田、気の力だと言い出す者たちに通じる、如何わしさを感じ避けたく思う。
なんにせよ、初心者は思い込みから余計な工夫をせず、ただ自分の師と先人の教えに素直にしたがうべし。師の言った通りのことを地道に続けることが上達の早道である。
あと編集者の師は、台湾で劉雲樵大師の側近や、通備門の八極拳の達人に手解きを受けているが、彼らの八極拳には震脚動作は見られなかったという。
まるで次に後述する、暗勁のようであって興味深い。ちなみに形意拳の兄弟門派である心意六合拳においても、練習では震脚を伴った動作を重んじるが、実戦で用いるものではないと断言する派(洛陽心意六合拳)が存在する。
このように震脚には、意と気と身体を合わせる、練功法としての意味合いもあるのである。
暗勁
二層目の暗勁(易筋功夫)では練法、意念を重視し、身体の筋を伸ばすように柔らかく綿の如き動作を練り慢練(ゆっくりと動く稽古のこと。その反対を、快練という)となる。緩みの中で出せる勁力を純化させ、明勁で得た短勁を、体のどこからでも発せられる長勁にしていく。威力を向上を意図して練習を行うのである。
短勁とは、勁道上の性質で区分された発勁の種類で、瞬間的に爆発的な威力を発する勁力をいう。これを爆炸勁ともいう(驚炸勁とも称されている)。身体を震わせて打つ、弾震勁などもこの短勁の一種である。
それに対し長勁は、短勁と比べてかなり持続的な威力を発揮し結果、重く波状的な衝撃を体内に与えて損傷させるものである。柔勁とも称される。
これらを打拳における間合いの長短の区分というような意味で、述べられることもあるが、編集者はそうは教えられていない。
形意拳でいう柔とは、ふぬけのようなものではなく、軟らかさのなかにも勁さがあるものが柔であり、剛も硬さのなかにも柔軟さ、靭やかさがあるものが剛である。この点は特に注意して欲しい。
暗勁の練習では、呼吸は自然で発声は伴わせず踏歩においても音を立てないように心がける。練気化神である。形意拳の歩法は滑らかな重心移動を心がけ、後ろ足で、やたらと地を蹴り出して進むことをとても嫌うが、暗勁の場合、特にそのように意識して歩く。
ちなみに物体が移動するとき体重も勿論、重心も必ず移動し、腕を僅かに上げ下げした程度のことでも、人体の重心の位置も変化するものである。よって、ちまたで散見される発勁の際に重心移動は行わないという説は、物理法則から離れた、過分に雰囲気的な物言いである。
屋外で稽古して、跟歩で後ろ足を引きずる際や、摩擦を利用した螺旋の動きが入る回身動作など以外で、足を擦る音が大きく聞こえたり、体育館で稽古して、どんな動作においても、靴底と床が触れて常にやたらと大きな音を立てる者は、たしかに目で見える型の動作手順は、正しいのかもしれないが、稚力は用いないという古伝の理合による勁力は、ほとんど体現されておらず、殺傷力はそれ相応であろう。
勁力を自らロスするかたちで動き、果てはそれを、スムーズな動きで良いとも誤解している。理想は、たとえ滑りやすい氷上で動いたとしても、力を発揮し滑ってバランスを崩してしまわないような歩法である。
この見方で八卦掌や太極拳における練度や理解力をも察することが、ある程度は可能である。他派のことではあるが、編集者が交流させていただいた太極武藝館 の故円山洋玄館長は、普段も床を蹴っては歩かれないことを徹底されているので、他の者と比べてサンダルの底が摩耗し難かったという。
の故円山洋玄館長は、普段も床を蹴っては歩かれないことを徹底されているので、他の者と比べてサンダルの底が摩耗し難かったという。
太極拳シューズやスニーカーなどではなく、伝統的な中国の靴底がフェルト製の布靴で滑りやすい屋内で練習をしてみたり、靴底がプラスチック製の安物の功夫シューズを履いて屋外で練習していると、自然と蹴って歩を進ませるような動作が戒められて意外と良いものである。このようなグリップ性の少ない靴を履いてなお、スムーズに動ける者は、発勁を体現出来ている者である。
ちなみに本記事の関連商品に掲載している武術シューズの「フェィユエ」は、世界国術総会の擂台(散打試合)で選手が履く公式シューズに採用されていたり、中国の武術学校などで昔からよく使われている、適度なクッション性とグリップ感のある履き心地の良い武術用のシューズであるが、底が若干、蒲鉾型に湾曲しているので站樁功の練習にはやや使い難い。
武術の力の使い方において、適正に地に立ち、身体を支えることで導き出される重力からの力を、余すことなく活用することは最も重要なことである。
化勁
三層目の化勁(洗髄功夫)では、剛柔を相済させて鍛える。必然的に緩急を伴った突破的は速さと柔らかさをかねそた動作となり、これこそ練神還虚である。ちなみに武術の緩急のコツに、投鐵網式というものがあり、緩慢に動く際は重い鉄の投網を投込むように、 そして、網一杯の重量物を引き込むが如くの意を用いよとの教えがある。 編集者は、師から回身式を行う際に、特に注意されたことである。
このような意念を持って動けば 「緩」の際に、まるで下手糞な踊り同然の、勁力の欠けたものとはならない。化勁は緩急の妙をとくに稽古する。「緩急」の「緩」とは、「のろのろ」、「ぐずぐず」、「がたがた」としたぎこちなくて、ただ遅いというだけの動きとは異なる。
また「急」も「発勁は箭を放つが如し」とはいうが、 力みのような力の溜めが、やたらと外見に表されてしまったり、 ただ打ちっぱなしにしてしまい、 意思によって打拳がコントロールを失ってしまうようなもの、 つまり、速さで粗雑さを誤魔化したような動きをいうのではない。
武術の緩急には動作の何処にも滞りのないものが要求される。技の終わりは次の技のはじまりなのである。つまり、定式(技の最後の姿勢)から、次の技の定式に至る軌跡である、過渡式が技の本体であり、定式とは、そのフォロースルーであり、フィニッシュの形に過ぎないといえる。
それと腰を廻し脚からのパワーと、体重を拳に乗せたストレートパンチのような突きに憧れるなら、若いうちは存分に稽古したら良い。ボクシングを習うのは良い経験となる。
ただ、そのような投擲の延長的な突きは、敵を打ち倒すことが出来る、有効な打突ではあるが、形意拳など内家拳が理想としている身体を一つに纏め構造的に堅固な物として放つ打法とは威力の出し方が異なり、門派のコンセプトには沿ってはいない。
これを「突きとパンチは違うもの」などと述べる者も居るが、上手く言ったものである。
また、下肢、体幹から生み出した力を、うねるように手に伝えて放つ、野球のピッチングのような力の使い方も、似ているようで実は武術からはかなり遠い。このような動作をそのまま武術の技として用いるには、あまりにもモーションが大きすぎる。野球の投手が投球する瞬間、その手の先は時速100キロにも加速されるが、現実的な突き技として、このようなうねるような力を打撃技として用いようとすると、全格闘技中最速といわれる、ボクシングのジャブですら、時速40キロ程度のものへと制限されてしまうのだ。
また武術では、自らのバランスを保つことが出来ないフォロースルーは、そのフィニッシュが居着きに繋がり、敵に乗じられることになるので避けられている。
古伝の武術の突きにおいて、キメ動作が嫌らわれるのは、同様の理由からである。敵を強く推したとして、敵に避けられたり退歩されると、たちまち前のめりにバランスを崩してしまうような突進やプッシュも、実戦では悲惨な結果となるだろう。
大きな力を発生させることが即、武術の発勁には繋がらないのである。戦闘技術の中で活かせ、敵を殺傷できうることに繋がる力でなければ、武術の発勁とはいえない。
『功夫の勁力は、正直にいえば制敵そして殺敵にある。つまりその殺傷力を論ずるものであって、破壊力を論ずるものではない』龍清剛 著 『中国拳法 秘伝必殺 鉄砂掌』より。
化勁での動きは、定式があってないかのようで、それでいてさりげなく、見識が浅い者には自己流にも思われ、出鱈目にも見えて、整勁など無いかのようにも思えるものだが、内勁によって技が発動されるため、威力は外形に縛られはしない。
比較的、さりげない外連味の無い動きを見せて、これが化勁だと謳う者もいれば、龍がうねり、蛇がとぐろを巻くかのような、奔放な動きを化勁だと見せる者の両方がいるのだが、編集者には、そのどちらが正否であるかは、個人的には断言出来かねる。他所の伝承を否定することになるからである。
編集者の師の形意拳は、間違いなく化勁に達しており、その真似事は出来るが、これだけが絶対の化勁だとは断言出来ない。
化勁は剛柔が相済しており、音を発しないという原則があるが、その内実を見極めることは難しい。
化勁に比べると明勁、暗勁を修得することは比較的容易だが、化勁は10人が10年、修練したとしても満足なものに達する者は、僅か2人程度のものとも言われている。
さらに後記する化勁の先にある、レベル4といえるような形の無い達した境地と、化勁の区別がつくほどの見識や実力も編集者にはない。
編集者の個人的な説だが、意拳や太気拳は、形意拳の化勁、そしてその達した境地を模したものだと思っている。剛柔が相済され、かたちのない姿は後で述べる、無勁の姿を思わせるのだ。
編者者のところでいう化勁は、下に動画で引用させていただいた、邸国勇師の演武のような動きとなる。
台湾に強大な発勁力で、物理的に人を引っこ抜くように浮かして、数メートルも飛ばしてしまう演武を行う、『易宗内家武學研究會』の創始者で、藩岳という、太極拳、八卦掌、形意拳の伝人で、発勁を修得したい者の駆け込み寺的に非常に人気の達人がいる。
氏が述べることを要約すると、「勁力というものは人は皆、先天的に持っており、武術の運動、特に站樁功によってその力を増強することが出来る。発勁が出来ない者ほど丹田、丹田というが、勁力は脚から生ずるのだ」と説いている。
この認識は意拳や太気拳に近いものだと個人的に編集者は強く感じる。
筋力というものは、対象に対して働く力としては補助的なものであり、姿勢によって地面からの反力を適正に導き出すことが正しいという説である。
これを「手を地面と直結させる」と表現する達人もいる。とはいえ、編集者の太気拳の師、松井欧時朗は、この藩岳や、同様の見解を述べる飛騨の山奥に住む謎の禅僧などの達人たちの手解きを受けたので、弟子である編集者も、その考え方に傾倒した理解であると思って欲しい。
とにかく、どのような説をとなえ、どのような原理であっても、結果として敵を打倒出来る発勁を、物理的に体現出来るならよいのである。体現できぬ者が蚊の泣いたような突きや発力をみせて、実戦であれば貴方を打ち倒していたと寝言を述べる例が観測されるが、そんなものは妄想である。
ちなみに藩岳は、誰もが利用出来る公園で衆人環境のなか教授しており、組手を好まれる先生である。この先生に殴られると途端に親切に教えてくださるそうなので、組手の指導はぜひ受けるべきである。
神勁(無勁)
これら明・暗・化を「三回九転これ一式」というように、繰り返し、修練することによって「拳は無拳、意は無意、無意の中にこそ真意あり」という、神と呼べる境地に至ると形意拳は説く。
これは錬丹における、錬虚合道(還虚合道)と相合する。このように、形意拳における三段功夫とは、具体的なものであり、段階的な練習法を述べたものである。勿論拳の習熟具合、それぞれの境地を表す意味でも用いられている。
『形意拳の道は内丹術の学びに似たところがある。 三易というものがあり、それは練精化気、錬気化神、錬神還虚である。拳術にもまた三易があり、易骨、易筋、洗髄である。 すなわち明勁、暗勁、化勁である』『拳意述真』第四章 郭雲深論形意拳 第四則から意訳。
とはいえ、現代では三層道理で説くように順繰りに勁を練るシステムは、あまり一般的な稽古法ではないと思われる。
動作と呼吸を一致させ、発声を伴わせることも、現代では殆どみられない。極々稀に、雷声を用いた表演を行う者もいないわけではないが、おそらく形意拳では、その源流となった、戴氏心意拳ほどの多種多様な発声法はないと思われる。
勿論、表には隠しているというのもあるだろうし、最初から達人の達した無声無音の姿を理想としているというのもあるだろう。
雷声とは、気合のようなものとは異なり、横隔膜で腹腔を圧縮させるように発し、動作と意念を一致させ、発勁の補助とする技法である。
腹圧によって自然と吐き出される吐気を抑えたり、それに独特の音を乗せるのである。陳氏太極拳における、意声と同様の目的のものである。編集者の形意拳では、五種類のものが伝わっている。これらの用法は打突を放つ方向や距離、用途によって変わってくる。
注意としては、形意拳でいう明勁、暗勁、化勁とは、太極拳や八卦掌、八極拳でいうところのものとは概念が全く異なるということも留意して欲しい。
これらは混同されやすく、中国武術の修行者同士でも話がさっぱり通じなくなることがある。
形意拳以外では、暗勁は、外部から勁道が見てとりにくい発勁や、接触状態から発せられる、寸勁、分勁、零勁の類を指す。
太極拳で化勁とは、内力における分力法や角運動、つまり、慣性モーメントに加算される、角速度等を利用して、相手の攻撃を逸し、無力化するような技法をいうが、形意拳のものは上記の通りである。
一説によれば太極拳でいう化勁は、形意拳のものの誤用であったとも言われている。
達人の境地であるとして、浸透勁だ、なんとか勁だと暗勁の類の威力を、ことさら神秘の技のように喧伝する者がいるが、たしかに外郭(人体の外側)を打ち貫き、内郭や背中にまで威力を通す打法は武術にはある。しかし人体でも固定されたものであっても、運動の第三法則に則り、打てば自分に反作用が返ってくる。
その緩和、緩衝のために半ば架式があり、自らの打突で、自分が突き飛ばされるような事態を防いでいるのだが、大木のようなものをチョンと触れて、全く反作用が返って来ず、あとから木がバッサバッサと揺れだして、葉が落ちるなどという光景は、マンガの中だけと、武術家が弟子に喜んでもらうために好んでいう、冗談の中にだけ存在する白髪三千丈のお伽噺である。
昔は技術書でさえも、読み物として面白くするために、ゴーストライターや編集者が提案して、面白おかしく大げさに書いては、読者を楽しませ、ロマンを掻き立てたものであるが、それはそういう時代ゆえの罪のないサービス精神である。そこは察して読むように。
武術の達人の非現実的な逸話の多くは、砕けた表現になるが、とてもこの人、どうみてもヤクザとなんて戦えないなというオジサン(武術家に多い)が、酒の席で酔っては、先輩、知人から聞いたことを、ふくらませて語る、法螺話しの武勇伝とさほど変わらないものである。
達人がいう「私が打てば人は死ぬよ」という類の言葉は、概ね愛嬌のある戯言である。いちいち真に受けて真剣に聞いていると、師を喜ばせるかもしれないが、冗談を理解できないと武術を学ぶ躓きの元となりかねない。
発勁で特に注意するが、武術では僅かに触れられた者が、簡単に跳んで行ってしまったり、それどころか触れられていないにも関わらず、操られている光景がよくみられるが、あれは一種の自己催眠、共感による感応のようなものである。
稽古の中で、自然と師の技を察して忖度し、跳んでしまいたい気持ちになるのである。面白いもので、物理的な発勁や技としてまるで成立していない触れ方では、武術の稽古を積んだ者が感応することはまずない。
編集者の形意拳の師も、編集者から威力のある分勁(ほぼ接触状態から放たれるワンインチパンチの一種)で打たれると、威力が突き徹る前に、声を上げて自ら後ろに大きく飛び退んでしまう。それで怪しみ、今度はいい加減な打ち方をすると、師は全く反応せず、ちゃんと打ちなさいと注意されるということがあった。
太極拳ではこれを、凌空勁(もっと高度で神秘的なものであるという主張もある)などという。その他にも自分より上級者に技を掛けられると、自然と余計に忖度してしまい、触れられずとも技にかかりたい気持ちになったり、それが癖になっていたり、腕を掴ませる、掴むなどの限定した条件を定めた上で、例えば、相手から崩されやすい方向や角度で、上手く曳かれたり、崩し技の際に、一度ある方向に圧をかけ、それに対して相手は抵抗し、バランスをとろうとして硬直する生理的な反応を利用するなどして、さらに力の方向性をきりかえし要領よく技をかけると、とくに回避を試みず(技から逃れる方法を知らない例もある)に簡単に技に掛ってしまう、あるいは、このまま技を掛けられ続けると、関節を傷めるので、たまらず自ら転がって投げられるようなこともよくある。
門外漢には奇妙に思われるかもしれないが、あくまでも練習の一環であり、本来は怪我を与えず技を稽古し、その練度を確かめるのに、都合の良いものであるので行われるだけである。
これらの稽古を意味のない、旦那芸であると断じ、嫌う向きもあるが、組手や実戦に活かせる技法となっている。実際の使用においては、必ずしもそのままの形で使用されるものではない。実戦では構造的に強い姿勢を作ることで自らの手の重さを効かせ、敵の防御とバランスを僅かに崩しつつ打つのである。
ちゃんとした崩し技や立ち関節技は強烈なもので、掛けられると一瞬で重心を浮かされたり、簡単に関節を破壊されるものである。その為、逆技や崩し技の稽古には相手への加減とお互いの信頼が必要である。
ちなみに、稽古の際に発勁で身体を打ってもらうことを、食勁という。師や仲間、弟子から打たれ、技を掛けられることで技に慣れ、技を掛けるコツや技から逃れる破法が身につけられるのである。
論外だが練習によって、達人風の演出して見せる、詐欺まがいの演武もある。それらには構造的に強い力を作っているようでもなく、バランスを崩すような動きも全く見られず、技を掛けるタイミングを見計らっていたり、視線で合図をしていたりするので、玄人ならすぐに察することが出来るが、しかし多くの武術未経験者は、それが武術の原理を以て魅せた技なのか、アトラクション的な見せ物なのかの見極めすら付かないのである。
さらには弟子が完全に洗脳されたようになっており、師が指をぴっと振ったら、遠くに立っている弟子たちが一斉に飛んでいったりというような信仰の高さを示すような演武をみせられると、武術の未経験者すら困惑してしまう。果ては、このような演武をみて合気や立ち関節技はインチキで抵抗する敵には通じないと、勘違いする者さえ出てしまう。
最低だが、空気が読めず技が掛からない生徒に、道場を辞めてもらうように圧力をかける先生すらいるという。
強い架式を作る練習として、非常に有効であるが、弓歩などの架式を使って、複数人で強く推しても大丈夫という演武(腰相撲)も、各人があまりにもバラバラに、本気で好き勝手に押し出すとまず成立しない。
そして、真剣白刃取りのような、武器対素手の演武においても、剣を振る方の熟練、加減の具合がより肝要であるという。
ちなみに、特殊部隊の隊員同士でナイフで模擬戦闘を行うと無傷では済まず、互いが刺されてしまう例が多いという。
これはある稽古会で確かめられたことだが、武術家同士が集まり、検証のために、刃引きの日本刀などを使って、徒手で本気で刃物を自由にふるう者を、相手取る稽古を行ったのだが、結果は、実力の高いと知られる武術の指導者、武道の高段者たちでも、何度となく容易に斬られ刺されてしまい、徒手で武器への対抗など、ほぼナンセンスなことであり、現実には非常に難しいことが判明した。
疑問なら、空の500ミリのペットボトルをナイフに見立てて、ナイフ獲りの稽古をしてみたら良いであろう。
これだと怪我をせず安全だが、間合いの中で自由に突かれると、防ぐことが困難であることがすぐに分かるであろう。やがてタイミングを察して目が慣れて、ペットボトルを奪えそうになると、今度は相手は奪われる前に反対の手に持ちかえて突いてくるのだが、これでまた振り出しに戻るわけだ。
また実際の刃物では腕を深く刺されれば防御すら困難となる。前腕の動脈を斬られれば、放っておけば死に至るものである。これらのことも考慮して稽古してほしい。
この稽古ではナイフ取りは何十回とやって、やっと成功するものであることが実感出来るであろう。
しかし現実には命は一回しかなく、失敗は絶対に許されないのである。失敗したのなら、稽古と違い次はやり直すことなど出来ないのである。
対武器術への過信は非常に危うい。たとえば、昭和のヤクザ映画の中でよくあったように、白木の鞘のドスを抜いて刃を逆さにしたヤクザと素手で戦って勝ったよというようなことを、ペラペラと豪語して述べるような者の与太話に惑わされないように。
白木の鞘は、実戦での使用や試斬に用いるものではなく、刀を錆びさせないように長期保管するために用いる容器にすぎない。その柄にも実戦で用いることを想定した強度や、クッション性などはない。
おまけに鍔がないために、手を滑らせると簡単に自分の指をも切断しかねない危険な代物である。このように前提として絵空事なのである。
武術で稽古される空手奪刀や空手奪槍(銃を奪う練習)は、そのような型もあるという程度の認識とし、過信は厳禁である。
プライバシー上、誰とは具体的にいわないが、本当に刃の中での実戦、多くの喧嘩の中をくぐり抜けた武闘派は、おとなしい文人タイプなどではなく、抑えられはしない恐ろしいまでの相応の気迫があり、一目で敵に交戦を避けさせる怖さがある。
例として編集者が教えを受けた喧嘩十段、故芦原英幸師の写真を下に掲載する。
このような武闘派は、その武術に対する言動には愛があり、武術に対する言葉は軽薄さとは無縁で重厚である。
刃物は振り回されるだけで素人、か弱い女性や子供さえも侮れない敵と変える恐るべき凶器である。けして甘く見てはならない。編集者は餓鬼の頃の喧嘩で右前腕を刺され12針も縫う破目になっている。ちなみに当然の話しではあるが編集者が交流した、名のある強い武術家たちでお聞きした限り、武器相手にあえて素手でやると述べた者はただの一人もいなかった。
だというのに、身内の間でのことで増長して、技に掛かる気が無い外部の者に対して、凌空勁や無刀取りのようなものが掛けられると思い込み、悲惨な結果になる例も、枚挙にいとまがない。
驚くことに長い武歴のあるはずの武術の指導者すら、こうした勘違いをするのである。
自らの技に絶大な自信があり、その技を信じられるということは、ある意味ピュアであるともいえるが、人が驚くような神秘的なパフォーマンスを得意げに魅せる者が、あっさり惨敗してしまえば、仮に優れたところがあったとしても、世間からは、ただインチキ武術家の一言で後ろ指さされることとなるだけである。
勝敗は武術家の常であるので、試合に負けるときもあろうが、神秘的な技を魅せておいて無惨に負ける姿などやたらと披露することは止めていただきたい。
錬功法 :静功・動功・排打功
站樁功(静功)
形意拳の基本功(基礎となる稽古)は先ず、内功を鍛える站樁功(たんとうこう)、日本風にいうと「立禅」という。樹木の真似だとされ、自己が地に打ち込まれた杭であるかのように立つ稽古からはじめる。
参考としてこの項目で紹介している、意拳・太気拳の大関智洋師範と、松井欧時朗師範、島村尚武師範の教習ビデオは、站樁を学ぶ上において、最適の資料となるものと思い推薦している。(現在ニコニコ市場の廃止により、商品の掲載は停止されている)
意拳・太気拳は形意拳から生じた分派で、形意拳と共通した教えを色濃く残した実戦的な武術である。
人は日常、自然に直立し、歩行することが出来るが、実験では人間の身体の質量配分と、姿勢を再現した物体を立たせても、直立させることは出来ないという。
この結果は、立つという行為自体が、勁力の働きの上のものであるのだから、至極当然のことであろう。つまり站樁も、身体の各個重心を最適化させるバランス制御と、そのための筋肉の力が必要不可欠な、運動であるとういうことを述べておく。
先ず最も基本となる「無極勢(預備式)」は、肩を下げ腕を自然とおろし、足を揃えて真っ直ぐ立った姿勢、並歩である。要領は拙力(強ばったような不器用な力)を抜き、気(意識)を下丹田に沈める。上虚下実ともいう。この姿勢を立正式ともいう。ここから「渾元椿 :こんげんとう(別名を「熊抱式」、「定勁樁」、「三円式站樁」など)」や「三体式站樁功(別名を「子午樁」など)」に移行する。
なお下丹田とされる場所は、東洋の武術にとって重心の要であり、形意拳では下丹田が人体における無極とされる。真っ直ぐ立った場合、人間の重心の位置も、だいたいこの場所にあたる、骨盤内の仙骨のやや前方にある。重心位置を足底から計測する方法があるが、平均的には成人男性で身長の約56%、女子では約55%の位置に重心はあり、重心線は後頭隆起から内くるぶしの間(重心点)となるが、重心は姿勢の変化によって胸の方にあったり、身体の外にさえ移動するものである。つまり混同されやすいが体重と重心は異なるものである。
渾元椿は、無極式の足を揃えて立った状態から、左脚を自分の肩幅の広さの位置に移動させ、両脚を肩幅の間隔に広げて立つ。爪先の向きは平行か、やや外側に向けてもよい。膝は軽く曲げる。高い椅子に腰掛けるように立ち、堤肛といって肛門を引き上げるようにする。
股関節、胯をゆるめ上体は後ろに仰け反ってはならない。体重は爪先より湧泉穴のあたりにかかり、足の指で地面をつかむように、踵は紙一枚分浮かすように立つ。踵に虫が居て、その虫を逃してしまわないように踵で抑え、だが、虫を踏み潰して殺してしまわないようにともいう。両脚の間で球体を挟んでいるようなイメージを持つ。
注意としては脛の内側、内踝の拇指球、土踏まずに力がかかるように立ち、足の小指側に力を逃さないこと。これが平歩である。ここからさらに胯を折り腰を落とすと馬歩となる。
馬歩站樁は通常、肩幅より広い歩幅で行う。ちなみに太極拳などは一般的に踵重心を説くが、つま先重心も踵重心もどちらも正解である。ただ「双重の病」と呼ばれる、空きのある居着いた状態を嫌っているのであって、臨機応変に動ける体勢であるのなら問題とはしない。日本においても、剣豪宮本武蔵は、居着くことは死ぬことであると説いている。
站樁中は最小限の姿勢を維持できる緊張を求めて、余計な力みを無くすこと。下に沈み込む重力の力と、それに対抗する上に押し上げる力(上下の力:この力が一番重要である)、物体を推すときに生じる前に倒れようとする力、この力に対してバランスをとろうと、後ろにもたれるかかる力(前後の力)という相反する力を感じ、それらが理想的につりあった姿勢と、自己の重心をときおり内観すること。
次に両腕をゆっくりと上げ、掌を肩の高さから胸の高さにもっていき、両手の指先を互いに向き合わせ、腕全体で大きな球体を、抱きかかえるような姿勢をとる。両手の掌の間隔は、拳2つ分~3つ分程度開け5指を開く。掌でも柔らかく温かいボールを掴むように思い窪ませ、開いた指の間にも、真綿のクッションが入っているように思い適度な間隔を開ける。
これを大樹を抱きこむようになどともいう。初心では仮想の球体は、強く抱きしめると壊れてしまう脆いものであるが、保持をしていないと、落としてしまうものと思い、適度な圧を求める。
ただ静かに立つだけではなく、大樹を抱き込むときは、その樹を強く引き抜く、埋め込む、まわしてみるなど強く思い、動くようで動かない、動いていないようで、動いているという運動(揺動法)を試したり、そのボールが暖かなものであると思ってみること、ボールの弾力や質量の増減を思ってみる。
ボールが膨らむ縮む、ボールは右に回っていく力が掛かるのを、自分は左に回していくなど、相反する力を素速くきりかえる、あるいは、全ての方向に力がかかるなど、様々なイメージングを行うこともある。この際、自然と身体が震え、微動してしまうことがあるが、これはあえて意図的に行うものではない。
しかし、武術的な効果をより早く得ようと、これら意念を用いた練功などをやりすぎ、精神にストレスが過剰にかかると、気功偏差という精神や身体への病態をまねくことがある。その場合は意念を強く用いる稽古は絶対に止めるべきである。
站樁でありがちな間違いだが、視線は遠くを視て目はけして瞑らないこと。過剰な上気を防ぐため顔の力を抜き、眉間にシワをよせたり絶対にしてはいけない。目を閉じれば気は迷走するものである。
顎を引き口は軽く閉じ、舌先は上顎の齦交穴の辺りの裏側につけておく。喉、首は力まず、緩ませる。こうすると、さながら美味しい水を飲んでいるような気分になることがあり、口のなかに唾液が自然と出るが、気功では、これは身体に良い反応とされ、わきあがる唾液は飲んでおく。
これら身体の力を抜いて緊張を解くという教えは、別の言い方をすれば、最小限の緊張を心がけよということである。
気功偏差では恐るべきことに、最悪、統合失調症のような症状となり、正常には戻らなくなることがある。
初期の症状としては、躁状態となり妄想、妄執が強化され、根拠のない万能感に囚われる。怒りっぽくなり他人に対して尊大、傲慢に振る舞うが、本人はその異常に気づかない。
偏差で人が変わってしまったようになる者はかなり見られるのだ。これを防ぐため無理はせず、気を下に落とすように心がけ、稽古中に何かを視たり、思いが起こったとしても、それはただの現象であるとして、起こることについては、一切何も思わない、連想しない、追い求めないことである。
もしも坐禅中に仏陀や観音がみえたとしても、それは悟りからは程遠く、槍で突き殺せとまでいう教えがあるほどである。
「気」や「丹田」の感覚というものは、自分の精神、即ち脳が作り出している、動作や姿勢の指標のひとつと考えるのがとても健全である。
統合失調症を患うと、体感幻覚、幻聴など、物理的に実際には存在はしないものを感じ、非現実的なあり得ないことを信じ込んでしまうが、人は禅のようなメソッドを用いて都合よく神秘を求めると、統合失調症患者が普段見ているような光景を見て感じることが出来ることも可能で、やがて、その世界に染まり戻れなくなるかもしれないということである。
心の底から忠告するが、たとえば私が気を与えたから成長があった、遠隔で丹田を調整したので、試合に勝てたというようなことを平然と述べるような先生たちからは、物理的に有意義な技法が学べるとは到底期待出来ないので即座に離れるべし。
それどころかその狂気に狂わされてしまうことであろう。そんな馬鹿なと思って冷やかし半分で近づいた者が「ミイラ取りがミイラになる」の諺の如く、とりこまれてしまう悪例もみられる。
困ったことだが、武術や気功が自己啓発やニューエイジ思想、スピリチュアル趣味などと結びついて、まるで夢を操ることで、現実をも変えることが可能だと説く、メキシカン・トルテックの魔術か、エドガー・ケイシーの超能力まがいの様相をみせ、新興宗教めいたカルト集団化をしているケースが割とあるのである。
日本古武道でも、これがある場合があり、初印象でその道場に新興宗教めいた雰囲気を感じたならば、そのことを忘れず、その信心業には深入りしないほうが良い。
もし自派の武術の到達点が霊能ありきで、夢見術や霊を憑依させることなどを言い出しているなら、それはもう呪いや信心行の世界であって、伝統的な武術の範疇から極めて逸脱したスピリチュアルなものである。
かつて同様な夢見術などを行っていた、オウム真理教の例をみれば、いずれ外に対して害をなし、先の危うさを感じさせる筈だが、こういった非常識に危険性を感じさせないように誘導し、安心させ、依存させるのがカルトや占い師の得意とするところである。
神霊を降ろすことが出来るという者が降ろす霊は、大抵のところ狐狸の類であるという。低級な霊ほど自分を偉大な神であると称するものである。
ちなみに神道では、神降ろしを行った者に対して、知恵者2人が質問攻めすることで真偽をはかるという。キリスト教では悪魔憑きほど神を語り、神のことをよく知っているが、嘘や利己的な物言いは隠せないものだと言われている。憑いた者を増長させ道を誤らさえる点にいては、霊的な存在もまた詐欺師と変わらない。
詐欺師は傲慢で、俺は騙されないぞと思っている、半端な知力を誇る者を狙う。俗に学校の教頭先生だとか、ワンマン社長らがその犠牲になると言われている。
邪な者は、とくにターゲットが生活に行き詰まったのを見て、親切に親しげに懐に入るものである。例えば善い人アピールをしながら、自分に心服させ、比較例として実際に善行を行う者を出汁として貶めては、自分は何かやったかのように振る舞うが、実際は善行などやったふりをするだけで何もしていないのである。
手口は占い師と同じで、自分の養分となる者の気持ちを察しながら、その望む答えを優しげに与えているだけの話しである。
性善説の観点から考えると、彼らは想像を絶するほどの悪辣ぶりである。武術界隈の詐欺師でも同じである。重ねて注意喚起をする。編集者は、宗教やオカルト自体を否定するものではないが、伝統宗教の本物の宗教者や求道者の信仰は犠牲を伴いニューエイジやスピリアル系のような、ライトなものではないことを知っている。
話を戻すが站樁の際、上から吊り上げられることと、下に落ちていく重さの上下の力を同時に感じ、また前後、左右からの力も感じてほしい。
内部が充実した弾力をもつ張る力、太極拳風にいうと、掤勁(ぽんけい)のある状態を求める。
ただふぬけたように、力がぬけ柔らかいだけで眠くなるようでは、その站樁にはリラックス効果以外のものは無いと思われる。
気は昇り滞ると精神は破壊され、降りて留まるままならば心は呆け、精神は弱体化するといわれている。
意識を全身に巡らせること。それでいて気を高ぶらせず、意識が落ち着いてくつろいでいる状態で立ちその感覚を求める。
特に注意しておくが1990年代以降、日本の古武道研究家らがよくいうようになった「脱力」という、日本語の表現から導き出される姿勢や動作は、必ずしも古伝の武術の要求とは合致しない場合も多い。
一例としては日本語で「腰」というと、腰の骨盤と、腰回りのベルトを巻く部分の腰椎のことを指すのだが、中国では骨盤から腰背部にかけて、腰椎から胸椎の下部までの広範囲を指すものとなる。
中国武術は外国の武術であるので、その理解には中国語やその専門用語は覚えておいたほうが懸命である。
中国武術で基本となる稚力を抜いた状態、放鬆(ファンソン)と表現されるものとは、力が抜けきったものでも、気が抜けたものでもなく、柔らかさのなかにも張りのある状態をそう表現したものである。
古人は柔を極めれば剛となり、剛を極めれば柔となるとたとえた。理想の真の柔とは太極拳でいう綿中蔵針が近いのかもしれない。この放鬆の状態を得るために、わざわざ力を発する練功法まで行う門派さえあるのである。
站樁をどれくらいの時間、どの程度の強度で行えばよいかであるが、自然な力を求める渾元椿は特にだが、前提として無理に長く立ち続けることは求めない。站樁は苦練を課す、空気椅子のようなアイソメトリック・トレーニングではない。
10分立てるのであれば、立てばそれで良いし、2時間立つ気分ならそのように自然と立てば良い。編集者の会ではいわないのだが、参考として形意門のある派では、40分程度を薦めている。ちなみに太極武藝館では5時間は立てるくらいでないと、本物ではないといわれていた。
長く立つことを俗に、站樁マラソン(立禅マラソン)ともいうのだが、たまには気軽にチャレンジすると面白いものである。
渾元椿を行うと肩の高さ、胸の高さで抱球姿勢を維持するのが難しいと感じるなら、手の位置を下腹部のあたりに下ろしても構わない。しかしどういうわけか、すぐに肩が痛くなって姿勢が保てず困難に感じるなら、自己の筋力的虚弱さを疑うか、腕の上げ方に無理があることを疑うと良い。
肩を落とし肘は適度に下げ、肘の下からも弾力を感じ、背中に意識があり肩甲骨を開き、背中から腕を上げ支えるかのようにすると、外部からの圧に強い抱球姿勢が作れ、疲れにくくもなる。これを、球気背抜という。
試しに練習相手に自分の正面に立ってもらい、抱球した両腕を左右から手で推してもらうと、簡単にパタンと潰れてしまったり、逆に両腕を開かれると、容易く抱球を保てないというなら、この球気背抜が全く出来ていないということである。
また脚についても、重心が適正に落ちているのならば、平歩で立った脚は重くなっており、練習相手に片足を掴んでもらい、脚を外側方向に開くように引っ張ってもらったとしても、そう簡単には架式を崩されない強い力が働いていることが、自分と練習相手の双方に実感出来るはずだ。
あと渾元椿で立った際、練習相手に前から手を推してもらうと、容易に抱球姿勢が潰される場合、それは腕の力が負けているのではなく、適正なバランスがとれておらず前後の力が弱いため、推されて後ろに倒れてしまうことを、抱球姿勢を潰すことで自ら回避しているのである。
日々、站樁を継続していけば20分、30分と自然と楽に立てるようになっていく。先ず5分を目標に気楽に立つことを勧める。腕が疲れたら意拳の休息樁のかたちで、手を腰の後ろに置いて休めの姿勢のように休みながら立つのも良い。
正しく站樁を行っていると、気感といって、手や全身の各所、あるいは意識に何らかの感覚がわき起こることがあるが、前記の気功偏差を予防する意味で、これを追い求めることは絶対にしてはいけない。
極端な例では屋外の薄暗い場所で站樁を行っていると、突如周囲が明るく見えてきたり、自分がなんでも出来るかのような万能感がわき起こるようなことさえあるが、特に気にしないことである。
武術の強さというものは、敵とする相手との相対的な実力差が基準であり、たとえ、このような神秘体験紛いのようなものがあったからとしても、実用に足る強さが得られたわけでは全くないことは、特に留意すべきである。
呼吸は自然に行うが、最初落ち着かないのであれば自分の吸って吐く呼吸を観察する。周囲の物音は意識せずだが自然と聴いておく。その時、たとえ突然床に針が落ちたなら、その物音にさえ、いつでも敏速に反応出来るほど意識がめぐっている状態が作れるのであるなら尚良い。
あるいは深くリラックスを求め、自分が風景の良い山頂に立って見下ろしているかのような雄大な気分、馴染みのお店で寛いでいるような、気張らない気持ちを思い出す。シャワーを浴びているかのような、心地よい気分で站樁に臨むことである。
站樁は鍛錬することと、休息することが一体となった気功である。
無我無心であることが望まれるが、無心になろうとして無心を作り出そうとしても、最初は難しいのである。站樁の要求を意識し、ひたすら没頭することで無心になれるのである。
最初は脚が痛いとか、腕が辛い、周りが煩い、今日の晩飯は何を食べようか、ラーメンにはチャーハンを付けるべきだなどと、とりとめのない雑念が起こって自然であるが、気を丹田に落とし、自己の姿勢を正して寛ぎ、ひたすら站樁という行為に没頭し、観たものは観たまま、耳に入る音は聴いたまま、あるがままを感じることで、やがて無心となっていくことが可能になるのである。なにか思ってもそのままにすること、それについて一切連想しないことである。
禅の考え方において、例えば誰かに不意に手を自分の顔の前に差し出されたとしたら、頭ではそれが手であると認識されるが、そこに見える物体以上の意味を求めることはしない。
手と呼んでいる言葉も人間がそう呼称し、そうだと自他が勝手に認識しているだけのものに過ぎない。あらゆる事物は宇宙の中で唯一無二の存在で、何かを説明した言葉や思いは、それそのものではない。手を見たとき自分が手を見ているという思いの内容も事実ではなく、これは既に事実を言語で説明したあとのことであり、現実に存在する手とは異ったものである。
自分が手を見ているというのは頭の中の思いに過ぎない。手は観察の必要はなくそれだけで今ここにあるものである。
迷いの根本とは思いの内容を事実として誤解してしまうことにある。あるものをあるがままに認識できる落ち着いた心の状態を禅では無我という。これは心を楽にしてくれる考え方であると同時に武術の奥義にも相通じる状態である。
武術において現実を正しく認識するということは死活問題である。古来、日本の剣術には「合気断つべし」という教えがあるが、これはある一定以上の技量の者が試合うと、敵に対して感応のようなものが起り、敵の動きに反応して自らが動き、結果敗れるという問題を警告したものである。先人はその解決法として禅や站椿を答えとした。
站樁功は、養生のための気功、心地よい健康法であると同時に、重心の感覚、整勁を知り鍛錬するための最重要の練功法である。
站樁が理解出来なければ、敵を打ち倒すことが出来る実用に足る技の修得には、時間が掛かるであろう。これはけして大げさに述べているのではない。
とはいえあまり気張らず、樹木に囲まれた公園などの落ち着いた場所で気軽に風を感じながら、のんびりやってみたら良いだろう。
『ネット上には、『武術としての立禅』をまことしやかに語っている胡散臭い輩が多い。
あまりにも多いので、いちいち目くじらを立てることさえアホらしい。
しかし、そいつらが本物か偽物かを見抜くのは簡単だ。
素手素面、何でもありの屋外での組手・・・とまではいかなくとも、
最低でも、他のプロ武術家やプロ格闘家と、
いつでも躊躇なく『ライトスパーリング』くらいはできるかということ。
そういう場に誘ってみれば、すぐに化けの皮は剝がれる。
武術家を標榜しながら、ぐちゃぐちゃ言い訳をして逃げるようなら論外。
「私は、スイッチが入ると、もはや自分をコントロールすることができない。私が、本気になったら、相手を怪我させ、場合によっては殺してしまいかねない。危険だから私は立ち会いはやらない」・・・などと嘯いている輩は、紛れもない『正真正銘の偽物』だ。
幼稚園児と戦って、本気で殴り殺す大人などいないように・・・自分の脳もコントロールできなくて、どこが武術だ?本当にそういう制御不能状態ならば、脳の機能障害を疑ったほうがよい。
今すぐに、病院に駆け込むべきであろう。
賢明な諸氏は、くれぐれも、そういう輩の戯れ言に耳を傾けてはならない。』三保俊敬太気拳創始者 澤井健一の直弟子。
動功
站樁で得られたような整った力を壊さず、円滑に動かし、勁力の運用にフォーカスした練功を行うのが、動功での錬功法ある。これから本格的に套路を学ぶ際の基礎的な勁力、身体の強靭さを養う意味もある。
極初歩の錬功でとても有用なものに、甩手(スワイショウ)という手を前後に振ったり身をよじって勢いをつけながら両腕を、でんでん太鼓のように振るなどのものなどがあるが、その説明は形意拳に限らず、中国武術や気功では極一般的なもののため、ここでは解説を省略する。
本記事では、動功の中で特に効果の優れたものの一例として鷹捉把功を紹介するが、この他にも、定歩、平歩での五行拳の練習など、様々な基本功・練功法がある。
武術では、型や用法はいくらでも明打(文打 表技のこと)といって、一般公開用に動作の要点を省いたり、殺傷効果の高い技法を隠して見せることがいくらでも可能だが、練功法は知られてしまうと要点が隠せないため、有用なものが外部に公開されることは稀である。
それと、たとえ功夫を積んだとしても明打はけして暗打(武打:明打よりも技撃として優れた用法・套路)にはならない。
最初から理に叶わないもの、殺傷力に欠た技は、たとえそれを1万回繰り返して稽古したところで、合理的な技に昇華されることはありえない。目的地を間違った航海は迷走するだけである。
生徒に用法を教えるが、それが敵の反撃を前提とするものではなく、ちょっと身を捩られると外されてしまうような、明打以下のものを教えておいて、「技が決まらないのは、お前の功夫が足りないからだ!」などと述べるような指導者は、はじめから技をかけるコツも、暗打的用法も知ってはいないし、おそらくそんなことは眼中の外にある。「俺に技を聞くな!」という指導者について学ぶのも徒労となる。
優秀で本当に実力のある指導者は、生徒から訊ねられると、有効的な用法をその場で様々に、即興的にやってみせることさえも出来るものである。
鷹捉把(定歩双劈掌)
先ず三体式で立つ。三体式の手の構えから両手でさながら、鷹が爪で獲物を掴んで捉えるかのように、あるいは手で水瓶の口を掴んで引き上げるように、自分の顔の高さまで手を上げたら、そこから緩やかに前方へ両手を打ち下ろしていく。
引き上げる際は、後ろ脚に体重がかかり身体は若干沈み開いていく。打ち下ろす際に身体を合わし前脚の方に重さが加わっていくが、前脚をさながら地に釘のように刺すように固定し、足、背中と伝わる勁力を、ロス無く送り出す。これを何度となく繰り返して練習を行う。脚が疲れたら軸足をかえ同じことを続ける。
呼吸は引き上げるとき吸っていき、打ち下ろすとき吐いていく。この時の呼吸法は自然と逆腹式呼吸のようになっていると望ましい。
言い換えると吸うときにも吐くときにも腹に力があると言っていい状態である。
ゆっくりと緩慢に手を振っていくのも良いし、速く振り下ろしても良い。そのときは腕が空洞で中に水銀の塊があり、振る際に手先にその水銀の塊が移動するかのように瞬間的に鋭く発してもよい。
この際、唸り声のような念音と呼ばれる、雷声の初歩的発声が自然と生じることがある。これは身体の内部で湧き起こる力を、勁力として具体的に外に発する練習となる。この雷声で起こる横膈膜の運動が下肢、丹田、背中からの勁力を滞りなく円滑に抹消へと伝える補助となっているといわれている。
この錬功法の意義は、形意拳でベーシックな発力である、丹田・脊椎を中心に縦回転で放たれる勁力(翻浪勁)を生み出す方法を、この練功法でもって感覚的に身につけさせ、勁力の増強をもはかるものである。
同様な錬功法に、やや語弊があるかもしれないが、意拳の扶按球試力、合気道の船漕ぎ運動がある。鷹捉把は動作としては前者とほぼ同じものである。
排打功(対打撃免疫力)
気功を実践し内功を積めば外功(硬功)と同様な効果が得られるので、外功は不要だとする説があるが、内家拳も古来は外功も非常に重んじはれていた。
外功も高度なものになると内功と化すともいわれている。いわゆるこれは硬気功である。
下に掲載した写真は形意拳、八卦掌、太極拳の達人として日本の武道愛好者たちの間においても知名度がある、王樹金師の排打功のデモンストレーションである。
CIAのエージェント、ロバート・スミスに全力で身体を突かせている。
他にもボクシング世界ヘビー級王者ジャック・デンプシーは、王の腹を突き手首を痛め、驚嘆したデンプシーが多数の練習生を王の元で学ばせたという逸話や、ヘビー級王者のジョージ・ルイスが王との試合を希望したが王を殴っても微動だしないことに驚き、試合をとりやめたという、その驚異的な排打功の力を示した例がある。
武術では攻撃目標として敵の構える腕を狙うことは常套手段でもある。
たとえば腕を叩いて入り、さらに反対側の手に換えて、もう一度敵の腕を打ち、防御する方の手と攻撃する方の手を、素早く入れ換えて敵の腕を封手する、換手法という技法がある。
換手は武術の愛好者たちの間では、螳螂拳や詠春拳、ジークンドーのトラッピング等で用いられる例がよく知られているが、中国武術に限らずこのように両手を連環させて攻撃、防御を行う技法は、我が国の武道においても沖縄空手や本土の伝統空手で型の分解の中で示されており、武術では至って普遍的な技法である。
換手は受け技の一種のようでいて敵の防御をきり崩す攻撃技でもあり、上級者が行う技にはまるで寸勁でもって腕を打たれたかのような、痛烈な威力が伴うこともある。
換手法どころか腕を打たれる練習を一切せず、鍛えられていない腕をしていたら、腕に重さを乗せることが出来る上級者相手には、ただ単純に剛的に突きを受けられた程度のことさえでもダメージを喰らわせられ、たちまち戦闘不能とさせられる場面でさえよくあるのである。
腕など打たれてもそんなの平気だろうと疑問ならば、試しに二人一組になって、お互いの腕と腕とを強く勢いをつけて、ぶつけ合ってみては如何であろう?
試されたらかなり痛くそれだけでも腕を動かすのが辛くなることだろう。
ちなみに編集者の友人で少年時代に家庭が極限状態の貧困に苦しみ、覚せい剤の密売人のボディーガードをするまで追い詰められた者(今は足を洗い他人にも心優しいパパである)は、実戦では敵の構えた腕を狙って撲るという戦法を好んでいた。
腹部の排打の方法であるが、これはただ腹筋を固めて耐えると誤解されがちだが、衝撃力を逃がす工夫が絶対に必要になる。
まず第一に姿勢が要となる。 三体式のような架式自体に打撃力を背中側、下肢へと逃し内郭にある内臓を守る防御力が備わっているのだが、これを上手く活かすのである。堤肛縮腎といって肛門を引き上げ、腰背部を適正にしておかなければならない。
腹部の打撃に対して腰を過剰にくの字に曲げて耐えたり、腹をはり腰を反って耐えようとすると、打撃による衝撃は、内臓を収めている骨盤の作る椀状のスペースによりこもる事態となってしまい、かえって余計に効かされてしまう破目となる。
敵の攻撃にさらされているときであっても、普段の稽古のときと同じように、身体は緩めているが上盤の重さが下盤にしっかりのっており、腹には自然と圧がある上虚下実が出来ている姿勢を心がけることである。
適正な姿勢で立ち胸を空とすることで、腹は自然と実となり、態々腹に力をこめなくても衝撃を反発させ、消化させることが可能となるのである。
さらにこの補助として、打たれる際に雷声(念音)を発して横隔膜の働きを利用すると、加えられる威力の程度と自分の練度にもよるが、前蹴りなどでみられる持続的に伝えられる強い衝撃をも、内部に突き徹ることを緩和させることが出来るのである。
この他にも壁に頭部を打ちつけて鍛える、少林七十二芸のうちの鉄頭功も、一般には単に頭突きの威力を高める為に行われるものだと誤解されやすいが、本来は敵に打たれたり投げられた際の衝撃に備え、それに慣れるための目的で行われた排打功の一種である。
排打功として有用な初歩のものに、中国武術においては極めて広く行われているスワイショウと併用して行う方法がある。
スワイショウで勢いをつけて手を振り回す際に、腰背部や肩を掌で拍打するように打つのである。
本格的な排打功の方法としては、自分の腹や顔を軽く自分の拳で打つ。掌で軽く全身を拍打する。樹木に上腕や身体を適度な強さで打ちつける。立った状態から極力受け身をとらないようにして地面に倒れる。練習相手と互いに前腕や背中を強めに打ちつけ合う。腹を軽く突き合う。顔を当て止めのような要領で軽く突き合う。大腿、脛など下腿部を軽く蹴り合うなど様々な方法があるが、けして無理はしないように怪我に注意して行って欲しい。
排打功は古来から先人が伝えてこられた有用な練功法である。これを軽んじて妄想的に内功さえあれば外功など要らないとはけして誤解せぬように。
むしろ排打功の力は単なる外功を鍛えた結果というよりは、身体の内にある内功の強さを表に顕して発揮されるものである。
練功法 補足
補足1:鉄砂掌功
鉄砂掌功は日本で流布された俗説では、敵討ちをする前に練習されるなどと、まるで殺人目的で行われる妖しげな練功法だと語られるが、拳法に実用を求めている者であるならば、南北、内家、外家の区別なく、あらゆる門派の実践者たちの間で広く行われ、多くの者たちが多少は経験するメジャーで極めてオーソドックスな練功法である。
例えば八極拳では、李書文の系統の長春八極拳などで日常的に練功がなされているものであり、掌を打ちつけて攻撃することも多い、八極拳の兄弟門派の劈掛拳においては必須の練功法だといわれている。
ちなみに台湾の長拳螳螂門の達人であった、故、高道生師は、90歳を超えた晩年も毎日、鉄砂掌功を欠かさず習慣とされていたという。
鉄砂掌功によって手が完成されると精力増強など、まるで内功のような養生効果もあり毎日、鉄砂袋を打袋せずとも、その功力は永く失われることはないとされている。
鉄砂掌はけして敵の生命に害を与える為に行うものでも、手を鉄のように硬く出来るという不可能な目的を叶える空想的な練功法ではない。
仏法と禅の精神を説く嵩山少林寺において、拳法の修行に用いられている少林七十二芸のひとつである。
鉄砂掌は人を打った際に手を怪我しないように鍛えるのが本義であり、この練功に通じると手はしっとりと柔らかいが、弾力のある丈夫なものに仕上げることが出来るのである。
また、さながらブラックジャック(革袋に砂が詰まった柔らかい棍棒の一種)のように、手をまるで武器のように用いることが可能となる。
もし何かを叩く練功で鍛えられていない拳や掌で、喧嘩となれば、すぐに自分の身で理解されることであるが素手で敵を強く打てば手が腫れ上がったり、内出血はよくあることである。
翌日になると手がどす黒く腫れて、箸も握れないなどということはザラな事態である。
これではすぐに敵討ちに来られようものなら、たちまち窮地に陥ってしまうことだろう。
修練を積み鉄砂掌功によって完成された手は、皮膚がぶ厚くなって大きな手となることもあるが、いつもしっかりと手のケアを心がけていれば、外見上は手を鍛えているとは他人に悟られない、どこにも違和感のない姿である。
あとに述べる手指のケアを怠ると、ガサガサとした皮膚の無骨な手となるが、これだと失敗だといわれている。
中国武術では空手の巻藁突きや砂袋を打つ稽古で作られる拳ダコがあるような、他人からみても一目で武術で鍛えていることが察せられるような手は、敵と交戦する際に警戒されるため避けられている。
武術家や東洋医学を多少嗜む者の間では、手指は経絡、神経が多く集まる場所であるので、調子に乗って手荒く鍛えてしまうと、途端に目が冴えて寝られなくなったり視力の低下、元気が出ず酷い体調不良に悩まされるなどの病態がよくみられことが経験的に知られており、練功の際にはこの注意喚起が強くいわれている。
その為、初心のうちから安易に効力をはやく得ようとして鉄砂袋を強く打つことは絶対に控え、打つ回数もむやみに多くの回数叩かないことである。
練功の後にはよく念入りに手指をマッサージし、漢方薬を調合した薬酒である洗薬で、手の炎症を抑えることがとても重要である。
鉄砂掌功によって手の経絡を強く刺激した結果、腎陽の消耗が起こり、衰える肝火を補う為に服用する補気薬としては、古典的処方が不可能な場合でも、一般的に入手出来る「補中益気湯」や、「杞菊地黄丸(ボディービルダーがステロイドを使用する際に、睾丸縮小を防ぐ目的で愛用される漢方薬でもある)」で問題なく代用可能である。あと補気効果があり練功に有用な食品には胡桃、カボチャの種、柿の葉茶、枸杞茶、枸杞の実などがある。
洗薬の調合も古典的な処方のものは様々なものがあるが、その処方の方は秘伝というほどのものではなく、先人たちが記された書籍の中で広く公開されているものである。
だが現代では外用消炎鎮痛剤の「タイガーバーム(白色の物の方である)」を塗ってケアすることで代用されることが多くなっている。これでも全く問題はない。
現代においては古典的な処方で調合された洗薬は、地骨皮などの漢方の生薬と酢の合わさった悪臭が不快に感じたり、鉄錆と生薬で着色された洗薬に手を浸してしまうと、たちまち手が赤黄色く汚れてしまい、扱いがとても面倒なので、全く避けられてしまう傾向にある。
しかしインドメタシンなどの非ステロイド性消炎鎮痛剤は、筋肉が痩せてしまうことが知られており、この代用にはならないと思われる。
鉄砂掌の練功には先ず腰の高さの台を用意する。材料はホームセンターで木材を買い、店でカットして貰って自作するのが良い。
次に帆布生地を用意して横28センチ、縦34センチほどの大きさの袋を縫って作る(日本国術会の物は綺麗な刺繍が施された木綿製である)。自分で縫うのが難しいなら、服の仕立て直しをしてくれる裁縫店や同じようなサービスを提供するクリーニング店で作って貰える。
その手間を惜しむなら代用に土嚢袋を用いる者も見かけるが、訊くとそれで全く問題はないようである。
こうして作られた袋に、鉄工所やネットで入手入出来るグラニュー糖ほどの粗い粒の砂鉄(鉄砂子)を、じょうごを使って中の砂鉄が動く程度に余裕をもって詰め(10キログラムほど必要)、開け口を縫い合わせて鉄砂袋を用意する。
これを様々な武術の手形でもって満遍なく打って練功を行うのが鉄砂掌功である。
最初、慣れないうちは、重力に任せて手を自然に軽く落下させることに任せ、絶対に強く打ってはならない。姿勢は武術の諸々の要訣を守り、けして不自然な立ち方で行わないことである。
打法には馬歩で鉄砂袋と正対して立って打つ方法と、半馬式となって半身に構えて左右の片側ごとに打つ方法があるが、後者が熟練者向きとされる。
こうして毎日欠かさず練功を続けていくと、力とは明確に違う、まさしく勁だとしか言い表しえないような感覚が手に得られるようになっていく。
それと実は地面や立木などに手や前腕を打ち付けても同様な効果がある。室内で騒音が問題となり鉄砂掌功が出来ない場合は、代用に打樹功が非常に便利である。樹木を打つ際は腕を振り打つかのように、立木に繰り返し前腕や掌を打ちつけ続ければ良い。
砂鉄の変わりに緑豆(他の豆ではすぐに割れてしまう)を袋に詰めた物を叩いても、入手がし易く有用である。
編集者が教わった方法は、正確な回数を忘れてしまったが、打ち付ける回数に制限があり、片手で40回ほどを越えてはいけないとされていた。練功の開始時は毎日欠かさず行い、二ヶ月(龍清剛の著書では三ヶ月とする)は射精を控えること。
性行為を行った場合は三日間は練功を止めることがいわれている。その理由を医学知識の方から類推すると、射精の際、人間同士の信頼関係を高める効果があるという、オキシトシンというホルモンが分泌され、様々なメリットがあるといわれるが、反面、プロラクチンというホルモンも分泌されてしまい、その結果筋肉など身体をかたち作っている蛋白質をアミノ酸に分解してしまう厄介者で、別名をストレスホルモンとも呼ばれている、コルチゾールというホルモンの働きを強めてしまう作用が起こるからだと思われる。
ちなみに、龍清剛師の鉄砂掌の本 は、日本における中国武術の有名な名著で、非常に赤裸々に武術のことが語られており面白いものだが、著者は日本における中国武術の軽薄な現状をとても憂いており、もしかしたら中には読んでとても怒りに思い、全く面白くなく感じさせられる読書も居るかもしめない。
は、日本における中国武術の有名な名著で、非常に赤裸々に武術のことが語られており面白いものだが、著者は日本における中国武術の軽薄な現状をとても憂いており、もしかしたら中には読んでとても怒りに思い、全く面白くなく感じさせられる読書も居るかもしめない。
龍師の双龍会の本部道場は、かつて京都の北区の閑静な住宅街に威容を誇ってあった。高い塀に囲まれた屋敷の中にあり(取り壊し済み)、さらにその門は頑丈な鉄扉なよって守られ、民間施設ではまだ高価で見かけることが少ない物であった監視カメラも備わっているという、どこからどうみても、ヤク◯ハウスにしか見えない立派な建物がその道場であった。
そこに鉄砂掌の本で興味を持ってしまった若者が見学に訪れると、応対にはまたしても、どこからどうみても筋者ヤ◯ザ幹部にしか思えない、見た目が非常に厳つい者が対応に現れて、若者に「紹介状は?」と問うてくるのだが、それで紹介状がないと知れると「うちは遊ぶ場所やあらへんで。餓鬼が帰れや!」と怒鳴られては、たちまち恐怖で逃げ帰る破目となる凄まじい塩対応をされる有様であったという。
現在でもこの龍清剛師や関係者たちに直接的・間接的に影響を受けていたり、縁があった教室は、実はあまり表だっては語られれないが関西を中心にいくつも存在する。
しかしこの現代では上記のような超絶塩対応はあり得ず、どの会も一般に教えられ、女性や子供たちも和気あいあいと武術を楽しんでいる。
記事の初稿を書いた編集者も編集者の師たちも、この龍清剛師に縁があった者たちが創設した協会の会員である。
かつて双龍会で怪我人が続出して、日に何度も生徒が救急車で運ばれるような、ほぼノールールであった激しい組手に明け暮れ、夜な夜な暴走族狩りを連日行っていたような方々も、現在はとても心優しい穏やかな姿をみせておられるが、武術について語るときとなると、たちまち猛禽のような鋭い眼光を放たれ、只者ではないことが伺わせられた。
補足 2:武術と筋力について
ところで、多少型が出来るようになり、中国武術の理屈が、おぼろげなくわかった者たちが、大した根拠もなく侮りがちなものに筋力があるが、実力者同士が、武術の技法を尽くして争う攻防において、不利な体勢に追い込まれたとき、そこから切り返す役目は、もっぱら力の出番となる。しかしこれは、蛮力といった不合理的な力では話しにならない。
求められるものは地面とのバランスの均衡をとった上で発揮される全身一致のパワーである。
筋力は重心を効果的に用いられる、バランスが整った体勢、身体構造を維持するためには絶対に必要なもののため無いと、簡単にいうと弱いわけである。
たとえば強い整勁と、それより弱い整勁が単純に正面から激突すると、弱い方は負けて、たちまち崩されるわけだが、この勝負で勝ち目がないときに、化勁(太極拳的な受け流し)が出番となるが、ところが、化勁もまた根源は重心の力であるため、筋力から全く離れられるものではない。
技に力を用いないと特にいう太極拳でさえ、数キロから2、30キロもある太極球という練功器具を持ち上げて、腕で転がしたり、実用での使用は、到底考えられないような高重量の兵器を操り、鍛えているのである。武術において、外部に影響を与える力は、重力に根本を発する勁力であるが、筋肉はこの勁力に方向性を与える装置のようなものである。
東洋では筋肉は、五臓六腑に源を発する経脈に属する、経筋であると捉えられており、その運動には、方向性があると考えられている。勁は筋から発するという言葉も古来いわれている。
よって、筋肉を養うことを全く軽視という考えは、伝統的な考えからしても非常におかしな話である。
しかし確かに筋力ばかりに頼ると武術として片手落ちであるが、若いうちは必死に稽古に打ち込み、全身の力を鍛えるべきである。それが後々、歳をとったあとも、円熟した枯れた技を支える、確かな功力として残るのである。筋トレのような強い力を発揮させるトレーニングは、筋肉の動きを支配する神経を発達させる意味があるからである。その他にも筋トレを止めて、たとえ筋肉が痩せたとしても、筋肉の核細胞は残されており、年老いた際に筋力の低下を防ぐ機能が、人間の身体には備わっていることもわかっている。つまり、筋力は鍛えれば鍛えるだけ貯金が出来るのである。これを俗にマッスルメモリーといっている。
また、武術の先人たちは日々の練拳はもとより、現代人とは比較にならない日常生活の不便さや農作業などの過酷な重労働の中で過ごしており、そもそも武術を稽古するにあたる前提とする基礎体力が現代人とは異なっていたことを忘れてはいけない。
(下の写真は弟子を指導する吉万山(左)1903年生-1978没。形意拳、錦掌拳の達人。ボクシングやレスリングにも通じ、1932年にロシア人レスラーとの試合に勝利し有名となった。哈爾浜市武術館連合会主任などを歴任)
さらに練功法として筋力が養成される、様々な効果的なレジスタンストレーニングも盛んに行っており、鉄牛耕地(腕立て伏せのようなもの。主に体幹部と胸筋、肩、上腕三頭筋を鍛える)、紅孩観音脚(片足立ちで行う足上げスクワット、ピストルスクワットのこと。下肢の徹底強化および全身を協調させたバランス力を養成し、これで重心の移動を内観する。多くの者がこの錬功法を筋力がないからできないと、錯覚・誤解しやすいが、実際は身体がその感覚に慣れていないケースが多く、最初はバランスをとるために杖や棒などを両手に持って支えて行うことを勧める。ただ、運動強度が強く、膝に故障があるなら絶対に行わない方がよい)のような、自重トレーニングや、石鎖という、石で造られたケトルベルと同様な練功器具を振り、反動を用いて全身を協調、連動させることによって、運動に活かせる神経とパワーを鍛える、現代の格闘家たちも取り入れているような、けっして古めかしくは思えないような、フリーウェイト・トレーニングさえも行っていたのである。
ちなみに八卦掌の伝説的な達人のひとりであった馬貴は、小柄な体格にも関わらず70キロもの石鎖を軽々と扱ったという。現代は太極拳のふるさとの陳家溝においてさえも近代的なウェイト・トレーニングが行われている。
ケトルベルは、先進的で研究熱心だったブルース・リーが、いち早く取り寄せてトレーニングに取り入れていたが、西側諸国で脚光を浴びるようになったのは、ソビエト連邦が崩壊した1990年代以降のことである。また筋トレなどろくにしたことのない者は、筋肉を簡単につけられるものと思いがちだか、逞しい身体を作っていくには、効果的なトレーニングと、筋力の向上に合わせた、相応の負荷の増強、苦錬に耐える気力、栄養の摂取が必要で、そう簡単に筋肉など付いてはくれないものである。
よくわかっていない者は、筋肉が付きすぎたら云々と絵空事をいうが、目に見えて筋肉を肥大させるなど大変なことで、筋力系アスリートのような見事な鍛え抜かれた身体は、半年、1年や2年やそこらの半端なトレーニングでは作ることはできない。
そして現代では、人類で最も速く動くことが出来る陸上の短距離走の選手も、驚異的な身体操作を行う体操競技の選手たちも、ウェイト・トレーニングで逞しい身体を作り運動能力を向上させているのである。
余談だが、米国の某専門家が述べた説で、トレーニングジムで、ベンチプレスを100キロを挙上出来る者は、成人男性のトレーニーのうち僅か500人に1人程度ということがよくいわれている。
たまに体格のよくない者が、自分は100何10キロは挙げられるよ、というので驚いて聞いてみると、チェスト・プレスマシンの話であったり、それも目盛りがキロではなく、運動強度を表す数字であったりポンドであったりして拍子抜けするのだが、フリーウェイトとマシンでは挙上を成功させるフォームの難しさと、要求される筋力が大きく異なる。ベンチプレスの成人男性の平均的な挙上重量は40キロ程度だといわれている。
ちなみにフィギュアスケートの浅田真央選手は、現役時代ベンチプレスを45キロでトレーニングしていたという。プロレスラーの棚橋弘至選手は入門から数年の時点で、ベンチのマックスは140キロであったという。
成人のトレーニーが、ベンチで100キロを挙上出来るようになるまでは、編集者の経験上、真剣に挑戦し続けても1年から1年半、またはそれ以上かかるものである。しかし、だというのに100キロを挙上出来る程度では傍目から見て、まださほど目に見えて筋肉が付いたようには見えないのである。
ちなみに日本人は体質的にたしかに欧米人と比べ、筋肉をつけ難い傾向もあるのだが、その国民気質にも一因があるといわれている。日本の社会では真面目さが特に、美徳として尊ばれるので、つい成果の出ないトレーニングだったとしても、真面目に打ち込んでしまうことがあるのだが、これがマラソンのような持久系の競技であれば、努力がそのまま成果となる場合もあるが、筋トレの場合は全く異なるのである。
かえって日本人よりも根気が続かず、飽きっぽい気質の外国人の方が、鍛えて成果が出ないのであれば早々にそのやり方は止めて、別の合理的なアプローチで工夫するので、筋肉に新しい刺激が得られて日本人と比べて短期間のうちに、逞しい身体を作くってしまう例が多いと、フィットネス業界ではいわれている。
それと日本は世界と比べて、筋トレやダイエットの常識がガラパゴス化しやすく、下手をすると何十年と遅れている。たとえばアーノルド・シュワルツェネッガーのボディビルの師であった、ジョー・ウィダーが創刊し、世界各国で多言語版が発行されている、米国最大手のフィットネス誌といわれる『マッスル・アンド・フィットネス』に、15年以上昔に書いているような、コレステロールの話しや低炭水化物ダイエットなどの健康情報が、何年も何年もと遅れてやっと日本で一般的に話されるようなありさまであった。
あと日本では、昔ながらの腹筋運動はやると辛く、鍛えたような気になれる種目のせいなのか、いまだ筋トレの基本であるかのように好まれるのだが、海外では、とっくの昔から軍隊である米国陸軍、米海兵隊、フランス外人部隊においても、シットアップは効果的ではなく、腰を痛めるものとして忌避され行われなくなっている。
編集者の知人のベンチプレスの世界大会で2位、全国大会で1位になった者は、腹筋が見事に割れているが、シットアップなど、一度としてトレーニングメニューに組み込んでいなかった。何事も昔ながらの方法が、良いとは限らないのである。「昔は俺らもやっていたから若いのもやれ」という考えは伝統などではなく、老害となった愚か者の特有の思考停止であり大害悪である。
また合気道の開祖、植芝盛平など、力など不要だと説いた達人が、実は人並み外れた大変な力持ちであった例もある。力がある者が説く「力はいらない、力を抜きなさい」というのと、全く貧弱な者が力を妄想的に完全否定することは、天と地ほども違うのである。
開祖の技には「茶碗を持つくらいの力で良い」という言葉を聞いて、茶碗より重い物を持たないなどやっては愚かである。
中国武術においても、南京中央国術館の少林門長であった王子平も、「大力千斤王」と讃えられたほどの怪力の持ち主で、石鎖功など様々な練功法を指導したが、外見上からは剛力のほどは覗えず達人然とした好々爺といった姿であった。
達人に筋肉質な者はいないとする説があるが、服を着ていると、一見痩せ細ってひ弱のようにみえても、実は鋼のように鍛えられた身体、という武術家も珍しくはないのである。極端な撫で肩をしていて、肩が落ちている者は、そのようなタイプであることが多く、武術の熟練者の証明的な体型のひとつなので侮れず注意を要する。
武術には、沈肩墜肘という、肩甲骨を下に落とすという教えがあるが、これには打突のインパクトの際のブレを少なくし、勁力を効果的に対象に打ち込む効果がある。肩が上がり、腋が不適切に開いて肘が上がっていると、関節の遊びが大きく、威力を逃してしまうのである。勿論、肘関節、肩関節に適度な角度を作り、インパクトの際に、効果的に対象を貫くように曲打する、圏捶(フック)や、栽拳(下方に打ちおろすフック)のような技法もあるのだが、それはむやみに腋が開いているとだか、肩が上がっているようなものとは異なる。
特に注意しておくが、武術では下盤(下半身)と、下で紹介している、双龍会の寺岡氏(故人)の写真で現されているように、体幹を重視して鍛える。足腰の強さはあればあるほど良いのである。
武術の諺では「拳を練って、腿を練らねば、老いては悔いのみが残る。拳を練って、功を練らねば、老いては何も残らない」とも言われるほどである。
敵の身体に打突を当てた際、当たり負けせず勁力を突き徹すには、腕を突き上げる上腕三頭筋や大胸筋よりも、後背部の筋力が強力であることが求められる。
ちなみに武術の練功方には、指立て伏せや樹の枝を強く掴んでぶら下がったり、懸垂を行う鷹爪功があるが、この際の握力は背中から掴めと指導される。
そして脚を上げることと、股関節の運動に最も重要な大腰筋などのインナーマッスルも、強力であることが求められるが、反して四肢の末端は、やたらと太くなればそれが重りとなり、せっかく体幹で発生させた力と速さを損なうことになる。
武術では脚の動きから遅れて、手が動くようでは遅いのである。鍛えるにしても、アームカールのような、主に上腕二頭筋を鍛えるだけのような筋トレは、運動パフォーマンスの向上には繋がらず、無駄で特に害である。
そんなことをやるくらいなら、勁道の養成のために、手のひらに皿を置き(置いたつもりでも良い)落とさないように腕を色々と動かし、手腕とそのスジを捻る練功(螺旋功、八卦掌の練功法)を行うことを勧める。
ちなみにダンベルカールでも、比較的軽い重量を持ち、反動を用い捻じり挙げて鍛える、スクリューカールは、運動パフォーマンスの向上に役立つといわれているのは、武術で行われる手首を捻る錬功法と共通点があるのかもしれない。逆説的となるが鍛錬で反動を用いて鍛えることで、反動を使わない身法が身につくのだ。
山西派の形意拳では三体式站樁の際に、老師がバケツに水を汲んで、それを弟子の前手の手首にバケツの取っ手を掛けてやらせるということもあるが、これと似たような稽古をするなら、軽めのケトルベルでも代用出来るであろう。
ただ西洋的な筋トレをするにも、ボディーメイク系のものや、ボディービルダーのやるような、個別の筋肉に効かせ、効果的に筋肥大を狙う鍛え方では、武術・格闘技において、使える筋肉にはけっしてならないと断言する。かえって運動が下手になるケースが目立ち、これがスポーツ界において、長く筋トレが忌避された理由でもある。
なのでそような例をもってのみ筋トレ全般を忌避するのは前時代的な迷信でもある。
武術に有用なワークアウトとして、パワーリフティングが基本とする、ビッグ3と呼ばれる、ベンチプレス、デッドリフト、スクワットの3種目は、全身をまんべんなく合理的に鍛え、全身を一致させて発揮させる大きなパワーを、身につけるのにとても有用であるので勧める。
それと、ウェイトリフティングの基本である、ジャークを繰り返すことも勧める。クリーン&ジャークは、下肢から発生させた力を、反動を用いて上体へと伝え、重いものを軽く扱うことを練習するが、これは武術の技にも通じ、スタミナも養成される。これらで鍛えられない場合は上で紹介した、ケトルベルやブルガリアン・サンドバックは役に立つだろう。爪先重心でなるべく立ち、反動を用い、個別の筋肉にあまり効いていないのでは?と疑問でも、サーキットトレーニングだと思って疲れるまでやって欲しい。
ちなみに爪先に荷重をかけたトレーニングを勧めるわけは、脚のハムストリングスを鍛えることで、武術やスポーツに活かすことの出来る筋力と身体の使い方を得るためである。脚を鍛えるにしても、昔の日本で盛んにいわれていたように、踵重心で鍛えていくと、大腿四頭筋の発達と比べてハムストリングスが不十分となり、適正なバランスが取れない、スポーツに活かせない身体で、しかもボディーメイク的にカッコいい身体にならないという、とんでもない弊害が近年知られているからだ。
ちなみにミスター・オリンピアに出る怪物的なビルダーたちのような、自然では絶対にあり得ない異常な筋肥大を望むなら、日本においてもアナボリック・ステロイドやプロホルモンはオオサカ堂のようなサイトから個人輸入することで安く取り寄せられるので、なりたいならな飲んで鍛えまくって凶暴化したりハゲでも、内蔵肥大でも、なんでもなればよい。
下肢を鍛える練功としては、上記で紹介した片足立ちスクワットの他にも、九宮狼穿功といって、片脚に全体重をかけ深く腰を落とし、片脚に座り込むような低い縮歩に近い歩幅の虚歩、南派少林拳でいう吊馬で、前足をやや引き寄せた立ち方で立つ、站樁功もある。これはアイソメトリックス的に脚を鍛える方法であると同時に、重心沈下の感覚を掴むためのものである。
いざ戦う段となってから、筋肉のパワーに恐怖しては遅い。武人が武人らしく鍛えられた身体をしているのは当然のことである。脆弱過ぎるひ弱な功夫であることなかれ。まだ若く鍛えられる時期に鍛えずして老人のような身体を目指しても、将来鍛えた同年代に嫉妬するのがオチで愚かしい。
ちなみに反射神経や持久力は、青年期を過ぎると共に自然と低下し、そのピークは20歳代前半にあるが、筋力のピークは、それよりも遅く、30歳代前半から40歳代前半がピークだといわれている。筋力系競技のアスリートたちが長く現役で居られるのはそのような理由からである。
つまり中年からでも鍛えるには遅くないのである。鍛えるのは今である。
尚、虚弱すぎる者が無理をして過激な練功法をすると年寄りの冷水のようなこととなるので、練功の強度の設定は功力の向上に合わせた相応のものとして欲しい。
交手法(応敵理論)攻防原理・眼法・歩法・応敵勢
攻防原理
形意拳には敵を殺傷せしめる危険な招法も、口伝的に伝わってはいるが、この動作は必ず受け技である、これは中段突きであるというような固定化された型の解釈は定めてはいない。
防御の中に攻撃があり、攻撃の中に防御があるのである。
形意拳は前進して打つことが強調されるが、しかし引き手をとってただ真っ直ぐ敵に突き進んで打つなどという浅い理解では、敵にステップでかわされ、たちまち顔面を殴られ撃退されて終わりである。
ちなみに形意拳に限らず武術では、引手をとる動作のある型の分解は、突きの蓄勁や予備動作などではなく、掴んで敵の体勢を引き崩して重心を浮かせ、据物にして打つ、あるいは引き手をとる際に、同時に敵の攻撃を抑え、敵と自分との間に橋をかけて打つことなどを暗示している。これを架橋手という。半歩崩拳などでも用いられている、形意拳で特徴的な槍の操法を徒手に応用した技術の一端である。
打つために態々引き手をとって、いちいち構えるなどという理解では、テレフォンパンチどころの話しではない。攻防の中で自然と引き手が取ら、その引き手をも技として活かせているのが理想なのである。
さらにいうと、形意拳の打拳は身体を纏めて放たれるため、露骨に引手を取らずとも打てるようになっている。寸勁・分勁などは、形意拳を学んだのなら本来出来てあたりまえであり、フィクションで描かれるような、いきなり遠方から投機的に飛び込んで、単発で打つというよりは、敵の攻撃を迎撃し、極めて近接した間合いに入って、寸勁でもって打つような招法である。さらに一旦打ちこんだなら敵が身を引くのに乗じ、たたみ込むように攻め続け、打打打という風に連撃(鼓打法)をもって敵の反撃を許さず、一気に粉砕してしまうのも倒すためには重要である。
ジグザグに踏み込み、斜めから入ることで角度を利用し、敵の攻撃を未発に抑えながら、迎撃を行うという教えもある。形意拳の戦闘法は敵の技の威力が、十分に発揮される以前に潰してしまう迎撃、相打ちが基本コンセプトであるが、硬打硬進するにしてもただ自らの都合だけを考慮するのでは妄想の類である。
万全な体勢をとっている敵を、ただ強く打ったところで、十分に効かせることは出来ない。確実に打ち倒す為には敵の重心を浮かせ、体勢を崩す必要がある。これを「起はヤスリのごとく落は鈎竿(古代兵器の戈の一種。穂先に鈎のように、内側に湾曲した刃が付いている)のごとくあれ。」という。これは必倒の打撃の大原則である。
この重要性を鑑み、武術ではよく敵の中門(中心)をとれと教えるが、ただ敵の真ん中に打ち込むという理解だけでは浅い。懐深く踏み込み敵の体勢を崩し、その位を奪うのである。
武術の攻防はバランスの奪い合いといっても過言ではないのだ。これを崩勢法ともいう。その際、最も有効なのはカウンターである。まるで錐や槍の穂先をもって突き刺すかのように、相手の攻撃の圧力を逸し、自分の攻撃は命中させる相打ちに、形意拳の真骨頂がある。形意拳ではこれを、円錐交叉法という。これは攻撃的な防御ともいえる。
形意拳でいう粘勁は、太極拳にも同様の概念があり、黏粘連随(粘連黏随ともいう)と言い表している。「黏」とは、敵の体に粘りつくように接触することをいい、「粘」もまた、敵と離れない粘性のことをいい、どちらも摩擦力のことである。
摩擦力とは、固体表面に作用する平行力に対するブレーキの事を示し、先人はこれを活用せよといっている。「連」と「随」は攻防において、敵の動きに対し、臨機応変に対応することをいっている。
単に敵の力に逆らわないとやっているだけならば、自分が敵にコントロールされるだけである。太極拳でいう「黏連、黏随して離れることがない」は、形意拳の戦闘法のなかにも含まれるものである。その摩擦力は、柔らかなだけではなくヤスリのごとく強く、腕と腕とが擦り合い、あるいは打ったところが擦られ、火傷のような擦過傷にすらなってしまうことすらあるほど強烈である。
形意拳が接近戦を得意とするのは、特に以上の理合からである。
起鑽翻落(起落翻鑽)という要訣がある。
形意拳の動作要領、勁道面を指すもののみと誤解されることが多いが、戦法を指し示す教えである。
「起」とは起動すること、技のスタートを指す。敵に踏み込み身を沈ませ、次の「鑚」で突き上げ束身し、敵の反撃を潰し避けつつ、手を翻して封じ「翻」、最後は敵に一気にトドメをさし、終わらせることを「落」という。技の終わりである落勢で、この要訣で述べることは完結する。
また別の教えでは「落起」「翻讃」だといわれている。虚手(一種のフェイントとなる仕掛け技)である落で相手を迎撃し、敵に反応をさせる。これが即ち起である。その反応を利用して、こちらは手を翻し、讃して実打するのである。理想は落起の段階で、敵を打倒していることが望ましいとされる。
落は落命に通じ、起は去である。古来「起は矢の如く落は風の如くあれ。」というが、敵を打ち倒す威力のない虚手など、敵にとっては脅威とはならず、端から無視され、何の意味もなく正面から顔面を打ち抜かれて撃退されるのがオチである。虚手にも必倒の威力と速さが求められるという教えでもある。
形意拳の攻防における教えは、迎撃の速さを特に説くが、こうして発せられる威力を冷勁と称する。
特に注意しておくが、戦う正当な理由があり、敵を打倒すると決めたのなら、恐れる心を知らぬものとし、対象を人間だと思って情けをかけてはいけない。これを狠(残忍という意味)という。
冷酷に躊躇することなく、人ではなく、さながら雑草でも薙ぎ払うかのように、仕留めるまで、けして攻撃の手を休めないことである。
なぜなら戦意を喪失したようにみせて、敵は敗勢を装い、反撃を試みているかもしれない。情けや躊躇は油断に繋がり、その報いは必ず自分や愛する者たちに、襲い返って来るからである。
実戦は組手ではない。敵に命運をまかせ、こちらに容赦をしてくれることを期待してはならない。
そして敵に打倒されたとしても気を抜いてはならない。編集者の学んだ会派では、倒れていると、殴られたり踏まれたり、蹴られたりと追撃がされ、果ては実際には外されるが、側転で跳び上がって踏み潰されるような有様となるため、その場で無防備に起き上がるようなことは出来ず、必ず身を捩って転がって距離をとり、鳥龍絞柱(スター・フィッシュ・キック・アップ)などを使って素早く起き上がる、構えて防御をした状態で起き上がるなど、必ずしなければならない掟であった。
現代の中国においては、比武の際、暗黙の了解的に転ばされることが即負けたことと捉えられ、双方の生命とメンツを守る方便的なマナーとなっているが、本来であれば倒したならば踏み潰し、或いは、まるで柔術のようにグラップリングを行い取り押さえるのが本当の姿である。であるので着法のなかには寝技に対する回避法まであるのである。
実戦は突発的に起こり、短時間のうちに生命に関わる重大な判断を強いられ、極度の緊張と興奮状態の中に置かれる。
そこでは組手の時以上に、「こう突いて来たらこう返す」というような固定的な用法を、いちいち頭で考えていてから使おうとしても難しい。
怯えの心があり、動揺していては、必ず敵に打ち倒されることとなる。闘争心を鼓舞させることである。
そのためには普段の稽古から、実戦の場に居るかのような腹づもりで、稽古に打ち込むべきである。戦える心理状態、臨戦態勢を作ることを学ばなければ、武術の技はどんなに巧妙であろうが舞踊と同然で、実戦ではけして使用可能とはならない。
たとえばまた口が悪くなってしまうが、ゆるい武術オタクたちの練習風景でありがちなのだが、普段から師に技を掛けられて飛ばされては、ヘラヘラと笑っているような巫山戯た態度で稽古していては、絶対に駄目である。
真剣な闘争時に生じる興奮は、普通なら痛みで唸り倒れてしまうような、強いダメージですらも無視させ、戦いを続行可能とさせるものであるが、フルコンタクト空手など、直接打撃制の格闘技を学んでいると、このことを自らの身体に感じる痛みとして実感し、経験するので、真剣に稽古に臨む重要さが自然と分かるものだが、排打功も組手も行わず、身体に打撃を当てないようなへぬるい稽古を続けていると、実戦における心理状態の重要さは全く軽視されてしまうのである。
型など上手になり、発勁など小利口に分かったとしても、実戦で使えないものであるならばそれは武術ではなく、武術を詐称し侮辱する、噴飯もののお遊戯にもなりかねない。
恐れの心があるのなら、そもそも、まともな稽古にもならない。相手がたとえ自分の師であろうが、先輩であろうが、いくら強かろうが相手も自分と同じ人間である。過剰に神格化して怯れる必要はない。
人が動くとき必ず攻め入る機会がある。その時、相手に怯え、痛みを恐れていては機を逃し、かえって怪我をすることになる。武術では痛みに耐えることは修行の一貫である。避けては通れないものである。
実戦においての理想の心理状態とは、恐怖と怒りの憤りを圧し殺し、迷わずただただ、戦いに没頭することである。意識を極度の緊張状態におき、戦いのブレーキとなる余計な感情を途切れさせ無心とする。
俗にいう「冷静な狂気の状態」を作り出すのである。ふと気づくと技が発動していて、敵が倒れていたという風であれば非常に宜しい。
雑念があって、敵の動きに動揺していては武術の技は使えない。恐怖は無いものとし勇気を奮い立たせ、攻撃も防御も技は、その時の自分の手に任せるのだ。
『倒れるかどうかは相手の勝手だ。自分ができるのは、ただ打つだけのことである』松井欧時朗 著『重力を使う!立禅パワー』より。
眼法(目付け)
敵の攻撃を察知するコツは、視線を一点に集中させるのではなく、相手の全体を周辺視野を使い、ぼんやりみることである。仏様のような落ち着いた、どこを視ているか分からないような表情となる。このとき目付けは地面を基準に水平をとり、視線をむやみに動かしてはならない。中国武術ではこれを、二目平視という。
形意拳ではさらに猴相といい、眼に毒があり心を残忍とすることで、口元には自然と微笑みが浮かぶような、戦闘を効率的に行える、ある意味、狂気的な心理状態を尊んだ。このようにすれば敵に惑わされず、手は自然と効き、防御も攻撃も円滑に行うことができるのである。
ちなみに二目平視は、バランス感覚の補助ともなり、その有効性は夜の照明灯が少ない薄暗い場所で、型を練習してみるとすぐに分かるであろう。普段人間は、バランス制御に視覚情報をかなりの助けとしているのだが、ところが、暗闇では、基準となる周囲の風景の把握が困難となるため、バランスをとって動くことが昼間よりも困難となっている。たとえば、暗い場所では、独立式や方向転換がある套路の動作が特に難しくなるが、それはこのような理由からである。
八卦掌の開祖、董海川が目隠しをして藪の中を全力疾走しても転ばず、怪我もしなかったという逸話があるが、これは二目平視とも関連性があることである。夜の薄暗い屋外での稽古を重ねると、自然とバランスの安定する目付を身につけることが出来るのである。その結果、聴勁(敵の僅かな兆しを読む力)も磨かれることになる。他にも互いに目隠しをしての対打練習も効果的である。
歩法
形意拳は歩法を重要視している。進歩に用いられる代表的な歩法に跟歩(こんぽ:ゲンプー)がある。技を発する際に同時に前足を半歩前方に踏み込んで進み、その後、後ろ足を前足の進んだぶん引き付けて技を終える。この際、明勁では震脚を伴う。
震脚は、踏み込むときに前足で行うのが主な派もあれば、引き付けるときに後ろ足で行うのが主の派、踏み込み引きつけの両方で行う派もあり、それぞれである。この違いは得意とする戦法や用勁の違いで生じたものと思われる。
跟歩、それ自体は同様な後ろ足を引きつけて継ぎ足を用いる歩法は、あらゆる格闘技にみられるが、形意拳は、とにかく前進する力で打つと説く会派では、これを特に強調していう傾向もある。
実は跟歩には打突の威力を高めるコツも内包されている。敵の内郭(内臓)に効かせる打法に、二度打ちがあるが、例えば崩拳を放つとき、踏み込むと同時に拳を当てるが、この威力はこのままでは人体の外郭(皮膚・筋肉・骨格)のもつ弾性に散らされ、内部には十分に効かせられないのだが、一旦この反発力を架式と腕の螺旋、脚の螺旋、即ち袖絲勁(螺旋勁)で飲み込み、続いて跟歩して後ろ足を引きつけると同時に、袖絲勁を開放させ第二撃目を打ち込むことで、敵の内郭を外郭ごと打ち抜くという打法に活かされる。
後方に退く歩法の退歩であるが、形意拳は退く際も攻撃の意を欠かさず、退歩崩拳などの技を伴わせることが多い。退歩しながら発する技には、借勁といって、敵の突進力が自らの攻撃力に転化されるため、前進して打つ技に劣らない威力が生じている。
敵に対して斜めから攻め込むために用いる歩法が、編歩(墊歩ともいう。斜め前方45度に踏み出すこと)してジグザグに進む歩法の践歩であるが、李存義がそのように稽古する必要性を説いたように、すべての五行拳の移動稽古においても、寸歩(半歩踏み込むことをいう。前方に進むことを上歩という)だけではなく、別の言い方ではこの三才歩あるいは反三才歩から翻って(これを翻三才歩という)、敵の懐に斜めから入る歩法(中国武術では一般的に、三角歩ともいう)、退歩などでも練習すべきである。
敵の打突に対し、角度をつけて入ることで、そのインパクトゾーンを外し、威力をまともに受けずに済ませ、敵の弱いサイド側に攻撃を行うことが出来る。また敵に狙いをつけさせず、被弾する確率を下げる意味もある。注意としては斜めに踏み込むことを、敵に悟らせぬように上体はあくまでも敵と正対して行わうことである。ジグザグに攻め込むことで翻弄し、敵に有利な体勢をとらせず、壁際などに追い詰めていく戦法も常套手段である。
膝を抱え上げ、踵から踏み込んで着地させることを虎歩といい、そこから、つま先をパタンと着地させて歩を進める一連の動作を鶏歩(紛らわしいが三角歩を鶏歩と呼ぶところもある)という。この歩法で膝を抱えあげて進むことを強調するものを、摩脛歩(堤空歩)と称している。編集者のところでは、炮拳や虎撲手を練るときに、践歩と併用して行うことが多い。歩法中に蹴りが暗示されている。足で脛の内側を擦るように進むことから、この名で呼ばれる。
その他にも、踏み込む歩法には、換歩という、後ろ足から蓋步(がいほ:足の内側から踏み込み踵、土踏まずを正面に向けること)して踏み込み、軸足をスイッチして踏み変えることで、玉環式(別名を剪子股式。高架の半座式(坐盤式)である、脚をクロスさせて、踏み込んだ架式のこと。その際、劈打と踩腿を伴う場合は、そのまま龍形拳の狸猫倒上樹となる)となり、そこから前方に進む、あるいはそのとき、八卦掌の扣歩、擺歩のように、踵を軸にさらに方向転換を行い、素早く小さな動作で敵のサイドに回り込み、脚を引っ掛けて転ばせるような技に変化させることもできる。
疾歩(槐虫歩)といって、尺取り虫が進むかのように身を沈みこませ、前方へ大きく踏み込み跟歩して進む歩法もある。このときマンガの描写などでよくあるように、極端に高く浮いて跳ぶようにしてはならない。軽浮の状態を避け、極力重心を下に落とし、安定させたまま敵の懐に潜り込むように移動することを心がけること。
大きく踏み込む際、古武術のいう縮地などと誤解して、やたらと高く遠くに跳ぶことを考えてはならない。疾歩は、敵の不意をついて遠くから跳びこむことよりも、攻防の中で敵の攻め気が止んだとき、その後退するに乗じて用いる場合に、より真価を発揮する。
敵の見ている遠間から跳び込んだところで、廻し蹴りでも合わせられて、悲惨な結果になるのであろう。
応敵勢(構え)
三体式を構えとして用いるとする派は、割とよくあり、これは比較的伝統寄りな教えでもあるのだが、片手を伸ばし前方に突出させることで距離をとり、攻防空間を拡大し、盾のように用いることには、メリットと同時に大きなリスクがあることには留意する必要がある。
腕や手指を掴まれることが先ず一つ。次に差し出した自分の腕を、換手法などで攻撃されることである。
また自らの手が視界の邪魔にもなり、敵の攻撃を察知することが難しくなる。指は特に親指を掴まれてしまうと容易に手を抑えられ、編集者が以前、組手で怪我をして手術した時のように、簡単に親指の靭帯を断裂させられてしまう。ちなみに小笠原礼法で掌を作る際、親指を開かず、人差し指につけるのは、親指をとられる危険性を回避するためだという。
手を抑えられたり掴まれたら、自ら手首を捻って、掴みを外してしまうのが無難である。ここで力や技で勝負しようとすると怪我の元である。総合格闘技などでも手指を取ることは禁止であるが、このような理由からである。
では、どう敵と相対すべきかであろうか。敵の拳足の届かない位置では、いちいち腕を上げて防御の構えをとる必要はない。
敵にこちらを攻撃する意図があるのであれば、後で述べる着法の中の誘敵勢(待敵勢)を以ってあたるのだ。こちらに近づいて来る不審者や敵に対して無防備であってはいけない。いつでも攻撃することが出来る体勢をとる必要がある。ちなみに不審者に対しては、必ず大きく声を上げて警告し機先を制すること。
手を構えるのは敵が間合いを詰めようとした頃合いで良い。注意しておくが、構えはボクシングの試合であるように、肘を引いて両拳を顎の前に置いてパンチの予備動作兼、ガードに用いようとしては、実は素手の攻防においては最悪である。
たとえば、機をみた敵に突進され、両手首を手で抑えられ、自分の手を自分の顔にぶつけられるなど、自らの攻防空間を自らで狭めたゆえに、敵からありとあらゆる攻撃を自由にされかねないのだ。勿論、組技に対しても無防備である。両拳を引いた構えは、グローブという敵の拳を遮蔽する防具と、手を前に突き出して防御してはならないという、ボクシングのルールゆえに成立する構えである。
構えは先ず、敵との適切な間合いをとり、被弾する確率を少なくするように位置取りを心がけるのが絶対の前提である。危険な間合いにいつまでも不用意に留まらないことである。
これは対多人数戦では特にである。また、敵が攻撃をして来ないのであれば、仮にお互いに攻め込む手段を見いだせず、お見合いとなったとしても、競技の場では無く、実戦、護身ならば、それはそれで大変結構なことである。
とはいえ、攻め手が無い状態では、決着はつかないため、敵の空きをつく必要が発生する。しかし戦いおいて空きとは、見つけ出すものでは無く作り出すものである。これを中国武術では、漏洞と呼ぶ。
攻める手段で有用なものは虚手であるが、守ることに有用なものが誘敵勢である。
誘敵勢とは、姿勢を変化させることで空きがあるように見せ、敵の技を誘う対敵姿勢である。
例えば極基本的なものだが、太極拳の無極勢(空手の自然立ちのような無構え)で立つにしても、敵に真正面を向けて立つ場合と、斜めに半身で立った場合とでは、敵の心理的に選択しやすい攻撃手段は変わるのである。
正面を向けて相対する場合、自分の側面に手を降ろしていると、敵は側面へのうかつな攻撃は実際そうなるのだが、受けられてしまうと感じ、我の防御が開いている、正中線を狙いたくなる。
斜めに構えると、敵は的が小さくなったように感じ、同時に我からの前側の手で攻撃、防御されるリスクを思わせ、攻める際は無難に、側面への圏捶や廻し蹴りなどを選びやすくなる。
またこの時、姿勢を低くし手で下段、中段を守る気配をみせ、あえて上段の守りがおろそかであるように開けておくと、敵の上段への攻撃を誘うことになる。
とはいえ誘敵勢は、知識がある者に対して露骨に用いると、容易にこちらの意図を見破られることになるが、敵に攻撃を仕掛けさせることで空きを作り出し、迎撃を以って倒すためには有用な手段である。
ちなみに前蹴りが届く位置は、多少踏み込めば、互いの突きが届くか届かないかの間合いである。誘敵勢はあくまでもこの間合のうちで通じることであり、この距離よりも間合いを縮められたならば、敵の出して来た攻撃を、こう受けてこう返すなど、のんびりとした対応は一切通用しないと思ってよい。
これは日本の古流、新陰流でも同様の教えがあって興味深い。巧者の突きが確実に届く近接で見てから技を回避することなど、どんな達人でも無理がある。
組手で無難な構え方としては、意拳や太気拳の丁八歩のような、やや半身の構え、つまり、後ろ足に力の貯めがあり、前足も自在に動かせることが出来る、三体式のような重量配分で立ち、腕は力を抜いて両の掌を敵に向けて適度に前方に伸ばして向け、顎の高さに手を置く、組手構えが使いやすい。
この構えで立てば、喰らえば即一撃で昏倒され兼ねない、上段への攻撃の軌道を自然と手が邪魔し、容易に手で遮ることが出来て、また腕を伸ばしきって構えていないため、たとえ敵に前腕を打たれたとしても、まるで柳に雪折れ無しといった感じで、こちらは腕を翻してやれば、楽に防御反撃が出来るため、敵にトラッピングのようなものを仕掛けられるリスクを極めて低下させることが出来る。
そして中段、下段についても、攻撃は手で払ってしまえば防御は容易である。これは上段への攻撃についてもいえ、敵の攻撃はさながら自動車のワイパーで、窓についた水滴を拭き落とすかのように払ってしまうのである。あと便宜上、「構え」とここでは書いているが、構えだとかガードだとかあまり思わない方が良いと思う。差し出す手はまるで昆虫の触角のようなセンサーであると思って用いると、半ば反射的に自然と敵の攻撃を遮ってくれるものである。
ちなみに形意拳における受け技のようなものは、1.鑚拳や横拳等で敵の攻撃を遮りながらカウンターを狙う(円錐交叉)、2.切掌や前腕で敵の拳足を斬り払う、3.纏法で敵の拳足を巻き取って反撃(架橋手)、4.敵の拳足を鐵槌や掌で拍打、などで概ねこれらの応用である。空手道の基本技にあるように「何々受け」というような受け技があるわけでは無い。形意拳では受け技も攻撃技も区別は無い。余談となるが古の空手もそうであったという。基本の突きや基本の受けは空手が沖縄から内地に入ってから、型を基にそう分解整理されたものである。
戦いにおいて防御を考えないファイティングスタイルなど自殺に等しいが、しかし守るばかりで攻める気の無い盾など怖くはなく、敵に見抜かれ、容易く押しつぶされるものである。構える際は常にこちらからの攻撃の気配を醸し出すことである。
さらにいうと、矛盾するようだが、こちらの攻め気、待ちに入ったところを敵に読ませないことである。常に動くことは間合いの攻防において重要であるが、ここで攻めるな、ここなら攻められると、容易く敵に読まれるような動きを自らしてはならない。表情もそうである。戦う時は気高い顔をして、感情を表に出さないことである。苦しいときに辛い顔をしては、敵に乗じられる。打たれて苦悶しても実戦なら戦いを止めてはもらえない。
現代格闘技が生み出したフットワーク、ステップは効果的ではあるのだが、あまり上下前後への細かい動きを無意味に行っていると、相手も同様なステップワークを用いているならば、問題は出にくいのだが、伝統武術のような落下を用いない歩法を使う相手に多用すると、後ろに重心移動する際などこちらの打てないタイミングを読まれ、素早く間合いを詰められてしまい窮地に陥ってしまう。
これを知り悟らないと、上級者相手の組手では、毎回のように100発100中で技を抑えられては、反撃も出来ず相撲の突っ張りよろしく壁まで推し飛ばされ不思議がる破目となる。これはたとえばヨーイドン!で戦闘体勢を整える癖がついている者相手に、体勢を整え終える前に攻め込めば、容易に不意をつけるが、これを短いスパンの中でやるような戦法のことである。
攻め気や守りに入ることを読まれ易い者は、得てして自らで読まれやすくしているのである。
単撃(用法対打)
ここでは順歩左劈拳の用法示例を紹介しよう。
初歩的な用法だが、三角歩を用いて敵のサイドに入って打つことを練習出来るので、覚えるときっと様々に応用が効き役立つことであろう。
とはいえ、編集者が組手で、このような用法を仕掛けられた経験のない、初観の者に使用すると、フルコンタクト空手の師範クラスを含めて、多くの者が対応出来なかったことは言及しておく。
こうやって斜めからジグザグに入ることで、敵の注意の盲点を突く消える動きとなるのである。
【1】(甲)(乙)は、お互いに向き合って三体式で立ち、塔手(互いに片方の立掌と立掌をかけ合わせ相対して構えた状態。交叉法の入りの状態を暗示している。)にて、お互いの左掌をかけ合わせて相対し準備とする。
【2】(甲)は(乙)に対し左立掌をかけ合わせたまま、 右足を右斜め前方45度に編歩して踏み出し(この際、上体は真っ直ぐ相手に向けたままとし踏み込みを覚らせないように)、続けて、右手立掌にて(乙)の左腕を斬りつけて換手しつつ、左足を右足踝の位置に引き付けて縮歩(前足の爪先を虚歩のように立て、歩幅を詰めた上歩しやすい架式)となり、(乙)の左斜め45度の位置に両足とも完全に踏み込む。この際、換手を行った右手立掌を鑚拳の形に変化させ(起鑚)、(乙)の左腕を圧しつつ、続けて打ち出す劈拳の為の発射台を形成させる(実戦ではこの時点で右鑚が(乙)の顔面を打ち貫くことになるが、 危険なのでこの場では暗示に止めている)。
【3】(甲)は縮歩の体勢より左足を(乙)の双足間に向けて踏み出し、 同時に(乙)の首筋の左側、肩口を左掌根の小天星をもって点撃にて打ちつける(実戦では顔面を打つ。注意としてはこの際、肩口の下を狙い過ぎて鎖骨を打ってはならない。これは打ち込む者が鎖骨を打って、手を痛打することを防ぐ意味もあるが、もしもこの劈拳で鎖骨を折ってしまった場合、丁度、この場所が欠盆穴に近く、折れた鎖骨で鎖骨下動脈を傷つける怖れがあるからである)。(甲)は劈拳のインパクトと同時に右足を引き付けて震脚し、三体式の姿勢となる。(乙)は打ち込まれる際、無理に打突に耐えようとはせず、劈拳の威力に身を任せ、後方に滑り飛ばされるようにして逃れること。下手な排打功で衝撃を飲み込むよりは、むしろこの方が受けるダメージは少ない。
【4】(甲)役と(乙)役は役割を交代させながら、この単撃の練習を交互に繰り返す。
【破法】(いかなる招法も口伝によって、打ち破ることが可能だといわれている)。(甲)が我の左側にサイドインする際に、こちらは踵を軸に(甲)の移動する方向に旋回して、(甲)の真正面に向き合ってやれば、(甲)は側面から劈を打つことは出来なくなり、(甲)は編歩の分だけ我より次の行動が遅くなるため靠撃(金鶏報暁)などで迎撃するのは容易い。
用法対打の練習は、最初は痛みに堪えられず、青あざだらけとなるだろうが、これで実際に人を打突する際の要領が学べ排打功の基礎ともなるので、繰り返し稽古するべきである。若いうちは少々打たれたくらいで、社会生活に支障などなく、健康を害することもない。むしろ鍛えられ強健な身体を作ることが出来るのである。
五行砲などの対錬套路も慣れたのなら、顔面への打撃以外は、相手に打たせた上で、打拳に対して切掌で封手し、退歩することで、突きの威力を軽減させる工夫や、相手の打拳に貼りつく練習をするべきである。絶対に打拳が当たることのない遠間で、スローペースの寸止めや、当て止めが前提の約束組手など、いくら繰り返しても、それは型の動作を覚えたというだけで、真に有効な対人練習となっているとは思われない。
『ガラスのようなボディや豆腐のような顔面では、一発食らったらそれでおしまいである。達人でもないのに、自分が一方的に相手のパンチや蹴りを一発も受けないで勝とうと思うのは、相手を板であると思っている思想に他ならないのである。
タイ国のムエンタイ・ボクサーと一度闘ってみるとよい。私のいっていることが完全に立証されるであろう。彼らは常になぐられ、蹴られて、その中を苦練して生き抜いてきたのであるから、その打たれ強さは想像を絶するものがある。これは、ムエンタイに限らずいかなる格闘技においても同様だ。ファイターと名がつく限り、バキバキ打たれても、簡単にはくたばらないように鍛錬されているものである。
高手でもない者が、ちょっと中国拳法のこむずかしいことがわかったという理由だけで、こうしたプロファイターを一発で倒せるという夢を見てはならない。 』龍清剛『中国拳法 秘伝必殺 鉄砂掌』より
我が国における実戦中国拳法の雄、雙龍拳法總會の総帥であった、龍清剛もこう語っている。へぬるい功夫であるべからず。上の写真は、龍師と双龍会幹部の玉井兄弟が、今はなき香港の九龍城砦の中で撮った記念写真である。地元の者にもうかつに中に入っては生きては帰れないなどと恐れられた、世界有数の犯罪多発地帯で、香港マフィアたちが蠢く巨大スラム街であった。
『功夫高手(本当に強い達人)は、皆温和であるという。それは浅い交際の人に対する中国の礼法であり、客気なのである。親しくなった者同士、武術を談ずるとき、そうした高手は何かにつけて、へぬるいのを嫌う。例えば、ヘヤースタイルや服装さえも、高手はへぬるいスタイルは好まない。私の知っている範囲の強い武術家は皆そうなのである。もし、そんなことはないという人がいるならば、その人は今までに本当に強い高手に会ったことがないか、あるいは会ったことがあったとしても、それほど親しくしてもらっていない証拠である。羊派(健身派・芸術派)はあくまで羊派であり、急に羊派が狼派(武用格闘技派)に転向することはできないのだ。』龍清剛『中国拳法 秘伝必殺 鉄砂掌』より
散手(組手)
上の単撃で紹介した、塔手から相手の腕を抑えて打つなどの例は、まだ実戦用法として、そのまま用いるのには無理がある。塔手からでは実際の交戦において発生する、敵との攻防空間の奪い合い、俗にいう間合いの攻防が省略されており、敵がこちらの行動に対して、対抗処置を行うということに留意する必要が、大幅に減じており、実際の戦いの様相からはかけ離れている。
相対稽古が塔手から始まるのは、あくまでも便宜上のことである。昔、日本で散打大会が盛んだったころ、中国武術の者が、日本拳法や大道塾など他の格闘技の者と試合をして、よく投機的に突撃をして沖錘(真横を向いて突く打拳)で突いては、難なくエスケープされ、距離をとられて小刻みに一方的に打たれたり、カウンターで一撃で沈められるという光景が観られたが、これは間合いの攻防を知らず、くっついた状態からの攻防しか、ろくに稽古していないからだったのであろう。
聴勁の練習とは成りうるが、相手と接触してからの攻防練習だけでは、たとえ何十年稽古を積もうとも、まともに戦うことなど不可能である。手脚、身体の打たれ強さを養う練功(排打功)を行い、単撃(用法を練習する約束組手)、対練套路(型形式の約束組手)、散手(定まった技の応酬から離れた自由組手)、博撃(より真剣勝負に近い形式の自由組手)と進み、組手慣れをして経験を積み、自信をつけておくことは必須である。現代は便利な防具もあり、組手や試合を行わない理由はない。普段から人を殴る練習をしていないと、いざというときに心理的な抵抗もあり、容易く人は殴れないのである。
このような逸話もある。かつての中国では、武士階級が支配した時代が長かった日本とは異なり、武術家と武術のステータスは非常に低く、野蛮なものと忌避される傾向にあったが、日本の武道や欧米列強での武道、格闘技の隆盛とその地位之高さをみて、中国武術は国の国技であるとする機運がしだいに高まっていった。中華民国年代に入ると、中国武術には正式に「国術」という総称が与えられ、国術には国民の健康を増進させ、精神力と体力を向上させるものとされ、近代国家を支える精強な兵を育成する基礎となる役割が期待されるようになった。
1928年には国民党の張之江将軍がプロジェクトのリーダーとなり、国術の研究機関として「国術研究館」が設立され、これがのちに、「南京中央国術館」と名称があらためられ、国術の全国的統一機関としての役割が与えられることになる。中央国術館には、内家拳最高の達人であると認められた孫禄堂が、武当門長として招聘され、中国全土から馬英図など、約400人もの優秀な武術家が集められ、孫禄堂が大会審判長を担当し、「第一次国術考試(國術國考)」という、優秀な武術家を選別する大会が開催された。
そこでは徒手による格闘試合も実施され、抽選によるトーナメント形式で選手の対戦が組まれ、無防具、目や金的、喉への攻撃のみが禁止、反則3回で失格、ただし重大な反則行為が認められる場合、即座に失格という過激なルールで試合が行われたのだが、それで判明した事実は、対戦はまるで素人の喧嘩のような殴り合いの様相を呈し、互いに相手を倒すことが出来ず、とにかく引き分けが多いという結果で、絶招(使用すれば敵を必ず倒すことが出来るとされる招法のこと)だとか、武術の功力(実力)のある者が打てば、一打で相手は必殺だというような、武術の誇大宣伝的な迷信の無意味さが白日のもとに晒されたことであった。
技撃の研鑽を真剣に追求しないのであれば、武術は形骸化し、戦う技術としての有効性は保てないのだという事実が、明確となったのである。中央国術館では、その後もこういった試合や組手が行われ、ボクシングさえも大会が行われ正課として研究されていたのである。
どうか現代において武術を志す者も、この先人たちの前例を真摯に受け取っていただきたいと願う。
それと組手は擂台(らいたい : レイタイ 中国武術での試合の場)で争われるような、勝ち負けを決めるものではない。あくまでも稽古の一環であり、互いの配慮と忖度があって成立するものである。
ガチスパーだといっても、やたらと危険な真似をする者は嫌われ、結果排除される。打撃技を全力でぶつけ合うことは稽古では危険であり、普段から素手素面で殴り合う組手を行う、太気拳ですら通常は避けられるものである。
理想は、まるで猫の仔がじゃれ合って遊ぶように、あるいは、子供たちが公園で遊ぶ仮面ライダーごっこのように、相手をしてくれる者と遊ぶかのようにやるのである。
その中で技を試し、良い技を放てたのなら自分の中だけで喜び、相手に良い技をもらったと感じたなら、心の中で自己の未熟を反省し、次に活かすと心得、相手の見事な技巧に敬意の念を持つことである。負けた体勢に追い込まれても、勝ち負けを決める場ではないので、そこで無理をして勝とうと足掻かないことである。そして追い込んだ方も、察して相手を危険な体勢に追い詰めないことである。こうすると事故が防がれ大きな怪我もなく、組手稽古が出来るようになる。
それと、このような稽古では俗にいう、組手ゾンビはとても嫌われる。まともにもらっていたならば、倒れるであろう技を、相手に気遣って止めてもらっているというのに、それを無視して平気で突進してしまうような行為である。これでは兆しを察し、間合いを読む稽古に全くならない。本気の比武(腕くらべ、試合のこと)でも、そんなつもりだとしたら、たちまち殴られて、近づくことすら出来ずに倒されて終わりである。武術では相手の手脚を刃物だと思う認識も必要である。
どれほど強かろうが、自分勝手で自己の強さばかり誇り、自分より弱い者に対してリスペクトのない者は多くから嫌われ、結果孤立し、自然と上達は阻まれ、去っていくものである。
『君は人より強いよ。だから負けたら恥だ、後れをとったらプライドが、自分が許せないと考える前に、推手や組手は一稽古と考えなさい。それを良く考えたら後輩には、愛のある組手をしてあげなさい。』澤井健一。
編集者の経験上のことだが、達人といわれる本当に強い先生は覇気があり、恐ろしく見えることはあっても皆、根は優しいものであり、その反面、武術・格闘技で優しさに欠け、他人の感情を無神経に軽視して不快させる言動が目立つ者、周囲の献身的な優しさによって、先生と御立てられている、反社会性を見せる者たちは、師の権威だとか、門下での序列を頼りとする、増長した批評家、自称達人、フォトジェニックな型や旦那芸を魅せるだけの大した実力の持ち主ではない者たちばかりであった。
キツイ言い方だが、彼らのような者たちは、自己だけを愛し、自らの中で思い込んだ正しさを振りかざす、他者への共感性に欠けた病人であるのかもしれない。
このようなタイプは虚勢をはり、外面を取り繕うことは巧みだが、肥大したプライドの持ち主で、弱みを見せかねない同好の士が集うような検証の場に出ることや、他との交流を異様に嫌がるので、すぐに分かるであろう。
また組手をやっていたとしても、事故で相手から思わぬ痛打を受けると、当てられてしまった自己の未熟を顧みず大騒ぎして怒り、相手をなじったりする様で、武術家らしくない、女の腐ったようなたちの悪い者がわかるときがある。上手い相手に手加減をしてもらって貴重な勉強が出来たというのに、実戦では自分が勝っていたつもりになっている痴れ者がわかったりと、組手は人間の本性がわかるものであったりもする。
比武をして、万が一負けたとしたら、流派が破れたことになるので駄目だなどと、大げさに論点をずらして身内に述べるやからもいる。
日本の武術の界隈では「実戦はオワコン」などという、寝言のような主張がまかり通りつつあるが、2021年現在、中国は空前の格闘技ブームの真っ只中で、武術愛好者の数は著しく増加し、陳氏太極拳など伝統派の武術家も盛んに比武を行い、使えないもの、戦えないものは、淘汰されつつある現状にあるのは皮肉的である。世界的にも積極的に、MMAの試合に選手たちを送り出している門派も存在する。
日本の中国武術や古武術の界隈で、妄想的な者や、すでに強さを諦めたような者は、得てして武道競技の選手たちの試合や格闘技の試合を武術ではない、ルールがあり実戦ではないと嘯くが、アスリートは金銭や名誉を賭けて、怪我や死のリスクすらある、厳しい勝負の世界に身を置き、日々さらなる高みを目指して、研鑽を続けているが、これが実戦でないとするならば、実戦とは、一体どれほどの過酷な闘争を指すのであろうか。戦場での戦闘やストリートファイトであろうか?
素人のプロ野球ファンが野球中継を観て、あれこれ批評するように、傍から言うだけならなんでも述べられるものだが、武術は自身が実践するもので、実証されなければ他人の信用は得られないものである。
自身のひ弱で覇気もなく、荒事などとても出来ない有様を客観的に鑑み、口を慎まれ、武術全体を愚弄するのは止めていただきたいものである。
武術は試合が全てではないが、程度の低い武術愛好者の実戦を持ち出した、雰囲気的な物言いの口功夫マウンティングは、在来武道や他の格闘技の実践者たちから、非常に悪印象に思われ、中国武術が蔑まれて見られる大きな原因となっている。
適度な負荷で効果的なボディーワークがしたいなら、『あへあほ体操 』のような、専門のボディーワークとして創られたワークアウトや、スポーツクラブのスタジオレッスンにあるような、各種トレーニング種目、ボディー・コンバット、ヨガ、ピラティス、健康太極拳で済み健全であろう。
』のような、専門のボディーワークとして創られたワークアウトや、スポーツクラブのスタジオレッスンにあるような、各種トレーニング種目、ボディー・コンバット、ヨガ、ピラティス、健康太極拳で済み健全であろう。
あえてわざわざ怪我をするかも知れず、先人たちが真摯に伝えた戦いの武技であり、突き詰めると必ず苦錬と技量の確かさが要求され、他者と相対的に実力が比較されることとなる、武道や武術、格闘技を学ぶ意味は薄いと思われる。
どうかライト感覚に伝統武術を愛好するにしても、武術の持つ本来的な意味、武術とは脅威に抗うという切実な目的によって生み出された戦闘技術だということを忘れず、自分のところがやっていないからと、組手や、肉体鍛錬ごときで批判して大騒ぎせずに、実用的な武術を求めて真剣に稽古を行っている、実戦派への敬意は払って欲しいところである。
長くなったが、自分が所属する会で組手練習が行われていない、安全に稽古できないという場合は、『掛け試し稽古会 』のような武術、格闘技の流派・会派を超えて組手で交流する集いがあり、個人からでも気軽に参加出来るのでお勧めである。
』のような武術、格闘技の流派・会派を超えて組手で交流する集いがあり、個人からでも気軽に参加出来るのでお勧めである。
掛け試し稽古会の主催者は、極真空手の元世界王者であり、武林隠者の達人として、長らく武術家たちの間でしかその存在が語られていなかった、達人たちを教える達人といわれる、刀禅 の小用茂夫
の小用茂夫 師範について形意拳を学ばれており、この集いには、中国武術や古武術の修行者たちも数多く参加している。
師範について形意拳を学ばれており、この集いには、中国武術や古武術の修行者たちも数多く参加している。
活法・薬功
活法について少し述べる。顔面蒼白で気絶している場合は、呼吸が止まっていないのであるなら、その場に安静が基本である。腹部への膝蹴りなどで、横隔膜が痙攣し呼吸が苦しく呻いているようなら、相手を仰向けに寝かせ、その上体を、背中からしゃがんで抱えあげて起こし、自分の両膝で胸椎の棘突起を挟むように圧し、抱え上げて軽く脊椎を垂直牽引する方法が、活法として有用である。
同じように両肩甲骨の間にある霊台穴(第6胸椎棘突起下方陥凹部:呼吸に関連する重要な経穴であり死穴でもある)に方膝を軽く当てて、牽引しながら圧して刺激する方法や、霊台穴を強く掌で拍打する方法もある。
腹部や胸部を打たれて、気分が悪い場合も、霊台穴を軽くポンポンと掌で数回拍打すると楽にする効果がある。こめかみにある太陽穴を、強めに親指で指揉法で指圧するなどもある。睾丸を蹴られて呻いているなら、腰の尾骶骨を後ろから掌や拳で数回軽く拍打し、続いて仰向け、あるいは横向けに寝かせ、臍下の下腹部を掌揉法で圧しながら回し撫でると楽になる。
鼻血を流してしまったり、目尻が切れて出血がある場合は、首筋にある亜門穴を数秒強く、指で圧迫することを何度か繰り返すと止血に効果がある。
推拿(中国の整体マッサージ法)や気功療法で施術する際、手に冷たさや痺れのような感覚を感じることがあるが、これは患者に清気を与えるかわりに、濁気を受けているからだといわれている。
上手い施術者はこれを理解しているので、自分の気が奪われることを最小限に抑え、患者の体内で滞った気を循環させるようにする。施術を終えたら、手で腕をよく擦り濁気を手先に集めて、水滴を振り払うように濁気を手から、屋外や樹木などに向けて、身体の外へ振り払ってしまうのが良い。
完全に気絶して動かない相手には人中穴に鍼を刺す、もう脈が止まって戻らない場合は蘇生法として会陰をつま先で蹴ってみる、というのが伝えられているが、こうなってはもはや手遅れ感がある。
重大な事故があった際は一刻も早く医療機関に連れていくことである。
胸部への打撃による炎症、気血のめぐりが悪くなる症状に対しては、漢方の瘀血(おけつ)薬(桃核承気湯など)が効果があるといわれている。排打功の効果を上げるものとして枸杞茶、枸杞の実、「補中益気湯」などがある。
八卦掌の孫錫堃は毎日、生の枸杞の葉を食していたそうである。ちなみに枸杞子には抜群の補気効果があり肝腎陰虚からくる眼精疲労、老眼などにも効きく。東洋医学において目は「五臓六腑の精気はみな目に注がれる」といい、その健康維持には五臓六腑全ての臓器が関わるが、特に肝と密接な関係があり『肝気は目に通ず、肝和するとき即ち目良く五色を弁ずる。』といわれる。
また枸杞子の甘みは四肢の働きと密接な関係にある脾胃にも良く、足腰が弱った際にも用いられる。枸杞の実は、諸臓腑を滋養する、天然の万能薬的な生薬ともいえる有用なものである。
昔日の中国武術において鍛錬に漢方薬を用いることはいたって常識的なことであった。これを薬功という。
ただ、「補中益気湯」や「杞菊地黄丸」などのオーソドックスな漢方薬。身体全体を改善させることで、
様々な治療効果が得られるようになされた処方の補気剤以外を用いる場合は、注意が特に必要となる。
本来、漢方薬の処方は「辨証論治」といって「望診(体つきや、舌などを診る)」、「切診(腹の上から内臓を触って診たり、脈を診る)」、「聞診(話し方や声の調子、腹の鳴りや咳などを聞く)」、 問診(患者に自分の症状を訴えてもらう)」など以上四つの診断法を経て「証」という個人の体質と、 病の病状を細かく分析して用いられるもので、素人が安易に補気・補腎剤以外の薬に手を出したりすることは、漢方にも副作用があり危険である。
必ずイスクラ産業 と提携しているような、老舗の漢方薬専門店で、知識のある薬剤師と相談し自分の証を診て貰ってから服用することを勧める。 また証が合わず、その薬が効果を発揮しない場合や、その薬その物が手に入らない場合は、同様の効果をもつ処方が必ずあるので、煎じ薬を入手すれば良い。良薬口に苦しとはいうが証の合った薬は、どこか美味しく感じ、合わない薬は非常に不味く感じ、服用後胃が痛くなったりする。
と提携しているような、老舗の漢方薬専門店で、知識のある薬剤師と相談し自分の証を診て貰ってから服用することを勧める。 また証が合わず、その薬が効果を発揮しない場合や、その薬その物が手に入らない場合は、同様の効果をもつ処方が必ずあるので、煎じ薬を入手すれば良い。良薬口に苦しとはいうが証の合った薬は、どこか美味しく感じ、合わない薬は非常に不味く感じ、服用後胃が痛くなったりする。
古典的処方にある「飛竜奪命丹」のような、強すぎる薬功をもつ薬は、一切用いる必要がない。極端な例では武術家の伝える処方には、ネズミの糞やゴキブリ、トリカブト、ヒ素、硫化水銀などの劇薬が含まれた薬があるが、これはこのまま放っておいて、死んでしまわれるよりマシであるから使われ、少量の毒は薬である、という漢方の古典的な考えから来たものであるが現代ではほぼあり得ない処方である。
オカルトっぽい言い方となるが、現代の東洋医学は、表向きは西洋医学の臨床に寄せているが、そのコンセプトは身体ではなく、人間の霊魂を治療するもので、西洋医学とは理論体系が全く異なるものである。経絡・経穴も解剖学的にはなく、三焦、心包も実質臓器などない。漢方薬も成分に含まれる気が重要だという。しかし不思議と西洋医学からの見地と一致し、治療効果があるものである。
武学: 護身と武術を学ぶ心がけ
実戦的な武術を学ぶうえでの心得を述べるが、古伝の武術は大成に至ると、その姿は各人それぞれあり、師と似ていると間違いである、一人一門派などともいわれ、本来、わずかな振り付けの違いのようなものに伝承の本質はない。
現代は型の表演に、過分に体育的、芸術的な要素がはらんでしまったためか、皆が皆、判で押したかのような動きをするが、武術における伝承の本質とは、型にはめられることではなく、拳理に沿ってその拳の実用性をより高めていくことにある。
それが先師にむくい、伝統と流派を守るということである。本来、武術が実用を考え強さを追求していくのは、純粋であたりまえのことであったのだが、この気風は治安の改善や社会不安の低減と共に、平和ボケした現代の日本では失われつつある現状である。
しかし、この日本においても目にふれないだけで、新聞やテレビのニュースにならないような暴力沙汰や傷害事件が毎日のように頻発しているのである。
人の恨みを買えば、いつか堪忍袋の緒が切れた者が、報復にやってくるかもしれないのである。
編集者の同門の刑務官いわく、刑務所の中はそうやって過剰な暴力を奮ってしまった武道、格闘技の経験者でいっぱいだそうだ。ちなみに台湾では、現代においても武術家同士でトラブルとなると簡単に血の雨が降るという。
基本的に警察は、事件が終わってから来るものである。弁護士も実際の暴力は抑えられない。
自分が暴行され、救急車で運ばれてから警官に来られても然程の意味はない。事件の解決が火葬場で荼毘にふされたあとでは最悪であろう。人から恨みを買わずと争いを避けることである。
ちなみに暴漢に路上で殴られたなど些細な事件は民事で訴えたところで、裁判官から勧められ相手側の弁護士から提示される和解金の額は僅か10万円程度である。刑事事件として訴えようとしたところで、相手が反社会的組織に属さない素人であるならば、検察は端から起訴にはせず起訴猶予処分が関の山で、相手には前科すらつかない場合が殆どである。オマケに民事で和解となっても、相手が支払いをしぶり僅か10万円すらも支払われ場合がある。口座に金が無く財産と呼べるものが無い相手からは差し押さえしようにも何も代償など得られない。なら暴力に曝されたなら必死に抵抗するなり、その場で殴り返した方がマシであろう。
喧嘩のような傷害事件は司法が特に面倒臭がるものであり、民事で慰謝料を要求しようにも、双方が暴力で争ったと主張されると、非常に面倒なことになり、これは刑事民事でも同じである。
俗に言う「検事も喰わない糞事件」となる例が非常に多い。
それどころか被害届を相手からも出され反訴されると、双方が原告、被告となり裁判となれば刑事罰となる例もあるのである。
また民事で勝訴したとしても、相手がたとえば生活保護受給者のような福祉で暮らす者や、破産者のように差し押さえされる財産すらないのであるならば、たとえ1億円請求したところで、1円すら入ってくることはない。こうなると裁判の費用すらも回収出来ないのである。銀行口座の金の差し押さえの為に弁護士が口座を照会するにも、ひとつの銀行を調べるだけで数万円もの手数料がかかる。ちなみに口座を差し押さえると、その1割か2割の金額が弁護士への報酬となる慣例だが、口座に10円しか入って無ければ、弁護士へは1円となる。複数の口座でこんな有様では依頼主の方がバカをみてしまう。
裁判慣れした者の中には、弁護士を立てず自分で裁判にのぞみ、何年も判決を引き伸ばしては、相手を時間的、金銭的に疲弊させる作戦を行う者もいる。
また、喧嘩をしておいて負けて自分は被害者だと主張し、不都合な部分を指摘されると記憶に無いなどと答えて、供述に偽証を疑われた場合、検察に追求を受け、非常に面倒なことになる。偽証の陳述は傷害罪より重い罪に問われる。
今は公園にさえも監視カメラが設置されており、事件となれば事件現場の足跡ですら検証されるのである。それで嘘がバレて、その時は強く頭を打たれて、忘れていましたなどと答えると警察や検事からの信性は最低となる。
交番勤務の警官でも、刑事起訴が可能な「微罪処分」も面倒である。
器物損壊などで相手を訴えてやると強く主張された場合、警察官はしかたなくその手続きを行うことになるが、その場で前科こそ付かないが、煩雑な手続きに、双方が交番などで大きく時間を奪われ、被疑者は職歴等と指紋、顔写真が警察署に登録されることになる。
しかしこれもくだらない喧嘩の場合、相手にも同様に訴えると主張されると、泥の掛け合いになるので、全く良い結果とはならない。たとえ警察に相手にされて事件化されたところで、裁判となれば互いが罪に問われることとなるため、裁判までは至らず起訴猶予処分で終わるのである。
それどころか、殴り合いの喧嘩のような些細な事件の多くは警察が被害届を受け付けることすら拒むのだ。
大阪では、腹でも刺されたら相手にしてあげるという感じだったというと、編集者は元アウトローの知人から聞いた。受け付けなければ事件にさえならないのである。
チンピラが繁華街で喧嘩を売った末逆襲され、血塗れにされているところを通報されて、警官たちが現場に押し寄せると、双方、俺は喧嘩をやっていないよ、と主張して押し通し、二人共捕まることもなく、ただ運転免許書を控えられるだけで、解放されるという事例さえある。
よく情けない者たちが、比武を避けるために、決闘罪だなんだかんだと騒ぐが、決闘罪が日本の歴史上で適用されることは極稀で、もし決闘罪で逮捕されたら、ニュースになるほどである。決闘罪がとわれるのは、大きな事件となっても双方から被害届が出されない事態を警察が重くみた場合だけである。
決闘を仕掛けられて受けて負けました、などと警察に駆け込めば、傷害で双方が任意動行されてそのまま留置場送りにされかねない。
弁護士が悪徳であった場合、商売であるため、全く勝ち目のない訴訟であっても、いつまでも示談にはさせず、起訴猶予の却下処分などを勧めて、養分から血を吸い続けようとするので、結果、何年も時間と金銭を浪費させられたあげく、やっと顧客が「日本の司法はおかしい!」と気づくまで、事態の収拾が図れないこともよくある。
その前に最悪、訴えた側が襲撃され丸裸にされて写真を撮られる、「お子さん可愛いいね(^^)(訳:もし後で何かあったら、お前本人だけではなく、家族をターゲットにしてやるからな)」などのまるで心の殺人行為のような恫喝をされて強制的に収められることさえあるのだ。
ちなみに武術家同士の喧嘩沙汰は警察や司法からは、試合であるとみなされ、殆ど相手にされることはない。
武術家同士が揉めて、試合にまで発展した場合、このような例をよく知っているので、敗北した側が訴えるなどいうことは稀である。また負けて訴えるような武術家など笑いもので、そんなとこに通う生徒などいないであろう。
トラブルで起こった武術家の殴り込みは、行くと相手に平頭平身されて「先生、お茶をどうぞ(汗)」となって卑屈に謝られる例も聞かれる。
ちなみに近年は武闘派とは縁の無い者が、インターネット上の誹謗中傷に端を発して争う例が見られるが、無知ゆえに、かえって事を大きくする傾向がある。
まあ、インターネット上での匿名の誹謗中傷など訴えようとすると容易く、仮に経済的余裕が無かったとしても、予め自分が住む地域にある、ネットでのトラブルが得意だと謳う弁護士の事務所を自身で選び、法テラスを通すかたちで弁護士に依頼すれば、直接自分で弁護士に依頼するよりも格安で発信元を開示させることが出来るのである。
費用の支払いは月々5千円など少額での分割払いが可能である。ちなみに生活保護受給者の場合、全額無料となる。法テラスを介して弁護士に依頼するのには、法テラスが定めた所得以下の収入であるという制限がかかるが、法テラスが利用出来ないなら、弁護士への依頼料の相場は50万円程度である。
先に着手金として20万円を支払い、事件の解決後に残りの30万円を支払うというような契約となる。
弁護士は面倒な作業を避けがちで、その方が労力が省かれて結果的に儲かるので、双方に即時和解を勧めるが、それで言いなりのまま和解が決まると、加害者が支払う和解金は100万円を超える場合もあるという。
悪辣なケースであるが、先に難癖をつけておいて相手を激昂させ、暴言を引き出した加害者であるのに、世間には被害者を装うことも可能である。
また和解には和解金のほかに、法的拘束力は無いが事件の内容を告訴した側の都合の良いように公衆に向けて発信し、相手側の反論を一切封じる意図がある条件が課されることも多々ある。とはいえ、そのような内容が公衆に発信された事実が明らかとなると、今度は被告側への誹謗中傷となり反訴のキッカケとなったりもする。
相手側の意図が知れこのような結果が見えているなら、裁判で争う構えをみせるのも有効である。
刑事事件の侮辱罪は起訴は難しいが敗訴すれば前科がついてしまう。もしそれで法廷で争うことになったなら、相手側に落ち度や語られては不都合なことがある場合は、その点も証言し、第三者から協力が得られるようなら告発をしてもらい、相手側のした別件の誹謗中傷などを提示して、向こうから和解を申し出させる戦法で対抗することも可能である。
他にも法務省の人権擁護局でも、個人での企業相手の開示請求の依頼の方法や、書き込みの削除を申請する方法を教えてくれる。
海外にサーバーがある、5chのような匿名掲示板においても、昔と比べれば犯罪に関わると疑われる開示請求だけでなく、個人の誹謗中傷による開示請求にも積極的に応じるようになったといわれている。
ちなみに、Twitter上での誹謗中傷で自殺された、ある女子プロレスラーのご両親は、開示請求は警察ではなく、法務省に助言を貰って自力でされたと、編集者はサイバー課の警察官から直接伺った。
また令和4年10月から法改正が行われ、開示請求の手間が大幅に簡略化された。弁護士費用も従来の半額ほどとなったという。以前は裁判まで1年掛かったが現在は3ヶ月ほどに短縮されている。
ただ注意するが、争う相手が素人のサラリーマンなどではなく、暴力での報復を厭わない者や不良(極道業界の用語でいうヤ◯ザのこと)や、何度も暴力事件を起こしている凶暴な精神障害等であったなら藪蛇となり、目も当てられない事態へと発展する恐れもある。お礼参りなどされては厄介である。さながらモデルガン1丁で相手を黙らせようとしたら、実銃を突き返されたような事態となる。
ちなみにヤカラたちと直接暴力的なトラブルとなると、次々と増援が招集されるため、仮に普段、数名しか待機していない小さな組に乗り込んだとしても袋叩きにされるのがオチである。
もし今どき、ヤクザの事務所に単身乗り込んで叩き潰したよと述べる先生が居たならば、「ああ、喜ばそうと夢を語っているんだなあ」と受け止めた方が良いと思う。
ちなみに街頭右翼は、ゴルフの打ちっ放しや土建会社を経営する社長などが、好きで趣味でやっている場合も多く、反社会的勢力とは一切関係ないこともある。そこの会社事務所に乗り込んだといっても別に自慢にはならない。
とにかく有事に際し、戦えることが出来るような強さがあってこそ、武術が護身となってくれるのである。
何かあったときに、大きな声で助けを呼べる力強い声、敵の追跡を振り切る脚力とスタミナ、周囲を警戒できる目と慎重さ、胆力も武術が養成してくれるものである。あと、正当防衛というものは成立が難しく、過剰防衛として罪に問われるケースが殆である。なので身を守るにしてもやり過ぎないことである。
こちらに非がないなら、チンピラ相手の喧嘩など、三十六計逃げるに如かずである。弱者に非道を行われていないなら、いちいち揉めるのも馬鹿らしいことである。
チンピラを殴り倒したところで、彼らは実に頑丈で、心配になって、おい大丈夫か聞くと「兄貴に殴られなれてますから(^^)」と平気で答えたりする。喧嘩の途中で、これは逃げられず敵わないとみると、凄い勢いで許してくださいと土下座の体勢をとるので呆れ果てることになる。
もし街でアホに因縁をつけられたら、一応、相手に普通の会社員か土方かを問うて、そうだと言われたら「お前よくそんな真似ができるね!相手をみてやれよ!」と説教してやり、違うといわれたら、「あっ、そう…バーカ!」とでも答えて、脱兎の如く逃げるのである。
しつこく追ってくるのを、物影に隠れて逆襲して脅かしてやり、さらに様子をみながら逃げまくっては疲れさせ、頃合いで一気に引き離し、視界からアホが消えたなら、タクシーを拾って、ああ面白かったな(^^)と愉しく帰るのである。
困ったことにガタイの良い者相手にも、あえてチャレンジしてくるチンピラは盛り場には意外と多いのだ。酔っ払って気が大きくなっているからである。
ちなみに編集者は、家庭環境や不動産業という仕事柄みてきたが、現代のヤクザは可愛らしいお洒落なスーツを好んだり、外見でヤクザとはみられない、極普通の会社員のような格好をしているのが大半である。ギラギラした派手な威圧的な格好をしているのは、概ね盃を貰っていないチンピラか、建設作業員、風俗店の店長、飲み屋グループの経営者などである。
彼らが首にかけている金のネックレスやブランド品の品物、腕の高級時計は、もし生活が苦しくなったら質に流すための財産でもある。普段、仕事に忙殺されているので、せめてファッションくらいは格好良くキメたいという思いもあるそうだ。
また、和彫を入れているからといって、ヤクザだと決めつけてはいけない。漁師町では、年配の漁師が全身に入れ墨を入れ、町の保養施設で湯に入っている姿もよくみる。和彫を入れている者が腕の良い美容師であったりもする。
テキヤとヤクザは境界があいまいだが、露天業の人間は、自分たちは神農に従う者であるとして、人様を喜ばすために真面目に商売に励んでいるのである。ちなみに日本における中国武術普及のパイオニアであったある先生の実家はテキ屋であったという。
余談だが、現代の日本で喧嘩に巻き込まれたり、武術家同士が比武で決着をつけるケースは少なくなったと思われるが、海を越えた台湾ではいまでも凄まじいもので、対応を間違えると、すぐに黒社会の人間が出てくる有様である。
たとえば近年あった事件だが、ある柔術家が、秦の始皇帝の子孫を名乗るある唐手家を愚弄して、試合をすることになったのだが、道場に行ってみると黒社会のヤクザが30人も居て、柔術家はタコ殴りにされたうえ、アキレス腱を刃物で斬られて半殺しにされるという出来事があった。中華系でも特に台湾人は気性が激しく、暴力で物事を解決しようとする性質が強いという。中国や香港の黒社会の人間からも台湾人とは交渉にならず、揉めると危険だと認識されているほどである。
特に言っておくが、武術には弱い者のための武術も、強い者がより強くなるための武術の区別などない。武術は一つである。武術が求める第一義は、ただ純粋な強さを求め、結果、無用な争いを未然に防ぐことである。確かな実力があると認識される者に、無謀な戦いを仕掛ける者はいないのである。
それと武術の界隈では不思議なことに、根拠も無く、あるいは、数々ある達人のお伽噺のようなものを拠り所とし、新しいものが古いものに劣ると思われがちなのだが、そこは熟考されて欲しい。
『武術と言うものは形があるようでその実、定型化されてはいない。故に変化が可能で、極論を言えば常に流動的なものでなければならない性質のものなのである。これはひとえに時代によってそれぞれの戦闘形態が異なるためである。
いわば、各時代によって移り変わる戦闘形態に順応できなければ容赦無くその門派はその代で確実に滅び去る運命となる。(例えとしてはあまり良くないが)これは近代化と共に激しくなる兵器の開発競争に似ている。
武術と言うものは何だかんだと騒いだところで、しょせんは技術にすぎない。戦闘における実用性が何よりも求められる中に於いて、すでに旧態化してしまった技術にいったい誰が目をかけてくれるだろうか?これは考えるまでもなく当然の理と言える。さらに、武術(技術)は一個人の憶測や推論だけでは絶対に生まれるものでは無い。
敵(相手)が存在してこそ、初めて必要性により生み出されるものである。当然、各時代によって敵が変化すれば、それに応じる形で従来の技術を何らかの形に変えなければ、武術としての実用性はおろか存在価値すらも無くなってしまうだろう。
よく誤解されるのが「開祖の代から完成されたまま今日まで伝わっている」とカン違いしている人が多いが、正しくは「開祖の代より、各時代々の戦闘形態の推移に適応する形で、本質を失う事なく変化し続けて今日に至っている」となる。』私学校龍珉楼館長館長 呉伯焔
武術の原初の姿とは、ゲームや舞踏、芸能などではなく、武人の戦闘術であり、暴力の行使の方法とその対処法を学ぶものであることには大いに留意して欲しい。道場も本来はカルチャースクールではない。修行の場である。
外見はスポーツ、体操にも似ているが本質的には禍々しいものである。打たれたら痛い、死ぬのは怖いという脅威に、あらがう必要性をもって生まれた技術である。
であるので、武術に超能力めいた空想的な夢を持ちすぎると、中年、老境に差し掛かった辺りで、結局それらがなにも得られなかったことに気づき失望し、武術を止めてしまう者も多いのである。
戦う技術も型に秘められた用法さえ知らず、ただ漠然と型をやればいつか功夫が付き、それで強くなれるというのなら誰も苦労はしない。また型や発勁は武術の一部であるが、その全てではない。安易な盲信や幻想をとり去り思考停止に陥ってはならない。
スピリチュアル方面から武術に入って挫折した者が、別の安易な疑似科学的な身体操作法や、仙術、心霊術まがいのものにハマり、引き続きファンタジーを追う例もよくみられるが、そういう者たちには、言い聞かせても反感を抱かれるだけなので、そっとしておくと良いのかもしれない。人には自由意志があり、本人がいくら狂っておろうと周囲に害がなければ自身の修行の方が一番大事である。
『昔、武芸の道に志したものは、情熱ゆたかで志は固く、技術の修練によく務め、挫けず、怠らず励んだものである。師匠が教えたことを信じて日夜心に研究を重ね、実技を試み、疑問があれば友に尋ねて、修業を積むことによって自らその道理を身に付けた。したがってその理解は、とことんまで徹底したものである。
師匠は、最初は技法は伝えても、それに含まれている道理を語ろうとはせず、自ら理解するのを待った。これを「近づけはするが明らかにはしない(引而不発:引きて発せず)」という。
これは惜しんで語らないのではない。この段階で心を働かせ、修行の実を挙げることを願うからこそのことである。これが古人の教育方法であった。これによって昔は、学術も芸術も、ともにしっかりしていて内容が豊であった。
今日では、武芸を学ぶ者も情熱が薄く、真剣な志を抱いていない。若いときから骨の折れることをいやがり、手軽なことを喜び、小手先のことで手早く上達するのを望んでいる。このような者に対して昔のようなやり方で教えたのでは、修行をしようという者がいなくなってしまう。
そこで今日は、師匠の方から手ほどきをして、初心者にも極意を説明し、その実際を見せ、さらには手をとってこれを教えこむほかはない。このようにしてもなお、退屈して修行を止めてしまう者が多いのである。
次第に理屈のレベルが高くなって来ると、古人の説では足らないと言い出して、修行の量が少なくても、天にも登るほどの技が出来る様に工夫をしようとする。これもまた時の勢い、しかたないというほかはない。』『天狗芸術論(口語訳)』から引用。
それと魅せることを重視したような、見栄えのある風に套路を表演できないというなら、嘆く必要はなく初めから出来ないで結構なのである。
そして歳をとったら歳をとったなりに、それ相応な円熟した武術をやればよいのである。若い一時だけできる剛猛な動作に拘らないことである。武術は新体操ではないのである。
また武術を養生と考え、その中に一種の哲学を見出し学問として探求することを、武学という。
武術は楽しいから続ける、それだけでも善いのである。武術は道徳を説かないと主張する者もいるが、それは途轍もない間違いである。
基礎知識
歴史
清朝末期、形意拳は山西省祁県で伝えられた戴氏心意拳(戴氏六合心意拳、たいししんいけん)を元に、李飛羽(李農然、李洛能 1808年 - 1890年没)が技法内容を今の形に近いものに改編し、実質的な開祖となって創始された。李洛能は生涯無敵といわれ、人と技を比べるときも「常に心の欲するまま動きつつ、手はおのずから至る」という入神の境地にまでに達していた故に、人々はついに彼のことを「神拳李」と呼び賞賛を惜しまなかった。 その弟子たちにも達人が多く輩出され、その拳名を高めた。
戴氏心意拳のルーツである心意拳は、明代末に姫際可(姫龍峰 1602年 - 1683年) によって創始された。姫は槍の達人で神槍と呼ばれていた。
形意拳譜の「姫際可自術」で語られる伝承によると、姫は旅先で立ち寄った古刹で、夜に雨のなか剣を抜き獣を追い払い悲しみにかられて歩いていると、土埃の中から不思議な光が立ち昇っているのを見て、そこを調べてみると一振りの宝剣と木箱があり、木箱の中には南宋の武将、岳飛によって書かれた六合拳経(武穆王拳経)という秘伝書があったという。その後姫は、十年の歳月をこの拳譜の研究に費やし、失われた岳飛の武術(鷹爪翻子拳も同じく岳飛を創始者としている)を復活させ、平和な時代には槍よりも拳法が重要になると考え、「槍を変じて拳となし、理を一本となす」と 槍の技を拳術とし、晩年はその技を科挙に首席で合格し、高級官僚となったほどの秀才、曹継武ただ一人だけに伝えたという。
曹は心意拳を馬学礼と戴隆邦の二人に伝え、前者が心意六合拳(河南派形意拳)、後者が戴氏心意拳として伝えられていった。岳飛からの伝承については、おそらく伝説上のことであると思われる。姫や曹の実在性すら疑問符がついている。心意拳のルーツは少林寺の心意把であるか、共通のルーツを持つ同種の拳術であったと思われる(姫際可が少林寺に伝えたのだという説もある)。研究者によって様々な見解があり真実は不明である。心意拳はその拳譜(三三[六]拳譜)によって陳氏太極拳にも多大な影響を与えた。
心意拳と形意拳は、その名称の中国語での読み「XinYiQuan(心意拳)」と、「 XingYiQuan(形意拳)」は極めて似ており、発音からは両者は区別が殆ど付かない(カタカナでは「シンイーチュエン」が近い)。
形意拳は河北地方に伝えられ、これを河北派形意拳(劉奇蘭、郭雲深など)と呼び、発祥地である山西省に残った系統(形意拳としては河北省から山西省への再伝来があったため、これを「山西派を復興した」と表現される場合があるが、本来の山西派であった、戴氏心意拳は滅びてはおらず、家伝として世間からは人知れず継承されており、失伝したわけではなかった。戴氏心意拳が広く知られるようになったのは、1990年代以降のことである)を、山西派形意拳(車毅斉、宋世栄など)と大別するのが一般的である。そのなかでも伝人によって様々な系統に発展して門派を形成している。
形意拳は、第二世代目以降で、独自の工夫が加味され、八卦掌や太極拳の影響も受けて発展したものと思われる。この三つの拳の伝人は、互いに密接な交流があり、内家三拳というカテゴリーで括られ、併修される会派も存在する。八卦掌からは扣歩、擺歩などの動作が取り入れられている。
形意拳の分派としては李洛能の有力な弟子で「半歩崩拳、あまねく天下を打つ」と讃えられた郭雲深は、晩年、王向斉を最後の弟子とし、王は意拳(大成拳)を創始した。
王は日本人である澤井健一を弟子とし、澤井は帰国後、大成拳から名称を太氣至誠拳法(太気拳)と改め、国内での王向斉の武術の普及をはかった。
先師たち著名な伝人
岳飛 - 1103年~1142年。
字は鵬挙。河南省湯陰県の人。宋代の武将であり、中華民族にとって救国の大英雄としても名高い。貧しい農民の出であったが、極貧の中勉学に勤め、若輩にして文武共に極めたという。異民族の金軍が北宋に侵入すると義勇軍に身を投じ、数々の武功をたて『精忠岳飛』の書を授けられる。その指揮する軍は岳家軍と呼ばれ精強を誇り、民衆に絶大な支持を得て、やがて岳飛は湖北一帯を拠有する大軍閥の首領にのしあがるが、 金との講和を画策する南宋の佞臣、秦檜により、主戦派の筆頭であった岳飛は疎んじられ、謀反の罪を着せられ獄中で無念の死を迎えた。彼の死後は無罪が証明され、武穆と諡される。 中国がモンゴルによって支配された元朝の頃、岳飛は民族抵抗の英雄として民衆に大いに祭り上げられた。 武術の伝説として岳飛を開祖とする門派は心意・形意拳の他にも、岳家拳、鷹爪翻子拳など多数に及ぶという。また古来からの養生功として名高い八段錦も、岳家軍で行われた訓練法を元にしているという。
姫際可 - 1602年~1683年(生没年は推定)
字は隆風。明末・清初、山西省蒲州の人。幼少より聡明にして文武に勤め、槍術に長じ「神槍」と諡された。成長すると嵩山少林寺での修行を志し、10数年間の歳月を少林寺での修行と、僧侶たちの指導についやす。嵩山少林寺を下山した後、各地を遊訪しながら自身の武術を研くが、終南山のある古刹に訪れた際のある嵐の夜、辺りに木霊する獣の叫びに虚しさを感じた姫際可は、剣を取って獣を追い、飛び込んだ廟内の地面に不思議な光を見る。そこを掘り起こしてみると、岳飛の銘のある美しい宝剣と木箱に収められた岳飛の武術の精華が記されている秘伝書、『六合拳経(武穆王拳譜)』を発見する。姫際可はこれに驚喜し、その地で自身の槍の操法と、六合拳経に書かれている武術を、一つとするための修行に没頭する。こうして10年の月日が流れ、姫際可は大成した。槍法を拳法とかえ、その拳の中に十二種の動物の象形(心意拳では十大形)とその意、天地万物の陰陽五行の枢機を含有し、外形内意を一つとし、人体の外三合、内三合の六合の原則を余すことなく体現する形意拳(心意拳)が誕生したのである。
曹継武 - 1655年~没年不明
姫際可は心意拳を創始したが、伝えるべき者にこれを伝え、それが叶わぬ場合は、この拳を失伝させる覚悟で自分の有望な後継者を求め、再び各地を訪れたが、そこで出会った者たちはことごとく低俗で、拳を伝授するに足る人物を見つけ出すことは困難であったという。だがついに、秋浦において曹継武という逸材を見つけ出すことに成功し、心意拳は失伝を免れることとなった。曹継武は姫際可について拳を学ぶこと12年にして大成する。そして朝廷の文官採用試験である科挙に首席で合格し、陝西省の靖遠総鎮大都督にまで昇進し、退官後は洛陽において馬学礼、戴龍邦などに拳を授けた。
これが後に心意拳が、馬氏心意六合拳と戴氏六合心意拳にそれぞれ分派する切欠となる。
李飛羽 - 1788年~1876年
字は能然。通称、李洛能。河北省深県の人。幼少より武を好み長拳に優れていたという。37歳の頃、商用で山西省を訪れたおり、心意拳の戴龍邦の高名を知り、その門下に入るが、だが最初の2年間のうち、李能然が戴龍邦から教わったことは、僅かに五行拳劈拳の一行と、連環拳の片側半路だけだったが、それでも李飛羽はなんら不満も洩らさず、誠心誠意練拳に努めた。やがて戴龍邦の母親の80歳の誕生日の宴に一人、ただ連環拳の半路のみを演武したことを、拳術好きのこの老母になぜかと問われ、李がこれしか学んでおりませんと答えると、戴の母親は戴龍邦に李を教えよと命じたことを切っ掛けに戴の篤い指導を受けることなり、苦練して学ぶこと10年、47歳にして大成する。李飛羽は生涯無敵といわれ、人と技を比べるときも、常に心の欲するまま動きつつ、手はおのずから至るという入神の境地にまでに達し、人々は、ついに彼を「神拳李能然」と呼び賞賛を惜しまなかった。
李能然は、李太和(子息)、車永宏、宗世栄、張樹徳、白西園、劉奇蘭、郭雲深などの多数の門生を育てた後、年80余歳で椅子に端座したまま一笑して逝った。
形意拳の基本姿勢である三体式及び形意拳の今に繋がる基本体系は、この李能然によって編み出されたものと考えられ、この李能然が、形意拳の実質的な創始者として知られている。
郭雲深 - 1839年~1919年頃
李能然の弟子。兄弟子の劉奇蘭と共に河北派形意拳の重要人物。郭雲深の練った道理とは、つまるところ腹は実を極め、心は虚を極めることにあった。また兵書を好んで熟読し、奇門遁甲にすぐれていた。 郭雲深の生涯は波瀾と多くの伝説に彩られ、 敵に半歩進んで崩拳の一打を発すると敵は皆倒された為、 人々は「半歩崩拳、あまねく天下を打つ」と賞賛を惜しまなかったという。
また彼の最も有名な俗説に、試合で相手を誤って打ち殺した故に、殺人の罪により監獄に収監され、そこで手枷足枷を付けられたまま虎形拳を練り、虎撲子の一手を編み出したという逸話があるが、これは門内の人間からは全くの誤りであると指摘されている。
郭雲深は確かに人を殺め3年間を獄で過ごしてはいるが、これは義憤に駆られた郭雲深が、ある土地で民衆を苦しめる匪賊の首領に害意をもたれていることを承知で招かれ、彼にピストルで襲われた際に、愛用の月牙剣をもってこれを討ったからであり、人々はこれを賞賛した。また獄での郭雲深は彼に同情的な官警の者たちの配慮と、その義挙に感銘を受けた人々からの多額な献金により、獄での3年間を何不自由なく過ごしたという。
郭雲深は超絶の技法を誇る奇才であったが、時運に恵まれず、 彼の多くの弟子たちとは異なり、世俗での立身出世は叶わず、北方数省で多数の門人を教授したのみだったという。 後に故郷に隠棲し70余歳でその生涯を終えた。
異説として意拳の達人として著名であった韓星橋の証言では、郭雲深は獄には入っておらず、警察署長が郭雲深を自宅に匿い息子の錢硯堂に形意拳を指導させたそうである。この錢硯堂は推拿の先生でもあり、その指導を受けたのが韓星橋である。王向斎が上海で意拳の指導を始めたとき話題となり郭雲深を懐かしく思った錢硯堂が会いにいったのだが、韓星橋が錢硯堂に王向斉はどういう人か聞くと「いい人だ」と答えたということである。錢硯堂は王向斎の崩拳で吹っ飛ばされ大変喜んだという。
劉奇蘭 - 1819年~1889年頃
河北省深県の人。拳術を好み、李能然を拝して形意拳を学び大成した後は田野に隠棲して門徒に教授しつつ他派とも交流を保ち、門派に偏見を持たなかった。初めて劉奇蘭に会った者のなかには僅か数語交わしただけで拝服し、弟子になる者がいたほどである。一説によると、郭雲深に八卦掌の開祖董海川を紹介した者は劉奇蘭だったともいわれている。劉奇蘭は70余歳で終わり、その弟子は李存義、耿誠真、周明泰、張占魁などが有名である。子息の殿臣は『形意拳抉微』を著し、劉の道をさらに明らかとした。
車永宏 - 1833年~1914年頃
字を毅斉、李能然の最も優れた弟子だったいわれている。李は車のことを「車二」と呼んでいた。車永宏23歳のとき、 まだその子息李太和と共に、太谷県に留まっていた形意拳開祖の李能然は、 遠方の人々にまで、その武功を賞賛されていたことから、 当時、太谷県一の富豪であった孟某の家に招かれて、 護院(ボディーガード)の仕事に従事していた。 車永宏は李能然が形意拳に達しているとの人々の噂を聞き付け、 李に憧れ、以前から李能然の顔見知りであった友人の紹介で、 李能然の門を拝することとなった。
車永宏はそれから20数年の歳月を、昼夜をとわず苦練を続け、 農閑期には護院の仕事に従事するかたわら、人に拳を教え、 その名声をいよいよ高いものとした。 車永宏の晩年のころ、清朝は益々腐敗し、強国の侵入を排除出来なくなった為、 国はしだいに動乱の時代へとなっていった。 車永宏は必ずしも弟子に愛国的思想を激起しなかったが、 車が天津に赴いた際、車の武名を聞き付けたある日本人の剣術家に挑戦されるが、 車永宏はこの剣術家を試合で敗り、後に彼は車に入門を願い出るが、 車は民族の秘宝を軽々しく外国人に教えることは出来ないと、 その剣術家の希望を退けたという。
富貴をあたかも浮雲の如くみなし晩年田間に隠棲した。彼の育てた門人の内で著名な者は山西祁県の喬錦堂を第一として、布学寛、呂学隆、樊永慶など多数に上る。
宋世栄 - 1849年~1928年頃
李能然の二番目の弟子だったといわれている。河北省宛平の人。 17歳の時に山西省太谷県に移住してこの地で時計店を生業とする。車永宏と共に李能然の最も早期の門人の一人である。
幼少より武術を好み、義侠心に篤く、囲碁や戯曲を愛していた。太谷県にて時計店を開設したとき、この土地に李能然という優れた達人が居ることを知り、人の紹介を得て李能然の門を拝する。宋は李能然の教えを受けてから、夜となく昼となく練習を続け、間断することがなかった。李から学び奥義に達しなかった技はなく、十二形拳においては特に神技とも呼べるような、高い練度を人に示すことが出来たという。
たとえば、宋が十二形蛇形拳を練るときなど、蛇の性質と性能を極限まで生かし、体を左に転じたときは右手で右足の踵をつかむほどとなり、 右に転じたときは左手で左足の踵が掴めるほどであった。十二形燕形拳の一技「燕子抄水」を行うと、身体が地に低く接地するほどに成ったときは、既にテーブルの下を一瞬で潜り抜け、さらにそこから一丈も飛び越えるほどであった。「狸猫上樹」を練る際も、身を躍らせて壁に貼りつくと、 そのまま数分手足を粘りつけていることが出来たという。
また、宋がある人と試合をした際は相手が宋に身を躍らせて飛びかかり、一手出した瞬間には、その身は既に矢のような速さで二丈余りも投げた倒されていたという。しかもその時宗は身体を少しも動かさず、ただ両手を一振りさせただけのように見えたという。 当時、同門同道、あるいは武術界以外の人々さえも宋の神技を見た者は多かった。
『拳意述真』を著した形意拳の近世三大名手に数えられる達人の孫禄堂は宋世栄を賞して、「先生は物事の性質をよく見極め、その特性を活かすことをされた故に神妙なる技を伝えることが出来たのである。」と絶賛している。孫録堂が宋の元に出向いたとき(『拳意述真』では80余歳のころと記されているが、宋の享年は79歳である。)宋は気力に溢れ、身の動きも柔軟でまるで若き日のままであったと記されている。そして後進の健者も自分に及ばないことを嘆かれたという。
最晩年は宋は五台山にのぼり僧侶となり、以後は武術について語ることが無かったという。 宋の指導は厳格で、また人を選んで拳を教えた為、 生涯で教えた弟子たちの数は僅かに20余名に過ぎなかったといわれている。
孫禄堂 - 1861年~1932年
孫福全、字を禄堂、道號を涵斎、形意拳、八卦掌、太極拳の代表的な達人。河北省完県の人。 人々から形意拳の近世三大名手の一人と賞賛されている。また孫は単に形意拳の高手であるに留まらず、形意拳・八卦掌・太極拳の融合論を説いた、内家三拳を代表する達人の一人でもある。体格は細身で動作は敏捷巧み、跳躍技にも秀でていた為、「活猴(かつこう・いきざる)」との異名でも知られていた。
幼少より郭雲深の得意門徒であった李奎垣(李魁元)に形意拳を学び、後に李奎垣が閉門するとその師の郭雲深を紹介され、郭の元で練拳に努める。孫は郭雲深に最も長期にわたり教授を受けた門弟として有名であり、郭の赴く所、乗馬の尾を掴んで一日百里を付き従ったともいわれている。
また八卦掌の達人であった程延華にも拝して、朝は郭につき、夕べは程について、形意拳・八卦掌にそれぞれ熟達した。
この頃孫は就寝の際に、火を燈した線香を指に縛り付けて眠り、線香が燃え尽きた熱で目を覚まして明け方早くから練拳を行ったという。当時孫は他流試合において無敵を誇り、その為、郭・程の両師に「汝は師の名を辱めず。」と評価されたという。
清朝・民国年代にかけて孫は軍人を職とし、この縁で李存義、王向斉、尚雲祥など同門の多くの者を、 国民党軍部の武術教官(全国陸軍部武技教習所など)として推薦した。50余歳の頃には北京において旅先で病に臥せっていた、 武式太極拳の郝為真の看病をし、郝為真は回復すると返礼に孫に太極拳を教え、 晩年孫はこれに形意・八卦の術理を組み入れ独自の孫式太極拳を創始した。これにより孫は形意・八卦・太極の三門は意図するところ同じであるとの認識を得、内家三拳の合一論を説くきっかけとなった。
1928年には内家拳最高の達人であると、中国武術の全国的統一組織である南京中央国術館に武当門(内家拳班)門長として招聘される。だが間もなく中央国術館内部の派閥闘争を忌諱した為か、江蘇省国術館に退き、そこで副館長兼教務長に就任した。 孫は『拳意述真』、『太極拳学』、『八卦掌学』などの多くの著作を残し、内家三拳の術理の理論的裏付けに貢献が大であった。孫の門弟で著名な者は、孫剣雲(長女)、孫存周(二男)、胡鳳山などがいる。
李存義 - 1847年~1921年
河北省深県の人。形意拳を代表する武闘派であり、その気性は財を軽んじて義を重んじ、戦いにおいても生涯詐術を用いなかった。 形意門中最高の豪気義烈を誇った武人。幼少より長拳、通背拳など各種拳術を学び、後に劉奇蘭を拝し形意拳を学ぶ。さらに郭雲深、八卦掌の董海川にもついて学び大成する。
1890年には清朝の武官劉抻一将軍の兵士に武術を教え匪賊を討つことでしばしば功績があり、やがて昇任されるもそれを辞退して天津におもむき、商隊の護衛を主に行う万通金票局(ばんつうひょうきょく)を設立。後に金銭に全く拘らなかった李は資金繰りが困難となり、万通金票局を閉鎖する。李は金銭に困っている者が居ると理由を聞かずに施したともいう。
李は各省を住来して保金票の業に携わるが、 護送中に賊が襲いかかると、自ら単刀を揮って悉く撃退し、後に賊は、李が商隊の護衛をしていると知ると、それだけで襲撃を諦めるほどとなり、また当時、義気人に勝る李の名を聞いただけで道を避ける者もいたほどであった。それゆえ人々は「単刀李」の通り名で李を呼び、やがてその武名は中国全土に轟くようになった。
1900年、「扶清滅洋」(清朝を助け、西洋を滅ぼせ。)をスローガンに山東省で起こった宗教的秘密結社「義和団」は、清朝の支持を得て暴動を全国各地に拡大。やがて居留地民保護を名目にして出動した、日本・ドイツ・イギリス・フランス・ロシア・アメリカ・イタリア・オーストリアの8ヶ国連合軍との戦闘状態となる。これを受けて、義気篤く愛国心に富んだ李存義も義和団に既に参加している李の師兄弟に協力して参戦。最も戦闘の激しかった天津の戦いにおいて、自身の経営する万通金票局を率い銃火器で武装した日米欧の軍隊を相手に血刀を揮い凄まじい戦いを展開する。一説によれば、これが「単刀李」と呼ばれた本当の理由であるとも言われている。
辛亥革命直後の1912年には、袁世凱大総統の親衛隊の武術教官であった李瑞東に招かれ、天津に全国武術家の友和を図って設立された「中華武士会」の教務主任となり、つづいて上海精武體育会、南洋公学院 ( 交通大学の前身 )などで教え、また1918年、北京に世界第一力士と自称するロシア人のボクサーが、万国比武大会という試合を企画して武術家たちを挑発したことに憤り、これと試合して破り政府より一等金質奨章に授賞される。李の生涯教えた門徒は甚だ多く、尚雲祥、王俊臣、李彩亭、陳俊峰などが著名である。李存義は晩年においても少しも倦むことなく数多くの門弟を教え、形意拳の普及に尽力し1921年、74歳でその生涯を終えた。
張占魁 - 1859年~1938年
劉奇蘭の高弟。八卦掌開祖、董海川の晩年の入室門徒。河北省河間県後鴻雁村の人。李存義、薛顛らなどと共に、天津においての形意拳・八卦掌の普及に貢献が大であった。張は若年より武術を好み、初学を少林大紅拳、後に秘宗拳を学ぶ。性格は大胆不敵、逞しい偉丈夫であった。大柄な体格から豪快に繰出される強烈な大業から人々に「砕天覇」、「閃電手」などの異名で呼ばれたともいう。
尚済の著書『形意拳技撃術』によれば張占魁の得意技は「連環劈」であったとされる。生家は農業を営んでいたが、河北地方一帯に発生した大旱魃により生活に困窮し、北平(北京)、天津などを遊歴し、後に天津に定着して果物販売業を営む。 張占魁20歳の時、李存義、田静傑、耿誠真などと知遇を得、その縁で劉奇蘭を拝して形意拳を学ぶ。 後に1881年、李存義の紹介により北京で程廷華との友好を結び、八卦掌開祖、董海川の門下ともなる。この時張は李存義、劉鳳春、尹徳安(尹福)らに呼びかけ、程廷華、田静傑、耿誠真などと共に七兄弟の盟を結ぶ。程廷華の死後、張は天津に帰り営務処頭領(捕盗官の長)の職など、警備関係の仕事に従事し、数多くの匪賊を捉えたという。
1911年には李存義の呼びかけにより天津中華武士会にも参加し、自身も天津に武館を設け数多くの門弟に教授する。張の弟子は甚だ多く、一説によると張の教えた門弟の数はゆうに数千人ともいう。晩年僧籍となり仏門に入るが、1938年食道癌により逝去した。張の弟子で著名な者は姜容樵、李剣秋などがよく知られている。また日本に初めて形意拳・八卦掌・太極拳の本格的な教授をはじめた王樹金は、張占魁の最後の拝師門徒であった。
尚雲祥 - 1864年~1937年
字を霽亭、山東省楽陵の人。小柄な体格であったが、その性は武を好み義気に篤かった。 郭雲深・孫禄堂らと共に、形意拳の近世三大名手の一人に数えられる。人生の辛酸を繰り返し味わいながらも、凄まじい修練の末に大成した達人である。
1863年、尚雲祥は鐙職人の家の子として生まれる。尚3歳の頃、山東省一帯を襲った大地震により尚は母親を失い、残された家族も生活基盤が破壊され為に、北京に移り住むこととなった。だが移り住んだ先の北京でも一家は生活苦にあえぎ、その為、尚の幼い頃の一家は極貧の中で暮らしていたという。困窮し尽くした尚の父親は、幼い我子の為に一計を案じ、当時、山東で富豪として成功を収めていた友人の邵承栄の家に、尚を下僕として使わせることとした。
邵の気性は義に篤く、かって黄四海を拝して八極拳を学んだこともあり、武術を唯一の趣味としていたという。その為邵の家には練拳所が設けられており、また常時多くの武術家を食客として世話していたともいう。幼い尚はこの邵の元で、日夜身を粉にするかの如く奉公し、また雇い主である邵も、幼いながらも誠心誠意尽くす尚を不憫に思い、やがて奉公の合間を見ては、尚に武術の基本功などを指導するようになったという。
こうして尚が12歳の時、晴れて今までの奉公を認められ親元に帰ることを許さるが、この時邵は、尚に帰郷の為の従者を使わせると共に、銀大枚二百両を餞別として渡したともいう。親元に帰った尚は家業を手伝いながらも腕を磨くが、ところが親元に帰ってからも、世はまだ太平が続いていた為か、相変わらず仕事の注文の方は殆ど無く、一家の日々の生活の為に、邵から送られた銀もたちまち底を尽いてしまう。
そこで尚は家業の方を完全に諦め、武術で身を立てることを志し、当時、北京で有名な武術家であった馬大義について、功力拳などを学び、次第に門内の中堅の内の一人として頭角を表す様になったという。尚が形意拳を学ぶ切欠となった出来事とは、一説によれば尚24歳の頃、形意門の李志和なる人物に、試合で負けたことからだといわれている。尚は李志和に入門の願ったのだが李は尚の身長160センチにも満たない矮躯をみて、これではとても形意門の名誉を守っていくことは難しいだろうと、尚の入門の申し出を拒否した説もある。しかるのち尚は当時、形意拳で広く高名が知られていた李存義に、目立たない多くの学生の内の一人として入門するが、尚はここで人に勝る程の苦練を己にかし、昼夜を問わず激しい荒稽古を行ったという、 厳寒の真冬にも木綿の着衣一枚というなりで大汗をかく稽古を行い、尚は、-10度の寒さの中でも、雪上で裸足というなりで練拳したとも伝えられる。
やがて尚の両腕は最も繰り返し練習され、その後尚の得意技ともなった木行崩拳の練習の為に、まるで鉄で出来たかの如く見事に鍛えられていったという。またある時、このような根気のいる基礎練習をひたすら行う尚を、冷やかして笑い者にしようとした性質の悪い者たちに、尚は練習中に足元に大豆をばら撒かれるという悪戯をされるが、尚は足を滑らせて転ぶどころか、ばら撒かれた大豆は尚の強烈な踏み込みにより、ある物は粉々に破砕され、ある物は大地にめり込み、ばら撒かれた大豆は悉く消滅してしまったという。
また尚が庭先で拳を練っていると、足もとの石畳は忽ち踏み割られていくので、この光景を見ていた人々は、「尚の足はまるで(鉄で出来た)仏のようだ、鉄腳佛だ!」とも驚嘆したという。日々苦練を繰り返した尚は、やがて自分の得意門徒であると、李存義に認められるほどの驚異的な成長を遂げたのであった。
その後尚は北京の五城兵営において匪賊の取り締まりなどを行う探偵(捕盗官)の仕事に従事し、尚は軍隊でも手を余す程の凶悪な犯罪者たちを相手に、著しい活躍を行った。一説によると尚は大槍を得意としていたが、匪賊たちとの乱闘の際槍が手元で折れてしまうが、その短い棒を持って戦い続け、賊を全て征圧したこともあると伝えられている。
尚は、こうして命がけで得た筈の賞金の殆どを貧民たちに施し、己は赤貧であることを良しとしたという。また後にはその腕を見込まれ、宮廷に使える宦官の長であった李總管の邸宅の護院の職にもついている。こうして尚は実戦の場で腕を磨きつつ、やがて天津に出向いた際に張占魁・王向斉らとの知遇を得て、その縁により河北派形意拳の大家、郭雲深にも直接師事することが叶ったともいう。郭について尚は益々己に修練をかし、郭への人々の賞賛であった「半歩崩拳遍く天下を打つ」の代名詞は、尚へと引き継がれる程となった(一説によれば尚の郭への師事した経緯で諍いが発生し、尚と李存義の師弟関係は悪化したといもいわていれる) 。尚は生涯において中国南北で数多くの弟子たちを育てたが、 晩年は故郷の山東省に陰棲し、そこで極少数の弟子たちに、これまでの自己の工夫を加味した独自の形意拳を伝授しつつも、1937年、73歳でその生涯を終えた。 尚の門弟で著名な者に趙克礼、桑丹啓、呂泰英、王永年、李文彬、尚芝蓉(娘)などがいる。
薛顛 - 1887年~1953年
形意拳随一の奇才。武痴と渾名された達人。字を國興。河北省束鹿の人。薛の父親の薛振綱は李洛能の子息、李太和の入室門徒であり、薛もまた、幼少からこの父親に形意拳を学ぶと共に、李太和の子息、李振邦を拝して形意拳を学ぶ。しかも李振邦の娘婿でもあるという、形意拳の嫡系に等しい教えを受けた、サラブレッド的な毛並みの良さを誇った人物である(異説として先に李存義の入室門徒であったという説がある)。
当時、門派を問わず多くの達人たちが集った天津において、形意拳の重鎮の一人として著名を知られ、天津県国術館の副館長・館長を歴任した。形意門きっての理論派であり、王向斉、尚雲祥などに多大な影響を与えるが、その反面奇行が激しく、一例をあげると、薛はある富豪の庭園で開かれた酒宴の席に招かれた際に、表演を希望され五行拳を演じたが、薛は只表演して御見せするだけでは客人がたも退屈であろうと言い放ち、庭に敷き詰められていた石畳の全てを、強烈な震脚で悉く踏み割って見せ、皆はこれを見て唖然として驚き、以来薛は人々に鉄腳佛と賞されるようになったという(鉄腳佛の異名は尚雲祥にも冠されている)。
また薛は若年の頃に南方を旅した際に五台山に登り、そこで霊空禅師、虚無上人などと名乗る齢130歳だという異人に遭遇し秘拳を教えられたとして、象形拳なる独自の拳法を創始もした。 薛の没後「その技は非常に剛猛硬質で実用に優れていたが、内家拳らしい柔らかさに欠けていた。」などと、かなり不名誉な中傷を、中国で再版された自身の著作の解説文に書かれたりもしたが、薛は十二形龍形拳の巧みさで知られていたともいう。薛顛には王向斉や傅長栄と比武を行い破れた逸話などが流布されているが、それらは薛や関係者たちの死後に発表されたもので真偽は不明である。
著作には『象形拳眞詮』、『形意拳術講義』、『霊空禅師點穴秘訣』などがある。薛顛は道教系秘密結社の一貫道の信徒であったことから国共内戦後、中国共産党によって一貫道が反革命的邪教であると弾圧された最中に捕らえられ、公開裁判で晒された後、一旦解放されるのだが、しかし間もなく再び嫌疑をかけられ、捕らえられる際に抵抗したとされ、兵士たちに射殺されてしまった。薛顛の妻娘、門弟も逃げ散り、薛顛の武術は長く失伝されたものだと思われていた。
王樹金 - 1905年~1981年
本名を王恒孫、字を樹金。河北省天津出身の人。恵まれた体格の大兵肥満の堂々たる偉丈夫で、真剣勝負を好んだといわれる達人。形意拳・八卦掌・太極拳を統合した門派「終南門」の開祖。この名の由来はその師の張占魁が、終南派形意拳の道士たちと交流があったためだと思われる。張占魁にその素質と才能を愛され最後の正式な入室門徒となり、李存義の有力な弟子であった陳泮嶺や、のちに意拳を創始することになる王向斉からも学び、八卦掌の開祖、董海川の弟子であった劉宝貞の高弟、蕭海波かも手ほどきを受けたともいわれている。
秘密結社的な色彩が色濃い道教の一派、一貫道(天道)の幹部信徒(第三位階)、菜食主義者であった。戦後の我が国において本格的に中国武術の普及にあたった、パイオニア的人物(合計21回来日)。 国共内戦中の1949年、もはや中国共産党の勝利が揺るがぬものと察し、自身の信仰する一貫道が、国民党に協力した邪教であると弾圧されるのをみて台湾に逃れる。台湾で一貫道の布教にあたりつつ武術を教え、「誠明国術館」を設立。 この頃の王は台湾の武術家を相手に積極的に比武を行い連戦連勝して無敗を誇る。晩年は日本の右翼の大物、頭山満の息子、頭山泉が中国の文化大使として中国武術で最高の達人を招きたいと蒋介石に希望し、その推薦により日本に来日し、中国武術の教授を行う。 王の教授した門弟は多数に及び、現代においても巨大な影響力を残している。
形意拳 - シンイーケン(ビデオゲーム)
2000年に台湾のIGSが発表した対戦格闘ゲームである。 『形意拳』は漢字圏でのタイトルで、英語圏では『Martial Masters』。
中華民族の英雄的武術の達人、黄飛鴻(1847生-1924没)を主人公にした映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ』の影響を強く受けている作品である。
主人公の用いる洪家拳は少林拳(南派拳法・外家拳)であり、武術における形意拳は本記事にもあるように心意拳に連なるものであり、少林拳ではなくそれとよく比較されて語られる、武当拳(武当派・内家拳)とされている。また地域的区分からも北派拳法にも分類されており、どうもタイトルを名付けた開発者がこの辺りのことをよく分かっていなかったのかもしれない。おそらく洪拳にも形意拳と同じく動物を模した象形拳の型が存在するため混同があったのだろうか。
ゲームのファンにはすまないが、武術の方の形意拳を愛好している者にとっては、タコ焼きを食べるつもりが、鯛焼きを出されたかのような感のタイトルにも思える。
ちなみに余談となるが洪拳は、某有名、中国武術漫画の『拳児』では、まるで八極拳に強さで劣る拳であるかのように描写されていたが、その精強さは中国では広く知られ渡っており、その代表的達人の黄飛鴻は民族の誇る英雄として愛されている。
作中では戦乱の中で伝えられた、じっくり修行する時間のない革命闘士たちが、すぐに戦えるようになるための武術であると紹介されたが、だが昔日の武術というものは、形意拳(「学んで1年で人を打ち殺す」)にしろ、詠春拳(詠春の諺に「学んで3ヶ月で使いたくなり、半年で喧嘩がしたくなり、1年で人を殺してみたくなる」というものがある)にしろ、武術はその殆どが(学んで使えるまで10年かかるといわれる太極拳を除く)学んで短期間のうちに実用になるものでなければ、顧みもされないようなものであった。
武術では「小成三年」といわれている。三年やってようやく一端の拳士を名乗れるのである。しかし武術の深奥は底知れないものであることは洪拳も変わらない。むしろ形意拳や八極拳と比べて学習内容は膨大で、その門派を収めたといえるほど習熟するには、大変な時間と、熱意と修練が必要であろう。そこはどうか誤解がなきように。
それと八極拳も本来は洪拳にも増して即成的なところがあったのである。八極拳は『拳意述真』でも言及があったように歴史が古く、多くの実戦の名手たちを輩出してきた名門であった。
国共内戦以前の中国武術の統一組織であった、南京中央国術館においても、少林門と武当門で共通で学ぶ正課とされたメジャーな拳であり、中央国術館ではその代表的な套路である大八極を元に、制定套路「八極小硬架」が作られ、これが国府軍の兵士たちの練兵にも採用されていた。
そのため皮肉なことに八極拳は漫画で描かれていたような秘拳どころか、かつては中国全土で広く普及しており、非常に学びやすい拳種だと見られる向きもあったのである。
勿論、八極拳の全伝を得てそれを習得し大成することはとても難しい。
ちなみに余談だが北京を中心に盛んであった、少林門の名拳である三皇炮捶に「八極拳」という名の套路が含まれていたり、少林八極拳という門派や、形意八極拳という門派があるが、おそらく中央国術館の影響があったものと思われる。
ゲームや漫画の影響で、中国でも知られるようになったとか、いい加減な風説から、どうのこうと述べる、くだらない説があるが、それはいいとこ、ゲームや漫画、アニメなどが好きな、オタクサブカルチャーを愛好する者に、それで知名度が上がった程度の話ではないだろうか。
関連項目
関連サイト
- STMG

- 旺龍堂

- 全日本柔拳連盟

- 中國武術鴻龍會

- 日本功夫協会 北関東支部

- 私学校龍珉楼

- 日本孫氏太極拳研究会

- 刀禅 神楽坂稽古会 刀禅形意拳

- 札幌太極拳錬精会

- 太氣至誠拳法 氣功会

- 太氣至誠拳法 武禅会

- 養武健身法

- 武塾相心会

- 太気拳尚武会

- Web秘伝 中国武術 全国道場ガイド

- 錬空武館 館長のブログ

- 花垣武学研究会ブログ

- 中国武術への道 Vol.13 内三合 内なるエネルギーの秘密(その四)

- カメちゃんのブログ めざせ亀仙人(*・ω・)ノ・・・亀コラム・「秘伝必殺・鉄砂掌」

- 孫禄堂 著『拳意述真』中国語全文 英語対訳

- 孫禄堂 著 『形意拳学』中国語全文 英語対訳

- 李存義 著 『五行連環拳譜合璧』中国語全文 英語対訳

- 劉殿琛 著 『形意拳術抉微』中国語全文 英語対訳

- 中国哲学 電子化計画

- 拳論雑談 形意補全計劃正奇八字功探求

- 23
- 0pt